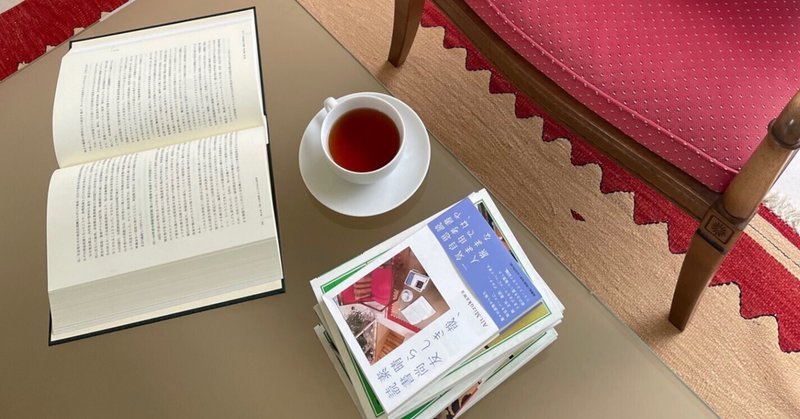
33. 枯葉散る坂道の古家に若き人
引き続き内田百閒から始める。東京から鹿児島に向かう鉄道旅行記「鹿児島阿房列車」。白砂青松の瀬戸内海を眺めるために、尾道で山陽本線から呉線に乗り換えたと書いている。1951年(昭和26年)6月のことである。待ち時間のあいだに駅前をひと歩きした。
33. 枯葉散る坂道の古家に若き人
「駅の前の広場のすぐ先に海が光っている。その向うに近い島がある。小さな汽船が島の方から這入って来たところである。潮のにおいがして、風が吹いて、頭から日が照りつけた。(中略)駅のすぐ前の、海を背にした広場に、小さな見世物小屋があって、看板の前に黒メガネをかけた男が口上を述べている。」
最初は、くだらないと思った百間先生だが、
「小屋の前を通り、小屋の横から又海辺に出て、引き返した。小さな小屋のまわりを一まわりして、もとへ戻ったら気が変わって、這入ってみようかと思い出した。」
と、見世物小屋に少し気を引かれたことを書いている。子供の頃、お祭りどきの神社の境内や遊園地の端っこの方で見世物小屋を見た覚えがある。おどろおどろしい蛇女や蜘蛛娘の看板がかかり、呼び込みの男の声も怪しげだった。このような見世物小屋は人が集まるとこに出来るのだから、尾道の駅前もさぞかし人で賑わっていたのだろう。
この時代、尾道の人口は約18万人。戦後のまだ造船業が元気な頃で人は多かった。ほぼ同時期の尾道の風景は、1953年(昭和28年)の小津安二郎の映画『東京物語』でも見ることができる。南北に細い坂道や石段が入り組み、海と島と寺と山が肩を寄せて集まった街の形がよくわかる。駅前の風景こそ映っていないが、海沿いに立派な瓦屋根の商家や住宅が続き、線路を挟んで北側の斜面には大きな寺院の本堂や塔が連なっている。海岸には大きな常夜灯があり、白壁の蔵も映画に出ている。甍や蔵の画面を見ているだけで、街の繁栄の歴史が窺える。それでも子供たちが東京へ出て行き、家族一緒に生活をしていた頃の賑やかさはなくなっている。夫婦二人と末娘の三人暮らし、そして妻が亡くなって家族が減っていく。成り行く形とはいえ寂しい。尾道を出た子供たちが生活している東京の風景も、近代的な東京というよりは地方から出てきた人々が暮らしを立てている小さな街や住宅が中心である。笠智衆演じる老いた父親が東京で暮らす小児科医の長男の住まいの場所を「東京の端じゃ。」言っていたが、東京で必死に生活を守っている地方出身者の気持ちのありようを伝える練り込まれたセリフだった。東京へ出て必死に生活する人々の姿と、徐々に活気を失っていく地方の人々の姿をゆったりとしたリズムで見せてくれる。あの時代の日本を写した映画だった。
国勢調査の結果から尾道の人口推移を見ると、戦後の第一次ベビーブームを迎えて1947年(昭和22年)に18万人を超えてから1980年(昭和55年)までの30年間は18万人台を維持している。そして、その後減少して現在は約12万人台後半になっている。尾道生まれの大林宣彦の映画『時をかける少女』の公開は1983年(昭和58年)だから、尾道の人口が減少し始めた頃である。画面に映る黒い瓦屋根と一部表層が剥がれて黄土色の下地が見えている白壁が象徴的だった。主演の原田知世の明るさは印象に残っているが、逆に明るい海は全く映っていない。モノクロの『東京物語』では、尾道水道は映っているがむしろ黒い屋根の連なりを引き立たせるための脇役のように見える。両方の映画が持つ明るい暗さとでもいうべき空気感が現代の尾道らしさなのだろうか。尾道の人口減少が始まって久しいことは、街の人の「だいぶ前から街に元気がなくなってきました。」や、スナックのママの「日立が元気だった頃は良かった。」という言葉からも伝わってくる。おのみち歴史博物館の近くには1904年(明治37年)にできた旧住友銀行がある。木造建築だが外装は本石とフェイクの石を使って上手くデザインをしている。尾道に活気があった頃の建物で、設計者も力を入れたようだ。それでも、今の姿はなんとなくバランスが悪く弱々しく見える。建物の一部が取り除かれて元の形が全部は残っていないからかもしれない。石らしい外観がかえって見窄らしく見えてしまう。前面の道路は銀行浜とも呼ばれ、金融機関が並んでいたという。繁栄の象徴だった場所なのである。住友銀行(現三井住友銀行)にとって尾道は、別子銅山との繋がりや並合業から銀行業への参入などから見て記念碑的な街である。旧住友銀行の建物は尾道の歴史を十二分に見てきたはずである。今は尾道市が建物の管理をしているというが、その寂しい姿はいかにも勿体無い。
人口が減っている尾道には海の見える空き家がたくさんある。細い坂道に面した建物は建築基準法の接道義務を満たしていないため、解体すると建物が立たない。そこで尾道市や若い人たちを中心としたNPOの活動によって、尾道に移住したいという人と空き家をマッチングさせる活動が2008年から行われている。これまでに百件近く空き家再生をしたそうである。若い人たちの知恵と行動には新しい尾道の萌芽が感じられる。
●内田百閒「鹿児島阿房列車」・・・『第一阿房列車』新潮社 2003年に掲載
●『東京物語』監督:小津安二郎 主演:笠智衆、原節子 配給:松竹 1953年・・・尾道の寂れて温かい風景が映画にあっていただけでなく、志賀直哉が一時期住んだことも尾道を舞台に選んだ一因だと言われている。小津は志賀直哉を尊敬していた。
●『時をかける少女』監督:大林宣彦 主演:原田知世 配給:東映 1983年
●NPO法人尾道空き家再生プロジェクト・・・古い街並みや景観の保全、移住者・定住者の促進による町の活性化、新たな文化・ネットワーク・コミュニケーション構築を目指している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
