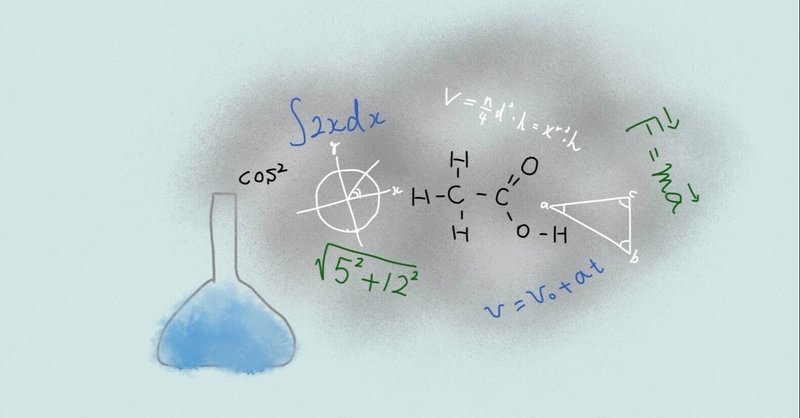
環境フレンドリーかつ強固な材料、セルロースナノファイバーの技術動向
本記事では、素材としてのポテンシャルやエコロジーといった観点で話題の「セルロースナノファイバー(CNF)」の大まかな概要と、最近の技術動向について執筆しました。
セルロースナノファイバーとは
セルロースナノファイバーは木材から得られる木材繊維(パルプ)を1ミクロンの数百分の一以下のナノオーダーにまで高度にナノ化(微細化)した世界最先端のバイオマス素材です。セルロースナノファイバーは植物繊維由来であることから、生産・廃棄に関する環境負荷が小さく、軽量であることが特徴で、弾性率は高強度繊維で知られるアラミド繊維並に高く、温度変化に伴う伸縮はガラス並みに良好、酸素などのガスバリア性が高いなど、優れた特性を発現します。
(日本製紙グループ HPより)

セルロースといえば紙やレーヨン繊維といったものの原料でもありますが、セルロースナノファイバーはそれらより繊維のナノ~マイクロ構造・配向を制御して、繊維としての性質を最大限に引き出すように工夫したものです。
これにより、バイオマス由来でありながら強度の高い優れた材料となります。
ナノレベルのセルロース繊維は非常に強固に相互作用しているため、通常はほぐすことができません。従って、セルロースナノファイバーを調製する際にはセルロースの塊(パルプ)に化学処理を施したり余分な成分(リグニン)を除去するなどして、ほぐしやすくするケースが多いです。
主な企業プレーヤー
大学やNEDOなどの研究機関はもちろんのこと、企業でも積極的に取り組まれています。実用化を目指して本格的に取り組んでいる企業として、
・日本製紙、王子製紙、大王製紙といった大手製紙会社
・東亞合成
・レンゴー
といったところが挙げられます。元々セルロースパルプを扱っている企業が事業の多角化を目指して研究開発を進めているケースが多いようです。
また、海外でも研究されている材料ですが、日本を含めて本格的な普及はまだ先というのが現状です。
一応、下記のように大王製紙(エリエール)のトイレクリーナーにセルロースナノファイバーを配合して実際に製品化しています。が、コストの点も気になりますし、何より本材料のポテンシャルを十分に引き出しているかは疑問です。
最近の関連ニュース
CNFの最大の課題はコストであり、いかにして生産コストを下げて販売価格を安くできるかが普及のカギとなっています。東亞合成では従来の5分の1という大幅な値下げを目指せる製造技術の開発に成功しており、今後の材料普及に繋がるかが注目されます。
CNFの性質として、強度やガスバリア性に優れていることは広く知られています。しかし、セルロースナノファイバーのポテンシャルはそれだけにとどまりません。日本製紙と東北大の共同研究では、セルロースナノファイバーを蓄電池にするという検討を行っており、2030年実用化を目指しています。
セルロースナノファイバーは普及するのか?
このようにCNFの分野では日本で盛んに研究されており、材料面/環境面に多大なメリットをもたらすように見えます。しかし、そのようなポジティブな見方だけではなく、以下のような普及に懐疑的な意見も散見されます。
この記事では、少量添加としての利用では大きな売上は見込めず、多量に使用するにはコストが高すぎるため、大きなビジネスにはなり得ないだろうと指摘しています。
また、より低コストなガラス繊維などの他材料で済ませられるケースも多いのでは、という意見もあります。
確かにこれらの考えは間違っていないと思います。しかし、先述の蓄電池のように新たな応用方法を見出されており、材料としてのポテンシャルはまだまだ底が見えていないようにも思えます。
私の意見としては、ガスバリア性やチキソ性といった「CNFならでは」の特性を生かした実用化を徐々に広めていくとともに、セルロースナノファイバーの材料としての基礎研究を国/企業/研究開発法人が一体となって進め、その潜在能力を明らかにすることを目指すのがいいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
