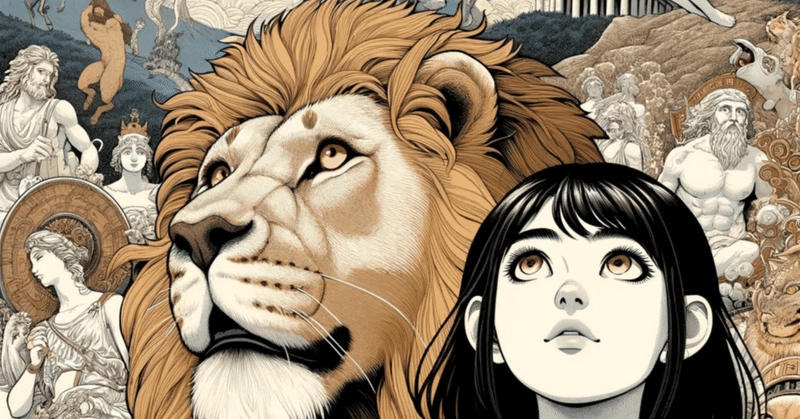
【セカコの世界史2024】 22-2 ローマの平
前回の記事の続きです。
ユリウス=クラウディウス朝
先生:1世紀のローマ帝国の様子を見ていきます。
セカコ:PAX ROMANAですよね。「ローマの平和」が到来しました。
先生:そうですね。実は、前回、アウグストゥスの時代で取り上げるのを忘れていた重要な出来事があるので、その話から進めましょう。
アウグストゥスの治世終盤の紀元9年、ゲルマニア北部で行われた(1)トイトブルクの戦いで、ウァルス将軍率いるローマ軍がゲルマン人に大敗し、以後ローマ帝国は、ライン川とドナウ川を国境として守りを固めました。
セカイシシ:トイトブルクはドイツを意味する「チュートン」の語源になっておる。中世と近代で登場するドイツ騎士団は、十字軍のチュートン騎士団から生まれたものじゃ。アウグストゥスがこれ以降、領土の拡大を目指さず、領土の維持を目指す方針を取ったことで、立て続けに対外戦争を行っていたローマ史の転機となったのじゃ。
先生:セカイシシさん、ありがとうございます。アウグストゥスの死後の話に進みましょう。
セカコ:二代目以降のローマ皇帝って、どうやって決めたんですか。元老院や民衆が選んでいたって聞いたことがあります。
先生:厳密にいうとそうではなくて、皇帝になるには元老院や民衆に認められる必要があったということになります。1世紀の前半、最初の五代はアウグストゥス(位前27-後14)の一族がローマ皇帝の地位を受け継ぎました。五賢帝の最初のネルウァは元老院が選んでいますが、他は前任の皇帝が指名した者や軍事力を使って実力で皇帝になった者を元老院が追認しています。
セカコ:そうなんですか。暴君ネロもアウグストゥスの子孫なのですか。
先生:二代目以降の皇帝は、アウグストゥスの直系ではありません。家系図がちょっと複雑なんですが、最初の五人の皇帝の時代をユリウス=クラウディウス朝といいます。
セカコ:教科書にはない言葉ですね。
先生:そうですね。初代ローマ皇帝アウグストゥスは、カエサルからユリウス氏族の家長の地位を継承しました。彼には実子がなかったので、彼の死後、妻リウィアの連れ子でクラウディウス氏族出身の(2)ティベリウスが第二代皇帝となり、ユリウス氏族の家長の地位を継承しました。これ以降、ユリウス氏とクラウディウス氏族の家長を兼ねた人物が皇帝をつとめたわけです。アウグストゥスからネロまでの5代がユリウス=クラウディウス朝です。第3代がカリグラ(位37-41)、第4代がクラウディウス(位41-54)です。
セカコ:第五代は(3)ネロ(位54-68)ですよね。キリスト教徒を迫害して、ローマ大火の責任をキリスト教徒に負わせた皇帝です。後世「暴君ネロ」と批判されました。
先生:そうですね。前節で取り上げた、クオ=ヴァディスのエピソードはこの時のものです。キリスト教側からの一方的な否定的評価だという説もありますが、そうとばかりはいえないかもしれません。『幸福論』など多数の著作で知られるストア派哲学者(4)セネカは、ネロの家庭教師をつとめ、のちに自殺させられました。
セカコ:お母さんのアグリッピナも殺していますよね。
先生:セカコさんはネロについて妙に詳しいんですね。お母さんのアグリッピナの名を冠した都市があることはご存じですか。
セカコ:それは初耳です。
先生:ライン川沿いに建設された植民市コロニア=アグリッピナ、現在のケルンです。中世には、ゴシック様式のケルン大聖堂が建設されたり、領主のケルン大司教が神聖ローマ皇帝を選出する選帝侯になったりと、重要な都市なので覚えておきましょう。
セカコ:名前が全然違いますね。
先生:ラテン語で植民市を意味するコロニアが、訛ってケルンに転じたようですね。
セカコ:先生はセネカがお好きなんですよね。よく引用されています。
先生:そうですね。
セカコ:だったらネロが憎いでしょう。
先生:そんなことはないですよ。お茶の先生が、千利休を尊敬しているからといって、豊臣秀吉を恨んだりしないでしょう。
セカコ:でも、ネロは、セネカも、お母さんも、ペテロも、他にもたくさん殺してますからね。
先生:まあそうカッカしないでください。
セカコ:セネカのことをもう少し知りたいです。
先生:話すと長くなるので、別の機会にしましょう。ここでは、著作名をいくつか挙げておきます。著作名を並べるだけで、セネカがどういう人物かわかりますよ。
セネカの主な著作
・『怒りについて』(De Ira)『人生の短さについて』(De Brevitate Vitae)
・『賢者の不動心について』(De Constantia Sapientis)
・『寛容について』(De Clementia)
・『幸福な人生について』(De Vita Beata)
・『余暇について』(De Otio)
・『善行について』(De Beneficiis)
・『心の平静について』(De Tranquillitate Animi)
・『神慮について』(De Providentia)
・ルキリウス宛て『倫理書簡集』(Epistulae Morales ad Lucilium)
フラウィウス朝
先生:ネロの死後、3人の短命な皇帝を経て、69年に皇帝となったウェスパシアヌスが、混乱を収拾し、フラウィウス朝を創始しました。フラウィウス氏族による帝位の世襲が三代30年(西暦69-96)にわたて続きます。
セカイシシ:ウェスパシアヌスはユダヤの反乱(ユダヤ戦争)を鎮圧し、70年にイェルサレムを陥落させておる。この後、2世紀前半の再度の反乱を経てユダヤ人は祖国を失い、(5)ディアスポラ(離散の民)となった。ローマに仕えたユダヤ人歴史家ヨセフスは『ユダヤ戦記』・『ユダヤ古代史』等を著し、イエスについて言及したことで知られる。
先生:ヨセフスの歴史書は、イエスが実在した証拠として重要です。
セカコ:イエスが実在した証拠ですか。
先生:イエスに関する記録は『新約聖書』に記されています。ですが、キリスト教徒の記録なので、自分たちに都合の良い創作や改変が行われている可能性があるわけです。一方、ユダヤ教徒のヨセフスの記述にイエスに関する記事があるということは、キリスト教徒以外からの客観的な記録ということになりますから、イエスという人物が確かに存在した証拠になるわけです。
セカコ:なるほど。
先生:ウェスパシアヌスのユダヤ戦争には、息子のティトゥスも同行していました。このティトゥスが次のローマ皇帝です。
セカイシシ:79年から81年まで皇帝をつとめたティトゥスの時代には、ナポリから一望できる(6)ウェスウィウス火山(ヴェスヴィオ火山)が噴火し、山麓の都市(7)ポンペイやヘルクラネウムが埋没しておる。天文・地理・動植物などの多様な知識を科学的に記した『(8)博物誌』の著者として知られる(9)プリニウスが、ウェスウィウス火山の噴火時に艦隊司令官として救助活動中に火山ガスで死亡しておる。
セカコ:ポンペイは世界遺産になっていますね。
先生:1世紀に火山噴火で埋没した都市が、18世紀になって発掘され、当時の姿がそのまま姿を現し、古代の都市生活の様子を知る貴重なてがかりとなったのです。
セカコ:いつかポンペイの遺跡に行ってみたいな。
先生:私は大学生の時にローマ史を専攻していたので、ポンペイ遺跡を丸一日かけて歩いたんですが、写真を撮ったフィルムが入った鞄を、ローマの地下鉄で擦られてしまった思い出があります。
セカコ:写真はどうなったんですか。
先生:返ってきませんでした。イタリアの人たちにはいつでも行ける場所の写真なので、そんなに価値はないだろうに。私としては返して欲しかったです。
セカコ:ポンペイは先生の記憶の中にあるわけですね。
先生:余計なお話をしてしまいました。進みましょう。ティトゥスの治世は短かったのですが、もうひとつ大切な出来事がありました。父ウェスパシアヌスが着工させた(10) コロッセウムが完成したんです。
セカコ:今もローマ市内に残るコロッセウムは、ティトゥスの時に完成したんですね。
先生:古代ローマの歴史家スエトニウスによる『ローマ皇帝伝』の一部を引用してみます。
ティトゥスは民衆の人気をとるために、どんな手段も見逃さなかった。ときには自分の建てた浴場で体を洗っているとき、民衆の入場を許した。
彼の治世にたまたま悲惨な出来事がいくつか起こった。カンパニア地方のウェスウィウス火山の噴火、三日三晩まるまる燃えつづけたローマの大火、これまで例のない恐ろしい疫病の流行などである。こうした大災害に、ティトゥスは元首としての配慮ばかりか、父親としての比類なき愛情も示した。あるときは布告で民心を労り、慰め、あるときは力の限り援助の手を差しのべ。
カンパニアの災害復興委員は、執政官級の人から籤で選ばれた。ウェスウィウス火山の噴火で圧死した人の財産は、その相続人が生存していない場合、ひどい損害をこうむった市民らの再起の資金にあてがわれた。
スエトニウス著、國原吉之助訳『ローマ皇帝伝 下』、岩波文庫、1986年。
セカコ:評価されていますね。
先生:ティトゥスは短命で病死してしまい、その治世は短かったので、良き皇帝としてローマ市民の記憶に残ったようなのです。
セカコ:アレクサンドロス大王とか、短命な帝王は、失敗もしない分、高く評価されるのかもしれませんね。
先生:今回はセカコさん、辛口ですね。確かに、後継者となったティトゥスの弟ドミティアヌスが皇帝は、二十年以上帝位にあり、圧政者という評価を受けています。
繁栄するローマ帝国
先生:歴代ローマ皇帝は、イベリア半島のラス=メドゥラス金山など属州各地で金を採掘して金貨を鋳造し、皇帝の権威の印として帝国に流通させました。(11)ローマ金貨はインドや東南アジアなど幅広い地域で出土し、当時の交易がアフロ=ユーラシアの広範囲に及んだことを物語っています。
セカコ:ローマは建築にも優れていたんですよね。水道橋が有名です。
先生:そうですね。フランス南部に残る(12) ガール水道橋(ポン・デュ・ガールPont du Gard)をはじめ各地に水道橋を建設し、都市に水を供給しました。都ローマをはじめ各都市には公共の(13)浴場が建設されていました。
セカイシシ:他にも、ローマ帝国各地の都市遺跡に残る(14)凱旋門や、都市に設けられた公共広場(15)フォルムは、ローマ時代の都市を象徴する建築物といえるだろう。ローマ市の中心部に残る(16) フォロ=ロマーノ(フォルム=ロマヌム)は共和政時代からローマの政治の中枢であった。
セカコ:街道も有名ですね。紀元前4世紀に建設された(17)アッピア街道以来、征服地に街道が張り巡らされました。「すべての道はローマに続く」という格言もありますね。
先生:共和政時代の有力者と同様、歴代ローマ皇帝は、無産市民に食料や娯楽を提供し支持をえました。これを(18)パンと見世物といいます。これは元来、ローマ市民の政治的盲目を批判した警句なんですよ。
セカコ:そうなんですか。すっかり、ローマの市民生活を象徴するキャッチフレーズになっていますね。
セカイシシ:(18)パンと見世物、ラテン語でPANEM ET CIRCENSESという言葉は、古代ローマ時代の詩人詩人ユウェナリス(60-130)が書いた『風刺詩集』にある。この言葉は、政府が市民の政治的な不注意を利用していることを指摘しておる。当時のローマでは、政府が市民に対して食料配給や娯楽を提供しておった。市民はこれらのサービスに満足し、政治的な問題には無関心になっていたという状況があったのじゃ。ユウェナリスは、このような政治的な無関心を批判し、市民が政治に対して関心を持つことが重要であると訴えておるのだ。この言葉は、現代においても政治的な腐敗や社会問題を批判する際に使用されることがある。政府が市民に対してある程度の生活保障を提供することは重要ですが、それによって市民が政治に無関心になることを許してはいけないというメッセージが含まれておる。
先生:セカイシシさん、ありがとうございました。ユウェナリスは、「Quis custodiet ipsos custodes」という言葉でも知られています。ラテン語で「誰が監視者を監視するのか」という意味です。この警句は、権力者が自己監視することができないため、社会において権力者を監視する必要性を表しています。「orandum est ut sit mens sana in corpore sano」も有名ですね。こちらは、「健全な精神は健全な肉体に宿る」という意味です。
セカコ:ユウェナリスは詩人だけあって、言いたいことを少ない単語で上手く言い表すことに長けているんですね。
先生:最後にローマ帝国時代の都市名から、現在の都市名を当てるクイズです。現代のヨーロッパの主要都市には、ローマ帝国時代の都市から発展したものがたくさんあるんですよ。
ローマ時代に由来する都市
①ロンデニウム→
②ヴィンドボナ→
③ルテティア→
④コロニア=アグリピナ→
⑤メディオラヌム→
セカコ:正解は、重要語句のまとめのあとで!
重要語句まとめ
セカコ:この節で学んだ重要語句をまとめておきましょう。
1 トイトブルクの戦い
2 ティベリウス
3 ネロ
4 セネカ
5 ディアスポラ
6 ウェスウィウス火山(ヴェスヴィオ)
7 ポンペイ
8 博物誌
9 プリニウス
10 コロッセウム
11 ローマ金貨
12 ガール水道橋
13 浴場
14 凱旋門
15 フォルム
16 フォロ=ロマーノ
17 アッピア街道
18 パンと見世物
セカコ:クイズの答えです。
ローマ時代に由来する都市
①ロンデニウム→ ロンドン
②ヴィンドボナ→ ウィーン
③ルテティア→ パリ
④コロニア=アグリピナ→ ケルン
⑤メディオラヌム→ ミラノ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
