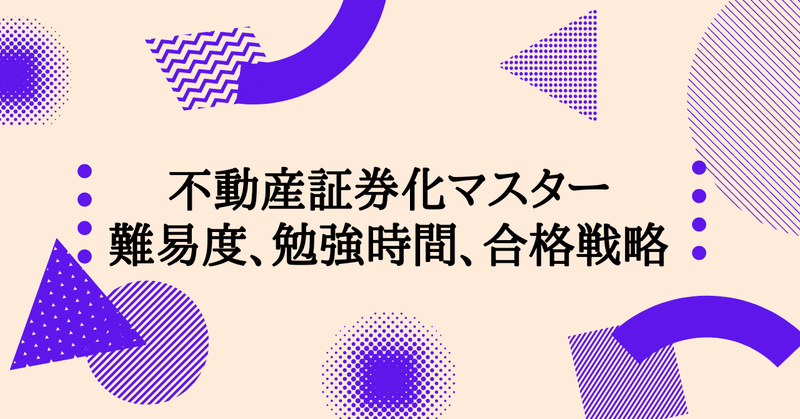
不動産証券化マスターおすすめ勉強方法(★2024年度新試験対応)
不動産証券化マスターのおすすめ勉強方法(サマリー)
不動産証券化マスターは7割正解すれば合格する試験。試験勉強もメリハリをつける。
試験の範囲は広範に見えるが、基本的には講義資料レジュメや過去問で扱う範囲から出題される。講義資料レジュメや過去問以外の論点が問われたとしても、他の受験生の正答率も低くなるので合否に影響はない。
学習の基本は過去問を解く→講義資料レジュメで論点を理解する、の繰り返し。このサイクルを最低3周する
得点戦略としては、最も難しい104不動産証券化の法務と会計・税務で6~7割正解を目指して、104以外の科目で8割正解を目指す。
具体的には、
102不動産証券化の概論、103不動産投資の実務、106不動産証券化と倫理行動、105投資分析とファイナンス理論の4科目は、過去問を解けば8割正解レベルに容易に達する。特に、105投資分析とファイナンス理論は見た目は難しそうに見えるが、過去問の論点を理解すれば安定して8割正解を確保できるため、絶対に捨ててはいけない
ただし、上記4科目は9割正解を目指すと効率が悪いので、まず上記4科目で8割正解レベルに到達することを目指し、過去問を概ね正解できるようになったら深追いしないで他の科目(特に104)に軸足を移す
104不動産証券化の法務と会計・税務は最も難易度が高いため、6~7割正解を目指す。104が難しくても他の科目で8割正解するベースがあれば合格できるのであきらめないことが重要。
(104で特に苦手な論点は当初は後回しにしてしてもいい。勉強を進めるうちに、ほとんどの論点は単に用語が難しいため難しく感じるに過ぎないことに気づく)なお、101企業と不動産は2024年度の新設科目。不動産証券化の概説的な内容であるため、出題範囲が広くなりがちで対策はしにくい。101は講義の受講してノートを取る王道の対策を推奨
以下、説明していきます。
不動産証券化マスターコース1修了試験の概要
不動産証券化マスターはコース1(試験)とコース2(スクーリング・レポート課題)に分かれています。コース2はレポート課題が与えられますが、基本的には作業時間を確保すれば合格できるものですので、コース1の試験の突破が最も重要です。

不動産証券化マスターのコース1の合格点は100点満点中70点(7割)が目安になります。
他の資格試験としてメジャーな宅建の合格点も7割が目安とされていますが、宅建と同様にいかに科目ごとにメリハリをつけるかが効率的に合格するためのポイントになります。
※なお、従前までは、一般的にコース1の試験を突破すれば、コース2は課題を提出しさえすれば合格する一般的に言われていましたが、試験実施団体は2024年度よりコース2においても不動産証券化協会認定マスターに相応しい知識と能力が習得できているかについて、提出したレポートや確認テストの結果によって今まで以上に厳しく判定されるとしています。
上記の試験実施団体の方針について、不動産証券化マスター試験研究会としては以下のように考えています。
コース2で行われるレポート課題は、レポート課題として数値が与えられて、講義や講義レジュメの誘導に従ってエクセル等で「作業」をした成果物をレポートとして提出するものです。コース2において根拠の薄い数値をとりあえず入れて提出するといった方法は今後は今後は難しくなるものと考えています。他方で、レポート課題は課題に対する一定程度の理解は求められるものの基本的には作業要素の方が強いため、講義ビデオを見て作業する時間さえ確保できれば合格点を獲得ができる性質のものです(コース1の試験は、過去問で問われる論点や問われ方が独特であるため、講義を聞いただけでは合格が難しいのとは対照的です。)。そのため、受験生にはコース2の実施期間中に対する時間的なコミットメントがより求められるということになるものと考えています。今年度の合格が必ず必要な受験生は、予め職場や家庭の理解を得ておくのがいいものと考えています。
試験範囲と合格戦略

不動産証券化マスターは、分厚いテキストが送付されてきますし、実際に試験の範囲は広範ですが、基本的には講義資料レジュメや過去問で扱う範囲からのみ出題されます(仮に講義資料レジュメに記載のないかつ過去問で問われたこともない論点が問われたとしても、他の受験生の正答率も低くなるので合否に影響はありません)。過去問で何度も問われるような基本を固めることと、講義資料レジュメで時間をかけて説明されている論点を確実に正解することが大切です。
最も難しい104は6~7割正解を目指す
104不動産証券化の法務と会計・税務は、不動産証券化の法律や会計・税務に関する科目です。内容が専門的でとっつきにくく、また不動産証券化業界に既にいたとしても実務で扱う機会の少ない不特法の現物出資などの細かい論点も出題されることから、不動産証券化マスターの科目で最も難易度が高い科目です。実際に、よく受験生で104不動産証券化の法務と会計・税務の難しさに圧倒されてあきらめてしまう方がよくいらっしゃいます。
しかし、他の科目で8割正解さえすれば、104不動産証券化の法務と会計・税務は足きり(足きりの具体的な点数は公表されていませんが、6割程度なのではないか言われています)にかからない程度の6~7割正解できれば合格点に達します。どうしても理解できない論点は捨てても合格することは可能ですので、104が難しくてもあきらめないこととが重要です。
8割正解を狙う科目(104以外のすべての科目)
102不動産証券化の概論、103不動産投資の実務、106不動産証券化と倫理行動の3科目は、証券化の基礎的な概念や不動産に関する基本的な知識に関する科目です。比較的にとっつきやすく、特に一般常識で正解できる問題も多いため、8割正解を目指しましょう。他方で、これらの3科目8科目の特徴としては、過去問で問われてた論点が何度も出題されるため8割正解レベルには比較的短時間で到達しても、マニアックな論点も時折出題されるため9割正解を目指すと効率が一気に悪くなることが挙げられます。そのため、過去問若しくは証券化マスター試験研究会の一問一答を9-10割正解できるようになったら深追いせずに、他の科目の勉強の重心を移しましょう。
105投資分析とファイナンス理論は、大学で受講する金融論の導入部分のような内容です。一見中身が難しいように見えますが、講義で扱う論点が限られているため、対策し易い科目です。対策すれば最低でも8割は得点できますので、105を捨て科目にしないことも合格には必須です。
※なお、105投資分析とファイナンス理論は、2024年度から金融理論部分に追加で、後半のストラクチャードファイナンスの知識問題が旧101から移動して追加されました。前半の理論部分は過去問の対策が非常に有用ですが、後半のストラクチャードファイナンスの知識問題は範囲が広くなりがちで旧101で出題されたときから過去問のみで高得点を狙うことが難しい分野でした。余裕がある方はストラクチャードファイナンス部分の講義を聞いてノートを作って対策をするか、余裕ない方は割り切って過去問の知識のみで試験場に向かうのも選択肢かと思います。
おすすめ勉強方法と勉強時間の目安(約100-150時間)
不動産証券化マスターのテキストの内容は膨大ですが、試験で問われる論点は限られています。過去問のほとんどの論点は講義資料レジュメ(授業のストリーミング画面で表示される資料、つまり講師が話す内容)から出題されています。
そのため、勉強方法は、過去問を解いて試験で問われる論点を確認することと、関連する部分の講義資料レジュメを読み関連論点に対して理解をすること、基本はこの繰り返しです。過去問を解く→講義資料レジュメで論点の理解を深める(できれば、自分で論点ノートを作成する)、というサイクルを3周することが合格の一つの目安です。
実際に、ARESも例年多くの受講生が過去問を中心とした対策をしていることを認めていますし、過去問題を題材に勉強するとしても答えを覚えずに、その周辺論点をしっかり理解するようにアナウンスしています。
上記の論点をまとめる作業の時間を短縮したい方は、不動産証券化マスター試験研究会のnoteで各科目ごとに主要論点とそれに対応する一問一答という形式まとめていますので、よかったら利用してください。
個人的におすすめする具体的な勉強方法は以下です。現時点で不動産証券化業界にいない方を対象に勉強時間は約100-150時間を想定しています。
予備知識なしで過去問を1年分時間を計って解いてみる
解いた過去問の解説を読む。理解できない論点は講義資料レジュメのPDFをダウンロード*し、Ctrl+Fで文字検索をして該当箇所を読んで論点をノートにまとめる。この段階で過去問1問に15分使っても理解できなければ、印をつけて飛ばす。(*講義資料レジュメのPDFは、ARESのマイページのメニューの中にある、コース1講義資料・補助資料からダウンロードできます。)
過去問をもう1年分を計って解いてみる
恐らく、2のステップでまとめた論点の大部分を忘れてしまっていると思うので、再度講義資料レジュメのPDFを読んでノートに補強する。新しく出てきた論点も同様にノートにまとめる。
この段階までくれば苦手な科目や分野がわかるので、苦手科目に限定して講義を頭から聞く。
これ以降は過去問を解く、講義資料レジュメのPDFを見る、論点ノートに補強するの繰り返し。
不動産証券化マスターの難易度→宅建と同程度
さて、不動産証券化マスターの難易度はどれくらいなのでしょうか?不動産証券化マスター試験研究会では、宅建と同程度だと考えています。
不動産証券化マスターの問題は、不動産証券化に関する法律(金商法、不特法、投信法、資産流動化法等)と会計・税務(連結基準、導管性要件、課税方法等)など専門性が高い内容が出題されるため、不動産証券化業界にいないとイメージを持って学習することが難しいと思います。他方で、不動産証券化マスターで求められる暗記量は宅建と比べて多くなく、また一般常識で正解できる問題も多いことから、専門性が高くとっつきにくい科目で挫折さえしなければ比較的少ない勉強時間で7割の合格点を確保することは難しくないと言えます。
また、不動産証券化マスター受験生の特徴として、試験の受験に受講料約10万円の支払いが必要なので本気度が高いことと、信託銀行等の受験慣れしてる受験生の占有率が高いことが挙げられます。

以上を踏まえて不動産証券化マスターの取得難易度を宅建と比べると、不動産証券化マスターの合格率は宅建の合格率の約15%より高いものの、それは受験者のレベルや本気度の違いによるものであり、試験で合格点を確保する難易度は宅建と同じくらいといえます。そのため、不動産証券化マスターの取得難易度は宅建と同程度と思われます。
実際に、不動産証券化マスター研究会の受験生を見ても、宅建試験の対策の勉強をして合格された方で、不動産証券化マスターの対策を100-150時間程度行ったにも関わらず不合格になる方は殆どいません。
試験対策Tips
最後に、不動産証券化マスター試験の対策についてのTipsです。
講義を頭から聞かない
邪道のように聞こえますが、不動産証券化マスターの科目は不動産又は金融業界にいる方には簡単な問題も出題されるのと、上で述べたように試験で問われる論点は限定されています。そのため、頭から講義を聞いても冗長に感じてしまうのと、試験でどのように問われるかわからないまま専門的な話を聞いても頭に入ってこないと思います。
おすすめは、上記で述べたように、まずは過去問を解いてみて過去問を題材に論点を整理していく勉強法です。自分で過去問の論点を整理した上で特に苦手な科目などに絞って講義を聞くと、最初はつまらなく感じた講義の内容が意外と興味深い内容だということがわかった、ということがよくあります。
(ただ、講義を頭から聞くこと自体を否定している訳ではなく、時間に余裕のある方はまず講義の全体をノートを取りながら聞く正攻法もありかと思います。)
テキストを頭から通読しない
不動産証券化マスター研究会が観察できた範囲で、不動産証券化マスターのテキストを通読している人は一人も見たことがありません。テキストは講義資料レジュメを見てもわからない論点について、辞書的に調べる用途で使いましょう。
過去問を覚えない
不動産証券化マスターの試験では、過去に問われた言い回しがそのまま出題されることも多いですが、近年では過去問を覚えただけでは合格できないように出題者側も過去問から微妙に聞き方を変えてきているので、過去問の言い回しを覚えるのではなく過去問で問われた論点とその周辺論点を理解するようにしましょう。
試験当日は午後に集中力のピークを持っていけるように注意
不動産証券化マスターの試験は4時間の長丁場です。また、最も難しい104は午後に実施されるため、午後に力を温存しておく必要があります。
緊張感もあり午前中で疲れてしまうかと思いますが、お昼休みはあまり食べすぎると午後に眠くなってしまうため気を付けましょう。お昼に炭水化物の量は控え十分に噛んで食べる、バナナやチョコなど軽いお昼にする等もいいかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
