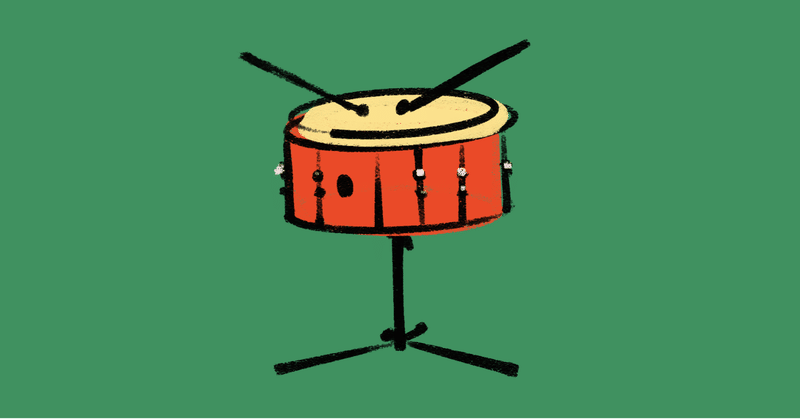
Photo by
twentynine
日本語学習支援ボランティア養成講座での学び(2)
前回の記事で予告編として載せていた内容を今回は詳しく書きたいと思う。
ボランティア講座1回目を受け、その学びをアウトプットすることで、理解の定着を目指すために記事を書く。
・モーラの等時性とは?
日本語の拍のはなし。基本は1文字に対して1拍(=1モーラ)。
例えば「にほんご」と発音した場合、リズムは一定で音の高低のみ変化がある。
そして、「マクドナルド」とカタカナで発音するとき、すべての文字の長さが均一。♪♪♪♪♪♪というイメージ。
一方英語では、「マクドゥナルズ」のように、文字数=拍数ではない。シラブルという音節単位で発音する。
ここからは私の想像だけど、この違いのために、文中にいきなり出てくるネイティブっぽい英単語は違和感があるのかな?
それが、日本人が英語を流ちょうに話すことが恥ずかしいと感じる一因にもなっているのではないかと思ったり…
そして、日本語の場合、1文字1拍というルールが前提であるからこそ、
「括弧」「格好」「過去」「加工」がそれぞれ別の単語として成り立つ。
逆に英語では、長さの違いだけで言葉の意味が異なるというものがなく、
例に出したような単語の聞き分けには苦労するそうだ。
日本でこういった文字を伸ばすかどうかだけで意味が異なる単語や同音異義語が多いのは、日本語の母音数が少ないことが要因と言われている。
同音異義語といえば、橋・箸の発音が標準語と関西弁で真逆だと知って衝撃を受けた。
関西弁で「箸が落ちた」と言ったら「橋が落ちた」ことになってしまうらしい。関東人と話すときには気を付けよう(笑)
次回は「子供の言語の定着について」書く予定。
それでは、良い週末を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
