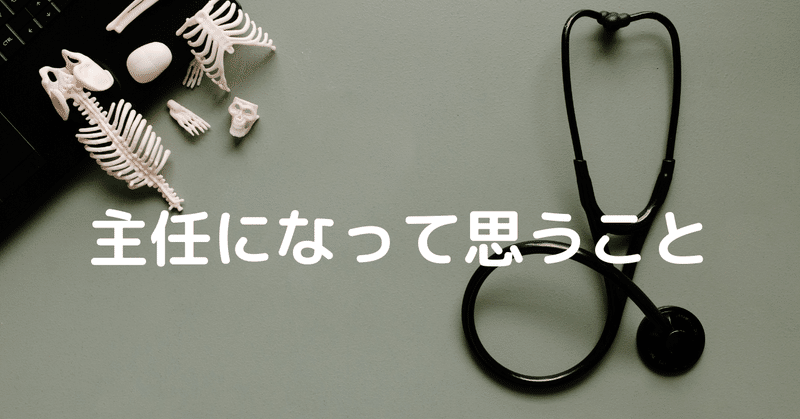
主任になって思うこと
私は約10年前に主任になりました。
同期の中では早いほうで、主任になってからのことを相談する相手は、上司でした。
自分の新人の時の主任を思い返すと
雲の上の存在で
立っているだけで、場の空気が引き締まる想いでいましたし、何か相談すれば、必ず答えが出る。
そんな存在でした。
私が思う主任のイメージは
現場の監督で、現場の責任を一身に担う、そんな漠然としたもので、とにかくがむしゃらに患者を把握する毎日でした。
昇格してしばらくの事ですが、
スタッフが、認知機能の低下した患者さんに、床に落とした薬を飲ませたと、家族からクレームが入りました。
そのことをきっかけに、ガタガタと色んな問題へと繋がり、大きな問題へと発展したことがあります。一度失った家族の信頼は、取り戻すのは難しく
医療安全を巻き込む、病院の問題になりました。
この時、病棟での緊急カンファレンスが行われたわけですが、私はとても複雑な心境でした。
病棟組織としての目線と、スタッフ側の目線。
両者の言い分がわかるからこそ、自分がどの様に発言すべきか迷いましたが、
結果、スタッフからは
「主任になったら、味方ではない」という様な言葉を受けました。
いつも現場の目線で見ていたものも、
立場が変わることで、考えが変わった自分に気づいた瞬間でした。
組織としての、どうあるべきなのか。
スタッフ側の気持ちを代弁していた一スタッフとしての自分は、そこにはもう居なかったのです。
現場がわかっている主任が発言する言葉の重みは、
この時まで、私自身が、軽んじていたのかもしれません。
私の中の軸をどちらに置くのか考えた時
私は、患者ファーストで。
そう結論づけたのことは、今も忘れません。
スタッフ教育、現場のケアのゴール、人間関係に至るまで、
全てを患者にとって良い環境を目指すことを主軸に考えた時、私の中での全ての答えが出た気がしたからです。
目の前の問題ではなく、何に向かっている組織づくりをするか。
それが重要だと、今も思います。
主任に昇格した後に
認定看護師となりましたが、
その答えが正しいものであると
今も考えることがあります。
医療は、何のためにあるのか。
職場環境づくりも、何のために頑張っているのか。
いい人間関係が築けない様では、人は看れない。
目の前で起きている問題を解決しようと考えると
その主軸が崩れそうになることがあります。
いつも一度立ち止まり、患者ファーストで考えた時、答えにつながる感覚は今も変わらずあります。
主任として私に求められていることは、
その姿を背中で見せていく。
それに尽きるわけですが、モチベーションを一定に保つことの難しさ。
どんな時でも、その信念を貫くこと。
私には、出来ることがそれしかないと信じて
毎日生きているわけです。
今思えば、私のイメージする主任は
私の上司であった方達の背中を見て
私が感じてきた何かなのだと思います。
私が今この考えに辿り着くには
その様な環境の中で育てられたことを
少し、誇りに思うのです、、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
