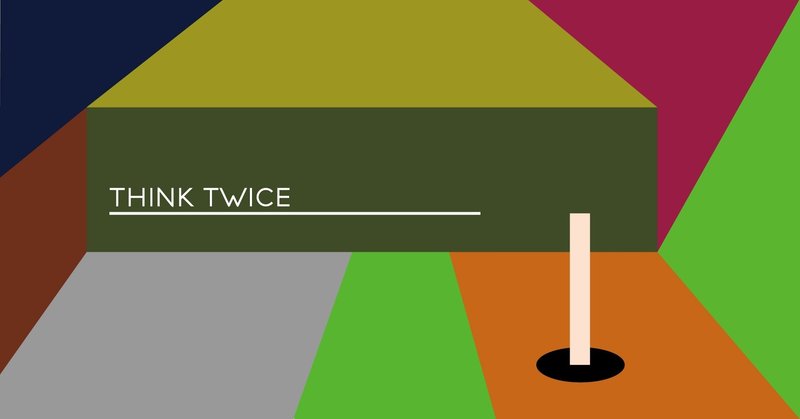
THINK TWICE 20200823-0829
8月23日(日) WE MARGIELA
アマゾン・プライムでメゾン・マルタン・マルジェラを題材にしたドキュメンタリー映画「ウィ・マルジェラ」を鑑賞。
友達の強力な薦めで観たぼくはマルジェラについてほとんど知識がなかったんだけど(男性か女性かさえ!)、独創的なリーダーを中心に、まったく新しいクリエイティヴな集団が立ち上がっていくプロセスは何より面白く、それがだんだん肥大化していき、経営が別の会社に引き継がれ、やがて重要人物が次々と去って、形骸化してしまう。
あまりにも眩しかった時間の残像に、いまも取り残されたように生きる人もいる。もちろん出演者たちは現実の人々なんだけど、まるで青春映画を観ているような気分になりました。
ファッション界って、デザイナー本人がメゾンを去っても本人の名前を冠したままで別のディレクターに引き継がれたりする(シャネルをカール・ラガーフェルドが、サンローランをトム・フォードが、マルジェラを今、ジョン・ガリアーノがディレクションしているように)のがユニークですよね。
マンガで例えるなら、手塚プロを浦沢直樹が、藤子プロを大友克洋が、赤塚プロを鳥山明が継承して、それぞれの新作を発表するようなものです。大友さんが『ドラえもん』(ドラの丸い手に番号の刺青)を、鳥山さんが『おそ松くん』(双子たちがそれぞれ玉を探しに行く)とか描くようなもの。
音楽界には、たとえばグレン・ミラー楽団みたいに、本人が死んだ後もバンドが公演活動を続けることはあるけれど、リーダーに成り代わって、新曲を発表したりすることはまず無いですからね。

劇中に、最初期のメンバーの集合写真が出てきたのですが、真ん中の列の右から2番目に「ヨシコ」と呼ばれる日本人女性がいるんです。
エンドロールのサンクスクレジットの中に「Yoshiko Edström」さんという名前を見つけました。
エドストローム淑子さん。マルジェラの代名詞でもあるアーティザナルに関わり、フランスのファッション雑誌『purple』の立ち上げにも関わってたというすごい人。現在は日本でエドストローム・オフィスというブランドPRの会社を立ち上げてるそうです。
ご主人は同じくマルジェラのオフィスで活躍していたフォトグラファーのアンダース・エドストロームさん(彼は『WE MARGIEILA』にもインタビューで登場する)なんでしょうかね。ヨシコさん、とても気になる存在です。
8月24日(月) NAKED GENERAL
日中は歩いていると裸になりたいくらい暑いけれど、夜は裸だと風がずいぶん涼しく感じる松山です。
さて、会期中に図録が完成していなかった広島の「式場隆三郎:脳室反射鏡」展で(終了から一ヶ月だったいまだに!)、ミュージアムショップに、この『山下清と昭和の美術』という分厚い本が平置きされていました。
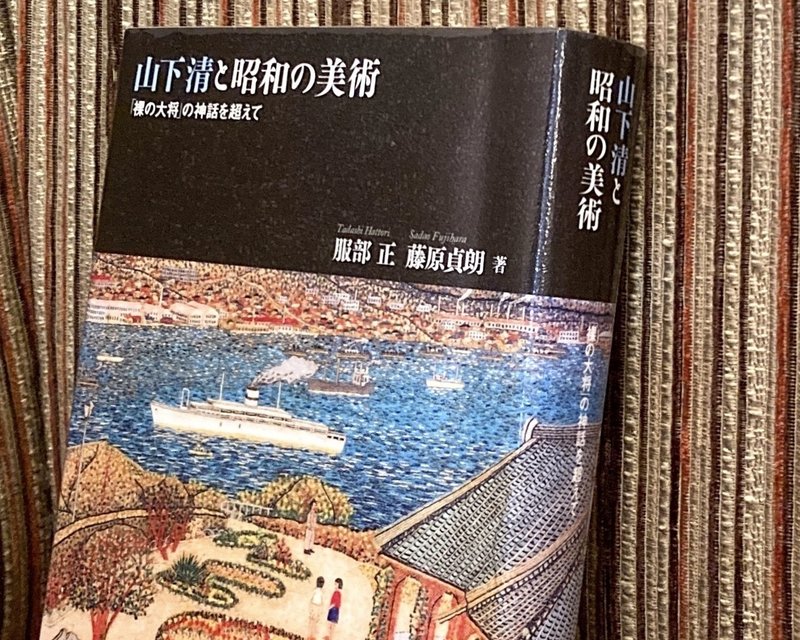
500ページ強の大ボリュームで、一ヶ月近く取り組んでようやく読了しました。

山下清といえば、坊主頭にランニングシャツに短パン。下駄履きで麻の大きなリュックを担ぎ、行く先々で施しを受けながら、気ままなスケッチ旅行を続けている、吃音で、ちょっと頭の足りない好人物───芦屋雁之助がドラマで演じた「裸の大将」像こそが、ぼくら世代のイメージそのものです。
実在の山下清は1971年に49歳の若さで他界していて、本物の彼をテレビで観た記憶もほとんどありません。また、彼を有名にしたちぎり絵の現物さえ、先日の展覧会まで見たことがありませんでした。
くだんの展覧会では、山下清と一時期、彼のプロデューサーのように関わっていた式場隆三郎についてのコーナーも設けられ、短い解説付きで山下の作品がいくつか展示されていました。
「裸の大将」とともに
大正11年(1922)3月10日、山下清は浅草に生まれた。昭和9年(1934)5月、12歳の時から八幡学園に預けられ、久保寺保久園長による子供たちの人間性を育む教育方針の中で、貼り絵の楽しみを知る。ゴッホ複製画展で成功を収めた式場隆三郎は、昭和30年(1955)に『山下清画集』(新潮社)を刊行、翌年3月に東京大丸で開いた山下清展には皇族方も来場し、80万人が見たとも言われる。以後、式場は山下清のプロデュースに尽力し、小林桂樹の主演映画『裸の大将』(1958)を監修、昭和36年(1961)には清のヨーロッパ旅行を企画・同行した。
山下や式場はこの文章からは思いも寄らないくらい激しく、芸術/福祉両方の当事者からバッシングを受けていたことを『山下清と昭和の美術』を読んで初めて知りました。その批判の言葉は、引用するのも気が引けるほど熾烈で、考えられないくらい非人道的な言葉も含まれています。
********
本来なら今頃、東京パラリンピックが開催されていたはずです(25日に開会式でしたが、来年8月24日に延期)が、義足の100メートルランナーとして無敵の強さを誇ったオスカー・ピストリウス、幅跳びのパラリンピック王者マルクス・レームのように、オリンピアンの記録に肉薄、あるいは超えるほどの能力を発揮していた選手たちも、絶えず批判や疑問の声がぶつけられていますよね。
自分の記録やライバルとだけではなく、本来ハンディであるはずの「義足」が彼らの走行や跳躍を有利にしているのではないか、という疑念とも闘っている彼らは、オリンピックとパラリンピックの世界を隔てている壁を、いまだ壊すに至っていません。
嫌な言い方をすれば、パラリンピアンたちにオリンピアンよりも劣っていてほしいわけです。身体的ハンディを持つ人々は、自分たちを凌駕するのではなく、自分たち健常者に負けないように頑張ってさえくれればいい、ただただ努力する姿を見せて、感動させてくれればいいのです。*1
*1 女子選手としての出場を議論され続けている陸上のセメンヤ選手のような問題もあります。彼女の場合、男性的な肉体を持った自己認識が女性の選手───のような紹介をされることが多いのですが、正確には性分化疾患(DSD=Disorders of DevelopmentまたはDifference of Development)というそうです。男性、女性それぞれが持っている性腺、内性器、外性器の分化がティピカルではなく発達した状態の人を指し、実は日本人の2,000人に1人がDSDだそうです。DSDの人たちの大部分は自らを「セクシャルマイノリティ」だと見做していません。
"これらの女性オリンピック選手に対する性別検査の問題は、単純に「男女じゃない性を認めよう」「スポーツの公平性を考えよう」という話ではありません。むしろ、体の構造の違いを理由に「男女の分類」を問うこと自体がDSDの方々にとっての人権侵害となり、高アンドロゲンの女性を「見た目が男っぽい」という理由だけで疑いをかけ「治療を受けない限り女としては認めない」と選手としての権利を奪ったことは、立派な女性差別となるのです。"
「インターセックスとは?DSD(性分化疾患)との違い」
JobRainbow Magazine 2020/4/6 より引用
───と、ここまで書いて、たまたまデスクに積ん読していた本『知のスイッチ 「障害」からはじまるリベラルアーツ』という本を開いたところ、まさにこのレーム選手について書かれた「障害者は障害を持つ人か」というコラムが載っていました。
すごい偶然ですが、こういうことはわりとしょっちゅう起こるので、とりわけ驚いたりはしません(笑)。
医療技術の発達によって「健康の回復と維持という目的を越えて、能力や性質の「改善」をめざして人間の心身に医学的に介入すること」も盛んにおこなわれるようになってきています。これをエンハンスメント(増強的介入)と言います。分かりやすく言うと、視力低下を眼鏡で補うのは治療で、顕微鏡や望遠鏡を使って裸眼では見ることができない視力を手に入れるのが、エンハンスメントです。しかし理論上ではともかく、実際は治療とエンハンスメントは白黒はっきりしているわけではなく、その境界線はあいまいです。例えばやけどによるケロイドをきれいにするのとしわとりはどう違うのでしょうか。どちらも皮膚をきれいにするという点で同じなのに、ケロイド治療は「治療」とみなされ、しわとりは「美容」といわれる。その差はどこから来るのでしょうか。(岩隈美穂「障害者は障害を持つ人か」)
すごく簡単にぼくの考えをまとめると、この差は「ずるい」か「ずるくないか」という、第三者が受ける印象でしか線引きできません。
試験会場にスマホを持ち込んで、時計として使うのは「ずるくない」けど、言葉の意味をグーグルで調べたり、誰かにメールで答えを聞くのは「ずるい」からダメ、ということです。義足も、眼鏡も、セメンヤさんのようなDSDの選手が男子の競技に混じってさえいれば問題視されないのです。
山下に浴びせられていた批判も同じです。
美術界からは「"日本のゴッホ"と呼ぶなどまったくおこがましい。山下清の絵には思想も深みもなく芸術とは呼べない。たしかに工芸としては巧みだが、彼が精神薄弱児だから注目されているのだ」と言われ、福祉側の人たちからは、ハンディキャップ抜きで、一人の芸術家として賞賛され、社会に認められたことに対して「式場が裏で糸を引く猿回しのようなもので儲けているのはズルい」という考えを持つ人さえ、少なからずいたのです。
山下本人(と式場)の死から10年以上が経ち、テレビドラマが作られるようになった頃には、日本全国を渡り歩く、素朴でハートウォーミングな風来坊───寅さんのような国民的ヒーローとしての山下清がお茶の間の人気者になったのは、結局、生前に浴びせられていたさまざまな批判の声が霧散しまったことが大きいでしょう。
また「裸の大将」シリーズを制作していた大阪のテレビ関係者は、関西で活躍する大喜劇役者、芦屋雁之助の当たり役(芦屋は1964年から舞台で山下清を演じ続けていた)という角度でしか、山下清の存在を見ていなかったのだろうと思います。
この本を読みながら心に刺さった「棘」のことが、あとがきにまとめられていたので、少し長いですが引用してみます。
山下の事例が障がいの否定による社会的成功であるなら、障がいそのものを肯定的に捉え、その社会的価値を高めたいと考える福祉の思想とは相容れない。障がいのある人の創作物は、現代人が失った原初的で純粋な芸術の力を示している。それは通常の芸術とは別の、あるいは通常の芸術以上の魅力を持っている。近年の障がい者アートのプロモーションはおおむねこのような前提に立っている。この「障がいのある人の創作物」という部分は、多くの場合において「エイブル・アート」や「アール・ブリュット」と置き換えることもできる。だとすれば、式場降三郎が何とか通常の美術として認めさせようと躍起になっていた山下清は、通常の美術とは別の価値を標梯する障がい者アートとも相性が悪いのも当然の成り行きだ。
私たちは本書で、山下清を位置づけるための場所を探してきたわけではない。昭和の日本美術史にも、障がい者アートの文脈にもぴたりとフィットしないこの居心地の悪さの理由について、あれこれと考えてきたのだ。例えば、アウトサイダー・アートに関係した講演会の質疑応答などで、山下清はアウトサイダー・アートかと問われることがある。服部が平成一五(二〇〇三)年に上梓した「アウトサイダー・アート 現代美術が忘れた「芸術」」のなかで、山下に触れているからでもあるだろう。しかし、同書のなかで山下は、アウトサイダー・アートの画家として紹介されているわけではない。欧米と同じような意味でのアウトサイダー・アートという概念が日本に定着しにくい理由をめぐる歴史的考察のなかで、式場隆三郎による山下清のプロデュースと、それに対する美術界の批判や黙殺を取り上げたのである。
美術と福祉の境界線上で論じられる障がい者アート/エイブル・アート/アウトサイダー・アート/アール・ブリュットからも締め出された創作者、山下清の深い深い孤独は日本の美術評論の偏向そのものである。本書では論じなかったが、それは文芸評論においても同様であろう。 山下は、多くの新聞や雑誌に連載を抱え、幾多の文集を世に送った人気文筆家でもあった。しかし、日本の近代文学史に彼の居場所はない。
ご興味のある方はぜひ。
サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰
