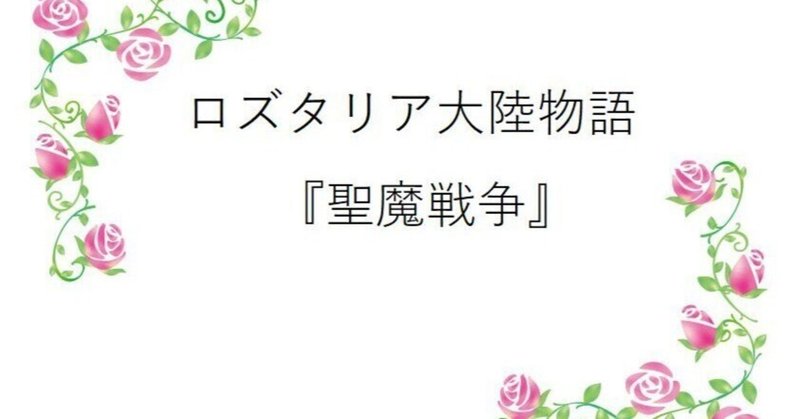
ロズタリア大陸『聖魔戦争』その12
その11→https://note.com/akihi_gfl/n/n983960ec8484
第三章 聖剣『女神の剣』
神話『創世記』
いまから約数千年前……
大陸を創造した金色の女神アイラは漆黒の男神ヘルヴィグタと夫婦神として、生きとし生ける存在全てと共に、いつまでも幸福に暮らしていた。
しかし、二千年前、ある日突然、ヘルヴィグタが荒ぶる破壊神と化してしまった。
『人ばかり優遇した結果やいかに!』
我とアイラが生み出した自然や動物を破壊するだけが【共存】ではない!
滅あるべし!!
そのように宣言すると、ヘルヴィグタは制止する妻アイラの手を振りほどき、絶するほどの怨霊と共に、数々の魔物を産み出し大陸中に放った。
大岩ほど背丈のある角のある一つ目の怪物、獅子の姿をした獰猛な獣。
二つ頭の犬の姿をして、腐敗臭を撒き散らし、その呼気を吸った人は生き絶えるしかない猛獣……など。
人々は逃げ惑い怯え、女神にひたすらすがり、祈り続けるしかなかった。
このままでは大陸自体が滅びてしまう!!
危機を抱いた女神アイラはわずかな兵力でも、未だ諦めずに戦い続ける若き人間達に、闇を祓う力を持つ神器の数々と自身の血潮を一滴、飲ませて不可思議な力を授けた。
劣勢強いられていた若者達は、瞬く間にそれら神器を使いこなし、魔物達を滅し始めた。
もはや絶滅は必須!死を待つだけの人々は、そんな彼らを『英雄!』や『勇者』『奇跡の聖女!!』などと讃え、再び希望を抱き、励ました。
志同じくする者達も続々と若者と合流し、彼らは行く村や町で歓待を受け、物資の援助や旅、戦闘の疲れ、傷を癒した若者達はついに悪神と成り果てた男神を倒し、見事冥府へと封じることに成功してみせた。
慈悲深きクラヴィス殿下
ローズテリア王国の中央に存在している、王宮のとある一室に、かつて所有財産を全て放棄して命からがら、商業都市から逃げ出した商人達が涙ながらに、目の前の人物にあまりの非道、仕打ちを嘆き訴えていた。
「おぉ~!なんとむごい!!
噂を聞きそなたらを案じておったが、耳にするほど、あまりの所業!!」
腹まで伸ばした金色の麦色に光り輝く髪を首あたりで軽く縛り止めた、一目みたら乙女が思わず溜め息を漏らし、うっとり見惚れてしまうほどの絶世の美男子が、やや大げさ気味に同情の念を表現する。
商人達をしかと抱きしめ、言葉を続ける。
「かくも非情な行い、容易くやってのける者、遥かな昔……人々を救わんと1人、立ち上がり生命賭けて戦い勝利せしめた勇者の末裔とは、私はやはりとても思えぬ。
父同様、詐称していたのであろう!!」
けれども…と大層、残念そうに首を横に降る。
「我が王国内での蛮行なれば、即座に軍を差し向け『討伐』の報いを授けることも可能であろう……」
あっ……!
商人達はそこで悟った。
自分達は【商業都市】即ち、他国での出来事。
いかに大義名分を訴えた所で、侵略行為に該当する。王国軍を動かすことは一方的に戦争を仕掛けることを意味すると……
そこまで大事は求めていない!
商人達は滅相もないと、慌てて手を振り否定する。
「も、申し訳御座いません。クラヴィス殿下……
我ら……そこまでは思い至りませんでした!!」
国王の首をはねてみせたクラヴィスは鷹揚に頷き、言葉を続ける。
「ただ、事情はそれだけではない。
宝物庫にて安置していた聖剣を手に取り、鞘から見事、白く光り輝く刀身を抜き放ち、真の主は誰か?
皆に示したなれど……」
そこで伏し目がちに己の至らなさを嘆いた。
「やはり簒奪に変わりなし!やら、聖剣そのものが贋作ではないのか?などと疑い、かつてのローゼンハイム家やローズテリア王国そのものに忠義を示す家臣は少なくないのだ」
「なんと!」
商人達は、王国領土内を完全に掌握しきれていない。意外な内情に大きく瞳を見開き、驚きの声をあげる。
「まして、シャールヴィ王子には、軍をまとめていた公爵家、そして文官筆頭である公爵家、それぞれの嫡男が側仕えしていた。
私のことを良く思わなんで当然なのだ」
下手に彼が滞在中の商業都市に王国軍を向ければ、そのまま王子の元に合流しかねない!
最悪、やはり戦となるは『必定!』
そのようにクラヴィスは商人達に説いたのだった。
急ぎ、庇護を求め、王宮に向かったものの『はて?この先どうするべきか?』戸惑う商人達にクラヴィスは、がっしりと肩を抱き、大丈夫!だと鼓舞させる。
「かつて築き上げた財を取り戻すことは『困難』なれど、なに!
そなたらには今まで培った経験と知識、人脈。
何より私の名において惜しみなき支援、確約しよう!」
ローズテリア王国で再び、商いをすればいい!
その為に必要な資金や物資は国の財が全額、一時的に負担する。
最後にクラヴィスは前髪をかきあげて、やや気取った表情でキラリ!白く輝く白い歯を見せ、笑ってみせた。
「これもそなた達が私こそが真の後継者に相違ない!
早い時期から見込み、金銭援助してくれた賜物!今こそ、その恩義に応えるが『義』というものだ」
商人達は感涙し、何度も何度も頭を下げ「ありがとうございます!」「流石、クラヴィス様!」「やはり頼って良かった!」など口々に褒めそやし、讃えたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
