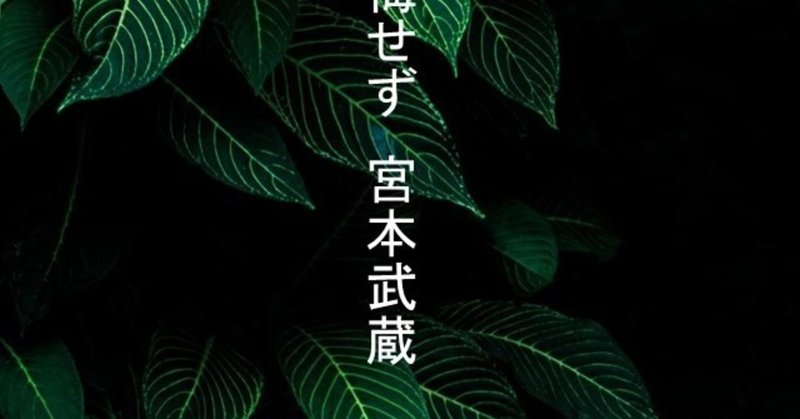
宮本武蔵の最期の言葉 戦国百人一首⑩
宮本武蔵(1584-1645)は、実在の人物である。
玄信(げんしん/はるのぶ)が本名で、武蔵は通称ということだ。
のちに武蔵の養子である宮本伊織が武蔵の菩提をとむらうために建立した小倉碑文には「新免武蔵玄信二天居士碑」と書かれてある。
剣豪で知られる武蔵だが、彼の父親の新免無二も兵法家だった。
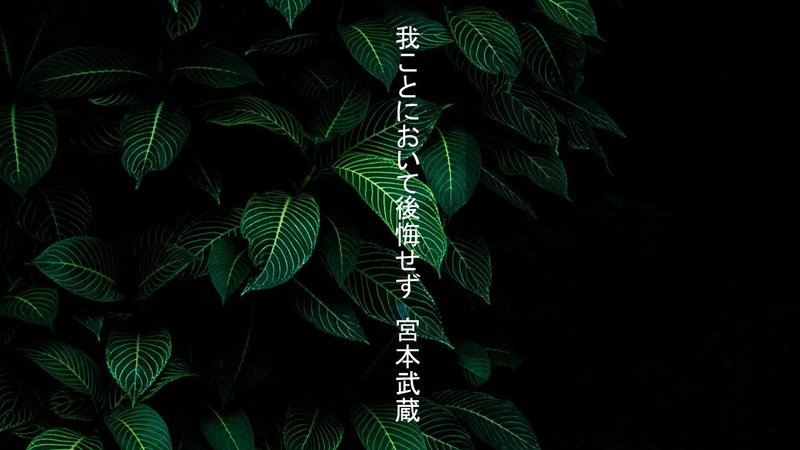
我ことにおいて後悔せず
「自分のしたことに後悔はない」
紹介した言葉は、正確には宮本武蔵の最期の言葉ではない。
『獨行道』という武蔵自分の生き方、武芸者としての心構えを21箇条にまとめたものの一説である。
彼はこれを亡くなる7日前に高弟である寺尾孫之允に、有名な兵法書『五輪書』と共に与えた。
彼としては遺書のような意味合いで渡したと考えられるので、その中からの一節を「最期の言葉」として選んだ。
彼が何を思ってそう書いたのだろうか。
その境地へ達するまでに迷った時期、後悔した事柄があったのだろうか。
例えば、巌流島での決闘に次いでよく知られる吉岡一門との決闘(1604年頃)のとき。
3度行われた決闘の最後の戦いは、一乗寺下り松(もしくは一条下り松)で行われた。
当時21歳だった武蔵が相手にする吉岡一門の大将は、なんとわずか12歳の当主・吉岡源次郎だったのである。
数百名の門弟が現場には集まっていた。
そこへ武蔵は背後から奇襲を仕掛けて、その12歳の少年を斬り捨てている。
多勢に対して一人で向かい、戦いに勝つための非情な戦法だった。
この方法でなければ、武蔵は門弟たちにやられていたかもしれない。
子供相手にも躊躇せず、最初に大将を倒したことで、吉岡一門に勝ったのだ。
勝った。
だがその勝ち方に武蔵が彼なりに悩み、苦しんだ時期があった可能性は十分にある。
13歳から29歳になるまで60回以上勝負して無敗だったという天下無双の剣。武将・黒田如水の元で1600年の関ヶ原の戦いに従軍し、1614年の大坂の陣では見込まれて破天荒武将の水野勝成客将として徳川方で活躍したと言われる。
多くの戦いを経験する中、どこかの時点で自分も相手も命を賭けるからには戦いに後悔したくない、生きるからには自分の行為に後悔はするまい、と変わっていったのだ。
そうして武蔵は剣の実力をあげると共に精神も強靱になっていった。
死を直前にした武蔵に人生への悔いはなかった。
