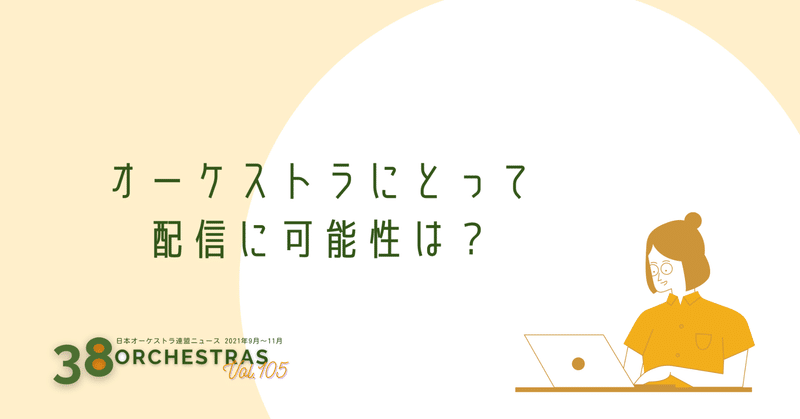
オーケストラにとって配信に可能性は?
みなさまはオーケストラの演奏配信を見たことがありますか?YouTubeやニコニコ動画などで見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
コロナ禍でライブやコンサートが中止になると、ライブ配信で音楽を届けようという動きが広まりました。その動きはポップスのみならずオーケストラでもありました。
今回は「日本オーケストラ連盟ニュース vol.105 38 ORCHESTRAS」より
生の演奏をお届けする活動をしてきたオーケストラが配信に取り組むことについて、インタビュー記事を掲載します。
オーケストラ・コンサートの配信
昨年3月、ライブでの演奏会が中止されていく中、真っ先に配信に取り組んだ東京交響楽団の辻敏 常務理事・事務局長に、配信に積極的に取り組まれてきた中で感じたことについて、お話を伺った。
―当時、どのような気持ちで配信に取り組もうと思いましたか?
辻:コロナに負けたくないという一心で。聴衆を迎えられないのなら、CD録音でも配信ででも音楽を皆さんに届けて、音楽芸術の存在意義を示したかったからです。
―配信の費用やクオリティは?
辻:オーケストラの理事の一人が運営している会社が配信にも取り組んでいて、協力いただき経費の負担なく開始することが出来ました。
オーケストラの収録経験がある方々でしたので、音と映像のクオリティはかなり良いものでした。幸運でした。(通常、質の高い画像、音声を録音し配信するには多くの機材・技術者が必要となり、高額な費用が必要。)
―当時配信を実行して、得られたものは?
辻:昨年3月にオーケストラの中では最も早く行った配信(無料)で、20万人を超える視聴者を集めたことは、音楽芸術の存在意義を示す意味では、大きなインパクトを残せたと思います。
また、この時期の配信を通じて多くのご支援・ご寄付を頂けたことも、意味があったと思います。
―今後、コロナを克服して、日常を迎えても配信を続けられますか?その課題は?
辻:年間10回程度の配信を行っていく予定ですが、よく言われるように配信することが生の演奏会の集客に悪影響を及ぼすとは考えていません。遠隔地(世界を含む)の聴衆にも聞いていただけることの広報宣伝的な意義は大きいと認識しています。
―オーケストラの収益力強化の方法として配信を考えた場合、感じることは?
辻:正直言って、配信が生の演奏会に代わるほどの収益力があるとは思いません。演奏会のチケット代よりは安くする必要があります。配信の場合は高くても平均1000円程度だと思います。これでは配信に係る経費すら賄えません。
一方配信には生では得られない面白味もあり、広報宣伝のツールの一つとしても上手く活用していけば、続ける意義はあります。ただし、協力者やスポンサーは必要ですが。
現在、私たちの収録しているものの音質や画質には満足していますが、それ以外の利用する上でのシステムのバージョンアップをしていきたいと考えています。
自宅からの参加による
アンサンブル配信 ~「パプリカ」の衝撃
新型コロナの感染が拡大し、音楽を愛する音楽家たち、聴衆の皆さんが不安の中にいた時、一つの映像が目に飛び込んできました。それがあの「パプリカ」の映像でした。
その仕掛人であった新日本フィルハーモニー交響楽団のトロンボーン奏者山口尚人さんにお話しを伺った。
―あの時を振り返ると、どんな気持ちで「パプリカ」は始まったのですか?
山口:演奏会が無くなって、何かしなければと考えていた矢先に東京交響楽団が無観客の状態で演奏会を配信しました。あれが衝撃的でした。
自分たちもやりたかったのですが、ホールの事情などあり出来なかった。そこで、家にいて集まることも出来ないメンバーを誘って、やれることを考えました。
― どうやって進めたのですか?
山口:皆が機械に強いわけでもないので、それぞれに録画して送ってもらうことにしました。最初は4人で。そうしたら、「面白そうだな」と皆が少しずつ集まってきました。
一方で、この経過を配信で見ていた一般の方も徐々に集まってきました。音楽の制作の過程が分かって、そこにドキュメンタリー的な面白さも加わり多くの人が集まってきた感じです。
― 制作していく中でこだわったことは?
山口:テンポを合わせるために、メトロノームを使う方法などがありますが、それでは各自が家で練習している音を合わせるみたいで、音楽が生き生きしてこない。
そこで皆、フーリン(小学生5人のユニット)が歌っている「パプリカ」を聞きながら演奏しました。狙いはいつものように、前にも横にも仲間がいて、合わせるという音楽的な感覚を無くして欲しくなかったので。徐々に皆が夢中になっていきました。
今であれば、もっと進んだ方法があるのでしょうが、あの時の方法は手作り感のある、皆の温かい思いが伝わる良いものだったと思います。
―誰のために、何のためにやったのですか、
どんな反響がありましたか?
山口:最初は家にいて不安な仲間が一緒になって、何か活動が出来たらと思って始めました。制作中は多くの仲間が自分の音を録音して、改めて自身の音を聞くと、それは満足できるものでなく、繰り返し練習するという現象が起きたわけです。これは良い結果をもたらしました。
また、この配信が評判になる中、オーケストラからは運営の支援のお願いをしていましたが、多くの皆さんから「パプリカ」の演奏を聞いて、オーケストラに支援をいただくこともできました。多くの皆さんから「勇気をもらった」、「感動した」などの声をいただくことも出来ました。
悶々としている自分たちがそこを脱出するために行ったことが、皆さんに喜び、勇気をもたらしたのなら嬉しいです。
―今回のようなSNSを活用した取り組みや配信の将来に向けての可能性は?
山口:伝統的な価値をこれまで引きついできたクラシック音楽が、このまま将来にわたっても続く保証はありません。
それに加え新しい聴衆を引き込むために、100人近くいるオーケストラのメンバーの持つ個性、生活感、空気感などを知ることができる手法は、有効なツールになると思います。見てくれた人が、コンサートホールに足を運んでくれれば…。単なる演奏会の配信は現状やや行き詰っているように感じます。
今、配信ですぐに収益力を上げることは難しいですが、配信には可能性があります。それは考え続ける必要があります。
(インタビュー:日本オーケストラ連盟)
