
型にはめること、括ること。
武田砂鉄さんの『わかりやすさの罪』という本を読んでいる。
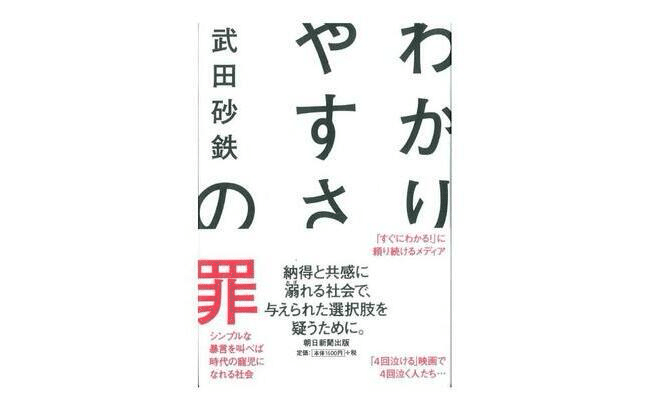
その中に、笑いに関する分かりやすさとその罪性というテーマで、明石家さんまさんの番組を例にあげて記述している章があった。
ちなみに今、手元に本がない状態でこの文章を書いているので、本の内容に関する記述は多少の正確さを欠くかもしれないが、どうかご容赦いただきたい。
砂鉄氏の論旨はこうである。
さんま御殿では、番組MCであるさんまさんが用意した笑いのパターンに上手く乗っかれるか(=さんまさんに「ハマれるか」)どうかという画一的な基準で面白さが評価される。しかし果たしてそうなのか。MCのルールにハマれないからといって面白くないと結論付けるべきではないし、視聴者がこれを画一的な笑いとして受け入れてしまうのはある種の危険性がある。
これに対する私の反応を一応書いておくとすれば、
「その通りだし、でも、面白さが保障されたパターンをなぞっていくのが、マスに広く受け入れられる番組を追求するバラエティの定石というものだろう」
で、私はこの本の批評がしたいわけではなく、この章を読んで先日見たとある番組を思い出したのだ。
それは、2月にテレビ朝日65周年記念で放送された、「MC芸人 奇跡の一夜 よくぞ集まったSP」という特番。
たまたまテレビをつけたら(我が家のテレビはいつも付いている)やっていた番組で、MCクラスの芸人たちが一堂に会した豪華なトーク番組だった。2部ではトークテーマはありつつ、かなり自由な雰囲気でトークが繰り広げられていたのだが、私はある種のスリルを感じながらこの番組を楽しんだ。

というのも、出演者はみな一様にMC芸人であるので、全員が全員、自身が普段MCを務める番組で用いてるであろう、お得意のパターンを持っているのである。それゆえ、番組の流れで誰のパターンにはまっていくのか、出演者が互いに出方を伺いながら手を打っていく。千鳥の流れが来たと思ったらホリケンさんの突飛な一言で流れが奪われ、ネプチューンお決まりの名倉さんいじりにありつき…というように、奪い奪われの攻防戦と、コロコロと潮目が変わりどこにありつくか分からない即興性は、なんともスリルがあって新鮮だった。
しかも、その場で即興で流れを作り上げて行くのはリスクと背中合わせであるはずだが、この番組に限っては全員がMC芸人であるだけに、「最終的には誰かがなんとかするだろう」という安心感もあって、いわば安心感のあるスリルで楽しめた。
ちなみに、この番組にはサンドイッチマンとバナナマンは出ていなかったのだが(この二組はテレ朝ではMCをやっていないのかしら)、サンドイッチマンとバナナマンは、とりわけMCとしての自分たちの色が薄いというか、MCを務める上での決まったパターンというものがあまりないように思う。だからこそ、どんな番組でも企画の持ち味を潰さず、趣旨に沿って進行が出来るということで引っ張りだこなのかもしれない。バラエティでは自分たちの色を消し、単独ライブやラジオなどの自陣で本領発揮する。こっちのプロフェッショナルの在り方もある。
脳盗で1月から2月にかけて放送されたTaiTanさんvsTBS局員の三部作は、まさに「型にはめる」というテレビの定石がその他のフィールドに持ち込まれることによって有害性を発揮した例だと思った。
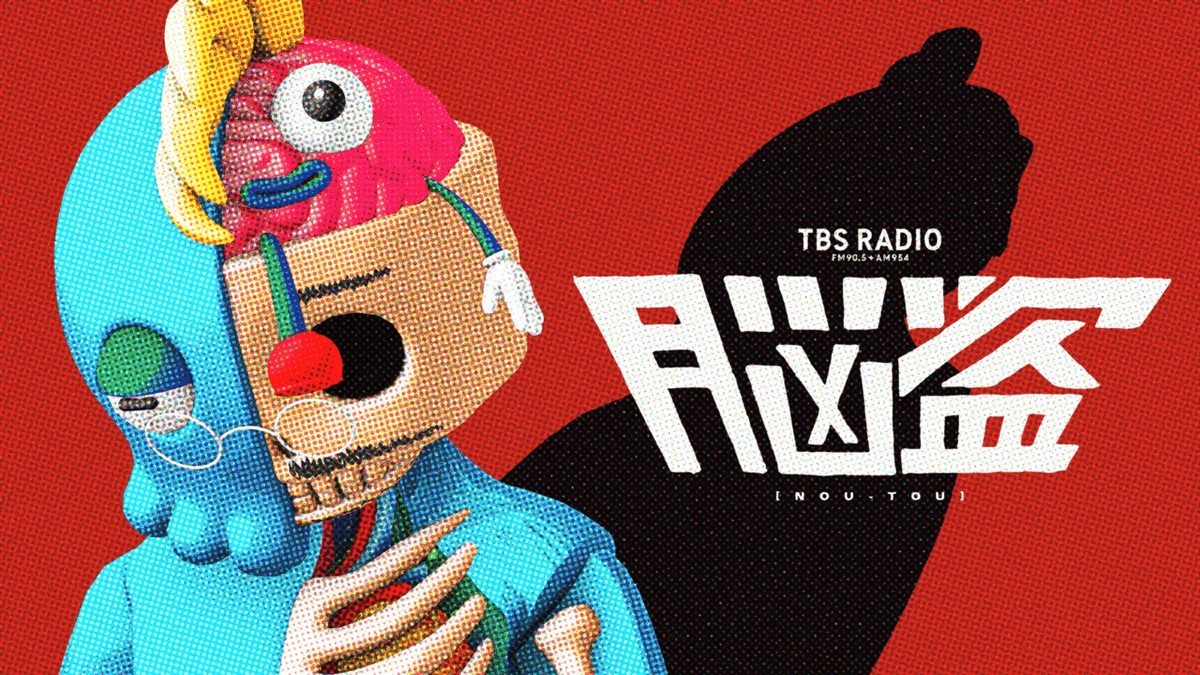
詳しいことはYoutubeでその時の放送を聞いてほしいが、ラジオ王を目指すTaiTanさんは妻の存在を公言するべきか否かという議題から始まり、話は恋愛が出来ないルサンチマン諸君とその弱さを愛でるパーソナリティの在り方や、脳盗のリスナーはサブカルオタクなのか、というところまで終始緊張感のある空気で両者の意見が飛び交った。
TaiTanさんがテレビ局員に向かって「あなたは人を括りすぎだと思う」と言ったが、私がテレビ局員に感じた全ての違和感もそこに集約されるように感じた。
ラジオ王になるためには、恋愛下手なルサンチマン諸君と同じ目線に立って理解を示す態度が必要なのかどうかという議論は一旦置いといて、あの局員さんは、人を「ルサンチマン」「サブカル好き」といったジャンルで括ったり、「悪者vsヒーロー」や「ルサンチマン諸君とその頭を撫でるラジオパーソナリティ」といった既存の構図に当てはめることが習慣化しすぎているように感じたのだ。テレビ番組ではそれで面白さが確約されるのかもしれないが、現実を型にあてはめ、粗く捉えてしまうのはあまりにも暴力的だ。
これはテレビっ子として育った自分自身に対する自戒でもある。テレビ局員が、TaiTanさんに詰められた際に「安心できる喧嘩」に持ち込もうとしたその立ち回り。正直、かなり既視感があった。自分でもやったことがある気がした。私は、知らず知らずのうちにテレビ的な価値観を植え付けられているということに危機感を覚えなければならない。時にはそれがコミュニケーションをスムーズにしたり、雰囲気を良くしたりするかもしれないが、そこにある暴力性には自覚的でなっきゃいけないし、テレビ的なフレームと現実とを混同してはならない。
「型にはめる」的な繋がりのまた似た話でいえばMBTI診断はすごい勢いで市民権を獲得した。あれは何なんだろうか。いつか読んだ文章で、「多くの人間は人とは違う存在でありたいと願うが、彼らが目指すユニークな存在とは、あくまでも既視感のあるそれである。つまり人間は、周りの人とは違うことを望みつつ、人と同じことに安心感を覚える生き物なのである」的なことを言っていた気がする。どこで読んだなんの文章だったのかは全く思い出せない。この仮説に沿って理解するならば、1/16のユニークさを持てることに人は喜びを覚えるか。
でも、この「型」もまた、暴力的に用いられる可能性は否定できない。
擁護者ならば、こうしてくれるだろう。
討論者だから、こういう人間だろう。
MBTI診断は人を簡易的に16種類に括るが、人って、性格って、そんな線を引けるものじゃないでしょう。
でも思い返してみれば、人を型にはめることで距離を測るという行為は、ごく日常的に行われている気がする。というか、私もこれをやっている自覚がある。初対面の人に対して「あぁこの人苦手だな」って思ってしまうのは大抵、目の前にいる人のどこか一要素が「私の苦手な人物像」に当てはまってしまうからある。そう思ってしまった途端、その人のことを多面的に見ることを諦め、かくして距離を取るようになってしまう。かなりよくない態度だ。
市原佐都子さんの『バッコスの信女―ホルスタインの雌』で突き付けられる問いの如く、自分という人間が内包する暴力性に自覚的でありたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
