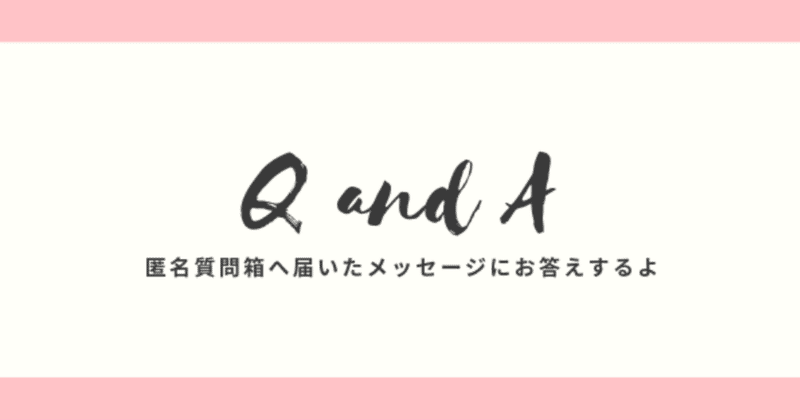
英日ゲーム翻訳と"キャラ性"・前編
昨日、このようなマシュマロを頂きまして。
こんにちは! ご質問ありがとうございます。日本語と同じ形式ではありませんが、英語でも"キャラ性"(馴染みがない言葉なので 使い方あってるか分かりませんが)をイメージさせる手法、いろいろありますよー。#マシュマロを投げ合おうhttps://t.co/5ivUpICDVc pic.twitter.com/PlgkpGj5ym
— かわばたあい/翻訳家 (@ai_prami) December 12, 2019
※と、Twitterのつぶやきを貼りつけてみましたが、質問文が画像になってしまっているので、読み上げパソコン等用にタイピングもしておきます:
こんにちは。言葉における性格のニュアンスについての質問です。日本の漫画では、一人称だけでも 僕・俺・私・アタシ(片仮名)・あたし(平仮名)・ワシ…などあり、それぞれでイメージさせるキャラ性が違います。さらに語尾 ~ですわ(お嬢様) ~ねぇか(ちょっと柄がわるい)など、さらにキャラ性を表現する場合がありますが、英語でもこのような表現はあるんでしょうか?また、先ほどのようなキャラ性を表すセリフの翻訳はどのようにされているのでしょうか?
では、今の私が答えられる範囲ということで、ゲームの英日翻訳に絞って書いてみます。
まずご質問内容ですが、以下2点ですよね。
Q1. 英語でも、日本のマンガのような(=直接的な/記号的な、と解釈して良いのかな?)"キャラ性"描き分けの表現があるかどうか
Q2. ↑こういったセリフの翻訳はどのようにしているのか(『どのように』の厳密な意味はこちらで解釈します)
…ご質問文の流れを見るに、Q2は「日→英翻訳」の場合を聞かれているような気がしないのでもないのですが、いかんせん私の専門は「TL(Target Language = 翻訳先の言語)が日本語」のゲーム翻訳、なので、そこはご勘弁を。
では回答、今回は前編ということでQ1について述べます。
免責事項
多くのゲーム翻訳家は(今のところ慣習として?)関わったゲームタイトルについてNDA(non-disclosure agreement = 秘密保持契約)を結んでいます。
そのため以下、例として挙げた英文はすべて本記事のために新規作成したものです。酷似する、あるいは偶然同一の表現が存在するおそれもありますが、あくまで既存の各種作品とは無関係であることを予めご了承ください。
セキュリティ上、ひとつの案件が終わったら、関連資料や原稿は返却か破棄をしています。そのため、この記事の例文は以下に挙げるパターンに沿ってはいますが、自作です。学校のテストとかで真似してバツもらった!とかいう苦情もやめてね。でもそうなったらごめんね、細心の注意は払ってるけども。
では本文!
※ご質問文中の"キャラ性"という言い回しにあまり馴染みがないので("character"の第一義が『性格・性質』なので、なんだか『性質の性質』と言っている気分)、とりあえず「登場人物の描(えが)き分け」と解釈して進めています。違っていたらごめんなさい。
Q1. 英語でも、セリフに人物の特徴が表れるような表現があるかどうか
――A1. 日本語ほど直接的ではないにしろ、ある、と言って良いと思います
a. 間接的に表出する例
「日本語ほど直接的ではない」というのは、おそらくご想像のとおりです。一人称はみーんな I ですし、話者が例えば軍の司令官であったり、中世ヴァイキングの猛々しい戦士だったりすれば、言葉遣いで性別を判断することも難しい。(ついでに、ゲーム翻訳に慣れていない方は、なぜか "Commander", "Warrior", etc.=男、と思い込んで訳しがち。)
【余談】ゲーム全体の舞台設定やストーリーのあらすじをまとめた資料も、ふつうは原稿と一緒についてきます。今までお仕事をした会社さんでは、いずれも LocKit(ロック・キット=ローカライゼーション・キット)と呼んでいましたが… たぶんこれが一般的な名称なのかな? ともあれその LocKit にキャラクターbio が載っていることもあります。
そして性別は、原稿で話者以外のセリフを読んでいけば分かることもしばしばです。たいてい代名詞(he や she)にすぐ置き換わるので。(ずっと she で呼ばれてるけど彼女の喋り方なんか変だな?と思ってたら『マザーコンピュータ』だった、みたいな SF世界の例外はありますが。)
あとは年齢も、主人公と関係性が近ければ近いほど分かりやすいです。「○○アカデミーの同級生→たぶん10台後半だな」とか。
以上のことを逆に見れば、
話者のセリフ「のみ」で"キャラ性"が分かるような例は少ない
と言えるでしょう。
年齢や性別といった、かなり基本的な情報ですら別途資料を見たり、クライアントに問い合わせたりしなければ断定できないのですから。
英語からの多言語一斉ローカライズ・プロジェクトの初っ端に、日本語やスペイン語・ドイツ語 etc.(要は名詞に性がある言語)のチームがこぞって質問を投げ、後日やっと「全キャラの性別・年齢・人種・ひとこと自己紹介・開発中でも画像があればそのスクショ」などをまとめた表が送られてくる… というのは、割とよく見る(やる)流れだったりします。
※慣れた開発会社さんは、早見表をあらかじめ別添してくれたり、原稿の「話者名」を「生存者A」等でなく「生存者A_female」などとしてくれます。
b. 話者のセリフ単体で分かる"キャラ性"
こちらの場合は、もっと深い、その人の「本性」や「教育の程度」、「会話相手との関係性」などが多い気がします。
とりあえず、ここ10年ほどで携わった30タイトルくらいから、印象に残っている例を7パターン挙げます。
ア) 否定文がことごとく ain't
are not はもちろん、am not, have not までもぜーんぶ ain't。別に文法上間違っているわけではないのですが(お手元の辞書をご覧ください)、やはり垢抜けない印象はあるようです。
イ) 三単現が使えない
Yes, he do. とか she don't understand. とか。
これはほぼ間違いなく無教養キャラ。ア)との併用も多いです。役名"Thug"となっているモブは、モブなだけに基本は下っ端の小悪党なのですが、たまーに敵対組織の中堅どころだったりします――が! ア)とイ)が揃えばまず安心(?)、十中八九ただのチンピラ。
あとは逆に、あえて無個性な訳になるよう気を付けるだけ…『龍が如く』で桐生に「出てこんかい!」的なことをムービーで叫ぶ(そして即ボコられる)だけの立ち位置… 西田(極で真島組にいた人)だとちょっとキャラ立ちすぎ… 抑えろ、抑えろ私…(基本的に翻訳していくと全キャラに思い入れが出てくるので、このへんの割り切りには毎回苦労します)。
【余談】it is の略 it's と、所有格 its をあえて間違えてあるのもよく見ます。一方、絶対と言っていいほど目にしないのは、「冠詞や、名詞の可算/不可算に関する間違い」。ここは本当に英語という言語のコアというか、英語を母語とする人の世界観の土台なんだなぁと、折に触れて感じます。
ウ)単文が多く、やたらぶつ切りで話す
「いっそ関係詞使ってくれ! 分かりづらい!」とSL(=Source Language. 原文の言語)非ネイティブの翻訳者でさえ思うような喋り方をするキャラ。徹底したケースでは "as ~" や "Although ~" などを使った複文さえ避けてある。
●ひとまず3パターン。以降は本人の性格・知性に加え、「キャラ同士の関係性」「発言時のシチュエーション」が関わってくるタイプです。
エ) 単語の綴りがくだけている/その他、表記が独特(可読性ギリギリを攻める勢いで)
・前者の例: you→ya、no→nah、~ing→~in'、them→'em
⇒イメージ: ざっくばらん、もっと言えばガサツな性格かも。
ただし「標的追跡中の兵士1」が "Got ya!" などと叫ぶのは、立場と状況による早口にすぎないので、粗野な言葉遣いにしないよう注意。
また本人の性格とは関係なく、単に相手と仲が良いのでくだけた喋り方になっている(そしてそれを脚本の表記に反映している)ケースも多い。
・後者の例1: 普段はひどく弱気なキャラが勇気を振り絞って発言↓
I... I, I lo.. llllove, her!(か、かか彼女のことが、だっ、大好きでっっ…!)
・後者の例2: 並々ならぬ敵意を抱いている相手に言及して↓
I.WILL.BEAT YOU!(絶ッッ対にぶっ○す!)
どちらもポイントは、「ふだんは『ひどく』弱気」、あるいは「『並々ならぬ』敵意」、というところです。
例1は、まず綴りが崩れているのはもちろん、普段なら読点が入らないところに入っています(基にしたセリフにはもっと難しい単語が使われていたので、当初『なんだろこの文字列…?』となった記憶があります)。
例2は、いわゆる「魔物に村焼かれた」レベルの怒りです。普段から気性の荒い人物であっても、ここまで大文字全開・句点大暴れで叫ぶ場面はなかなかない。逆に同じ目に遭っても、みんなが皆これほど爆発するとは限らない。なので一度でもこうした「壊れた」表記で憤怒を吐露したキャラは、他の、普通に綴られているセリフもやや勇ましい口調に寄せたりします。
他に見たことがあるのは、マッドサイエンティスト的なキャラのセリフが、上のようにしばしば句点で区切られているパターンです(大文字小文字のルールは文法どおり)。この場合は「マッドサイエンティスト」という背景に鑑みて、全体的に大言壮語となるよう調整しました(実際に難しめの単語を使ってた、という理由もありますが)。
オ) Yes/Noクエスチョンが「(日本人が学校で習うような)ふつうの疑問文、もしくはスタンダードな付加疑問文」でなく、「平叙文+"huh?"等 」の構成になっている
例1-1: This is all ya got, huh?(これがアンタの全力?/フルパワーでこのザマ?/その程度か。)
例1-2: Bet you thought that you won, eh? (『やったか!?』とでも思ったー?)←主語が省かれると、よりおちょくってる感じ(私の主観かも)。
例文のクセの強さは見逃してください。なにせ基がゲームなので(今さら)。
この2つは敵のセリフでしょうが、仲間内でも同様のやりとりはあり得ます。その場合はエ)と同じく、「かしこまる必要が無い間柄」ということになります。ケンカ中かもしれないけど。例を3つ挙げます。
例2-1: You know what the stuff does, right?!((機械か何かの)使い道は分かってるわよね?!)
例2-2: You're kidding me, right?(ウソだろ?/本気じゃないよな?/冗談だろ?)
例2-3: It's been hurting, no?((怪我を)ずっと我慢してたでしょ。/ホントは痛いんだろ?)
↑ no? は right? に比べて、「自分には全部お見通しだけど一応確認しとこうか?」というニュアンスが強まる気がします。
●ここまでは、ご質問文の言い方を借りるなら「ちょっと柄がわるい」感じの例が続きました。残り2つは"キャラ性"が変わります。
カ) 使ってる単語が固い・小難しい、言い回しが大げさ、時にキザである
例1: [大意] お前の負けだ!
→[ふつう] You lost! / You failed!
→[キザ] You've colored me triumph!(あなたは私を勝利で彩ってくれました!/引き立て役、ごくろうさま!)
例2: [大意] 話し合おう。
→[ふつう] Let's have a talk about it. / We need to discuss it. ※後者はちょっとシリアス
→[キザ] Are you interested in having the privilege of conversing with me?(この私と語らう栄誉に与りたいか?)
最後の人に食い気味でNoって言いたい。
そんなわけで(?)ここからは所謂「頭が良い」キャラ、あるいは「高飛車な敵キャラ」をイメージしていただければと思います。
上の例文は、自分でもちょっとやりすぎた気はしますが、とにかくメインの動詞・名詞の「普通はもっと簡単な語使うだろ」感がキーです。
例1なら lose、というか win を triumph に変換。
例2なら talk → discuss → converse の順に固く。
あとはひたすら長ったらしく…でしょうか。文型も関係あるかなぁと思ったのですが、少なくとも自分の経験内ではハッキリしたものを掴めませんでした。一言で何か言えたら面白かったんだけどな。
キ) フランス語、ラテン語の単語をそのまま使う
Entrée(オーントレイ //仏語: 料理の『メインディッシュ』)、déjà vu(デジャ・ヴ //仏語)、et cetera(エトセトラ //ラテン語)…日本まで伝わっている表現もたくさんありますので、通常の英会話であれば「ふつうの人」が使っていても特に違和感はないと思います。
ただ少なくともゲーム内の人物描写としては、この項に当てはまるキャラが上記ア)やイ)の層とかぶる、ということはまずないでしょう――and vice versa(and バイス・バーサ //ラテン語: 『逆もまた然り』)。
* * *
以上、急ごしらえの記事で恐縮ですが、ひとまずパッと思いつく分をまとめてみました。つまり
【まとめ】日本語と同じ形ではないし、重視する点もやや異なるが、英語で"キャラ性"を表現する方法はいくらでもある
というのが私の意見。重視する点が異なるというのは、例えば日本語のように、ひとつのセリフを読んだだけで話者のジェンダーが分かるようなケースは少ない、という意味合いです(脚本上の話ね。声が入ればそりゃ一発で分かるので)。
Q2の「そのへんの翻訳」については後編で。ではではっ。
よい一日を、お過ごしください(*^▽^*)
