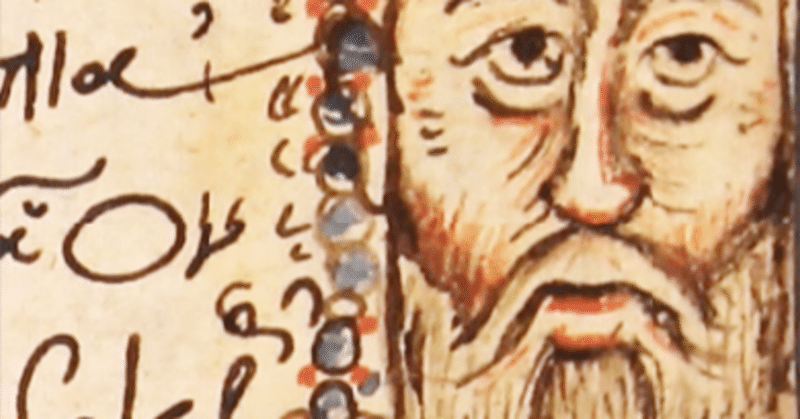
ホロノグラフィア 第二巻 コンスタンティノス八世
ミカエル・プセルロス Μιχαήλ Ψελλός (1017年か18年生まれ、1078年没)の『年代記 Χρονογραφία 』の訳、第二巻、コンスタンティノス八世
1.
バシオリスの死後、弟のコンスタンティノスが二度目の帝位に就いた。バシリオスは死ぬ直前に、コンスタンティノスを王宮に呼び寄せ、王権を託していたので、誰もがコンスタンティノスが王座に上ることを承認した。コンスタンティノスは、七十歳の時に、帝国の統治をすることになったのだった。彼の性格は至って温和であった。彼の心は楽な方へ流れていたのだった。それだから、金で溢れかえっている帝国の宝庫がいくつもあるのを見ると、自分の生まれながらの傾向に従って、身も心も様々の遊興に没頭したのだった。
2.
歴史的な伝承では、彼の人物像を次の様に私たちに描写して見せている。理解が遅く、権力には頓着していない。「屈強な体躯であるが、臆病な精神である」。その上に、既に老年になっていて、遠征に出ることは出来なかった。そうした分けで、悪評を聞く度に、激怒していた。そうであっても、私たちの周囲で機会を窺っている蛮族のどれかが、たとえそれが少しであっても、軍隊を動員していれば、賞を与えるか、贈り物を提供するかして、その動きを止めていた。
寛大さではなく、ありとあらゆる報復的な拷問で国民を服従させていた。彼の様な人物は他には少ない程、怒り易かった。怒りに捕われていて、彼への反抗が疑われることに関わっていれば、どの様な噂でも易々と耳を貸すのだった。こうしたことが契機になって、彼は、哀れな彼の犠牲者たちを無慈悲に罰したのだった。軟禁や追放、あるいは、牢獄へ収監すると言うことはなかった。暫く留め置くことはなく直ぐ様に、灼いた鉄で目を抉り出したのだった。その刑罰を誰にでも例外なく適用したのだ。軽い犯罪の犯人だと思われていても、重大な犯罪でもだ。しかも、軽い犯罪の者については、それが初めて犯罪を行なった者でも、重大な犯罪の者については、ただ彼の犯行だと思われているだけの者でも、等しく適用したのだった。
彼は、犯罪の重さに比例して刑罰を課すと言う手間は取らなかった。彼が心を配っていたのは、ただ、どの不安への気掛かりも無くしてしまうと言うことだけだったのだ。実の所、彼は、失明の刑罰は全ての刑の中で最も寛大な刑だと言う考えを持っていたのだ。失明の刑が罪人を無力化すると言う観点から、秩序立てて考え、この刑を選んだのだった。その上、貴族から最下層の国民まで決まって同じ刑を適用したのだ。また、刑事方針を拡張し、聖職者の領域まで及ぼすのに、時間は掛からなかった。それが大主教であっても遠慮することもなかったのだ。一度、激怒すると、平静に戻るのは中々難しいのだった。況してや、それが誰のであっても、忠告を聞き入れることは、尚、難しいのだった。
しかしながら、彼はひどく短気ではあったのだが、慈悲の心を全く失っているのではなかった。災害の被災者たちを前にすると、心を痛め、涙ながらに彼に物語る人々に対しては、同情心のある振る舞いをしたのだった。彼の怒りは、兄のバシリオスと同様に、宥めることは出来ないものであったけれど、すぐに治ってしまうのだった。そうして、自分のしてきたことに対して、深い悔悟を示して見せたのだった。更に、もし誰かが彼の怒りの炎を消すことが出来たならば、彼は全く拘泥しなくなり、どんな刑罰のことも忘れてしまうのだった。その上で、自分を制止してくれた者に感謝の言葉を掛けるのだった。
反対に、制止する者が誰もいない時には、怒りは度を越したものになるのだった。ところが、弁明が始まると直ぐに、彼は、自分の犠牲者たちに同情し、その者に愛着を覚えて抱きしめると涙を流して、悔恨の言葉を述べて許しを乞うのだった。
3.
また、彼は、すべての皇帝の中で最も雅量に富んだ人物だった。ただ、彼の贈賜品は、公正な気持ちに導かれて出したものではなかった。コンスタンティノス帝は、慈善放出を行い、金を砂の様に積み上げて見せたのだった。ただ、この慈善は、彼を取り巻いている人々だけに与えられ、王宮から遠く離れている人々には、彼の美徳は示されていないのだった。加えて言えば、彼を説得するのは、主に、幼年期に性器を切除した者たちだった。コンスタンティノス帝は、その者たちを、去勢の後、侍従や王宮の使用人として使っていたのだ。
この侍従や王宮の使用人たちは、貴族の出身でもなく、自由人でさえなかった。蛮族の出身で異教徒だったのだ。けれども、彼らはコンスタンティノス帝に教育を施されており、帝自身の性格を手本に作法を身に付けてきたのだからと言って、他の誰からでも、最大の尊敬と高い評価を求めたのだ。蛮族の出身で自由人でもなかったにも拘らず、この者たちのそうした恥ずかしい面は、見事な精神の所為で隠されていた。彼らは、物惜しみせず金に執着しなかったのだし、熱心に慈善事業を行い、極めて高貴な所作をしたのだからだった。
4.
コンスタンティノスがまだ若い時、即ち、兄のバシリオスが王であった時、彼は、最も高貴で誰もが尊ぶ家の出身の女性と公式に結婚していた。その女性はエレニーと言い、その当時高く評価されていたアリピオスの娘だった。美しく高潔な女性だった。コンスタンティノスに三人の娘をもたらした後、亡くなった。
そうして、彼女が与えられた時間を生きこの世を去るまでの間、彼女の娘たちは、王宮の中で、皇帝としての躾けと教育を享受したのだった。バシリオス帝は、彼女たちをとても愛していた。優しく気遣っていたのだ。彼女たちの将来については何の親切なこともしなかったのだが、それでも、権力から遠ざけていた弟に彼女たちの養育を任せてはいたのだ。
5.
娘たちの中の年長の娘は、家族の他の者たちと似ていなかった。彼女は、子供の時の何かの疫病の為に顔にしみが出来ていて、あまり美しい女性ではなかったのだが、優しい性格で、大変に優雅な所作を見せていた。真中の娘は、その方には大変高齢になられた時に私自身が会ったことがあるのだが、威厳のある美しさ、堂々とした立居振る舞い、多くの尊敬を受けていると言った、皇帝としての風采に於いて抜きん出ていた。この女性については、私の歴史書の後の方で、細かな所まで叙述を広げようと思っている。ここでは、姉妹全員について、概略を述べる。三番目の娘は、背が高く、流暢であったけれど無愛想に話した。そして、姉程には美しくなかった。
皇帝であり彼女たちの叔父であるバシリオスは、彼女たちが王位へ上がる為の用意をすることなく死んでしまった。彼女たちの父でさえ、王座に登った時にも、娘たちの将来について懸命な備えは何もしなかったのだ。真ん中の娘は別である。彼女は威厳があったのだ。ただそれも、彼の生涯の終りになってからであった。そのことは、私のこの歴史書の後の方で明らかにする積りである。無論、このコンスタンティノスの次女と三女は叔父と父の考えに賛同していて、何の野心も持っていないのだった。
けれども、エウドキアと言う名前の長女は、権力に無関心だったか、天上に憧憬していたかで、神に身を捧げさせてくれる様に父に嘆願したのだった。彼は反対せず承諾した。娘を、彼の身体から生じた娘を、犠牲として神に捧げたのだった。残りの二人の娘に対しては、コンスタンティノスは、自分の意図を全く明かさないままでいた。ただ、私はその事についてはまだ触れる積もりはない。
6.
私の歴史書が目指しているのは、皇帝の性格をその行動に於いて、誇張することも過小することもなく叙述することである。そこで、帝国の統治の全責任が彼に委ねられた時、彼は、この厄介な事柄に自分自身すべてを費やしてしまう様な人間ではなかった。それだから、問題のすべてを何人かの賢者に任せて、自分自身は、外国の大使に謁見するか、簡単な案件を少しだけ扱うだけだった。そうして、目を瞠る様な威厳のある風体で玉座に座っていた。
それでもやはり、口を開いて演説すると、その度に、彼の論理と論証で聴衆を驚かすのだった。彼が佳良な教育を受けていないことは確かだった。実際、小さな子供が正確に知っている程のギリシャの学問の知識しかなかったのだ。けれども、彼は、生まれ付き優雅であり、また器用な人物で、幸いにも、柔らかで美しい声音で、彼の魂から発せられた考えを述べることが出来、また、そうした考えを印象的な言葉で表現することが出来たのだ。そうして、公式な皇帝の書簡の幾つかには、彼自身の言葉を口述筆記させようとしたのも事実だ。と言うのも、自らの言葉を筆記させることが、権威に関わると彼は考えていたのだ。
ところが、これまでの例には殆ど見られない様な、有能な筆記者たちを、それも多数配置することが出来たのにも拘らず、その中の最も速く書ける筆記者でさえも、彼の口述の勢いには追い付くことが出来なかったのだ。彼の言葉の速さにたじろいだ筆記者たちは、大量の意味や言葉を暗示するある特別な記号を考案したのだった。
7.
彼の体躯は巨大だった。九ポディアの高さがあったのだ[ 2メートル70センチほど? ]。自然は、彼に何でも溶かす胃と信じられない程の消化能力を与えていたのだ。そして、薬草に関する技能の一廉の専門家になっていた。様々な色や薫りを組み合わせた独創的な料理を供していたのだが、それは誰でもの食欲を唆ったのだった。
大食と止まることのない好色の所為で、結局、身体を壊し、重い関節炎に苦しんだのだった。両足を甚だしく痛めさせるので、歩くことも出来なくなっていた。この病気が理由なのは確かだろうが、彼が王座に就いて以来、誰も彼が自信有り気に足を動かそうとするのを見ていないのだ。彼は常に馬に乗るのを好んでいた。馬上ならば、全く安全に座っていられるからだ。
8.
一方、コンスタンティノスが一番に熱中したのは賭け事、競馬だった。競馬のことばかり考えていて、馬を交換し再度交換しては、馬が走り出すのをひどく心配しながら見詰めていた。ギムノペディアの競技[ 一対一で対戦するレスリングの様な競技 ]は、長年避けられていたのだが、彼一人が手配をして、競技場へ再度持ち込んだのだった。そして、皇帝としてただ観戦するのではなく、一人の競技者として参加したのだった。その上に、対戦者たちが自分が皇帝だからと言って故意に負けるのではなく、自分に対して全力で戦うことを希望したのだった。そうすれば、より輝かしい勝利を手にするからと言うのだった。
そして、それだけでは飽き足らずに、更に、試合について延々とお喋りをし、遂には、一般庶民とも会ったのだ。それでも、競馬を一番好んでいた。では、狩りについては何か言われているだろうか? 彼にとっては大したものではなかった。重要だとは思っていなかったのだ。猛暑も寒さも喉の渇きも彼には恐れるものではなかった。野生動物を狩る一廉の狩猟家であったのだ。弓矢、槍、剣の技術を既に身に付けていたからだった。それ故、何も逃さないのだった。
9.
皇帝の職務を等閑にする一方で、一層、賭け事と勝負事に熱中したのだった。実際、賭け事にひどく熱中し、自分の試合に熱くなっていたので、彼の遊び事が終わる前に到着してしまった大使たちは彼を待っていたのだが、コンスタンティノスは、彼らの任務には全く関心を示さなかったのだ。
彼は、昼も夜も遊びに興じて、身体のなくてはならない機能までも蔑ろにする様になったのだ。実際、食べ物は何でも貪り喰らう彼であったが、遊びたいと思うと、全く絶食するのだった。最期には、賽子賭博で王権を賭けていた時に、死が彼を攫って行ったのだった。その時には、自然の法則でそうなるのは必定なのだが、老いが彼を抱き竦めて、痩せ衰えさせていた。
評議員たちが彼を説得出来たからなのか、自身が自分は玉座にいると理解したからなのか、兎も角、最期が近づいていると思う様になった時になって初めて、自分の後継者を探し始めたのだ。その者に真ん中の娘を嫁がせる算段だった。けれども、これまでと同様に、元老院の誰かに一瞬の眼差しを向けることさえも軽視していて、理に適った選択は彼には甚だしく難しいのだった。
10.
コンスタンティノスが考えていた人物たちの中に、当時、他の元老院の者たちよりも抜きん出ていて、行政官の長に昇進していた者がいた。だが、「帝国の原則で、緋色の衣は着られない」のだった。彼は、子供であった時に結婚していて、それ故、玉座に就く有望な候補者の中にあるとは思われていなかった。彼は、確かに、家柄と身分の点では、他の者たちよりも適切な人物だった。けれども、彼が結婚していると言うことは、彼に可能性をあまり残してはいなかった。また、これから彼が皇帝と合意すると言うことは、少なくとも世間の目には、様々な問題が見えていたのである。
しかしながら、コンスタンティノスが陥った事態は次の様だった。彼にはもっと考える時間は多く残されてはいなかった。また、近づいて来る死は、彼に候補者の詳細な調査を許さなかったのだ。それ故、その他の者たちは皇女との結婚に値しないとして、その全員を拒絶し、その男だけを考慮に入れたのだった。しかしながら、コンスタンティノスは、その者の妻が彼の目論見に同意しないことは知っていたので、彼女の夫に対して宥め様のない荒々しい怒りを抱いている振りをしたのだった。直ぐに、王室の実行部隊を派遣し、彼を見掛けだけ厳しく罰したのだった。また、彼女自身は世俗から引き離し修道院へ送ったのだった。
妻は、この共謀の目的に気が付かず、また、怒りが嘘だとは見抜けなかった為に、抗議することもなく、自身の運命に諦めたのだった。けれども、彼女が髪を切られ、黒い服を着せられ女子修道院に閉じ込められた、その時、彼女の夫であるロマノスは、そう言う名前だったのだが、宮殿に上がり王家に受け入れられたのだった。そして、コンスタンティノスの娘たちの中で最も美しい娘は、彼と初めて会ったまさにその時、直ぐ様、彼の妃になったのだった。こうして、父であるコンスタンティノスが生きていたのは、二人が将来結びつくことを予感出来た時までで、主の元へ旅立ったのだった。そして、後継者に娘婿のロマノスを残したのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
