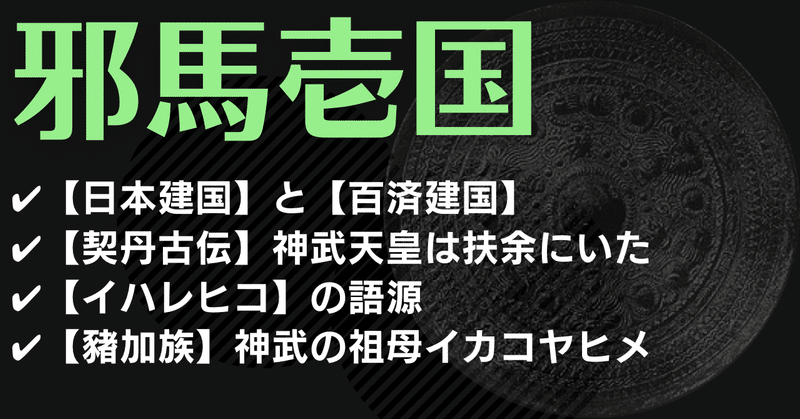
【神武天皇と朝鮮半島】神武天皇は高句麗の副王だったのか…?!〜古書から日本の歴史を学ぶ〜
※この文章はYouTubeで視聴することも出来ます。
こんにちは、今回は神武天皇のお話です!宜しくお願い致します。
前回の動画では卑弥呼が遼東から帯方郡へ南下したところまでをお話しました。
当時の帯方郡では公孫模が兵を興して韓・穢を討ち、倭人と韓人は帯方に属して扶余王仇台は帯方郡の土地に伯済国を建てていました。
この朝鮮半島の歴史と日本の初代天皇である神武天皇は時代も国も接点が無い様に見えますが、どのように関連しているのでしょうか。
【扶余と日本】
では先ず古事記の神武東征伝説から見ていきます。
この説話は広く識られているので簡略しますが、前半部分は海上航海のお話で神武の兄である五瀬命が主体になって話が進みます。
五瀬命が陸上にあがると直ぐに登美毘古(長髄彦)に討たれ傷を受けて死んでいます。
これに対して後半部分のイワレヒコは五瀬命の死後、陸上戦を戦い勝利しています。
つまり古事記の神武東征は海担当の兄と陸担当の弟が2人で国覔ぎに出かけ、海の兄は死に、陸の弟が成功して建国、というストーリーになっています。
このストーリーに類似しているのが百済建国伝説です。
[三国史記]の百済本紀を読んでいきます。
《高句麗の祖先の朱蒙(しゅもう)が北扶余から難を逃れて卒本扶余へやってきた。そしてそこの王の女をめとり、長男の沸流(ふっりゅう)、次男の温祚(おんそ)の2人の子供をもうけた。
※ 沸流と温祚は義兄弟の説も有ります
ところがそこに朱蒙が未だ扶余にいたときにもうけた子供の類利(るいり)が母と共に北扶余からやって来たので、朱蒙は後から来た類利を自分の太子にした。
そこで後妻の子である沸流(ふっりゅう)、温祚(おんそ)の兄弟は自分達は太子になれないので落胆し、祖国を出て新しい国を求めて南下した。そして漢山にいたり今のソウルの北の負児岳(ふじたけ)に登って住むべき場所を探した。ところが兄の沸流は海岸のほうに行って住もうとした。
皆が諌めたにもかかわらず沸流は自分の民を引き連れて海浜(今の仁川付近)に行って国を作った。
一方弟の温祚は内陸の河南慰礼城に都し、国を十済(じっさい)と号した。
海岸の方に住んだ沸流は土が湿っていて水は塩気が多いという不健康地なので永住出来ず、弟の住んでいる河南に戻って来た。
すると河南の慰礼城は非常に繁栄していて、人民が安楽に暮らしている。
それを見て沸流は自分には目がなかったと恥じて自殺してしまい、沸流の臣下は皆温祚の部下たちと合体し、これが後の百済となった》
とあります。
神武建国神話と百済建国伝説は物語としては異なっていますが、基本構造である兄と弟の2人が国覔ぎに出かけて、海の兄は死に、陸の弟が成功して建国、という構成は一致しています。
また、神武東征では速吸門(はやすいのと)を通るとき、亀の背に乗ったサヲネツヒコが現れ、東征軍の水先案内をしましたが、朱蒙が建国の際に川を渡るときは亀が現れて橋をつくり、その上を渡ることによって建国という説話があります。
神武東征では亀の次に熊野の村で熊に遭遇し、熊の妖気によって昏睡状態に陥りますが、神剣の霊力によって回復するというお話があります。そして最後に八咫烏が登場し、軍を先導して勝利に導いていきます。
最初に水の動物亀、次に陸の動物熊、最後に空の動物鳥、という順番に出てきて、亀と鳥は神武に協力的でしたが熊は敵対しています。
これと同様に朱蒙の建国神話にも獣、亀、鳥、という順番に動物が登場していて、亀と鳥が朱蒙に協力的なのに対し、陸の動物である獣だけが朱蒙と敵対していました。
※詳しくは[三国史記]高句麗本紀を読んで下さい。
この他にも日本と百済や高句麗の建国神話には共通点が複数見られますので、古事記と三国史記を比較しながら読んでみて下さい。
次に[魏志]高句麗伝を読んでいきます。
《高句麗は遼東の東、千里に在る。南は朝鮮・濊貊(わいはく)と、東は沃沮(よくそ)と、北は夫余と接していてる。
首都は丸都である。面積は二千里平方くらい。戸数は三万。大きな山や深い谷が多く、平原や沢はない。山や谷にそって住み、谷川の水を飲む。土地柄良田はなく、耕作にはげむが、腹を満たすには足りない。
高句麗の人民は節食の習性を身につけている。王の宮殿はよく整備されている。
王の居所の左右に大きな神殿を建てて鬼神を祭り、また祖霊、霊星、社稷(しゃしょく)を祀る。
国民性は凶暴で短気。また他国に攻め込んで強奪することを好む。国には国王がいる。官には、相加(そうか)、対盧(たいろ)、沛者(はいしゃ)、古雛加(こすか)、主簿(しゅぼ)、優台(ゆうだい)、丞(じょう)、使者、皁衣(そうい)、先人がある。むろん専卑の違いや等級の差がある。
東夷の旧語は夫余の別種。言語や諸事万端も夫余と同じであるが国民性と衣服は同じでない。
〈中略〉
畑仕事をせず、坐食している者が国中で一万人近くも居る。そして下戸が遠い所から食糧、魚塩をかついで来てこれに供給する。
民衆は歌や踊りを喜び、夕暮れになると男女が群れ集まり次々に歌い踊る。村有の大倉庫はなく、めいめいの家に小さな倉があり、その小倉を桴京(ふけい)という。人々はきれい好きでよく酒をつくり蓄えている。
跪拝(きはい)する時には片脚を立て礼をする。これは夫余の跪拝の型と違っている。行歩(行軍)の時は皆走る。
十月に天を祭り、国中の人間が大いに会同する。これを東盟という。公の会同に出席する時の衣服はみな錦の絹織物で、金や銀でこしらえた飾りをつける。
〈中略〉
牢獄はない。罪が有れば諸加が評議して重罪ならば死刑に処し、その妻子は奴隷にする。
結婚話が決まれば女の家の母屋の後ろに小屋を作る。これを壻屋と言う。
日暮れに花嫁の家に行き、戸の外で自分の名を名乗り、跪拝し部屋に泊めさせて下さいと頼む。是を再三繰り返すと花嫁の父母はこれを聞き入れて小屋の中に泊まらせる。
金銭や絹を積んで花嫁に贈る。子が生まれその子が大きくなると、入婿は妻を連れてわが家(男の生家)へ帰ってゆく。
〈中略〉
高句麗の馬はみな小さく山へ登るに便利である。高句麗人は気力旺盛で戦闘訓練をよく積んでいる。沃沮(よくそ)や東濊(とうわい)はみな高句麗に服属している。云々》
とあります。
次に[魏志]夫余伝も見ていきます。
《夫余は万里の長城の北、玄菟郡(げんと)を去ること千里のところにある。南は高句麗と、東は挹婁(うぷる)と西は鮮卑と接している。北に弱水があり、国の広さは二千里平方である。
その民は土着し、遊牧はしていない。宮殿、倉庫、牢獄がある。山陵が多く、沢は広い、東夷の地域にあっては最も平坦な地で、土地は五穀(麻、黍、稷、麦、豆)によく、ただし五果(李、杏、棗、桃、栗)は生じない。夫余人は大柄で性質は勇敢、謹み深く情が厚い。
また他国に攻め込んで強奪などはしない。国には君王がいる。官名にはみな六畜の名をもってつけ、馬加(まか)、牛加(そか・うしか)、豬加(ちょか)、狗加(くか)、大使という。大使は使者である。
村々には豪民があって奴僕をたくわえ、その奴僕を下戸と呼んでいる。
〈中略〉
料理の時は俎板(まないた)を、飲食の時には杯をつかう。宴会では酒盃をおがみ、盃洗する。階段の昇り降りには互いに会釈して譲り合う。殷の正月(十二月)に天を祭る。
この祭日には大勢の人が集まり、連日、飲み歌い踊り大賑わいをし、これを迎鼓(げいこ)という。この時、獄につながれていた囚人を解放する。
夫余人は一般に衣服の色は白を尚び、袂袍(べいほう)や袴(はかま)を着る。革靴をはく。
〈中略〉
通訳が言葉を伝えるときは膝まづき手を地面に付けひっそりと話す。
〈中略〉
兄が死ぬと嫂(あによめ)を弟が妻にするのは匈奴と同じ習俗である。弓矢、刀、矛を武器とし、家ごとに鎧や杖を持つ。
〈中略〉
軍事のときは天を祭る。牛を殺して蹄(ひづめ)をみて吉凶を占う。云々》とあります。
[魏志]高句麗伝にある婚姻関係について、入婿の男性が女性の実家に金銭や絹を積むとあり、結納を女性の実家に渡す習慣があったようです。
母屋の後ろに“婿屋”を建てたとありましたが古代日本では“婿屋”のような住居を“妻屋”と云い記紀や万葉集などにもよく見られる習俗です。(妻問婚)
また[魏志]夫余伝にあった、兄が死んだら兄の妻は弟が妻にするという慣習は、戦前までの日本では“直る”と言ったそうですが三国志の著者である陳寿という人物はこの慣習を匈奴の俗と同じであると述べています。
酒盃をおがみ、盃洗してから酒を注いでもらうというマナーは夫余や日本以外にも古代満州の礼儀作法とも一致しています。
以上の習俗の記述は古代日本と古代朝鮮半島の支配者層が持っていた文化系統を示唆しています。
【神武の名前】
では次に神武天皇の名前について調べていきます。
古事記では神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれひこのみこと)や若御毛沼命(わかみけぬのみこと)、豊御毛沼命(とよみけぬのみこと)、
日本書紀では神日本磐余彦天皇(かんやまといわれびこのすめらみこと)、諱を彦火火出見(ひこほほでみ)、幼名を狭野尊(さののみこと)、磐余彦尊(いわれびこのみこと)、磐余彦帝(いわれびこのみかど)、美称として始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)などと記しています。
ホツマツタヱでは、カンヤマトイワワレヒコやイハワレなどの他に神武天皇の諱を武仁(タケヒト)などと記しています。
【イワレヒコの語源】
イワレやイハレの語源は「イハアレ」や「イハフレ」でフレは古代朝鮮語の「村」プレとう意味があります。
古事記の編纂者の1人として知られる稗田阿礼も固有名詞ではなく稗田村という意味の普通名詞なのですが、このことは万葉集に磐余のことを“石村”石と村でイワレと表記していることからもわかります。
古事記・日本書紀では大和の磐余(イハレ)という地名は旧名を片居(カタヰ)あるいは片立(カタタチ)といったとあります。
日本書紀ではカタヰをこの様な漢字で表記していて➡︎伽哆萎、カタタチを︎➡︎伽哆哆知このように記していますが、カタヰとカタタチという言葉を語源学で書き改めるとカタヰとカタタチの“カタ”は豬加の加豬(かた)のことであり、どちらも豬加の住む土地、を表す同義異語重層方式の地名です。
磐余(石村)はイハフレの約音でイハレですが、イハは伊哈や狗加となりフレは村だったので、イハレは狗加の村です。
日本書紀にある神武軍が片居を占領したのでその地名をイハレに変えた、というのは先住の豬加の住む土地を狗加が占領したので狗加の地名に変えたことを意味しています。
このことは[山城国風土記]で神武天皇の祖母が伊可古夜日女(イカコヤヒメ)であることとも関係しています。
神武天皇の母親については[古事記][日本書紀]には玉依姫(玉依毘売)とあります。
[山城国風土記]によると可茂別雷命(かものわけいかづち)の母も玉依姫なので、神武天皇=可茂別雷命なのではないかと推測できます。
ホツマツタヱ第24章コヱクニハラミヤマのアヤには神武天皇を蓬萊太公(はらおきみ)又は“ワケイカツチ”と記し、兄の五瀬命の飛鳥大君とともに父の国から分離したことを述べています。
※秀真全訳を著した吾郷清彦氏は第24章の蓬萊太公(ワケイカツチ)を皇孫、飛鳥大君を天孫と解しています、ワケイカツチの注釈は無し。
[契丹古伝]第17章には秘府録(ひふろく)に曰く、として“イカツチワケ”という人物が登場するのですが、言語学者の川崎真治氏によれば、ホツマツタヱがワケイカツチとするのは秀真がセム族系語法によって副王を表す“ワケ”を語頭に持ってきたからで、契丹古伝秘府録のイカツチワケは“ワケ”を語尾に付けるハム族系語順の特徴であるとしています。
契丹古伝の第17章は次のようになっています。
《秘府録に曰く、神祖地を幹浸遏(アシア)に拓く。區(く)して五原となす。
伯屹紳濃和氣(ハキシノワケ)、馬姑岣(マコク)に治す。是を西原と爲(な)す。
泱汰辰戞和氣(ワタシカワケ)、羊姑岣(ヤコク)に治す。是を東原となす。
納兢禺俊戶栂(ナキクシコメ)、尹樂淇(イラキ)に治す。是を中原となす。
湮噉太墜和氣(イカツチワケ)、柵房熹(サハキ)に治す。是を北原となす。
沄冉瀰墜和氣(ウナミチワケ)、柟崤藐(ナカハ)に治す。是を南原となす。
ここにおいて旦賅安閔(タカアメ)を御し、波那阿沄(ハナアワ)を調し、矩乃古諸(クノコロ)に教して、畿覲怙曾(ききんこそ)あること勿(なか)らしむ。》
とあります。
イカツチワケは《柵房熹(サハキ)に治す。是を北原となす。》とあり、北原とは[三国遺事]にもあるように扶余を指しています。
この章では神祖が拓地して、マコク、ヤコク、イラキ、サハキ、ナカハの五原としたことが書かれていて[秘府録]と[西征頌疏](せいせいしょうそ)の神祖とされている人物は高句麗第6代王の太祖大王か高句麗第8代の王、新大王の伯句(はくく)のどちらかだと比定されています。
何れにしてもイカツチワケは扶余からわかれた高句麗と関係の深い人物だと考えられます。
[山城国風土記][ホツマツタヱ]から神武天皇であるイワレヒコはワケイカツチであること。
さらに[秘府録]ではイカツチワケは北原とされる扶余を治めていたことから神武天皇の建国神話が百済や高句麗の建国神話に類似していたことと少しづつ繋がってきました。
ワケイカツチは神武天皇を作り上げるために借用した人物の1人です。
次回は伊都国から神武天皇について見ていきます。
古代史には膨大な学説がありますので、今回の内容はそのうちの一つだと思って頂いて是非皆さんも調べてみて下さい。下記の参考書籍も読んでみて下さい。
最後までご覧頂きありがとうございました☺︎⭐︎
📖参考書籍📖
鹿島曻著書「倭人興亡史」「邪馬壱国興亡史」
石原道博著書「新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝」「新訂 旧唐書倭国日本伝・ 宋史日本伝・元史日本伝」
房玄齢等著書「晋書」
東洋文庫「三国史記1新羅本紀」
浜名寛祐著書「契丹古伝」
吾郷清彦著書「日本建国史 全訳ホツマツタヱ」
佐治芳彦「邪馬臺国抹殺の謎」
鈴木武樹著書「消された帰化人たち」「日本古代史の展開」
宮崎康平著書「まぼろしの邪馬台国」
藤間生大著書「日本古代國家」
斎木雲州著書「出雲と蘇我王国」
富士林雅樹著書「出雲王朝とヤマト政権」
余裕のある方はサポートして頂けたら嬉しいです☆*
