
イマここに生きる!オーガニックオーダーの旅・暦のお話 《大暑 初候 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)》
一年を通して様々な季節が味わえる日本。古来より大切にされてきた暦に触れていくことで、その豊かさをより深く感じられます。知ることは伝統や智慧、ひいては叡智とつながる第一歩。オーガニックオーダーを感じ、イマここに。
★古来より親しまれてきた暦『二十四節氣七十二候』についてはこちら★
2020年7月22日
二十四節氣 第十二節目及び雑節 大暑
2020年7月22日~27日
七十二候 第三十四候 <大暑 初候>『桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)』
桐の花の開花は4月~5月(種類によりすこしづつ違う)。
これはその頃咲いた花の実が結んでくる時を表しています。
大暑初候が桐始結花となったのは、日本で初めて編纂された暦『貞享歴』からで、編纂者の渋川春海考案のオリジナルです。
ちなみに七十二候で花が咲くことは「華」「開」「笑」などの文字で表されています。
ですから「結」は実を結ぶ、なのですね。
身近?憧れ? 実は知らない桐のこと
箪笥や下駄、木箱や米びつの材として有名な桐。
材質は軽く、熱伝導率が低く、調湿性に優れるという特徴があります。
その特性を活かして、貴重な書面を保存するための箱、雅楽の伎楽面や琴のような芸術・文化に関わる使い方、日用品の材料として箪笥や下駄の素材とするなど、生活にも深く浸透し幅広く利用されてきました。
国内の桐生産量は昭和34年をピークに減少し続けており、現在ではピーク時の2%程度の生産量となっているそうですが、国内の需要は増えており、材木の不足分については輸入品で賄っている状況なのだそうです。
とても希少と言える国産の桐。
現在でも、貴重な書画を入れる保存箱、独特の風合いを持つ桐タンス、琴など、特別な品には、品質的に優れている国産の桐が不可欠なものとなっているそうです。
主な生産地は、東北地方・「会津桐」(福島県)、「津南桐」(新潟県)、「秋田桐」(秋田県)、「南部桐」(岩手県)。
ある、会津の生産者の方の手記に「桐は、植えた人が丹精込めて作る木」とありました。
桐は、「植える木、育てる木、植えた人が自分で切る木」という考えが元々はあり、生育が早い桐は、一人の人が大切に植え、育て、加工して、更に生涯大切に使うというものだったのだそうです。
また、女の子が誕生すると住居の周辺に桐を植栽し、結婚が近くなるとその桐を使って花嫁道具をあつらえるという風習もあったのだとか。
わたしは今回調べて初めて知ったのですが、なんと温かな風習、そして考え方が大切にされていたことかと驚きました。
また、「残念ながら今のところ、輸入した桐にこの考え方が当てはまるかと言えば疑問です」とも述べられていました。
そもそも、日本の産地である東北産の桐と、輸入される桐は種類も違うとのこと。
長い時間をかけて培われた日本の桐産業、守られる手立てがなんとかあって欲しいと思います。
日本政府の紋は『五七の桐』
日本の文化に深く根差していた桐。
実はその桐の花の紋は、現代の日本国民にとっても殊更馴染みもあり、また特別なものでもありました。
『五七の桐』と呼ばれる桐花をモチーフにした紋、これは日本政府の紋章でもあります。
元々は、約1200年前、嵯峨天皇によって創案された紋でした。その後、菊紋が正紋として使われるようになり、桐花紋は副紋とされました。副紋といっても格式はとても高く、大変貴重なものという位置づけです。
桐花紋は功績のあった臣下に下賜されることもあり、それは大変名誉なことでした。

ほとんどは『五三の桐』という紋で、五七の桐の次に格式のあるもの。
それでも十分名誉あることで大切にされました。
ですから『五七の桐』を賜るといえば、相当に特別なことというわけです。
明治時代、1869年の大政官布告で菊紋の使用は皇室関係に制限されました。
そこで、菊紋に次いで格が高い五七の桐を日本政府の紋章として使うようになりました。
ちなみに法務省の紋も桐。こちらは『五三の桐』です。
実は一般市民でも五七の桐を持っていることがあるのです。
それは、パスポート。
日本国のパスポートのデザイン、表紙に菊の紋は誰もが知っていますね。写真のページに五七の桐花紋が使用されています。
知っていると、実用面以上に大切なものとなる氣がしますね。
暦を使ってセンスを磨こう
㋃、㋄に咲いた花が実を結ぶという今回の七十二候の句。
これを取り入れて、チャンスセンスを磨いて一年の飛距離に艶を出すのも楽しいもの。
大暑の頃を目標地第一通過点にして、何か新しいチャレンジを始めてみると、季節の氣脈に乗って取り組みやすくなりそうです。

例えば、とっても忙しくて落ち着かない…というときも10分瞑想を取り入れてみる。
ゆっくり過ごせるときはできるけど、忙しいときはちょっと、という方も、10分ならいかがでしょう。これは、5分を2回でも、1分を10回でもヨシとするなら負担は回避できそうです。がんばる自分に毎日ミラクルリラックスタイム、プレゼントしてあげましょう。
他には、30分だけ歩くを一日の行動にプラス!とか。
一回、二回と重ねると…、新しい景色とすっきり美脚をゲットできちゃうかもしれません。
通勤がある方は、行き帰りに15分づつ、在宅ワークさんは、朝晩15分づつなど、『ちょっぴりプラス』のケアがやがて大きな実りとなって還ってきます。
できるようになったその先に、ちょっと素敵になった自分の姿がある。
そんなわくわくしちゃうものがおすすめですよ。
自然とチャンスセンスが磨かれる、桐始結花のシークレットエッセンス。
無理なくチャンスタイムを三カ月分。立つ世界も見える世界も変わっちゃう可能性を秘めています。
また、今実っていることをピックアップして、4月、5月の振り返りをしても。思わぬ点が繋がって、新たに感謝の機会となるかも知れません。
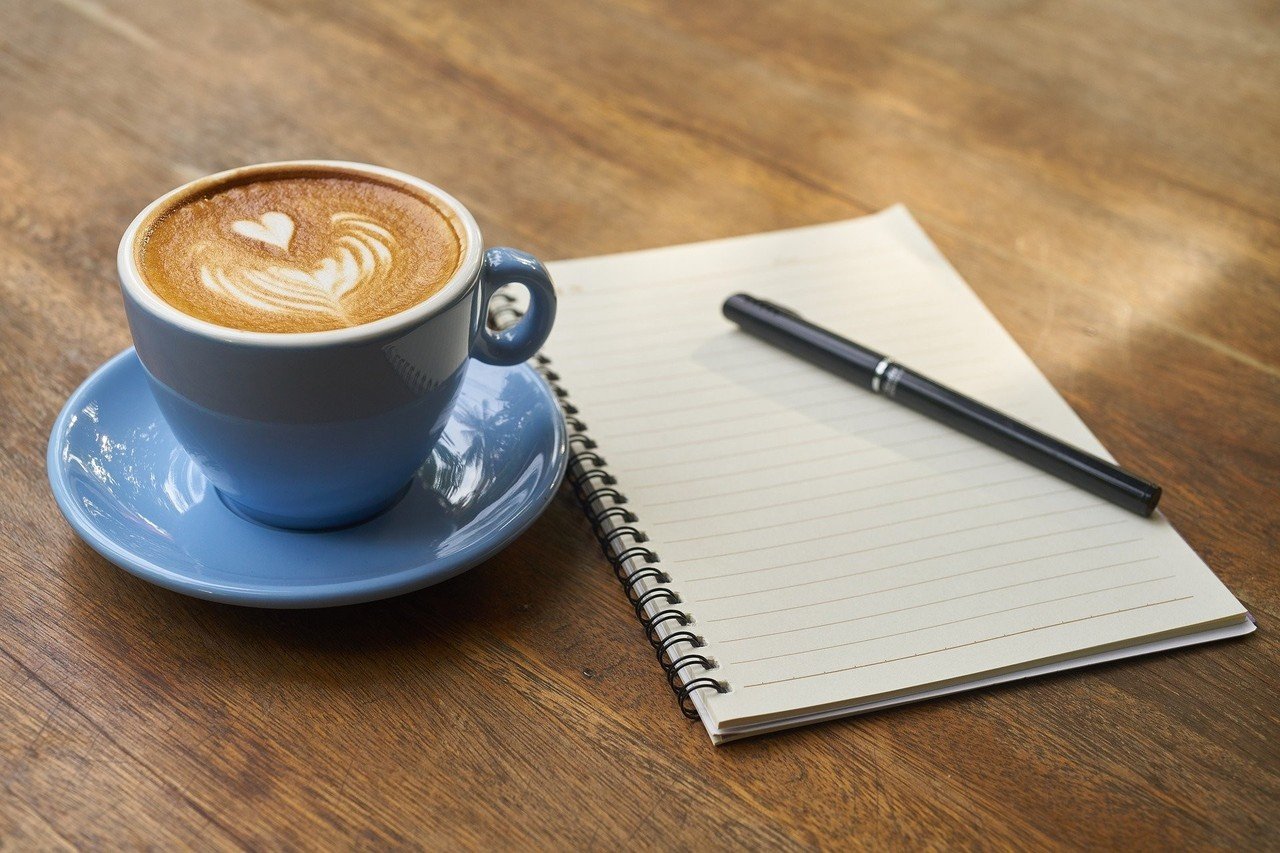
ちなみにわたしはどうだったかな?と手帳を紐解くと…
一杯ありすぎて書ききれない!
ピックアップしてみると、例えばこの時期、楽しくて次々チェックした若手クリエイターさんの音楽作品クリップ。
これが刺激になって描いた絵が、新しいお仕事に繋がりました。嬉しかったし、今もチームで協力して展開し続けていて、更に良い刺激を頂いている次第。これの元がここだったのね〜♪って、また楽しいことが起こる元です。
物事の繋がりに気付き、関係性に気付けると、自然と感謝が膨らみます。今あるしあわせに気付けるセンスは、充足感に満ちた、ポジティブな幸運体質への秘訣。
暑さを避けて休憩する昼下がりや、1日の終わりを少しだけ早くして、『感謝タイム』を持ってみるのも心の暑気祓いになりそうですね。
暑中見舞い、残暑見舞いを書くときも、before/afterで、書きたいことが違ったものになりそうです。

大暑はどういうとき?
『暑気いたりまつりたるゆえんなれば也』
という言葉が、江戸時代に発行された暦便覧(太玄斎の書いた暦の解説書で天明七年(1787)に出版されたもの)にあります。
これは最も暑い頃というような意味。

これから8月7日頃までが大暑ですから、「確かに…」とうなずきもしますが、実際はこの期間以降の残暑と言われる期間の暑さも相当なもの。
すでに世界各国で周知のことですが、気候の変動は近年、過酷なものとなっており、これまでの概念が通用しにくくなっています。
今年は梅雨もまだ明けておらず、そうかと思えば6月末から東京では33度を超え、以降も35度、38度を記録した日もありました。油断大敵、熱中症への注意も重ねて喚起されており、十分にケアしていきたいものです。
こんなときだからこそ、ひとつの物差しとして暦を使うなら、変わったもの、変わらないものをしっかりと観じていくことができそうです。

この時期の養生ポイント
「土用の食い養生」という言葉や風習があります。
これは養生法をよく知るセラピストさんからしたら『あなおそろしや💦』かも知れません。
腹が減っては戦は出来ぬ、食は元氣の基本!という考え方もありますが、この言葉、鵜呑みは危険。
激しい暑さや、湿度、空調による環境の目まぐるしい変化にさらされると、身体の消化にまつわる動きは減退しやすいのです。
詳細は個々人によるところですが、総じて言えるのは、食欲減退中は、まずは刺激も控えめに、ということ。
思い付きの荒療治は試みず、直接触れられない大切な臓器、行動を控えて労わってくださいね。
安定してマネージメントできていれば、旬を迎える食物が色々とあり、楽しい時でもあります。

先日、地野菜の販売所に行ってみましたが、棚には色艶美しい夏野菜や果物たちで一杯でした。
少しづつ食卓に取り入れて、季節の恵みでまずは気持ちを潤していくのもまた養生。
とある料亭さんが、青唐辛子の炒め煮をこの時期のお献立にご紹介なさっておられました。暑気あたりしやすいこの時期、美しい夕空を観じながら頂く青唐辛子のお料理は、心身をおいしく養ってくれそうですね。
2020年7月22日
(参考資料:東洋経済オンライン他)
『透明な栄養』をテーマに有形無形の造形活動をしています。ホリスティック~全体観~という捉え方を活動の基盤にしています。この捉え方は、いのちの息苦しさが紐解かれたり、改善される可能性をかんじます。noteでは日々の思考研究も兼ねて、この考えをもとに書いたものをシェアしています。
