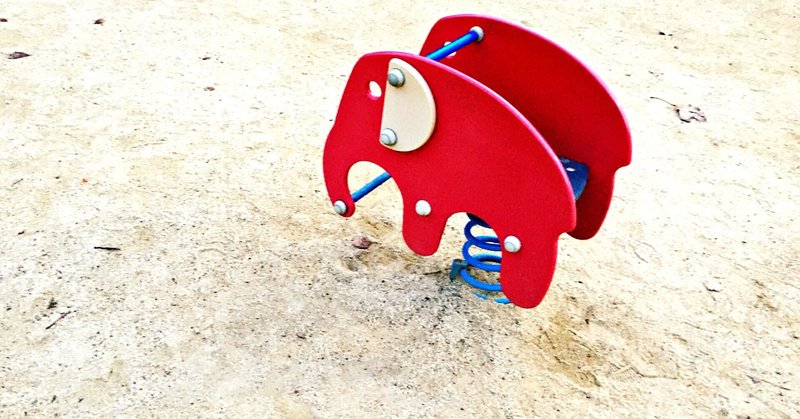
かげふみ
影踏みの鬼をしていたあの子は
逃げ廻る黒い染みを追いかけて
何処かへ行ってしまった
迷子になった子犬のように
きっとひとりで泣いている
名前を呼んでも帰らない
探しても見つからない
繁る木々の中
冬の風が冷たく吹きすさぶ
呼び声が風に攫われて引き裂かれる
早く辿り着かなければ見失ってしまう
その姿を追い続けなければ
名前すら忘れて仕舞うかも知れない
どうかぼくの名を呼んで
心細いのならこの名を叫んでくれ
世の中のすべてのものが
ぼくの前から消え去っても
構わない 君さえ居れば
もう 何かを堪えなくていいから
何もかも投げ出して
ぼくの前で好きなだけ泣いておくれ
+
看護婦に手渡された赤ん坊は、くにゃくにゃと頼りなく、真っ赤な顔をしていた。思ったよりも重く、落とさないよう慎重に抱いた。佟子に見えるようにすると、疲れた顔に笑みを浮かべて手を伸ばしてきた。
「可愛い、ぽちゃぽちゃの顔してる」
「可愛えかあ? 猿みたいやん」
ひどい、と彼女は膨れっ面をしてみせた。看護婦が笑って赤ちゃんは皆こんな風ですよ、と云って、一旦新生児室に連れて行くからと赤ん坊をぼくの腕から引き取り、抱き上げた。車椅子で病室に戻される佟子についてゆき、少し落ち着いてから名前はどうしようかという話になった。
「左人志は何か考えてるの?」
「男の名前は一応、考えちょったけどな」
「どんなの」
「生郎」
「影郎君からとったの?」
「うん。あんな風に早死にしてもらいたないし、あいつの分まで生きて慾しいし」
いい名前じゃない、と佟子は云った。
息子は生郎という名前になった。草村君に知らせると、早速やって来た。生郎を抱き上げ、「重いな、元気な子なんですね。丈夫に育つといいな」と云った。彼はまだ結婚していない。女性とつき合ってはいるようだが、どうも所帯を持つ気はないらしい。影郎の死のショックからは立ち直ったように見えるものの、他人に拘るのが恐くなってしまったのだろうか。
子供が好きらしく、よく生郎の顔を見に訪れるようになった。生郎も彼にはひと見知りしないで懐いている。不思議なことに、言葉が喋れるようになると草村君のことを「紘君」と呼ぶようになった。誰も彼を下の名前では呼ばなかったのに、何処で知ったのだろう。影郎が草村君のことをそう呼んではいたけれども。
「おろーあん」
「お父さん」
「おとーらん、こーくん、いりゅうりゅろ」
「まーちょい上手に喋らんかい。うりゅうりゅ云うても判らんわ」
「草村さんはいつ来るのかって」
「翻訳せんでも判るけどな。いつ来るんじゃろうなあ。店が不定休じゃけえ、判らんのう」
「こーくんにあいらい」
「ほな、電話して来てもらおか」
電話を掛けると、店はいつでも休めるのでそちらの都合のいい時に行きますと云った。ぼくは普通の会社員なので休みは土日である。それに合わせてもらうことにした。バーのような店は週末はあまり繁盛しないので恰度いいだろう。
土曜日に草村君は玩具の土産を下げてやって来た。
「いつもすまんのう。生郎、お礼を云いなさい」
「こーくん、あいあと」
「どういたしまして。それで遊ぼうか」
土産を受け取ると生郎は名状し難い歓声を上げ、草村君にしがみつき、足踏みするように彼の手を握りしめ、
「んとね、これはね、ぼくがさきにやる」
と云った。
「それはジャンケンで決めないと」
牽制するように草村君が云うと生郎は負けん気を起こして、「ぼくまけないもん」と踏ん反り返り、そっぽを向いた。その様子を微笑ましそうに見遣ると草村君は、
「そうだな。じゃあ、あっちの部屋へ一番に行った方が先にやろう」
生郎はその言葉を聞くや否や、とたとたと廊下を走ってゆく。その姿を草村君は微笑ましそうに眺めているが、その眼差しには暗い翳りも見受けられた。しかしそれを指摘するのは憚られる。その鬱屈した感情を刺激するのは適切ではない。
愉しそうにはしゃぐ声が仏間から聞こえてくる。佟子がお茶を出して戻ってくると、くすくす笑って「草村さん、ほんとに子供が好きなのね。生郎と一緒になって遊んでる」と云った。
「自分で作りゃええのになあ。なんで結婚せえへんねやろ」
「なんとなく判る気もするけど」
「どんなん」
「影郎君のことが忘れられないっていうのもあるんだろうけど、もう他人を必要としてないんじゃないかな」
「そんなもんかのう。それじゃあ淋しいやないか」
「ひとと一緒に居ることより、孤独を取ったんだと思う。ひとりだったらそれ以下の単位になることはないもの」
「えらい消極的な人生じゃのう」
「そういう生き方もあるんじゃない?」
佟子は呟くようにそう云った。
草村君が帰ろうとすると生郎はぐずって、しまいには泣き出した。彼は困った顔をして生郎を抱き上げると、「ごめんね、もう帰らなきゃいけないんだよ。また来るから、それまで我慢しようね」と、あやしていた。それでも生郎は泣き止まず、彼の胸に顔を埋めていた。
「明日、午前中は予定ないんじゃろ。泊まってったらどうじゃ」
「いえ、そんな図々しいことは……」
「ええやん。前はよう泊まってったやないか」
「こーくん、ろまっれ」
彼は苦笑いして生郎の頭を撫でると、「じゃあ、お言葉に甘えて」と泊まってゆくことにした。佟子と結婚する前は影郎が死んだあと、互いに淋しくて慰め合うように晩飯を一緒に喰い、酒を酌み交わしたものである。車で来ているので泊まって行ったのだ。
佟子が作った晩飯を四人で囲み、ベビーチェアに座る生郎に草村君はスプーンで食べさせてやっていた。もう大人と同じものが食べられるのだが、食べ易く細かく刻んであり、薄味に仕上げてある。食べてみたら、醤油をかけたくなるような味だった。
ビールを飲んで他愛無い話をする。もう影郎のことは話題に上らない。思い出に別の事象が蓄積して、蓋がされた。それでいいのだと思う。過去に囚われていたら健全な生活が出来なくなる。忘れ去る訳ではない。ただ、駒を先に進めただけなのだ。
盆休みに実家へ帰ったら、近所の農家で飼われていた家鴨の雛を生郎が気に入り、戻る時には連れて帰ると云って聞かなかった。
「他所んとこの家鴨じゃ、諦め」
「左人志君、ええよ。あげるで連れて帰り」
「ええんですか」
「ええわ。こないにして可愛がってもろうたらこいつも本望じゃろ。いずれは潰される運命じゃったでのう」
「生郎、くれるんじゃて。良かったな、お礼云い」
「おりやん、あいあろ」
「ええよ、可愛がったってな」
家鴨はがあこと呼ばれるようになった。黄色い羽毛はじきに生え変わり、生郎の半分ほどの大きさに育った。があがあと煩瑣く啼き、家の裡では飼えなくなったが、近所迷惑になるので夜は家に入れていた。生郎は一緒に寝たがったが、下敷きにしてしまいかねないのでケージで飼っている。
午間は庭に出していた。影郎が耕した畑は、今では佟子が花壇にしている。色とりどりの花の中を白い家鴨がのたのたと歩く様は、滑稽だがほのぼのとする。
草村君が来ると生郎は駆け寄って飛びつく。ぼくが大学受験の為にこの家へやって来た時、影郎も同じように飛びついてきたのを思い出させる光景だ。
「左人志、ずっと此処に居るの?」
「受からんことにはそうならんがのう。まあ、合格するように願掛けでもしてくれや」
無事大学に合格し、草場の家で生活するようになった。一年後、叔父夫婦は仕事の都合でドイツへ行くことになり、あとのことを頼むと、家と影郎を任された。影郎はそれまで寝起きしていた庭の倉庫から母屋に移り住んだ。
「おまえ、ようこないなとこで暮らしちょったのう。隙間風入ってきとるじゃねえか」
「新聞紙詰めてたから平気だったよ」
「何が楽しゅうてこんなとこにおったんじゃ」
「愉しいからに決まってんじゃん」
「おまえはほんまに変わっちょるのう」
変わってないよ、と彼は笑っていた。その倉庫には今、庭いじりの道具が入っている。ひとが住んでいたとはとても思えない。影郎の部屋も納戸と化している。もう彼を偲ばせるものは、仏壇とアルバムの中の写真だけである。
「こーくん、があこ」
そう云って、生郎は草村君を庭に連れ出す。彼は生郎を抱いて庭に出ると、ぼんやり家鴨を眺めている。その後ろ姿を見て「草村さん、生郎に影郎君の面影を重ねているのかなあ」と、佟子が云った。
「どうじゃろうなあ。なんや最近、あいつに似てきたけどな」
「左人志には全然似てないね」
「ほんまにわしの子ぉか?」
「なんてこと云うのよ、左人志の子供に決まってるでしょ」
「そやかて、ちっとも似ちょらんがな。性格まで影郎みたいになったらかなんで」
「大丈夫でしょ。接したこともないひとには似ないわよ」
「だとええけどな」
生郎が幼稚園に上がる時、草村君も入園式に来てくれた。スーツがなかなか似合っている。そういえば影郎はとても華奢で痩せていたので、スーツのような服が似合わないと云っていた。顔立ちも子供のようなので、中学の制服もまったく似合っていなかった。
草村君の方に生郎は笑顔で手を振っていた。生郎がいつまでも片言で喋るから三人で心配したものだが、この頃にはちゃんと話すようになっていた。
式が終わり園児や父兄がぞろぞろと帰る中、門の処で生郎とぼくら夫婦の写真を草村君が撮ってくれた。彼と生郎の写真を撮ろうとしたら、いいです、いいです、と固辞した。なんで、と訊いたら、写真に撮られるのがあまり好きではないと云う。そういえば影郎がそんなことを云っていたのを思い出した。
「こーくん、一緒に撮ろうよ」
「また今度ね」
「一緒に撮ったことないじゃん、記念なんだからぼくのお願い聞いてよ。ほらお父さん、撮って」
彼は生郎には弱いので、撮影を承諾した。ファインダーの中のふたりは年若い父と息子のようである。ふと、生郎の背がひゅいと伸び、影郎の姿になったような気がした。草村君にはいつも彼の面影がつきまとっているからかも知れない。
生郎が幼稚園に通うようになってから、佟子はフラワーコーディネーターの仕事を再開した。元の花屋ではなく、自宅で教室を開き、注文を請け負ってホテルや店舗の花を生けていた。家は広く部屋が余っていたので、その一室を利用して生徒に教えている。
前に働いていた花屋がいろいろ便宜を図ってくれて、生徒にも仕事にも困ることはない。生郎が生まれてから買い替えた車で花を運んだりしているうちに、佟子が一緒に仕事をしてくれないかと云いだした。
「今のままじゃあかんの? わし、一度銀行辞めちょるで、もう転職はしとうないんじゃけど」
「わたしの仕事はずっと続けられるから大丈夫だよ。花や花器の運搬や、わたしを出先に送ってって慾しいの。ふたり分の収入は充分あるから生活には困らないと思うんだけど」
考えさせてくれと云って、その話は保留にした。三十一の時に転勤を断った為、職場の待遇が悪くなり辞職し、その後は暫く影郎の店を手伝ったが、どうにも水商売は性に合わず再就職した。現在は自動車ディーラーの営業をしている。車が好きなので愉しかったが、やはりそれだけでは済まない。
会社の人間や客との揉め事もある。小さい会社なので銀行のようにはいかない。そんなこんなで、草村君の店『ハカタヤ』へ久し振りに行った時に相談してみた。
「いいんじゃないですか。夫婦でやるなら気が楽でしょうし、フラワーコーディネーターの仕事は切れることなくあると思いますよ」
「そうじゃろうけえども、花のことなん詳しないし、わしかて花っちゅう面しちょらんがな」
彼は笑って、顔は関係ないですよ、と云う。そこへ甘利がやって来た。
「お、左人志、来てたのか。珍しいな」
「たまにゃあの。おめぇ、こんな時間に飲み歩いとってええんか」
「たまにはね。草村君、いつもの」
彼にも仕事のことを打ち明けたら、草村君と同じようなことを云った。
「花も車も一緒だろ。必須のものじゃない。でも、あれば愉しい」
車は兎も角、花はどうなのだろう。花瓶に挿された花を意識したこともなければ、特別きれいだと思ったこともない。当然のことながら、誰かに贈ったこともなかった。
+
結局会社を辞め、佟子の仕事を手伝うことにした。専門知識は必要なく、車を運転して花などを積み込むだけだった。それ以外の時間は生郎の相手をしていた。楽なものである。
生郎を連れて近所の公園へよく行った。家鴨は尾を振りながらちょこまかとついてくる。生郎は家鴨に合わせ、ぼくは生郎に合わせて歩くので、目と鼻の先にある公園に行くにも結構時間が掛かった。公園には滅多にひとが居ない。今時、こんな処で遊ぶ子供は居ないのだろう。
ぼくが子供の頃は、公園や原っぱでばかり遊んだ。凧を揚げたり、紙飛行機を飛ばしたりした。そういったものは自分で作り、友達と競い合う。どんな紙を使えばよく飛ぶか、重りを何処につければいいか、凧の足はどれくらいの長さにすればいいのかを、子供なりに研究したものである。
まだテレビゲームなどはそれほど普及しておらず、子供たちは素朴な遊びに興じていた。空き缶を使った竹馬擬きやビー玉遊び、女の子はゴム跳びや人形遊びをした。男の子と女の子が混ざって遊ぶ時は、かくれんぼや鬼ごっこ、缶蹴りなどをする。そんな素朴な、今からすると何が面白かったのか疑問に思うようなことを、飽きもせず、繰り返し繰り返し楽しんだのだ。
明るい夕暮れの陽射しの中、しゃがんだ生郎の影が伸びていた。ふと思いついて、お父さんの影を踏んでみろと云った。彼は不思議そうな顔をしていたが、立ち上がってぼくの影を踏もうとした。すっと体を躱したら、生郎は「ずるい」と怒る。ぼくは笑って、こういう遊びなんだと教えた。彼は理解したらしく、ぼくのあとを追いかけて影を踏もうとする。此方もそうはさせまいと逃げ廻る。
家鴨を踏まないように、小さな公園をふたりで駆け廻った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
