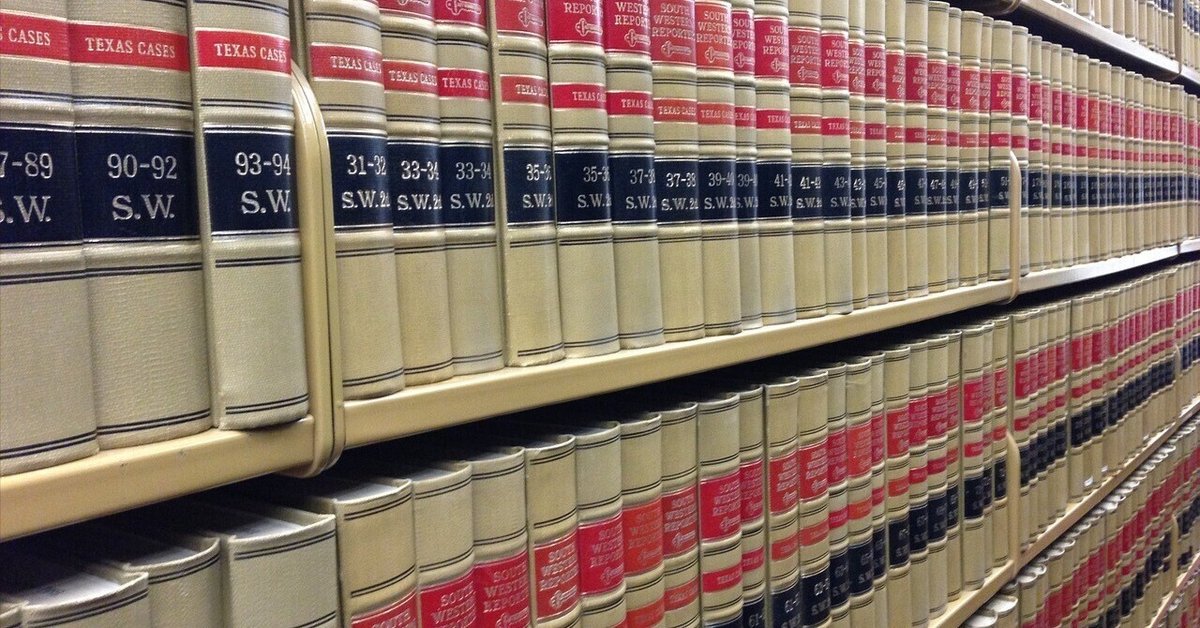
剰余金の分配可能額とM&A
前回まではしばらくカーブアウトM&Aを対象とした記事が続きましたが、今回は別のテーマをみていきたいと思います。昨今、剰余金の分配可能額の規制に違反して配当等を実施したとして上場企業等がプレスリリースを行うといった事例が頻発しており、報道等で触れられることも多くなっています。この背景には、かつての商法から現行会社法へ制度変更があった際の経緯や、国内企業の内部統制・ガバナンスの問題といったことが挙げられると思われますが、少なくとも経常的な配当の場面で間違いを起こさないようにするためには会社としての具体的な対応が必要となります。また剰余金の配当は、毎年の配当といった経常的な場面だけでなく、M&Aのような一過性の局面でもキーポイントとなる場合が少なくありませんが、実務の中で必ずしも分配可能額に適正な注意が払われていないと感じる場面もあります。最悪の場合、プリンシパルやアドバイザーの隙間にボールが落ちてしまうことでディール遂行に大きな影響を及ぼすことも考えられます。今回は分配可能額規制の概要と、M&Aにおける剰余金の配当について見ていきます。
剰余金の分配可能額の概要
株式会社が利益配当や自己株式の取得等を行う場合には、法律上財源規制が定められていますが、現在の制度上、当該規制は会社法によって規定されています。「現在の制度上」とあえて記載したのは、ご存知の方も多いように、かつては商法という法律がこれを規定していたことという歴史的背景があるためです。
かつての商法の時代には、「配当可能利益」や「配当可能限度額」といった用語が使われており、現行会社法が施行された2006年よりも以前から経理実務などに関与されていた方であれば、現在でも分配可能額の文脈でこういった用語を使われることもあるでしょうし、特に法的に厳密ではないインターネット上の記事などでいまだにこれらの用語が使われていることも珍しくないように思います。こういった用語の使い方については、特段関係者との意思疎通のなかで支障をきたすようなことがなければ、目くじらを立てるようなことでもないと個人的には思いますが、かつての商法と現行会社法とでは剰余金の配当(等)のコンセプトについて変更になっている点もあり、こういった中身の問題に関してかつての商法時代の理解を引きずってしまっていると、冒頭に述べたような各種誤りの遠因になることもあり得ると思いますし、現在の制度自体の正確な理解を妨げることにもなり得ますので、まずその規制自体の概要を整理したいと思います。
なお本稿は分配可能額の正確、詳細な計算方法の説明を意図したものではなく、その概念的な理解を深め、またM&Aの局面における具体的な注意点を示唆するのが本旨となりますので、特に技術的な内容は例えば監査法人のウェブサイトなどをご参照ください(そういった情報を必要とされている場合でも、本稿をご覧いただくことで全体の理解の一助となるよう構成したいと思います)。
分配可能額の計算構造の変更
かつての商法では、端的に言えば、直近のBSの数字から直接「配当可能限度額」の金額を計算し、これ以下の金額について配当することが可能、という規定になっていました。荒っぽく言えば、BSの情報さえあれば限度額の計算が可能であり、よって営業年度の終わりに配当を行う際には、この金額を算定して、配当予定額がその金額以下になっていることを確かめる、という手順を踏むことが制度上予定されていた訳です。一方現行会社法では、最終的に配当等のできる金額を算定するにあたり、「剰余金の額」と「分配可能額」という2種類の概念を導入しました。具体的にはまず剰余金の額を算定し、そこから調整を加えて分配可能額に至るという構造になります。
(余談)
かつての商法の「配当可能限度額」は読んで字の如く、配当することができる限度の額という意味となります。しかし会計や法律等の専門用語には、読んで字の如くだと必ずしも正確な意味内容をつかめないものが多くあり、例えば金融畑の方が会計用語を読んだり、経理畑の方が法律用語を読んだりする場合には注意が必要となります。
会計用語として例を挙げれば、「資産除去債務」はその言葉を読んで想像する印象(資産を除去するときの債務?)と比較すると、実際に指している内容はかなり狭いものであると言えると思います。
概念が2種類あることを仮に理解していなくとも、会社法が定めた数式にただひたすら準拠して正確な分配可能額が算定できれば、その限りでは問題ないことになります。しかし、後述するように会社法の分配可能額の算定式は非常に複雑なものとなっており、実際の実務では、合併や自己株式の交付といった取引は行っていない、期中の配当も中間配当以外には実施していないといった、計算要素を単純化できる条件を前提に、結論に影響を与えない程度で大まかに計算しているというのが実態かとも思われます。最近の分配可能額が問題になってしまった事案ではおそらくそうであったようにシビアな計算が必要となっている局面(限度額スレスレの分配)では、当該概念を理解した上で実際の計算に当たることはミスを回避する上で不可欠と言えるでしょう。
ではなぜ会社法はあえて2種類の概念を導入したのかということですが、これは剰余金の配当等が機動的に行えるようになった(理論的にはいつでも可能)ことと関係していると考えられます。たとえば3月決算の会社が毎月配当を行うとした場合には、当然8月のときと9月のときでは配当できる金額は変わっているはずです(剰余金の額が減っているため)。このときにかつての商法のように配当可能限度額を1発で計算するロジックをとっていれば、8月でも9月でも(それ以降でも)毎回同様の計算を繰り返さなければならない構造となります。これはかつての商法で、今年の配当可能限度額の計算をする際に、昨年がいくらだったかを気にする必要が基本的になかったことと同様です。
これに対して現行会社法は、まず「前事業年度末」の剰余金の額を算定し、期中の資本取引等(配当そのものも含む)による変動を追いかけて配当時点の剰余金額を算定します。よって、期中に何回配当をしようとも、事業年度が切り替わらなければ(正確には新たに計算書類が株主総会で承認されるまでは)、毎回前期末からスタートするという構造になります。このときに分配可能額という抽象的な概念とは別に、剰余金という会計的にある程度明確な概念を期中はずっと持ち越していくことにした方が構造的には好ましいという判断があったと思われます(もちろん純法律的な観点からそれ以外の要請もあってのことでしょう)。一部例外はあるものの、基本的に最終的な分配可能額はこの剰余金の額の範囲内で規定されるという関係にあります。すなわち現行会社法では2段階で枠を絞っていくイメージだと捉えるとわかりやすいでしょう。
現行会社法の計算式の概要
前述のように、現行会社法では大枠として以下のような構造を取っています。
(剰余金の額)±(政策上の調整)=(分配可能額)
ここで剰余金の額(配当時点の剰余金の額、と読み替えるとわかりやすい)は、前期末の剰余金の額(その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計)に、期中の自己株式取引、配当および株主資本の計数変動による剰余金への影響を反映して算定します(組織再編に関する調整は簡単化のため考慮外)。これらの取引によって増えた剰余金は増加させ、減った剰余金は減少させるわけです。言葉による式で書けば以下のようになりますが、会社法の実際の条文を追う際でもコンセプトを理解しながら読んでいくことが有用です。
前期末の剰余金の額±期中の自己株式処分差損益−期中の配当実施済み分+期中の資本金・準備金からの取崩額−期中の資本金・準備金への組入額−期中の自己株式償却額=剰余金の額
(参考:株主資本の計数の変動)
株式会社では、新しく増資をして資金を受け入れたり配当のために資金を払ったりすることがあり、このときには資本金が増えたりその他利益剰余金が減ったりといった変動が起こります。一方このような資金のやり取りが生じずに個々の資本項目の間で金額が振り替わることもあり、現行会社法ではこれらを株主資本の計数の変動として一括して整理しています。何を言っているかというと、経済実態とは無関係に単に数字が上に行ったり下に行ったりしているだけ(それによる会社の財務状況への直接の影響はない)ということです。例えば、減資は字面としては資本金を減らすことですが、会社法上は以下の組み合わせとして整理されることになります。
・剰余金の配当(実際の資金の外部への支払いがなければゼロ。いわゆる無償減資。)
・計数変動(資本金が減少し、同額がその他資本剰余金(資本準備金の場合もあり)になる。減資をする以上これは常に生じる。)
配当を行う際に同時に減資を実施することもあり、その場合には上記のような構造を理解しておくことが重要となります。
分配可能額の算定には、これにさらに政策上の調整を加えていきます。大きく分けて以下のような調整が行われます(組織再編に関する調整は簡単化のため考慮外、また臨時決算の実施も1回までと仮定)。
配当時点の自己株式の帳簿価額および期中に処分した自己株式の対価の減額
※期中の自己株式処分による剰余金増加は前述のように剰余金の額に反映されるものの、この規定により分配可能額からは除外臨時決算による利益影響額(通常は増額。後述。)
のれん等調整額の減額
評価・換算差額がマイナスの場合、当該金額の減額
※評価・換算差額はプラスであっても分配可能額を構成しないが、マイナスの場合には減算要因となる連結配当規制による調整額の減額(後述)
3百万円 −(資本金・準備金・新株予約権・評価換算差額等の合計)
※資本金などの配当対象外の項目が3百万円未満の際に、不足分は剰余金を残すための規定
上記の計算をすべて誤りなく実施して初めて正確な分配可能額の導出が可能となります。会計的な知識が必要となることは当然ですが、複雑なケースでは法の趣旨の理解などがあった上でなければ正確な計算は難しいということがご理解いただけるものと思います。
分配可能額における主な誤解
分配可能額に関しては様々な誤解があり、それらの大半は上記で述べた詳細な計算過程をトレースすれば(本質的には)解決することではあるものの、例えば(会社法の条文を参照せず)BSだけを見て判断をしようとする傾向なども一般的に見られるところであり、冒頭の問題も、分配可能額に対するそのような理解、姿勢から生じたとも言えるのではないかと思います。
(1) 分配可能額は単体BSに基づいて算定する
日本でも連結財務諸表の開示が定着して久しく、逆に制度会計上単体財務諸表が参照されることはほとんどなくなっていると思われますが、会社法(あるいは一般的に法規制全般)において数字を参照する先は単体財務諸表、すなわち分配可能額においては単体BSとなります。日常的に会社分析や財務分析等で連結財務諸表に慣れ親しんでいる方々の間ではこの点が忘れられやすく、連結BSに豊富な剰余金があればすなわち配当も実施可能、と短絡的に捉えられがちのため初歩的ではありますが注意が必要です。
なお上記「現行会社法の計算式の概要」の5. で連結配当規制を挙げていますが、これは連結財務諸表(正確には連結計算書類)の数字が参照される数少ない例外となります。具体的には連結BSの株主資本等が単体BSよりも小さい場合(≒子会社の財政状態が悪い場合)に当該少額な分だけ分配可能額を減少させるという規定となります。これは会社が任意で選択する規定であり、適用しない限りは影響がありません。注意すべきなのは、当該規定を適用したとしても、連結BSの株主資本が単体BSよりも大きい場合にその分を分配可能額に取り込むことはできないという点です。あくまで分配可能額を保守的に算定するための仕組みということになります。
(2) 期中に稼得した利益は分配可能額を構成しない
株式会社は株主総会の決議で期中いつでも配当を実施できるため、例えば第3四半期末を基準に配当を実施したいということがあります。このときに上場企業であれば四半期報告書を提出しているため、その剰余金の額を見れば分配可能額がわかるのではないかと思われる方がいますが、それは2つの点で誤っていることになります。
まず1つ目は、上記のように分配可能額は単体BSで判定すべきところ、四半期報告書には連結BSしか掲載されないため、情報としてそもそも不足している(四半期報告書では判定できない)ということです。そして2つ目ですが、第3四半期末のBSには当然9ヶ月間のPLの結果が反映されている訳ですが、前事業年度末以降期中に稼得している利益は、まだ分配可能額に入れることはできないということです。よって仮に四半期報告書で単体BSが確認できたとしても、分配可能額を過大に算定してしまうことになります。利益が分配可能額に入るには、1年間の事業年度が終わり、計算書類が作成されそれが承認されることが必要となります。
この点現行会社法で新しく設けられた制度に臨時計算書類(臨時決算)というものがあり、これを作成することでたとえば9ヶ月間の利益を、事業年度の終わりを待つことなく、分配可能額に含めることが可能となります。年度末の決算をタイミングを早めて行うというイメージで考えるとわかりやすいと思います。
前期末時点で剰余金が不足していたり期中で大きな利益が発生していたりする会社には便利な制度ですが、実はそれほど安易に適用できる制度ではなく、いくつかハードルがあります。本項ではその詳細までは触れられませんので、機会があれば改めて説明したいと思います。
(3) 分配可能額は監査法人の監査対象ではない
冒頭に述べた事案の大きな原因の1つと考えられるのが、分配可能額に関して監査法人が会社に言及をすることはないということです。かつての商法では計算書類の中に利益処分案が含まれており、これが適法に作成されているか監査法人が監査するものとされていました。適法というなかには当然に当時の配当可能限度額の制限に服しているか、という点も含まれると考えられますので、結果的に配当可能限度額の制限を守った利益処分(配当)になっているかを監査法人が確認していることになっていた訳です。
しかしながら現行会社法施行に伴い利益処分案は計算書類から廃止されたため、監査法人が剰余金の配当に関して少なくとも直接的に指摘をするということはなくなりました。期中配当であれば、監査法人が配当内容に関する情報を入手するタイミングもそもそも限られます。四半期報告書のドラフトの確認中に知った時には、社内で金額は決定されており、実務の手続が進んでいる、といったケースもあるでしょう。監査法人が事前に確認してセーフティネットになるということは究極的にはできない構造になっているのです。
すなわち、法は配当等の実施に際して、会社自身がその適法性を自らの責任で検証するよう求めているということになります。
分配可能額を誤る背景
上記までで既に触れている内容でもありますが、分配可能額に関する問題が生じてしまう背景についてまとめておきたいと思います。
商法から会社法に変わっての内容面でのアップデートが実務の中で必ずしも認識されていない、重く捉えられていない。
→これについては少なくとも法律の内容自体は不透明な部分なく整理が可能なものですので、社内で確認をしたり、会計事務所・法律事務所等に(金額そのものではなく一般論として)レクチャーをお願いしたりといった対応がすぐにでも可能です。分配可能額を計算するための仕組みと誤らないようにするための内部統制がともに構築されていない。
→分配可能額はBSの情報だけでは計算できないケースがあり、法律に基づき必要となる情報はどのように適時に入手するか、ということを場当たりではなく社内の仕組みとして作っておく必要があります。第一義的には経理部門の情報チェックリストといった形が考えられますが他部門(財務資金部門、法務部門、総務部門など)から連携される情報もあるはずで、これらをオペレーションとして組み込むことになります。また計算式が複雑なため、結果を検証する内部統制も合わせて必要です。式自体はあらかじめ設定し変更できなくした計算フォーマットの利用、入手情報と計算項目との整合性チェックなど、単に上位者がレビューするといったことではなく実効性のあるコントロールの設定が求められます。間違っても監査法人が教えてくれると誤解している。
→すでに述べているように分配可能額について監査法人はセーフティネットにはならず、その点の覚悟が必要です。もし技術的な点で不明確と思われることがあれば、会社側から監査法人にぶつけて見解を取るようにすべきです。
剰余金の配当とM&A
前置きが長くなりましたが、本題のM&Aについてです。配当は、年度・中間など経常的に行われる事項でもあり、その際に分配可能額等が問題となりますが、M&Aにおいてもそのような問題に直面することがあります。具体的には以下のような事例が考えられます。
子会社の株式を外部に売却する案件で、クロージング以前に当該子会社から資金を配当で吸い上げておくというのがストラクチャリング上行われることがあります。
ストラクチャリングの一部に自己株式の買取が含まれる案件があります。対象会社(または対象会社群)の(その時点で発行されている)株式の全てを買い手が直接・間接に保有する形でストラクチャを組むのではなく、一部については発行会社自身が直接の買い手になることが織り込まれている形です。
事前配当パターンの概要と留意点
まず1. について、これ自体はごく一般的な税務ストラクチャリングです。すなわち、子会社株式の売却で売却益が生じる場合、およそ30%の実効税率により課税され、これ自体に対してはあまり工夫の余地がありません。一方クロージング前に配当を行う場合、その受取配当には課税されません(国内の子会社で、株式を継続保有している場合)。これとともに、配当で現金が社外に流出することにより、理論的には株式価値が同額減少し、その結果外部に売却した際の売却益を圧縮することが可能となるため節税となる訳です。
株式の譲渡時点は案件次第で(子会社の事業年度の)期中のどの時点でも設定される可能性があることから、期中の分配可能額が問題になるケースが多くなるものと思います。この場合当該子会社は、一般的には上場企業等の継続開示を行なっている会社ではないため、配当を検討する段階で期中の株主資本の推移を、帳簿や試算表ベースで改めて整理する必要が出てきます。100%子会社であれば自己株式の動き等がある可能性は低いですが、それまでの期中配当やそれによる準備金の積み立てなどによる変動は考慮する必要がありますし、もし通常は配当を実施していない子会社なのであれば、のれん等調整額や評価・換算差額等の細かい点にも改めて(もしかすると初めて)注意が必要となるでしょう。
なお、子会社株式の売却時には当該案件のPMOチームまたはその周辺に通常その子会社の実務担当者が参画しているものとは思いますが、ストラクチャリングの細かい検討に当該担当者は深く関与しないあるいは当該担当者が経理財務分野の細かい実務に必ずしも精通していないといった状況も考えられます。このようなときに親会社のPMOチームで子会社の前期末の決算書を引っ張り出してきて、そのBSのみを確認して、配当が可能といった判断をくだすのは危険な場合があり、期中の情報の確認や財務会計アドバイザーの見解を求める等慎重な対応が必要です(実際の意思決定については後述)。
自己株式取得パターンの概要と留意点
次に2. の具体的な形については、例えば、譲渡対象群に含まれる一部の子会社(孫会社)に外部の少数株主がいる状態で、案件としてはそういった会社も含めて全て買い手の100%支配下になる前提(買い手以外に譲渡対称群の持分を持つ者はいない)で進んでいる場合に、当該子会社(孫会社)自身に少数株主から株式を取得させるケースや、対象会社に個人株主と法人株主があり、個人株主の株式は買い手が直接取得する一方で法人株主の株式は対象会社が取得するといったケースです。
これについては、買い手(または売り手)が求める資本構造を実現するための必要な手続(手段)として自己株式の取得が行われる面もあれば、タックスメリットを追求した結果(経済的な目的)として行われる面もあるでしょう。
タックスメリットという意味では、法人の株主にとって保有する株式を発行会社自身に取得される(つまり自己株式の取得)ことは、税務上買い手への売却の場合と異なり、みなし配当として取り扱われるという特徴があります(個人株主でもみなし配当はありますが、メリットになるとは限らない)。これにより(みなされた)配当部分は(完全子会社でない場合)一部が益金不算入となるのと同時に、株式の譲渡対価は資本金等の額相当分に限定されるため、税務上の譲渡益を圧縮または譲渡損を拡大させることが可能となります。
(みなし配当)
法人株主A社が保有するB社株式を発行会社B社に取得されることを考えます。関係する金額等は以下の通りとします。
・株式の買取金額:40百万円
・B社の資本金等の額(※):100百万円
・A社のB社への持株比率:30%
(※)税務上の資本金等の額は、実際にはここでこのような金額であると詳細に説明できる性質のものではありませんが、ここでは単純にB社の資本金の額と同じ(B社には資本準備金残高がない)ものとします(詳細は税務の専門書等を参照)。
ここでA社が受け取った金額のうち資本金等の額相当は100百万円×30%=30百万円であり、みなし配当は40百万円−30百万円=10百万円となります。
よって、形式的にはA社は株式を40百万円で売ったと見えますが、税務的には30百万円で売却し、プラス10百万円の配当を得た、という取り扱いとなります。
自己株式の取得はいわゆる配当そのものとは異なりますが、このようなケースでは配当と同じ財源規制に服することとなり、したがってこれまで出てきたような剰余金の分配可能額が問題となります。
対象会社の設立年度が古く、過去から蓄積した利益剰余金が多い一方で、事業内容は成熟してしまっておりDCF法等による株式価値はそれほど高いものが見込まれない場合などでは問題は小さいかもしれません。しかし対象会社が若い会社で、設立来利益はほとんど計上していないものの魅力的な事業計画があり相応の株式価値がつく場合には問題が生じます。すなわち自己株式を取得したくても、その高い株価で買い取ることができるような剰余金(分配可能額)が存在しないということになるわけです。なお、これはあくまで計算上の分配可能額の不足という問題であるため、仮に金融機関から融資を受けられて買取資金自体はしっかりと手当てできる、ということになったとしても何ら問題の解消にはつながりません。分配可能額と必要資金量はそれぞれパラレルに考慮する必要があります。
現実の案件では、FA(ファイナンシャルアドバイザー)含め個別に対応策が検討されることとなりますが、一般的に考えられるのは、
資本金、準備金が過大であればこれを取り崩す。そのための株主総会開催のほか債権者保護手続が必要な場合もあり、法的なハンドリングが求められる。
対象会社の保有資産で含み益の大きいものがある場合これを処分することで売却益を計上し、利益剰余金を積み上げる。ただし、前述のように当該利益を分配可能額としてカウントするには年度末の決算を待つ必要があり、機動性には欠ける。
外部(M&Aの文脈では主に買い手)から資本の形で対象会社に資金拠出する。買い手にとっては、広い意味での買収資金の一部を対象会社への資本提供という形で用いるということになる。提供額は、資金量として必要な分ではなく、あくまで分配可能額として必要な分になるということに注意が必要である。
M&A当事者自身の覚悟が重要
上記のように、M&Aで配当や分配可能額が問題となる場合、売り手および買い手ともに利害当事者となる可能性があります。ストラクチャリングや課題解決策についてはFAも関与の上で検討されていくことになりますが、具体的な分配可能額はいくらなのか?という点になると、通常FAでは算定をしてもらえないことが多いのではないかと推察します(概算はあり得るかと思われます)。
案件により別途財務会計アドバイザーがアサインされていることもあり得るためこちらに助けを求めるという道もありますが、彼らも対象会社(分配可能額が問題となる会社)の監査を継続的にやってきているということは一般的にないはずですので、例えばかつての商法下で配当可能利益の確認をしていた監査法人と同様のレベル感で分配可能額の算定にコミットするというのはこちらもなかなか難しいであろうと考えられます(その案件で初めて関与した会社のことでもあり、また現行会社法施行以降は会計事務所が配当の実行可能性に問題意識を持つこと自体が実務の中でなくなってきてしまっている)。
結局のところ、その配当等を行うことによる利害当事者である売り手または買い手自身が(サポートは受けながらも)主導し、またコミットして分配可能額を確認していくしかないというのが実務的な立場からの結論となります。このような言い方をすると、案件のPMOチームが経営企画部門中心であったりする場合には、え?となってしまうことも考えられますが、ただ一方で当該配当等の実現可能性は、ストラクチャーの根幹であったり、案件のエコノミクスの重要要素であったりしますので、案件を主導していく以上避けて通れないキーポイントであるということを言わざるを得ません。
さいごに
剰余金の分配可能額は、表面的には法務の技術的な論点であり、上場企業が毎年これを適切に遵守して配当を行なっている限りにおいては、特段注目もされないような内容です。しかしながら実際には様々な落とし穴があり、本項で細かく触れられなかったものでも以下のような論点がまだまだあります。
臨時計算書類(臨時決算)における注意点やメリット/デメリット
連結配当規制を適用したい会社はどのような条件が必要か
M&A以外の組織再編・グループ再編における留意事項
M&Aの場面でも用いられる現物分配など関係論点
企業の経理ご担当の方はもちろんですが、特にM&Aの場面で問題に対処されている方々には、安易に結論を出さない、法務・会計・税務など複合的に助言を求める、シビアな問題であることを認識しつつ当事者として覚悟を持つ、といったことを意識していただきたいと思います。
#MA #エムアンドエー #MandA #会計士 #fas #分配可能額 #配当可能利益 #配当可能限度額 #剰余金 #会社法
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
