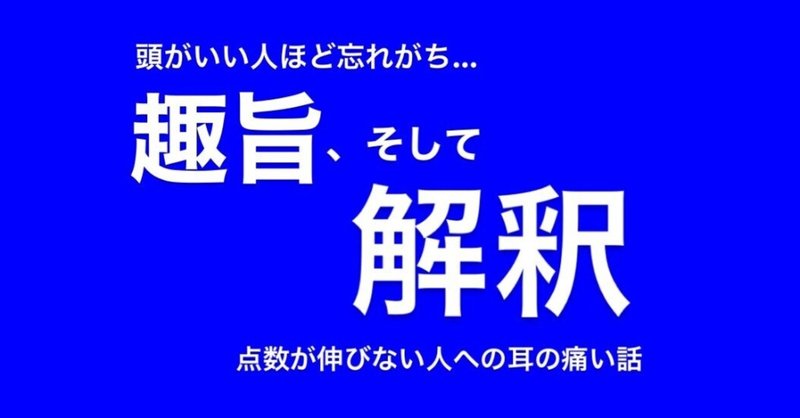
【弁理士試験】#004 頭がいい人ほどやってしまう悪い論述
#003では、条文の内容は、具体的な事案への適用を考えることによって、真に理解できることをお伝えしました。
今回は具体的な事案への適用を考える際に必ずしなければいけないアレ(つまり省いた時点で不合格となる)、そう、「法解釈」について、まずは少しだけお話します。
条文は抽象的
頭のいい人ほど「法解釈」があることに気付けない!?
弁理士試験は、「具体的な事案に対する知的財産権法の適用について問われる試験」だということは、#002でお話しました。
法律の条文は非常に抽象的に記載されており、具体的な事案に対して条文を適用しようとした際、その条文にはドンピシャリの言葉が並んでいるわけではありません。
条文は、具体的な事案にそのまま適用することはできないのです。
条文の文言を、当該事案が適用できるように変換し、「法解釈」する必要があります。
どういうことでしょうか?
例えば、発明「地球表面全体を紫外線吸収フイルムで覆う方法」が、特許法29条1項柱書がいう「産業上利用できる発明」に該当するか判断するとします。その際は、①「『産業上利用できる発明』とは技術的観点から事実上利用できないことが明らかな発明はこれに該当しない」という解釈をし、かつ、②地球表面全体を覆うような巨大なフィルムを作成することは今日の技術では不可能であることを確認し、はじめて該当性を否定することができます。(なお、前者①が「法解釈」であり、後者②が「あてはめ」になります。この2点は最も重要ことですので、次回以降、「法的三段論法」の解説を兼ねて詳述します。)
頭の良い皆さんなら、発明「地球表面全体を紫外線吸収フイルムで覆う方法」は「産業上利用できる発明」には該当しないことは至極当然のことと思うでしょう。その結論に至る思考プロセスを意識までもなく、高速処理によって結論が出せてしまいます。それゆえに、その思考プロセスの中に、すくなくとも「法解釈」と「あてはめ」のプロセスがあることに気付けないのです。
論文式試験では、このような一見「当然」に思える思考プロセスを言語化していく必要あります。
(上述のとおり、具体的な事案に対する知的財産権法の適用を考える際は、法解釈が必須であることから、「具体的な事案に対する知的財産権法の適用を問う試験」は、それと同時に、「法解釈を問う試験」ともいえるでしょう。しかし、法解釈さえできればいいのかといえば、法解釈は問われている処理の一要素にすぎません。「あてはめ」という難関もあります。なので、「法解釈を問う試験」とは思わないでほしいです。)
ミッション:条文の行間を読め!
では「法解釈」とは、具体的にどうすればよいのでしょうか?
それは条文の文言に記載されていない行間を読むことです。
これこそがまさに「解釈」です。
「解釈」について簡単な例をみてみましょう。
Aは、山をバイクで下山中、高さ50mは下らない峡谷にかかる木製の橋桁を備えた古い吊橋にさしかかりました。橋の横をみると、以下が記載された看板がありました。
「1948年設置 この橋は馬で渡るべからず。 設置者B」
この看板には、バイクで渡ってよいかは何ら記載されていません。
したがって、この看板をAに適用し、車で通行できるかを判断するには看板を解釈する必要があります。
そこで、看板の行間を読んでみましょう。
・・・・。
そうです、看板の文言にはそれ以上の情報はないのです。
なので、行間を読むには、看板の文言に現れていないその背後に思いを巡らせる必要があります。
まずは、この橋が木製の吊り橋であることから、この看板の設置者は「橋の強度が高くなく重い物が通ると崩落の危険がある」ということを知らせたかったのかもしれません。このようの立場からは、この看板の趣旨は、重い物が橋を通ることを防ぐ点にあり、看板の「馬」には、馬以外の重い物も含まれるということになりそうです。
(なお、この点、馬以外の重い物も通行を禁止するのであれば、「重い物での通行禁止」等とその旨を端的に書いているはずであり、「馬」と記載されていることと矛盾するとの反論もあり得ます。この点、1948年の看板設置当時はこの橋を渡り得る重い物といえば馬だけだったという事情を説明して反論できるかもしれません。)
また、さらにいえば、どのくらい重い物であれば「馬」に含まれるのでしょうか?馬と同程度の重さでしょうか?看板の設置が1948年で当時は馬と同程度の重さを想定していたかもしれませんが、更に70年が経過し、木製の橋ということで劣化が生じている可能性を踏まえれば、「馬と同程度の重さ」よりも軽い物であっても、相当の重さがあれば「馬」に含まれるといえそうです。あとはバイクがこれに該当するかという問題ですが、馬ほどではないが一定の重さがある等の評価をし、Aはバイクで通行できないという結論を出すことができます。
他方、この橋が「設置者B」という記載からBの私有物であり、その上で、Bは、橋が汚れる等の理由から、ピンポイントに「馬」だけはは通らないでほしいということを知らせたかったのかもしれません。このような立場からは、この看板の趣旨は、馬(動物)の通行防ぐ点にあり、看板の文言に忠実に、「馬」には馬以外の物は含まれないことになりそうです。あとは、バイクは馬ではないので、Aはバイクで通行できるという結論を出すことができます。
避けてはとおれない「趣旨」の勉強
「解釈」の出発点は「趣旨」にある
上記の例でも分かるとおり、ルールの文言をそのまま検討事案に適用はできません。そして、ルールの文言を「解釈」するには、文言を離れ、その背後にある「趣旨」に思いを巡らせる必要があります。
そう、「解釈」においてキーとなる必要不可欠な要素は「趣旨」なのです。
ルールの「趣旨」をどうとらえるかによって、ルールの文言の範囲が全く異なってきます。
弁理士試験において、合理的な結論を導くためには、条文の「趣旨」を正しく指摘することが非常に重要となります。
「趣旨」を間違うと、上記の例のとおり、答案の結論が真逆になることもあり、おそろしいものです。
※[頭の体操]
私たちの日常生活にも、このような解釈が必要なルールだらけです。頭の体操に、ルールの「趣旨」を意識して、以下の行為が禁止されているか考えてみてください。
・「この公園で野球は禁止」という看板がある公園で、キャッチボールはいいのか?バッドの素振りはいいのか?はたまたバトミントンはいいのか?
・「他のお客様の迷惑になる行為は禁止」という貼紙がある電車で、通話はいいのか?声を出さないビデオチャットはいいのか?逆に「他のお客様の迷惑になる行為は禁止」という看板がある駐車場では、通話はいいのか?)
「趣旨」はどうやって決まる
ルールの「趣旨」は、本来であれば、そのルールを作った人の意図になるはずです。しかし、実はこれは間違えです。
そもそも、作った人の意図なんか知る由もないことは多々あります。
先の例であれば、看板設置者Bの意図となるでしょうが、Bに聞かない限りはわかりません。また作った人が誰かわからないこともあります。法律の場合、立法者の意図とは誰の意図でしょうか?(法律の文言案を作った担当者?担当省庁の大臣?国会議員?知財法であれば産業構造審議会の委員?)
仮に、ルールを作った人の意図が判明したとしても、これだけでは決めることはできません。ルールの意味合いは時代と共に絶えず変化するものです。
これはつまり、ルールができて時間が経過した場合は、当初の意図とは異なる機能を発揮している可能性も十分にあり、この場合は、ルールを作った当初の意図をぶつけて解釈したとしても、それは現時点では的を得ないことになるでしょう。(先の例でいえば、設置者Bは「馬」が嫌いであるから看板を設置したものの、時が経過し橋が傷んだため、この看板は重い物が通行することを防ぐという効果を発揮するようになり、Bがそのまま設置し続けた場合には、看板設置当初の趣旨のみで解釈しても意味がありません。)
したがって、法律の「趣旨」は、その条文を解釈する時点における様々な要素を考慮して、総合的に判断する必要があり、その代表的な考慮要素として、①立法者の意図(分かれば)、②当該条文の効果、③他の制度・条文との関係、を少なくとも検討するべきといえます。
「趣旨」の勉強法はコレしかない
「青本」は覚えなくていい
条文の「趣旨」は青本に書いてあるとよく言われます。
これを鵜呑みにしてはいけません。
先の述べたとおり、立法者の意図だけでは、条文を解釈する時点での「趣旨」といえない可能性が高く、不十分です。
また、青本には、すべての条文の、すべての文言について、立法者の意図が記載されているわけはありません。
なので正確には、「青本には、立法者の意図が中心となって『趣旨』を考える上で参考になる情報が記載されている箇所もチラホラあります。」でしょうか。
それではどのように「趣旨」を特定すればよいでしょうか?
いくつか考えてみましょう。
例1:訂正の目的
例えば、請求項における「~によって柑橘類の検査方法」という記載を「~によってミカン科のミカン属・キンカン属に属する植物の検査方法」と訂正する場合は、特許法126条1項3号の「明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正」に該当するか検討するとします。
まずは、「明瞭でない記載の釈明」とは何を意味するか解釈する必要があります。それでは、本号の趣旨(立法者の意図)を青本(467頁以下)で探してみましょう。
しかしながら、この点は明確に規定されていないようです。本問では結局、青本は役に立ちません。
<考慮要素>①立法者の意図
②当該条文の効果
③他の制度・条文との関係
つぎに、考慮要素②・③を検討します。
まず当該条文の効果については、当該条文は訂正が認められる目的が規定であることから、「明瞭でない記載の釈明」であれば訂正が許され得るということです。なお、訂正によって、はじめから訂正後の内容で権利が存在したとみなされることになります(特許法128条)。
また、他の条文との関係について、特許法126条1項1号「特許請求の範囲の減縮」や、同項2号「誤記又は誤訳の訂正」に該当する場合は、特許法126条7項の独立特許要件が課されるのに対し、他方、同項3号「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正に該当する場合は、これが課されておりません。
これらの事項から、特許法は、訂正後の発明で特許権が存在したとみなされるため、訂正後の発明が特許要件を満たすことを要求しているものと考えられます。そうであれば、訂正後の発明について、本来であれば、一律に特許要件を課す必要がありそうです。しかし、「明瞭でない記載の釈明」については課されていない、つまりこれは、課す必要がないことを意味しています。それはなぜでしょう?
訂正前の発明は特許となっていることから特許要件を満たしているといえます。これらから導き出せる答えは、特許法は、「明瞭でない記載の釈明」であれば、特許要件を満たしている訂正前の発明と、訂正後の発明が同一であるといえるため、訂正後の発明に改めて特許要件を課す必要がないと考えているということになります。
そうであれば、「明瞭でない記載の釈明」を規定する「趣旨」は、特許発明の技術的範囲が変わってしまう「特許請求の範囲の減縮」等と区別する点にあり、「特許請求の範囲の減縮」とは、訂正の前後で特許発明の技術的範囲が変わらないような訂正を意味すると解釈できるでしょう。
そして本件についてみると、「~によって柑橘類の検査方法」という記載を「~によってミカン科のミカン属・キンカン属に属する植物の検査方法」と訂正しています。他方、柑橘類の定義は、「ミカン科のミカン属・キンカン属・カラタチ属に属する植物」です。つまり、訂正後の発明は、「カラタチ属に属する植物の検査方法」が含まれなくなるという点で、特許発明の技術的範囲が変わっています。よって、「明瞭でない記載の釈明」には該当しないと結論を出すことができます。
例2:産業上利用できる発明
例えば、発明「地球表面全体を紫外線吸収フイルムで覆う方法」が、特許法29条1項柱書がいう「産業上利用できる発明」に該当するかという冒頭の例を趣旨も踏まえて検討するとします。
「産業上利用できる発明」の解釈について、その「趣旨」を考えます。まずは、青本(86頁)の記載をみてみましょう。
<産業上利用することができる発明>特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を総称して工業所有権という用語が一般的に使用されていたが、それは本来フランス語のプロプリエテ・アンデュストリエルを訳したものであるといわれている。しかし、ここにいう原語のアンデュストリエルは狭義の工業に限られるべきものではなく、むしろ産業という意義に近い。このことと同様に旧法一条にいう「工業的」とは農業、商業、鉱業等と対立した意味における狭義の工業のみに限定されるものではなく、広く農業、鉱業等も包含したものとして考えられてきた。このように旧法においては用語と実体間にずれがあったわけであるが、現行法はこのずれを埋める意味において改正したものであって、実体的な改正を意図したものではない。ここにいう産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。
「産業上利用できる発明」の解釈について、「産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。」と記載があります。これを反対解釈すれば、学術的・実験的にのみ利用することができる発明に該当しない限りは、すべて「産業上利用できる発明」と解釈できることになります。
しかし、これではあまりにも広すぎるような気がします。
先に述べたとおり、青本は、立法者の立法当時の意図を中心に記載したにすぎず、考慮要素の1つでしかないのです。本問でもまた、青本は役に立ちません。
<考慮要素>①立法者の意図
②当該条文の効果
③他の制度・条文との関係
それでは、考慮要素②・③を検討します。
効果については、「産業上利用できる発明」に該当する場合は、他の要件を充足すれば特許を受けることができることになります。特許となれば特許権者が独占して実施することができます。
他の制度・条文との関係について、特許制度とは、産業の発達のために、新規な発明の公開の代償として独占権を付与するものであることから、特許出願に際しては、発明の詳細な説明の記載(当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な程度)が求められ(特許法36条3項3号、同4項1号)、かつ、その内容が公開され(特許法64条等)、公衆に利用の機会が与えられます。
これらの事項から、特許法は、特許の対象となる発明は、当業者が実際に実施できることを前提としていることが読み取れます(実際に実施できなくてよいのであれば、特許法36条4項で「当業者が実施できる程度の説明」を要求する意味がありません。)。したがって、本条の「趣旨」は、当業者が実際に実施できない発明を特許の対象から除くことも狙いの1つであるといえ、この点からは、「産業上利用できる発明」には、技術的観点から事実上利用できないことが明らかな発明はこれに該当しないと解釈できることになります。
あとは、地球表面全体を覆うような巨大なフィルムを作成することは今日の技術では不可能であると評価できることを指摘し、「産業上利用できる発明」には該当しないと結論を出すことができます。
悪い例として、青本の記載を「趣旨」とみて論述してみましょう。
「本条は、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明を排除する趣旨であることから、学術的、実験的にのみ利用することができる発明は、産業上利用することができる発明には該当しない。本件についてみると、地球表面全体を覆うような巨大なフィルムは、実験的にのみ利用することができる発明であるから、これに該当しない。」となるでしょうか。これでは頭に疑問符が浮かびます。「地球表面全体を覆うような巨大なフィルム」=「実験的にのみ利用することができる発明」という等式に論理の飛躍があるからです。(このような論理の飛躍は、「当てはめ」を軽んじる人に起こりがちですが、これは解釈が悪い例になります。なお、あてはめも非常に大切ですので、後日しっかりとまとめます。)
青本のインプットに明け暮れたた場合は、このようなイビツな解釈を展開しかねず、大変危険です。
(強引にこのイビツさを解消するとすれば、「地球表面全体を覆うような巨大なフィルムは、学術的、実験的にのみ利用することができる発明ではないから、産業上利用できる発明に該当する。」と、明らかに「不正解」的な結論にいくしかないかもしれない….)
だから「青本」は役立たず
上記2つの例を見ていただいたらわかるとおり、青本には、法解釈に必要な「趣旨」は書かれていません。
つまり、青本をいくら覚えても、全く意味がないのです。
(それに青本の記載だけで解釈した場合は大事故になりましたね。)
「趣旨」は、具体的な事案に合わせて自分で絞り出すしかありません。
それには、特に、②当該条文の効果、③他の制度・条文との関係という考慮要素が重要になってきます。
上記の例で、僕は、例1では検討対象と同じ条文の126条7項を、例2では他の条項である特許法36条4項を、決め手としてもってきました。これが唯一の正解ではないとしても、特許法の体系的理解の下、横断的な指摘があり得るのであって、これはつまり、「『趣旨』はこう作る!」といった必勝メソッドはないのです。
感覚としては、毎回が閃きであり、しかし、思いつくか思いつかないかのギャンブルというわけではなく、当然そうなるよなという感じです。
僕は、アウトプットを通して、繰り返し練習する他はないと考えています。
(もし何かよいメソッドを思いつけば随時更新したいと思います。)
「趣旨」に裏付けられた「法解釈」を忘れてはいけない
まとめます。
しつこいですが、弁理士試験は、「具体的な事案に対する知的財産権法の適用について問われる試験」です。
しかし、条文の文言は抽象的であり、具体的な事案にそのまま適用することはできません。
そこで、条文の文言を「解釈」し、検討している事案に適用できるように言い換える必要があります。
そしてその「解釈」は、条文の「趣旨」をどのように捉えるかによって決まります。
「趣旨」は、その条文を解釈する時点における様々な要素を考慮して、総合的に判断する必要があり、その代表的な考慮要素として、①立法者の意図(青本を参照)、②当該条文の効果、③他の制度・条文との関係、を少なくとも検討する必要があります。
もうお分かりいただけたと思いますが、論文試験では、上述のプロセスを言語化すればよいだけです。
どうでしょう?インプットの勉強がいかに最終的にしなければいけないことの一面であるかが見えてきませんでしょうか。
やることは分かりました。
さあ、過去問の答案を書きましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
