
日本海軍艦艇命名考(3) 軍縮条約まで
日本海軍の艦艇の命名の歴史をたどっています。今回はワシントン軍縮条約まで。前回の記事は以下になります。
日露戦争後
日露戦争も結末が見えつつあった明治38(1905)年8月22日から9月30日までのどこかで「艦艇命名標準」が制定されたと推測される(前回参照)。このとき実際に決まったのは、戦艦には国名、一等巡洋艦には山の名、二等巡洋艦と通報艦には川の名、砲艦には名所旧跡、といった具合だろう。この標準が適用されるのは新造などによる新規取得の場合のみであって、艦歴の途中で艦種が変更されても原則として改名されることはない。つまり新造が想定されない艦種については標準を定める必要性そのものがない。内部的には規定されていたのかもしれないが実例で確認もできない。三等巡洋艦や海防艦がこうした例に該当する。水雷母艦については大正期に新造計画が立ち上がったが明治38年の時点では他艦種からの転用が主であり新造は想定されていなかったのではないか。
上の記事では割愛したが、海軍省の原案には「扶桑」「秋津洲」などの特殊な艦名は適宜再使用するとの項目が含まれていた。明治天皇は維新で功績があった軍艦の名や日清・日露戦争で功績があった軍艦の名は再使用すること、事故で喪失した艦の名前を再使用する場合は少なくとも二、三年は期間をあけることとの指示があった。それについて海軍省としても特に異存はなかったのだが、ただ維新で功績を挙げた艦の例として明治天皇が挙げたのが「第一丁卯」「第二丁卯」だったのである。両艦はもと長州藩船で明治政府に献納されたものだが、比較的短期間で両艦とも事故で失なわれており特筆するような功績は残されていない。なぜ明治天皇がこの両艦を例に挙げたのかはわからない。海軍省も総論としては依存ないが「第一丁卯」「第二丁卯」については「終わり方がよくないので再使用するにはよく検討が必要」と回答している。実際両艦の名前は以後再使用されることはなかった。
日露戦争がはじまってまもない明治37(1904)年2月13日、イギリスに発注された一等戦艦に「鹿島(かしま)」「香取(かとり)」と命名された。まだ命名標準の定まっていない時期であり、それぞれ茨城県の鹿島神宮、千葉県の香取神宮からとられた。
命名標準に関するやりとりがなされていた最中の明治38(1905)年6月11日、いずれも国産の一等戦艦「安芸(あき)」「薩摩(さつま)」、一等巡洋艦「筑波(つくば)」「生駒(いこま)」「鞍馬(くらま)」「伊吹(いぶき)」が命名されている。6月6日の明治天皇の指示にある「戦艦は国名、一等巡洋艦は山の名」にのっとったものとみられる。
前回既述だが同年9月30日に二等巡洋艦「利根(とね)」、通報艦「淀(よど)」が、12月6日に通報艦「最上(もがみ)」が命名された。いずれも川の名である。
明治38(1905)年12月12日に艦艇類別標準が改定されて戦艦の等級が廃止された。二等戦艦は海防艦に類別変更された。
また艦艇類別標準の外として運送船、病院船、工作船が規定された。
明治42(1909)年には戦艦「摂津(せっつ)」「河内(かわち)」、二等巡洋艦「筑摩(ちくま)」「矢矧(やはぎ)」「平戸(ひらど)」が命名された。「摂津」「河内」は旧国名、「筑摩」「矢矧」は川の名だが、「平戸」は島の名である。このころは二等巡洋艦の艦名として島の名も想定されていたのかもしれない。しかし大正時代に入ると島の名は敷設艇に使われるようになる(昭和期には海防艦に広く使われる)。

明治44(1911)年には一等巡洋艦「金剛(こんごう)」「比叡(ひえい)」「榛名(はるな)」「霧島(きりしま)」、二等砲艦「鳥羽(とば)」が命名された。「金剛」以下4隻は巡洋戦艦として就役したが艦名選定時は一等巡洋艦だった。「鳥羽」は伊勢神宮に近い景勝地である。
大正元(1912)年8月28日に艦艇類別標準が改正される。巡洋戦艦が新設される一方で、水雷母艦・通報艦と、巡洋艦と海防艦のうち三等が廃止された。巡洋戦艦の艦名は一等巡洋艦と同様に山の名とされた。
同年、二等砲艦「嵯峨(さが)」が命名される。京都近郊の行楽地である。
大正3(1914)年、戦艦「扶桑(ふそう)」「山城(やましろ)」「伊勢(いせ)」「日向(ひゅうが)」が命名される。「扶桑」は日本の雅称であり襲名でもある。「山城」「伊勢」「日向」は旧国名である。
第一次大戦の冒頭、ドイツが中国で租借していた膠州湾を攻略、軍艦の多くは脱出したが商船を3隻捕獲した。いずれも周辺の地名をとり「膠州(こうしゅう)」「青島(せいとう)」「労山(ろうざん)」と命名された。「青島」は膠州湾に面した都市、労山は膠州湾入り口に聳える山である。
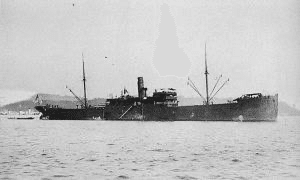
大正4(1915)年、新造の運送船に「志自岐丸(しじきまる)」と命名される。志々岐埼は長崎県平戸島の西端の岬(志自岐は当時の表記)。
八八艦隊時期
大正5(1916)年、戦艦「長門(ながと)」、二等巡洋艦「天龍(てんりゅう)」「龍田(たつた)」を命名。「長門」は旧国名、「天龍」「龍田」は川の名であるが襲名でもある。
大正5(1916)年5月17日、病院船を廃止し敷設船、工作船、運送船を総称して特務船と呼ぶこととした。この時期までに就役した特務船は既存船舶の転用が多いが、「志自岐」を初例として以降は岬の名があてられるようになる。大正4(1915)年の敷設船「勝力(かつりき)」、大正5(1916)年の運送船「剣埼(つるぎざき)」、大正6(1917)年の運送船「洲崎(すのさき)」「室戸(むろと)」「野島(のじま)」はいずれも岬の名である。
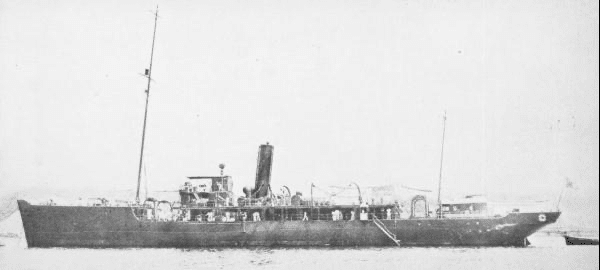
このころ、後年の八八艦隊につながる八四艦隊計画がはじまる。中心となる主力艦や戦闘艦艇だけにとどまらず艦隊の行動を支援するための補助艦艇の整備が盛り込まれ、結果として海軍が保有する艦艇のバリエーションが大幅に増えることとなった。命名標準としても対応が必要になる。
大正6(1917)年には戦艦「陸奥(むつ)」、二等巡洋艦「球磨(くま)」「多摩(たま)」。
大正7(1918)年には戦艦「加賀(かが)」「土佐(とさ)」、二等巡洋艦「北上(きたかみ)」「木曽(きそ)」「大井(おおい)」、運送船「能登呂(のとろ)」「知床(しれとこ)」「襟裳(えりも)」。
大正8(1919)年には巡洋戦艦「天城(あまぎ)」「赤城(あかぎ)」、二等巡洋艦「長良(ながら)」「五十鈴(いすず)」「名取『なとり)」、運送船「佐多(さた)」「野間(のま)」。
戦艦は旧国名、巡洋戦艦は山の名、二等巡洋艦は川の名、運送船などの特務船は岬の名が与えられており例外はない。
大正8(1919)年10月21日、特務船「鳳翔(ほうしょう)」が命名される。最終的には航空母艦として就役した。「鳳翔」は明治時代の砲艦の襲名でもあり、また「鳳」字も「翔」字も飛ぶことに関係する文字であるから、命名の時点から航空母艦として考えられていたことがわかる。艦艇類別標準が改定されて軍艦に航空母艦が追加されるのは翌大正9(1920)年4月のことである。

大正9(1920)年4月1日の艦艇類別標準改定では、航空母艦のほかに水雷母艦、敷設艦(敷設船を改称して移した)が軍艦に加わり、さらに特務艦艇類別標準が制定された。特務艦には工作艦と運送艦が、特務艇には敷設艇・掃海艇・潜水艦母艇が含まれた。
この時点で航空母艦・水雷母艦・敷設艦に類別された艦はすべて他艦種からの転用で新規命名はない。
大正9(1920)年に命名されたのは戦艦「紀伊(きい)」「尾張(おわり)」(旧国名)、巡洋戦艦「高雄(たかお)」「愛宕(あたご)」(山の名)、二等巡洋艦「由良(ゆら)」「阿武隈(あぶくま)」「鬼怒(きぬ)」(川の名)、二等砲艦「勿来(なこそ)」(名所旧跡)、運送艦「尻矢(しりや)」「石廊(いろう)」「鶴見(つるみ)」「神威(かもい)」(岬の名)。
「勿来」は勿来の関からとられたが、中国で警備にあたる砲艦が「来る勿かれ」では具合が悪いとして翌年「安宅(あたか)」と改名された。

大正10(1921)年に命名されたのは航空母艦「翔鶴(しょうかく)」、二等巡洋艦「加古(かこ)」「那珂(なか)」「川内(せんだい)」「神通(じんつう)」「夕張(ゆうばり)」(川の名)、二等砲艦「勢多(せた)」「堅田(かたた)」「比良(ひら)」「保津(ほづ)」(名所旧跡)、砕氷艦「大泊(おおどまり)」である。
はじめて航空母艦として命名された「翔鶴」は広く特殊名とされるが実際には空を飛ぶ動物(実在あるいは架空)からとられている。10月13日には「鳳翔」が航空母艦に移された。
8月2日、特務艦に砕氷艦が追加された。「大泊」は樺太の町の名であるが湾の名でもあり、後者と解釈される。
ワシントン軍縮条約
大正10(1921)年から11(1922)年にかけてアメリカ、ワシントンで日米英仏伊5カ国による軍縮会議が開かれ、主力艦の総数を制限して新規建造を停止することとなる。すでに命名済みの艦のなかにも消え去ったり、あるいは他の艦種に移されたりするものが多く現れた。
原則として一度命名された艦名は艦種がかわっても改名されることはないから、航空母艦に改造された「赤城」「加賀」は戦艦としての旧国名や巡洋戦艦としての山の名を名乗り続けた。「加古」の名前は一等巡洋艦に転用された。

大正11(1922)年から13(1924)年にかけて特務艦に測量艦・練習特務艦・標的艦が追加されている。実際にこれらの艦種に充当されたのは第一線からはずされた艦の転用ではあるのだが、軍縮条約は後方支援にあたる艦種の充実をもたらした。
大正11(1922)年に命名されたのは一等巡洋艦「衣笠(きぬがさ)」「古鷹(ふるたか)」(山の名)、水雷母艦「長鯨(ちょうげい)」、運送艦「隠戸(おんど)」「間宮(まみや)」「鳴戸(なると)」「早鞆(はやとも)」である。
水雷母艦「長鯨」ははじめて計画時から水雷母艦として設計されたものであり、海棲生物からとられた。なお大正13(1924)年12月1日に水雷母艦は潜水母艦と改称した。
運送艦はいずれも海峡または水道の名で、特務艦としては新しいパターンとなる。以後の実例をみても特務艦はその艦種にかかわらず広く岬、海湾、海峡または水道の名をつけるというものであったらしい。ただし例外もあった。

大正12(1923)年には一等巡洋艦「青葉(あおば)」「妙高(みょうこう)」「那智(なち)」が命名された。
大正14(1925)年に命名されたのは一等巡洋艦「足柄(あしがら)」「羽黒(はぐろ)」である。
軍艦建造のペースが落ちており、かつ中心が一等巡洋艦に移っていることが見てとれる。
まとめ
八八艦隊計画とワシントン軍縮条約は、結果として日本海軍において後方支援にあたる補助艦艇の種類と数を充実させた。それにともなって制度もあわせて整備された。後世の目からすればまだ不十分な部分はあったが、太平洋戦争を戦う準備が出来つつあったと言えるだろう。
この時期に命名された艦艇の多くは太平洋戦争にも登場している。
次回は時系列を追うことをいったん止めて、水雷艇と駆逐艦の命名について検討したい。
おわりに
自分で書きながら「単に時系列でイベントを列記するだけで意味があるんだろうか」と思っていたのですが実際にやってみるとこれまで気づいていなかったことが見えて来ました。全体を眺めることで新しい発見が得られたのは収穫です。そんなこととっくに知ってた、という方もおられるでしょうが。
ではまた次回お会いしましょう。
(カバー画像は航空母艦に改造された「赤城」)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
