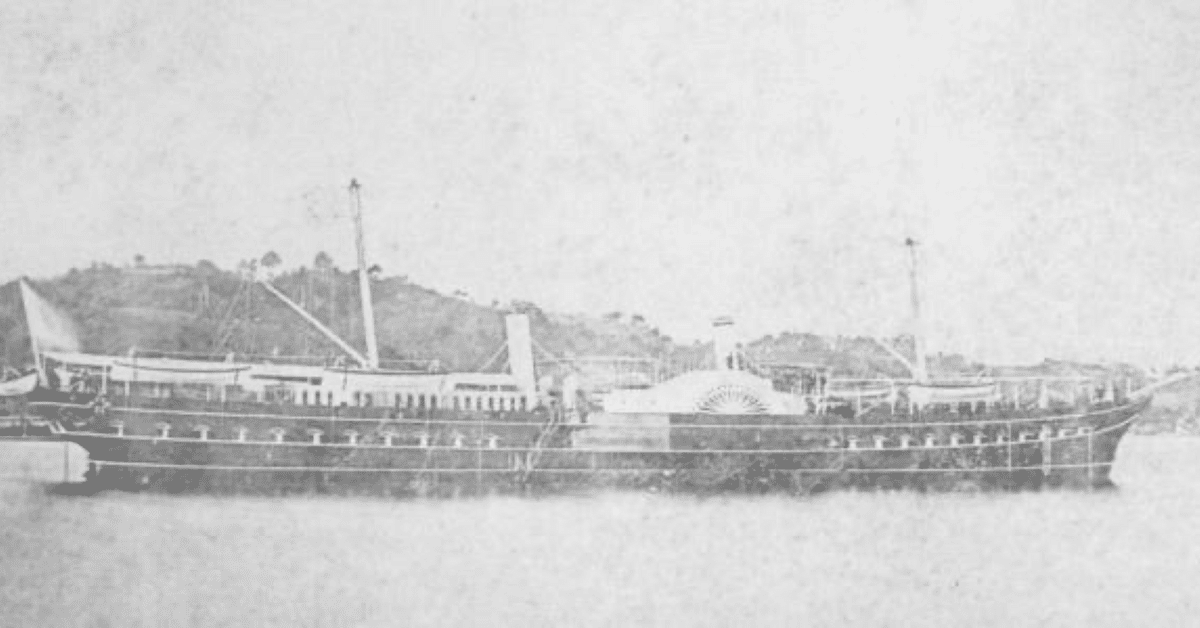
聯合艦隊司令長官伝 (9)角田秀松
歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は角田秀松です。
総説の記事と、前回の記事は以下になります。
江華島事件
角田秀松は嘉永3(1850)年2月12日に会津藩に仕える医師の家に生まれた。戊辰戦争に幕府方として従軍し、青森県に移された(厳密にはいったん除封のうえ再興)主家に従って下北半島に赴いた。その後商船の船員として身を立てたが、乗船が台湾出兵のために雇い入れられたことをきっかけに海軍と接点を持った。まず雇員という形で長崎の海軍事務所に勤務し、砲艦雲揚に乗り組んだ。明治7(1874)年12月22日には正式に海軍少尉に任官する。翌年9月、井上良馨艦長が指揮する雲揚は朝鮮との武力衝突である江華島事件を引き起こす。角田少尉は陸戦隊指揮官のひとりとして上陸して砲台を占拠した。
帰国後は国産スループ清輝に移った。艦長はまたも井上良馨である。西南戦争では機関不調もあり大きな戦闘は経験しなかった。終戦直後の明治10(1877)年9月28日に海軍中尉に進級し、翌明治11(1877)年はじめから地中海を経てイギリスまで往復した。帰国したのは明治12(1879)年5月のことである。5月27日に海軍大尉に進級し、まもなく装甲艦東副長に補せられた。明治13(1880)年の水雷練習所、水雷術練習艦迅鯨を皮切りに水雷関係の配置が続く。明治16(1883)年2月10日に海軍少佐に進級し、海軍省水雷局、長浦水雷営、迅鯨艦長、横須賀水雷司令を歴任した。明治20(1887)年10月25日に海軍大佐に進級する(この時期、海軍中佐の階級は廃止されている)。巡洋艦浪速艦長を2年つとめ、佐世保知港事(のちの港務部長に相当)をさらに2年つとめて海軍軍令部第一局長に補せられる。作戦計画を担当する主務者の役割だった。
日清戦争の開戦を軍令部第一局長として迎える。広島に設置された大本営で海軍作戦全般の指導にあたった。黄海海戦や威海衛の攻略を経て清国艦隊が無力化されると角田は第一局長を退いた。
常備艦隊司令長官
清国艦隊が壊滅し、戦局の焦点は割譲された台湾の平定に移った。明治28(1895)年8月15日に海軍少将に進級すると同時に台湾総督府の海軍局長兼参謀副長に任じられる。このあと職名は変わるが樺山資紀総督、のち乃木希典総督(桂太郎は短期間就任したが赴任しなかった)を海軍参謀の長として支えた。なお、薩摩や佐賀が強い海軍の中で将官に進級したのは、戊辰戦争の「賊軍」である会津出身者では角田がはじめてだった。
帰国すると、佐世保鎮守府と呉鎮守府の司令官を相次いでつとめた。鎮守府司令官は、司令長官をたすけ所轄組織を統率監督して鎮守府の業務を整理する、とされているが明確な職掌は規定されておらずまもなく廃止された。鮫島員規長官のもとで常備艦隊司令官をつとめたあと、明治33(1900)年5月20日に海軍中将に進級すると同時に海軍艦政本部長に補せられる。佐官時代に水雷関係の配置が多かったことを買われたのだろうか。海軍艦政本部は艦船や兵器全般の主に技術的な側面を広く担当する海軍省の外局で、本部長の格は高かった。当時の日本海軍では世界的にも最新レベルの軍艦を導入している最中であり、こうした軍艦の技術的な問題を解決して戦力化するためにも艦政本部の役割は重要だった。
明治34(1901)年10月1日に東郷平八郎を引き継いで常備艦隊司令長官に親補される。これも会津出身者では初めてになるが、そもそもこれまでの長官(常備小艦隊司令官も含む)は全員が薩摩、長州か佐賀の出身者に限られていた。角田が長官の時代に日露戦争で日本海軍の主力となる六六艦隊がほぼ完成した。1年弱つとめて待命となる。
竹敷要港部司令官
待命になって1年が経過すると休職になる。休職が2年続くと自動的に予備役編入となるが、それ以前に予備役に編入される可能性も高い。しかし幸か不幸か、その前に日露戦争が始まった。角田が起用されたのは竹敷要港部司令官で、親補職を歴任した角田にとっては格下げになるが、朝鮮海峡の真ん中、対馬に位置する竹敷の重要度は勝るとも劣らなかった。竹敷要港には多数の水雷艇をはじめとする守備部隊が配置されて朝鮮海峡に睨みを効かせるとともに、日本本土と朝鮮半島の連絡路を守った。水雷専門家の角田にとっては適材適所だっただろう。しかし準戦地ともいえる土地での長期の勤務で体調を崩し、平時体制への復帰直前に病死した。戦病死扱いとなり、嗣子武雄に明治40(1907)年10月2日男爵が授けられた。
角田秀松は明治38(1905)年12月13日死去。満55歳。海軍中将従三位勲一等功二級。贈男爵。

おわりに
角田秀松は会津出身ということもあってか歴代長官の中でも特に無名ですが、日露戦争中の竹敷要港部司令官としての功績はもっと評価されてもいいんじゃないかと思います。出羽重遠の先輩にあたるわけですね。
次回は日高壮之丞です。ではまた次回お会いしましょう。
(カバー画像は副長、艦長をつとめた迅鯨)
附録(履歴)
嘉永 3(1850). 2.12 生
明 7(1874).10. 7 長崎海軍出張所雇
明 7(1874).11. 5 雲揚乗組
明 7(1874).12.22 海軍少尉
明 8(1875).11. 4 清輝乗組
明 8(1875).12.12 孟春乗組
明 9(1876). 4. 6 清輝乗組
明10(1877). 9.28 海軍中尉
明12(1879). 5.27 海軍大尉
明12(1879). 9.18 東乗組
明12(1879). 9.27 東副長
明13(1880). 3.24 扶桑乗組
明13(1880). 4.30 海軍水雷練習所在勤
明15(1882). 8. 3 迅鯨副長心得
明15(1882).10.30 海軍水雷練習所副長
明16(1883). 2.10 海軍少佐
明16(1883). 2.16 海軍省水雷局副長
明19(1886). 1.29 長浦水雷営長
明19(1886). 2. 6 長浦水雷営長/長浦水雷営武庫主事
明19(1886). 2.15 長浦水雷営長心得/迅鯨艦長心得/長浦水雷営武庫主事
明19(1886). 5.10 横須賀鎮守府水雷司令兼武器部次長
明19(1886). 6.19 長浦兵器部派出所
明19(1886). 6.23 長浦兵器部派出所/長浦水雷営長心得
明20(1887).10.25 海軍大佐
明20(1887).10.27 横須賀軍港水雷司令/長浦水雷営長
明22(1889). 5.15 浪速艦長
明24(1891). 6.17 佐世保知港事/佐世保予備艦長
明26(1893). 5.20 海軍軍令部第一局長
明27(1894). 6.19 海軍軍令部第一局長兼第二局長
明27(1894). 7.13 海軍軍令部第一局長
明28(1895). 6. 4 海軍軍令部出仕
明28(1895). 8.15 海軍少将 台湾総督府参謀副長兼海軍局長
明29(1896). 4. 1 台湾総督府軍務局海軍部長
明30(1897).11. 1 台湾総督府海軍参謀長
明30(1897).12.27 佐世保鎮守府司令官
明31(1898). 5.14 呉鎮守府司令官
明32(1899). 1.19 常備艦隊司令官
明33(1900). 5.20 海軍中将 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員
明34(1901). 7. 3 海軍将官会議議員
明34(1901).10. 1 常備艦隊司令長官
明35(1902). 7.26 待命被仰付
明36(1903). 7.26 休職被仰付
明36(1903).12.28 竹敷要港部司令官
明38(1905).12.13 死去
明40(1907).10. 2 男爵
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
