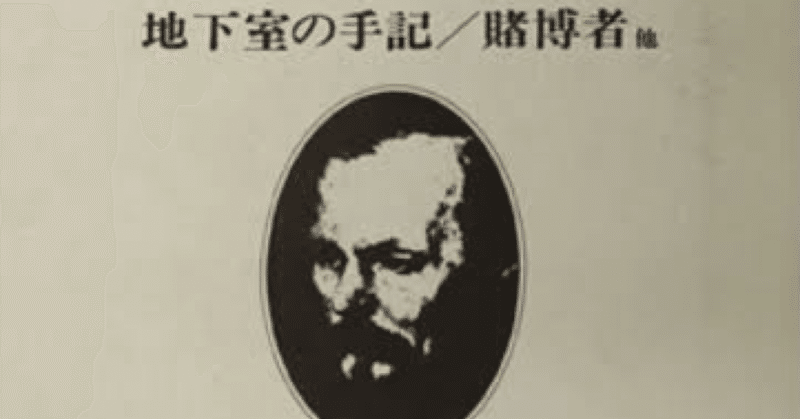
ドストエフスキー『地下室の手記』授業レポート
短いですが、600字程度で自分の意見を書いてみなさい、という課題に対して僕が書いた文章です。
バフチンは、『ドストエフスキーの創作の問題』(平凡社ライブラリー) の中で、『地下室の手記』をこのように評している。
「この小説には、自分自身と自分の対象だけを充足させるような言葉、つまりモノローグ的な言葉はひとつもない。〔…〕かれは、あたかも自分が他者の意見を恐れていると他社が思いはしないかと恐れている。〔…〕主人公の自意識と言葉が陥る出口なき悪循環が、ここから生じてくる」(p.236)
「自身にたいする他者の意識の支配から解放され、自分自身のために自分自身にたどりつこう とする最後の必死の試みとして、他者のなかでの自分のイメージを破壊し、他者のなかでの自分のイメージを汚染させること――これが、実際、地下室の人間の告白全体の定位である」(p.242)
「世界についての言葉のなかにも、かれにとってはいわば二つの声〔=自分自身についての声と世界についての声〕がひびいており、それらのあいだでかれは自分や自分の世界を見いだすことができない。というのも、世界をも、かれは逃げ道をともなって定義づけているからである」(p.252)
「地下室の人間の言葉とは、純粋に呼びかけの言葉である。〔…〕あるのは呼びかける言葉、他の言葉と対話的に接触する言葉、言葉に向けられた、言葉についての言葉だけなのである。」(p.253)
バフチンが「内的無限性への傾向」と呼んだ主人公の終わりのない対話の構造は、マンデルブロ集合で有名な、数学における「フラクタル構造」と似ているように思う。しかし、確かに「最終的な定義」を自らに与えることを頑なに拒否し、あるいは寧ろ憎むがゆえに、「終わり」がないというバフチンの指摘は、構造上正しいと思うが、私は、地下室の主人はもはや、自ら産んだその終わりのない対話の構造全体の形相に対する恐怖さえ覚えていると思う。実際バフチンは「このさい、地下室の人間はこうしたことすべてをみごとに自覚しており、他者にたいする自分の態度が歩んでいる円環に出口がないことをよく理解している」と言っている。地下室の主人がそもそも何故このようにしか語り得ないのかに加え、どうして抜け出せないのかについて、バフチンが仮に見落としている(p.232~254で)ものがあるとすれば、それは、フロイトのいう「反復強迫」のようなものを、醒めた主人公が感じているからではないだろうか。自ら創出した無限に反復する対話のフラクタル構造から永遠に抜け出せないという恐怖は、主人公に一層その創出も、その恐怖も、その没落をも加速させる作用を持つと、私は思う。
授業で扱ったド・マンは、露出の無限反復について「こうした構造は、暴露の欲望を暴露するという説明が暗示するように、入れ子状に引き継がれていく。暴露が新たな段階を迎えるごとに、さらに深刻な羞恥、暴露のさらなる不可能性が現れ、この不可能性を出し抜くことに、さらなる満足感が呼び覚まされる」と述べているが、これはルソーがいわゆる「露出狂」であったからで、地下室の主人においては「不可能性」に対して(パロディ的に述べた上で一時の快楽を感じることを除いて、本来は)恐怖と憎しみのみを感じているように思う。ここにおいて、もしかするとルソーと地下室の主人は対立するのかもしれない。
※ 追記で、個人的にはアウグスティヌス、ルソー、ドストエフスキーが三者ともに『告白』を中年期に書いているのが面白いな、と思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
