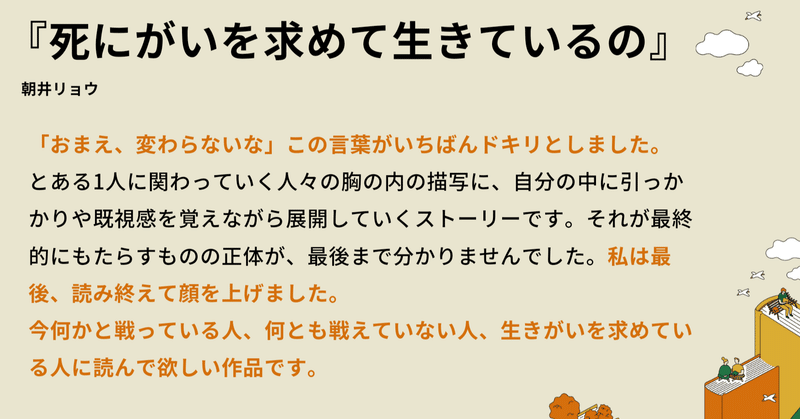
「死にがいを求めて生きているの」を読んで
朝井リョウ著「死にがいを求めて生きているの」を読み終えた。つい昨日だ。思えば、一冊の本をまるまる読み終えたのは久しぶりだった。子供を産んで、仕事を始めてからゆっくり本を読む時間から随分と遠ざかっていた。
私はこの本を、note感想文の推薦図書だったから選んだ。最初にnote感想文募集の記事を知り、参加してみたくなり、そこから読む本を探した。本来の本を読むという主旨からは外れているかもしれない。読んだ本が面白かったから感想を書いたのではなく、感想を書くために本を読んだのだ。
「手段と目的が逆転している」。作中に出てくるセリフだ。この物語は、6人の登場人物がとある1人と関わりながら展開していく。その中で時代も巡っていく。最初はおそらく今。そこから平成初期まで遡り、「今」までを辿っていくその中身は、とても既視感があった。それもそのはずだ。後書きを読むと、作者が私と同年代だった。物語の中で登場人物たちが直面する出来事、引っかかり、思考。小、中、大とそのフィールドが上がっていく中で、私も同じようなことを感じ、思い、流されてきたことを覚えていた。作者がもしかしたら話に投影し、なぞったかもしれないことを、きっと私も思い返すことが出来る。
この話のテーマは「対立」であるという。
すべての話で対立がありありと描かれている訳では無い。そこには対立は悪であると教えられ、それをしたくはないと水面下で足掻く人達がいた。そんな中で誰かと、何かと、常に対立しながら生きていくのが、6人と関わっていく堀北雄介という人物だった。彼は周りから、端的に言うと引かれていた。目立ちたがり屋で口先ばかりで、何かを率いている自分をアピールすることしか考えていない堀北は、何も変わらないまま体だけ大きくなっていく。小中までは目立つ男子という立ち位置でも、周りが体とともに中身も変わっていく中で不変の堀北は、周囲から敬遠される対象だった。
一方、堀北雄介の幼馴染で友人である南水智也という人物は、その対極にいた。争いごとに興味が無く、穏やかで落ち着いている彼の存在は、堀北雄介の存在を時折際立たせていた。
私たちは教えられてきた。
「みんな仲良く」「仲間はずれはダメ」「1番じゃなくていい」「あなたらしくいたらいい」「個性を大事に」
そんな耳障りのいいやわらかい言葉たちとは裏腹に、世間は正反対であるとちゃんと気づけたのはいつだったんだろう。もしかしたら、まだちゃんとは気づけていないのかもしれない。どこかで「私らしくいていいんだ」と自分に言い聞かせたい私も存在している。上記に並べた言葉たちは、一種の洗脳であり呪いだ。それは綺麗に磨いたワックスの下にこびり付いた汚れのように、私の中に残り続けている。
みんな仲良くなんてできないことも、自分らしくしたら生きづらいことも、大事にされない個性があることも、もう全部わかっている。だからその事実をちゃんと知っても、きっと絶望はしない。私たちは耳障りのいい言葉たちと一緒に、そうではない現実もずっと目の当たりにしてきた。そこから目をそらす方法を学びながらも、視界の片隅にある世界を知っていた。
読みながら感じたのは、私の中にある複数の目だ。登場人物が抱く感情に強い共感を覚え、その人物と同じ景色が見えているのに、同時に堀北雄介が見ている景色も見えるのだ。その見える景色の違いにヒヤリとして、しかしその距離はあまりにも近くて、それにもヒヤリとする。
作中で「自分は絶対こうはならないって言い切れない気持ち悪さがある」というセリフが出てくる。堀北雄介、南水智也と小学校時代に仲の良かった前田一洋のセリフだ。前田はこうも続ける。「自分の中にも堀北雄介がいる。何かと戦っているように見せかけて、本当は別のものから逃げ続けている(要約)」この部分を読み、私はドキリとした。自分の心が文章になっていた。堀北雄介のことを、客観的に見てるだけでいたい。やってることに対して有り得ないよねと切り捨てるだけでいたいのに、少しだけ同調してしまう自分がいるのが気持ち悪くてたまらない。
前田だけではない。
白井友里子の、いつの間にか無くしてしまった「絶対」という気持ちを奮い立たせる熱さに触れ、流されるまま社会人として生活を送っている自らに対しての燻るような思い。
坂本亜矢奈の、南水智也へのもどかしく揺れ動く気持ち。
安藤与志樹が、堀北雄介と同じような虚栄心を振りかざしていることに自ら気付き、それを認め、肩の荷を下ろしたその安堵。
弓削晃久の、取り返しのつかない劣等感。
どれもこれも、私には覚えがあった。その気持ちを知っていた。触れたことも、抱えたこともあった。誰かと比べ、自分に他人を介入させたり、自ら介入したり。大事にしなきゃと抱きしめていたものを離したときに、信じられないくらい心が軽くなったこと。全部全部覚えがあって、だからこそ、そのときどきでの彼らの表情を、肌の赤みを、冷や汗を、見える景色の色を、とてもリアルに思い浮かべることが出来た。
堀北祐介は、人間は三つに分けられると語った。
「一つ目は、生きがいがあって、それが家族や仕事、つまり自分以外の他者や社会に向いてる人。これが一番生きやすい。生きる意味を考えなくても毎日が自動的に過ぎていく。最高だよ」
「二つ目は、生きがいはあるけどそれが他者や社会には向いてない人。趣味や好きなことがある。やりたいことがある。自己実現人間。自分のためにやっていたことが、結果的に他者や社会をよくすることに繋がるケースもある」
「三つめは、生きがいがない人。自分自身のための生命維持装置としてのみ、存在する人」
堀北祐介は、南水智也を二つ目で、自分は現在三つ目だと言った。
「皆とりあえず働くのは、三つ目の人間に堕ちたくないからなんだろうなと思う。自分が自分のためだけに存在し続ける方が気が狂いそうになることを、どこかで気づいている」
堀北雄介は、ずっと探していた。生きがいを。自分の存在する理由を、誰かと競うことで成り立たせていた。死ぬまでの役割が欲しいだけなんだと語る堀北雄介に、南水智也の「それは生きがいではなく、死にがいじゃないか」という言葉が、どれだけ彼に響いたかはわからない。堀北雄介は淡々と、仕方が無いのだと語っていた。淡々としていたが、きっと彼がは自分で作り上げてきた競うための何かに、溺れないように必死だった。今までも、これからも。
南水智也のことが、この本を読み続けながらずっとわからなかった。作中の登場人物たちの脳裏にも、「どうしてこの二人、仲良いんだろう」という疑問が幾度も過っている。私も同じだった。どうしてずっと一緒にいるんだろう。小、中までなら幼馴染、腐れ縁という理由で納得もいく。でも大学まで同じで、まだ連絡を取っているなんてなんだか異常だとさえ感じた。それほどに二人の間には目に見えない大きな乖離がある気がした。
それが解きほどけていく終盤で、南水智也の過去が、心内が、私たち読者にだけ曝け出されていく。父親が幼い彼に巻いて、ずっと巻き続けた糸を、智也はきっと毎日解いていた。それでも絡まって、纏わりついて、切っても切り切れなくて、それは恐ろしい洗脳のように感じた。自我を忘れず、冷静を保っていると自覚しているであろう智也は、すでにがんじがらめだった。それでも必死で、絡まって覆われたものをはがそうとしていた。がんじがらめの隙間から、物事を見ようとしていた。先入観、自尊心、虚栄心、その場の感情。流されてもおかしくないすべてのものを、真摯に見ようとしていた。
誰とも競わず凪いだ海のようだった南水智也も、ずっと闘っていたことを知った。
私が思い出したのは、自分のSNSでの過去のことだ。
現在Twitterをやっているが、正確には一度やめて、もういちど始めた。そもそも最初は好きな芸能人が出来て、その人を応援したくて、同じく応援している人と繋がりたくて始めた。だんだんと、やっているうちに違和感を感じるようになった。作中の言葉が蘇る。
「手段と目的が逆転している」
応援したくてツイートしているはずなのに、ツイートしたくて、自分を見て欲しくて応援しているふりをしている人。
好きだからしていたことのはずなのに、反応を貰いたいがためにエスカレートしていく人。
この人がいるから生きていけるのだと、芸能人を生きがいにして、その行為に酔ってそれを発信し続ける人。
違和感はどんどん大きくなっていき、やがて私は遠巻きに見るようになった。自分の承認欲求を満たすために、好きなはずの相手を擦り減らしていく行為が気持ち悪くてたまらなかった。
それでも、思うのだ。
私の中にも、堀北雄介がいると。
何かを言い訳に、得ようとしたものがあった。ファンであることを建前に、承認欲求を満たそうとしたことがあった。本当はあまり響かなかった関係作品を、大袈裟に褒めて賛同を得た。
探し出せばたくさんいる「私の中の堀北雄介」は、きっとこれからも現れる。外に見える堀北雄介を見つけては、私は違う場所から眺められているのだと安心する。私は、一つ目だった。
「死にがい」とはなんだろう。読んで流されていったその単語は、題名であるはずなのにピンとこなかった。堀北雄介は、「何かとの摩擦が無いと、体温がなくなる」と言った。読み返して思った。つまりそれは「死」なのだ。雄介にとって、誰かと、何かと対立して、摩擦して生まれる温度は生きる理由だ。それがなくなってしまう「死」は、雄介の望む「死」ではない。
「死にがい」とはなんだろう。
「死にがい」の「かい」はきっと「甲斐」だ。辞書で調べると、「したことの結果としての効き目。効果。また、するだけの値打ち」とある。死んだ効き目。値打ち。それを決めるのはきっと、遺された側の人間だ。つまり雄介は、その「死にがい」を他者に認めさせたいのだ。
最後、智也は覚悟を決めた。雄介と、この世界と摩擦し、対話し、向き合って生きていくことを。ラストに語られる描写は壮大だ。壮大だが、私たちの目の前の世界のことだった。ずっと絡み合ってきた無数の摩擦を生む糸の上を、私たちは今歩いている。それは途切れない。どこかに蹲っても隠れても、必ず存在する糸を私も垂らしている。この世界の一つになっている。覚悟を決めて生きていくしかないのだと、諦めにも近い描写のラストに、私は顔を上げた。自然と顔を上げた。向き合わなければならない世界と、誰かと、できれば対立ではなく対話が出来たらと、そう思えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
