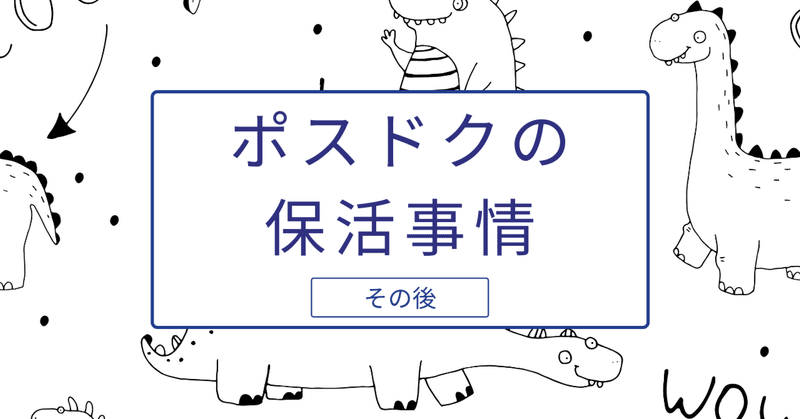
ポスドクの保活事情…のその後 「小1の壁②」
頼りは学童保育所
まず頼りにするのが「学童保育所」(もしくは「放課後学童クラブ」などと呼ばれる施設)です。厚生労働省のウェブサイトには以下のように定義されています。
児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
厚生労働省 放課後児童健全育成事業について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosodate/houkago/houkago.html
つまりは、家庭に代わって子どもを見守ってくれるのが学童保育所です。放課後、親が勤務中の時間や、夏休み等の長期休暇の際や、運動会等の行事の振替えによる平日の休校日にも対応してもらえる、大変心強い存在です。
自治体によっても異なりますが、公立小学校に連携して設置され、自治体の運営なので一般的に費用の利用者負担も高くはなく、保育園に通っていた子どもの多くが利用を希望します。ここでも「待機児童問題」は健全で、人数に制限があるため希望者全員が入所できるわけではなく、保育園の時と同様、申請書によって必要の優先度が審査され、入所の可否が決まります。幸いにして、我が子の入学した学校には十分な定員を確保した学童保育所が増設されたこともあり、保育園入所の時ほど苦労することなく、学童入所がきまりほっとしました。
学童保育所には馴染めたものの…
学童保育所は休校の平日にも対応をしてくれるので、学童に入所が決まった新一年生の多くは、4月1日、小学校の入学式以前の春休みから学童保育所に通うことになります。保育園の頃のような慣らし期間というものもなく、我が子も初日からお弁当持参で朝の8時半から夕方の5時まで、学童で過ごしました。
我が子の場合は、小学校入学までの間に、保育園、幼稚園、子ども園と、転園を重ねてきた経緯から、同じ学童保育所に通う同級生のなかにも友人が多くいたこともあり、スムーズに馴染むことができたようです。保育園のように迎え時に先生から一日の様子を聞くという機会はなくなるので、子ども本人の語るところでしか中の様子はわかりませんが、ボードゲームやカードゲームなど大人数で遊ぶゲーム類が用意されているほか、児童書やマンガも揃っているということでした。話を聞く限りでは、児童館、図書館、マンガ喫茶、ボードゲームカフェの要素をあわせたような、かなり遊び甲斐がある魅力的な施設にみえます。
公立小学校に「学習指導要領」が定められ、ある程度均一化されているのとは異なり、学童の施設や備品、方針は自治体ごとの違いが大きいとききます。その意味では、我が子の通う学童保育所が整った環境にあったことには感謝しなければなりません。しかし、環境が整っていても、やはり通うのを渋る場合もあります。学校に通っている同級生には当然、学童保育所に通っていない子もいますし、放課後に学童児以外の友達と遊びたいということも出てきます。また、学童保育所の仲間のなかにも、習い事や親の就労の都合などで定期的におやすみしたり早く退所する子もいるので、保育園と異なり、「毎日通うのが当たり前」という感覚を持ちにくい面があります。
記事の続きを読む

株式会社アカリク(https://acaric.co.jp/)は「知恵の流通の最適化」という理念の下、大学院生やポスドクを対象とした求人情報の提供やキャリアセミナーを開催しています。また、現役大学院生から大学院修了者まで幅広く対応したエージェントサービスも提供しています。他にもLaTeXの環境をクラウド化できるサービスも運営しています。
【運営サービス一覧】
◆就職ナビサイト「アカリク」
◆アカリクイベント
◆アカリク就職エージェント
◆アカリクキャリア
◆Cloud LaTeX
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
