
偏見まみれのビルディバイド考察-第2話「命を燃やせ!刹那的なゲーム性-手札は命より重い、わけではないけど手札がないと命を守れないし命を奪えない」
前回までのあらすじ
限界サラリーマンあーちゃんは、誰に頼まれるでもなくビルディバイドの全テリトリーを採点し始め、その言い訳を全5回くらいでnoteに連載を始めたのであった。
ビルディバイド世界にもたらされた「プレイアブル」なカード群を色別・種類別・時系列でまとめ、4弾以降の空白の半年間の存在を指摘。
奇しくもその半年間はシャドウバース・ワンピースといったクソデカ新興TCGの販売開始タイミングと一致しており、若干元気のない(あーちゃん調べ、諸説あり)ビルディバイド界隈の一因であると邪推している。
あくまで邪推であり、やはり偏見である。
依然として偏見ベースで話を進めていく所存である。
今回は「プレイアブル」というふんわり言葉を、ビルディバイドのゲーム性を考察するとともに掘り下げていく。
大前提
何事も前提を共有せずに話を始めると、ロクなことが起きない。
人はしばしば、クソデカ主語やクソデカ客体を持ち出して、見えない何かと戦ってしまう。(今この瞬間も、僕は存在しないクソデカ主語を使う人間と戦ってしまっているとも言える。)
なので、自分の偏見の大前提となるゲームシステムについて事前に共有しておく。
僕の考えるビルディバイド大原則は下記3点である。
1.盤面のユニットの数だけ選択肢が生まれる
①相手のライフを詰める
②相手のユニットを破壊する。
③相手からのライフ/ユニットへの攻撃に備えて立たせておく
原則、ユニット1体につき3つの選択肢がある。(例外はバーサーク等制約により選択肢が少ないケース、ヴェロニカ等タップトリガーで選択肢が多いケース。)
要するに自分のライフを守り、相手のライフを削るのは盤面の生物である、ということである。
2.ビルディバイド世界の命は、儚い
①ライフから飛んでくる除去(序盤は基本的に即死)
②被ダメージを減らすためにも盤面の生物は除去しなければならない
③自ターンのみ大きくなるテリトリー効果、ユニット効果が多く、詰みにくいカードデザインがなされている
ターンをまたいで生物が生き残ることは稀である。除去に失敗すると相手に選択肢を与えてしまうため、除去しなければならないというのが実際のところである。
テリトリーも自ターンにのみ大きくなるもの、自ターンメインフェイズに除去を飛ばせるものなど自ターンの除去行動を肯定するものが多く、相手のターンにもサイズを維持するテリトリーは稀である。
その分ショットの除去力は高めに設定されており、半端な有利盤面ならショットで瓦解しうるため攻撃側もある程度のケアを要求される。
ビルディバイドの命は儚い。
3.手札が無ければ、君を殴れない。手札が無ければ、自分を守れない
①毎ターンのドロー枚数<アクションを取るときの消費
②手から打つ除去は使い切り、1-1交換
③ユニットも基本的に使い切り(命は儚い)
何かしらのアクションを取る場合、エナジー置き+プレイでカードを2枚使用する。毎ターンのドロー枚数は1枚なので、手札は原則減っていく。
どちらかがユニットを処理できなくなったときに、ゲームが傾く。ユニットの除去札orコンバット用の生物を適切に抱えるためのハンドリソースが必要になる。
ユニットを守るためのパワー増減カードや、相手ターンに使用できる除去札は、ハンドリソースが無ければ有効シチュエーションを作りにくい。ハンドリソースの無いデッキには、クイックを構える余地がない≒相手に裏目を踏ますことが出来ない≒自分を守ることが出来ない
以上3点が僕の偏見の論拠である。
ふんわりとした話にふんわりとした話を重ねすぎてしまっているため、事実を陳列するパートに入る。
ビルディバイドのハンドの細さ
ビルディバイドにはゲーム中「テリトリー開放ターン」が存在する。
では、テリトリー開放時点でカードが何枚手札にあるのかを計算してみる。

テリトリー開放まで何もせず、エナジーを置いて相手にターンを渡す場合、開放時の手札は先攻なら3枚、後攻なら4枚である。

開放までにある程度のカードのやり取りが発生したケースを想定する。
この場合先手はテリトリー開放時点で手札は1枚のみであり、後手でも2枚となる。
ハンド枚数を減らさずにプレイできるユニット・コマンド、あるいは新兵器開発や発掘調査のようなカード枚数が増えるカードを使用した場合、ハンドが尽きるタイミングを遅らすことができる。

まとめ。ゲームシステム上、単純計算で先攻なら4回、後攻なら5回カードをプレイすると手札が尽きる仕様であり、登場時に手札が減らないor増えるカード群によってプレイ回数をかさ増しすることができる。
当たり前体操~
このゲーム性における「プレイアブル」なカードとは
限られたプレイ回数で、最大限のリターンが欲しくなるのが人の性ってやつで、とは言え効率だけ追い求めても殺伐としちゃうよねという、難しいバランス感覚が人生においてもカードゲームにおいても起こりうる。
しかし、実はこのビルディバイドにおいてそんな最大限のリターンみたいな挙動はおろか、最低限ハンドを維持する、みたいなカードですら貴重である非常に禁欲的なカードデザインがなされている。
そんなゲーム性・デザインにおけるプレイアブルの定義とは、
・自分の選択肢を増やす
・相手の選択肢を減らす
カード群であると、独断と偏見をもってここに宣言する。具体的に言うと5パターンくらいに大別される。
①死ににくいユニット

・体がでかい
・ダメージ軽減持ち
・自己蘇生持ち
盤面のユニットの数が選択肢であり、相手の除去が間に合わなくなったらゲームが傾く。ターンをまたいで生物が生き残りにくいゲーム性において、生き残りやすいカードは自身の選択肢を増やし、相手に除去の択を強いる、あるいは相手に除去の選択肢を諦めさせる事ができる。
そんな生物をテリトリー開放ターンに繰り出せるテリトリーはどう考えてもゲームシステム上の強者であると言わざるを得ない。
②手札が減らない(増える)カード

・登場時or使用時ドロー効果
・出たときデッキトップn枚中該当カード回収
現状あまりにも少ない。「選択肢を増やす」カード群である。
テリトリーにその機能が備わっているととてもハッピーなのだが、それだけ査定が高いらしくドロー効果以外のオマケをあまり貰えなかったりする。
③1枚で複数展開できるカード

・テリトリー解放時効果でオマケユニット追加
・アサルトテリトリー
・踏み倒し効果
基本的に1-1交換が大原則であるため、複数展開により生物が盤面に定着する確率を上げることができる。生物の枚数が選択肢の総数を増やす。くどい
特にアサルトテリトリーはゲームシステム上かなり強い挙動であり、相手がテリトリーに除去を打つ行動はアドバンテージ損挙動になる。
④1枚で複数除去できるカード

・全体ダメージ
・全体マイナス修正
・複数アタック持ち
1-1交換が大原則なので、1体で相手の盤面を複数除去することが出来たならかなりゲームを優位に進めることができる。相手の盤面を減らすことは選択肢を減らすことである。盤面劣勢を返しうるため、捲り札として期待したい。が、こちらもちゃんとバランス調整がなされていて現状テリトリーの補助火力がなければきちんと複数除去出来ないデザインがなされている。禁欲的~
⑤1枚で複数体分のライフレースが期待できるカード
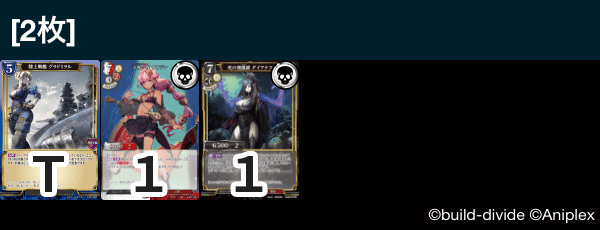
・hit追加
・クソデカhit
・踏み倒し効果
ハンド枚数がなんぼのもんじゃ死ねと駆け抜けよう、というカード群。ライフが減りすぎた相手に防御の択を強いることができる。グラドミラルによるヒット増が代表格。
基本的に殴りきったほうが勝ちというゲームなので、どこかでリスクを取って顔面を詰めないといけない。ヒット2なだけでちょっとプレイアブルに見える。
ヒットを通すために体がでかいとかブロックされないとか対象に取られないとか付いてるとなお良い。
そんな観点で「プレイアブル」を定義している。漏れはあるかもしれない。
けれどそんな意識外のカードをぶつけることに、カードゲーマーとして喜びを感じませんか?
プレイアブルなカード、出力の高いテリトリーは限られている。
だからこそ、挙動を読むことができる。対策をすることができる。
その対策をいなすことができる、その「いなし挙動」を潰すことができる。
特にビルディバイドは序盤の攻防戦はある程度パターン化されている。テリトリーの開放がマストだから。
ゆえにテリトリー開放付近でのアドバンテージ獲得挙動はデッキ構築段階で意識すべきことであり、そこを制す事ができたなら相手よりも多い選択肢をもって快適にゲームを進めることができるのだ。
まとめ:ビルディバイドの楽しさを広く知ってもらうためにも、新兵器開発配ろうよ
大前提を共有し、プレイアブルなカード群・テリトリー同士で遊ぶビルディバイドは楽しい。と僕は思っている。
テリトリー解放ターンに飛んでくる除去のケア、解放ターンにコンバットでアドバンテージを獲得されないような立ち回り、解放ずらし、そもそも不利益を被りにくいデッキ選択、その対策・・・。
ビルディバイドのゲーム性には、カードゲームの面白さが詰まっていると確信している。
詰みにくいシステムと、それでいてプレイング分岐を生むクイックプレイタイミングでのやり取り
細いリソース管理の中で発生する、テンポを取るかアドバンテージを取るかという選択
しかしそれはハンドリソースあってのことで、それをテリトリーやエース効果だけで補うことのできるデッキは限られている。
新兵器開発、もとい青系リソースカードさえあれば、大体のデッキを救うことができるはずで、しかしながら新兵器開発はその需要の割に供給量が多くないため価格が高止まりしてしまっている。
僕は初心者にこそ新兵器開発入りのデッキを握ってほしい。
(だから新兵器開発をばら撒いてほしいです)
次回予告とか
ビルディバイドのゲーム性を自分なりに言語化してみました。
こういった評価軸において、採点だったりプレイアブルカード選定をしてきた次第です。
くどいようですが、1ユーザーの偏見にまみれたゲーム観でしかありません。
ですがせっかくなのでこのまま思っていることをすべてnoteに表現していければと思っています。
次回以降は主要アーキタイプを、ここまでの評価軸をもって構築した上で、採点上位群のいるプレイ環境においてどのように変遷しうるかを綴っていこうと計画しています。
そんな環境変遷を体験できるBO3体験会があるらしい
興味のある方はお声がけください!一緒に色々なカードに触れて、ゲーム理解を深めていきましょう!もぎリーグ3も2月中に開催予定!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
