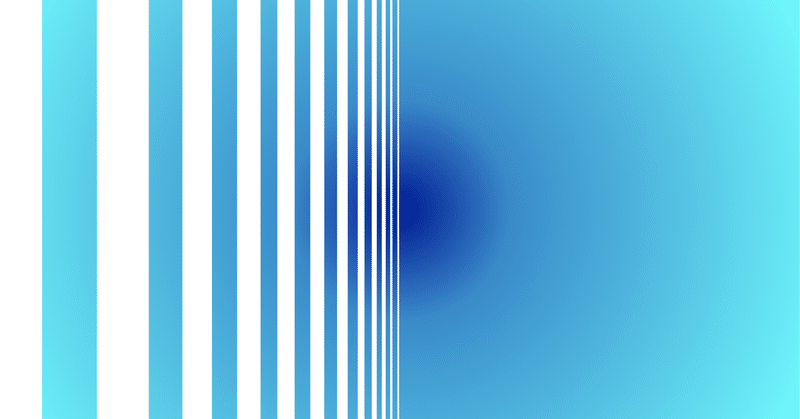
寓話 『 出会い、耕しの終わり 』
その時には言葉というものがなかったので、何と言うべきか分からぬものと、同じように分からぬものが、出会いそしてぶつかり、その反動で大きな空間が発生した。その空間の下の方の、ひずみとも言える深い奈落に、最初の衝突によって発生した沢山の塵が降り積り、大きな渦を作り上げ、そこからエネルギーが噴き出していた。
時代は下り、そのエネルギーが生命とも呼べる程に組織され、運動を開始し、よって時間が空間に流れ込み始めた頃、それまでの過程の大体を、視界の片隅で見守ってきたあるものは、物事の進みの余りにも気が遠くなる程の緩やかさに、誰にも聞かれぬ嘆息と溜息を漏らした。すると、二つの息吹はするりするりと、それまでに生まれていた命のそれぞれに溶け込んでいき、生命と物事の進みを大きく早めた。
神の息吹を受けたあるものは、生命の渦を解いて鉱物へと戻り大地を支えた。あるものは空と地を繋ぐ管、植物となった。あるものは植物を繋ぎ合わせる、そのために動き回る動物となり、その中のあるものは動物から一歩はみ出て、これら全体の依存とサイクルを見届けつつも調整する、神の健気な代理人となった。
それぞれのものはそれぞれに、他に特にやることもなく、後に地球と呼ばれるこの第三惑星で、緩やかなシンフォニーの第一楽章が始まった。
*
第二楽章つまり承へと進んだのはこのずっと後、今と呼ばれる時代から約一万年前、後に人間と呼ばれる一種族が、それまでは空に放ってきた槍という道具を、土に突き刺したことに起因する。偶然だったのか必然だったのか、今から丁度一万年前、その種族のある者が、土に突き刺さった槍を徐ろに抜き、そこに穿たれた穴をじっと見ていた。そこに一つの大きなアナロジーがあるように思えた。
それからその者は土に穴を穿つことに没入した。森の合間の平坦な地に、縦横無尽に気が向くままに、上下左右無数に穴を穿ち続けた。土表を占拠していた名も無き草々は薙ぎ倒され、土に混ぜ込まれて養分となり、同時に注入された空気は土壌を柔らかな寝台と化した。動物の肉を裂くのとは異なるような、特殊で完全な征服感がそこにはあった。
視界に収まる限りの平野を一様に、柔らかな土色の風景に帰した後、その者はその真ん中に満足そうに寝そべり、疲れを癒そうと数日を眠った。するとふと起きた時、自分の腰あたりの土中から、一つの新芽が生え伸びていることに気が付いた。どうも、腰巾着から滑り落ちた食用の木の実が、柔らかな土に落ちて速やかに根を張ったようだった。その者は興奮した。大地を征服、蹂躙し、更新したのである。自分で穿った穴の一つ一つに、今度は自らの意志と意図によって、木の実や種を一つ一つ挿し込んでいった。原始の時代においても強烈な、始原的とも言える快楽がそこにあった。
その者に続いて、その者から伝播した快楽に導かれるように、その種族の多くの者がこの原始的快楽〜土を蹂躙して更新し、自分が望んだ通りに子を産ませること〜にのめり込み嵌まり込んでいった。そのために木が倒され山が削られ、もっと後には海さえもが埋め立てられた。時代毎の些細な異なりはさておき、この時から人間は、土壌、森林と生命の守人という位置付けから離れ、ただ組織的かつ急進に、土を裸にして耕し、自分が望む子を繰り返し産ませ続けた。当初、耕せば耕すほど土は多くを産み、結果として人間も生み増やされていった。まるで土と女の多産は手を組んで進展しているかのようだった。
このようにして、人間と呼ばれる種の大多数は、土と女を使役することで増殖していく道を歩んでいった。そこから外れた進歩や静止を選んだ者や集団は、狭い平野に沢山の人間が詰め込まれて規則正しく動いている風景を、遠くから訝しんだように眺めていた。狩猟採集という、それまでの在り方を採り続けていた彼らは、数こそは少ないものの重厚な想像力を持ってして、自らの立つところの土を掘り崩し続ける平野の民の未来を、彼らにしか分からない未分化な言語やイマージュで語ったりしていて、森の精だけがそれにゆっくりと相槌を打った。
*
第三楽章つまり転、事の転換は約束された必然だった。実態としては細分化と均質化であった耕すという行為は、土そのものが孕んでいた多様性を次第に侵略し、遂に失わせてしまった。レーザーやケミカルによってターンオーバーを早め過ぎた肌のように、土が土として保持してきた構造は打ち壊されており、まともな角質層つまり表土が現れなくなっていた。土はただ柔らで均質な繊維層となっており、なけなしとなっていた有機無機双方の成長因子も、その時代を支えた最後の作物に吸い尽くされた。
人々は土から奪うだけではなかった。返せるものは返そうとし、不要となったものの内で有要と思われるものは土に返そうとしていた。しかしながら人間の恣意と選択などは自然にとって奇形でしかなく、返って目に見えぬアンバランスを土に蓄え、最終的な崩壊のインパクトを大きくしていた。異変は幾つかの面で見られていた。まず、時を追うごとに作物の質、実感としては味や色、特に味が変わっていった。言葉によって永遠の定点観測をする人間には気付かぬところで、作物は違うものへ姿を変えていて、最終的にはどの作物もが無味無臭の繊維質となっていった。一方では土がよく腐るようになっていた。鋤を入れて空気を入れてやらないとすぐに腐るようになったり、逆にそうするとすぐに腐るようになったりしていた。嫌気性であったり好気性であったりする一部の細菌群が、それまでのバランスを遠く離れて他を蹂躙し、増殖しているようだった。とかく人間の目や耳や手では分からぬが、臭いや味としては感じられるような深層のレベルで、土はもう構造を変えてしまったか、かつての土としての構造も機能も手放してしまったかのようだった。
全ては頃合いのように思えた。実を言うと土に従って人も不作となり、あらゆるレベルで奇形を抱えるようになっていた。それは作物中の栄養の不足やアンバランスによるのかもしれなかったし、またはそもそも農耕という居住形態そのものによるのかもしれなかった。それまでの生活形態と比べて明らかに、一人の人間が接する情報や触れる空間、そして浴びる刺激の種類は減り、何よりも質が落ちていた。人間は人間に囲い込まれ、四角く区切られた土地の狭さに収まりながら、同じ方向を向いて同じようにただ夕暮れを、耕すという行為をしながら時間を潰して待っていた。そして日が暮れると家に帰って土の分け前を喰い、翌朝にはまた囲いの中へと入って土を耕していた。
農耕に適する平野の開拓スピードを人口の上昇スピードが追い抜き、耕地面積当たりの人口密度が上昇してきたあたりから、事の悲惨さは極端になっていった。それ以外にもやることもやれることもなくなっていた人々は、時を追うごとに狭くなっていく担当区分に、それまでより増していく頻度で鋤を入れ続けた。もはや土に鉄をぶち当てていくだけのような自暴自棄さがそこにはあった。
すぐ隣の区分を伺うと、同じような背格好の同じような人が、やはり同じようにして荒々しく鋤を振り上げ、その鋤の頭はこちらの区分の領空を侵犯しつつ、こちらの頭をかち割りそうな程だった。このままだと土を殺めながら我々は、機械のような偶発的事故によって同胞を規則的に殺めてしまう事になる、と、極少数の耕しの民が慰めに空想し始めた頃、そんな滑稽な死傷事故が実際に連続し、その後にそれより滑稽な殺傷事件が多発した。もうこの頃には誰もが、狭い土地の僅かな土を耕し続ける疲労と徒労におかしくなっていて、互いを隣人として一切合切の恨みをぶつけ合うようになっていた。ということでこの時代の遺跡からは頭蓋陥没した人骨化石が多数出土する。
槍の使い方を変えることなく森で山で動物として動物を追い、時に植物を愛でたり拾ったりしたながら、山林の調和とバランスの一部であり続けた人々は、相変わらず遠くから、訝しげに平野の耕地を眺め渡していたのだが、彼らのある種の知的無力は平野の民に対してそれ以上の判断をすることも、これ以上の破滅を予言することもなかった。山林の原野と平野の耕地はパラレルに時を進めていた。
そうして平野の農耕民は、何も産まなくなった土の上で争いを始め、残り僅かな貯蔵物を奪い合ったり、極まれば互いの肉を貪りながら、それでも時間を掛けて少しずつ、この生活が終わりを迎えている事を理解し始めていた。しかしながら時に物事の進行そして転換と終焉は、そこに生きる人々の着実な理解と行動によるのでなく、空から降って来たような偶発的事象によって決されることがある。この度においては土から突如として溢れ出た黒い濁流が、土表の全てを流しそして燃やし尽くしたのであった。
この度の終焉、そして次なる段階への転換は、地下の深みから突如として齎された。耕しを投げ捨てて争いに明け暮れる社会を尻目に、土に変わらず鋤を入れ続けていた気狂いのような馬鹿真面目がいた。彼は土の上の現実から逃げおうせようと穴を下へ下へ深く深く掘り進めた。そしてもう誰の視線も届かない地底の闇に呑まれながら、遂にはこの時代の土台を成す太古からの地層の、ひずみに溜まり溜まっていた生命の黒い記憶にぶち当たった。
長大な縦穴の目に見えぬ奥底で、その阿呆が地球に最後の鋤を入れると、カチンかコツンと音が響いて、そこから地球の黒い血潮が、重力に逆行する滝のように溢れ出た。最後の鋤を入れた張本人は黒い濁流に流されて消え、耕され切った死の土地の一帯は、死が煮詰められた生命のスープに浸された。飲み込まれた家家から火が生命のスープに燃え移り、絶え間ない濃密な延焼が平野を洗い流して山にぶつかった。炎の乱舞はそれから数年は続いたが、これを記す物語も文字も灰となって消え、山に生きていた人々だけが歌としてその風景を語り伝えた。
こうしてとある一文明は破滅を迎えたが、この事件を契機としてまた違う一つの特異な文明が開始された。彼らは黒い生命のスープを原資とした錬金術、その上に家を建てる人々だった。
*
そして第四楽章は更なる転換を奏で、過去の営為に殺された土の全てが、アスファルトに覆われた時代に始まって終わる。
耕すことの遺伝子を孕んだ農耕の民は、この時代に土の代わりに時間〜抽象空間における豊穣の源泉〜を、かつての土のように耕すことで生きていた。抽象された果実は貨幣という名で約束され、それは遠く辺縁の土が産んだ作物との交換が予定されていた。担い手となる者共の知的能力の亢進に起因する若干の異なりはさておき、目に見えず手に触れぬ領域にある、我々には掴めぬほど複雑かつ壮大に展開するシステムを、直線のような鋤を入れて耕し続けること、その意味合いはこの時代でも勿論変わらず、細分化の末の均質化によって、複雑を単調に、豊穣を不毛に帰すことを意味していた。そのようなプロセスと相俟って起こる人々の認知と肉体における奇形の進行もあってか、全体的な事態が進んでいく程に事態の全体性が見失われていくという、皮肉な逆説も同時に展開されていた。
とかくこの新しい、石油と貨幣の時間文明で、人々はかねてよりの営為で殺した土に蓋をしながら、その上でやはりかつての営為と似たような様式に添いながら時間を、揃いも揃って同じように耕していた。時間に伴ってあらゆる体験と経験、その内の感覚や感情が細分化され均質化されていった。かつてと同様にまるで、薬剤によって新陳代謝が急かされた肌のように、急ピッチで粗造な角質がボロボロと、生み出される傍から捨てられていった。あらゆる物質や体験が記憶と一緒に消費され、その先のことや全体を知らぬままに忘れられていった。
この時代の人々の生き方は、この時代に生きる人々自身によってありとあらゆる風に形容され評価されていた。民主主義市場経済、大衆消費社会、マスアテンションエコノミー、時にメタバース、ある人によるとマトリックスーーー、その他人によって気ままに自由に呼称して崇めたり貶したりしていたのだが、誰が何をどのように言おうと、誰もがこの強力な構造から抜け出せずにいることだけは間違いなかった。耕すことの短期的利益から離脱することは難しく、離脱することの長期的利益を想像することはもっと難しく、何より、そんな人が社会に充分に存在することや、そのような人々が出会い、そして行動や活動を共にすることなどは、本当に本当に難しかった。
ここにはまたちょっと違う難しさと悲しさもあった。かつて同じ土地に展開された土を耕す農耕文明と違い、時間を耕すこの金融文明においては、人々を閉じ込める囲いが何処にあるのかが分かり辛かった。実態としては抽象空間においてそれまでと変わらず上下左右に、囲いは差別や階級として展開されていて、その中に生きる人々を絶対的に規定しており、よってその中に生きる人々は社会的な相対物と化していて、なので非常にアイロニカルに、生への絶対的感覚を得ることが以前より難しくなっていた。この土地に足で立って生きていること、この土地に生える植物を食し、この土地を走る動物を食すること、何より私は私であること、そのような素朴なプロセスと感覚を失いながら、そのような、充分なスペースと余裕がなければ不可能な生活を取り戻すことはもうあり得ない、社会を支持する各々はそのことに何となく勘付き始めていた。
ということでこの頃である。この圧倒的多産に彩られた不毛社会で、一見して理由のない殺傷や自殺が伝染病のように横行した末に、突如として目を瞑る、目を瞑る人が現れ始めたのは。彼らはまるで現実を否認し認知を黒いヴェールで覆ってしまうかのように、瞼を絶対の意志で落とし切っていた。目を瞑ること、最初それは一時的に流行する根無しのライフスタイルかと思われていたのだが、だんだんと目を瞑る人が増えてきて、本当にずっと目を瞑り続けて社会生活を放棄する人までもが出て来て、その末に絶命する人までもが遂に出た。そして時を追ってそのような、人ならぬ人々が増殖していく事態となった。
彼ら目を瞑る人の代謝は極端に低下しており、まるで根を張る植物のようにそこに鎮座し、何らかの経路で土と空と繋がっているかのようだった。そうとしか思えない程、何も食べずに長く生き、彼ら目を瞑る人の周囲の空気は緩やかに回転しているように思えた。植物への退化と証する人があり、社会と自然への新しい適応と評する人があった。それらの雑音を尻目に彼ら目を瞑る人々は、目が瞑られた漆黒の世界で、瞼の裏に時たま星のような光を仰ぎつつ、かつての現実の生活を遠い過去か惑星のように眺めながら、一方ではかつてより広く深く濃密に感じられる感覚世界を、目的も欲望もなく穏やかに漂っているかのようだった。求めるもののない境地で既にあらゆるものが与えられていることに気が付くような者もいた。
目を瞑る人が周りに増えると、その人も目を瞑った。目を瞑った人々の幾分かは、その暗闇の向こうに長大な歴史、あらゆる神話、生命の深淵な記憶を掘り当てて、そこから湧いてくる無限の果実を、同じ領域に達した異なる人々と混じり合いながら分かち合い、そして味わったりしていた。しかし現実の実際のレベルでは、不毛を極めた多産の末に、人々の瞑目と社会の活動停止という、明らかな最終的不毛が広がっていった。
目を開けて現実に対処し続けた人々は、それこそあらゆる手段を講じて社会の覚醒と活動の水準を維持しようとした。しかし、静かな植物のような新生児が生まれた時、しかもそれが、目を瞑り代謝を極度に低下させた妊婦の腹から帝王切開で救い出された赤ん坊であり、そしてその後も満足そうに目を瞑りながら成長を拒絶し、新生児のサイズのままで数年を生き続け、その後に静かに息を引き取ったこと、そのような一連のストーリーがニュースとしてこの文明圏に広く伝えられた時、そしてそんな新生児が着々と増えていることに人々が気がつき、それが事実や真実として共有された頃、まさにこの文明は、文明としての一切の意識的努力を終わらせることを、意識の奥深い領域において決定した。
*
それから暫くの時が過ぎ、欠伸も出なくなった頃にまたふと地球を眺め渡してみると、数として百億くらいの新種の植物が、この惑星の調和とバランスの核、またはネットワークとして動き始めていた。彼ら新種の植物の、鱗のような瞼の向こうに失われた瞳は闇に帰り、そこでは太古からの生命の圧縮記憶が渦巻きながら、またいつか空気に触れて土を満たすことを夢見ているようだった。
それまで山森にあった人々は、遂に平野に降り立ち槍を捨て、これら高次の植物の周りを一心に踊り続けた。そうして最期にこの星は、静寂と、たった少しの舞踊と音楽だけに満たされて、それらを音頭にゆったりとした回転を再開した。方向を失った完全は今も宇宙を浮遊している。
ae
