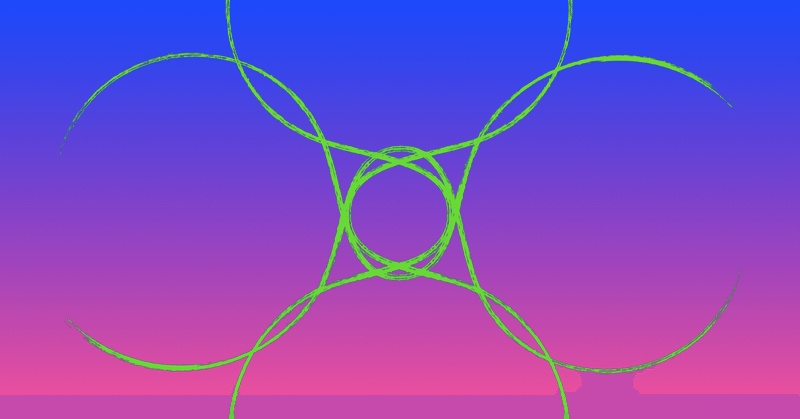
寓話 『 花街騒乱 』
パチン と 神様が指を鳴らした
するといくつかの時空が交錯した
波は常に灯台を越える
大統領は今日とて溜息をつき、頭をごりごりさすっていた。今より少し未来の、とんでもなく技術と制度が発達したこの世界帝国の、その巨大ピラミッドの頂点を成す彼の頭脳と心理は、常に陳情と不安〜不安とはここで彼に押し寄せる他者のそれであり、そしてその波に意識を攫われんとする彼のものであった〜に溢れようとしていて、今日も自分の頭蓋の輪郭を保つために彼は、溜息により体圧を下げ、そして自分の意識が肉体から飛び出していかないようにと、物理的な刺激によって自らを威嚇していた。
朝のブリーフィングはいつも、帝国を成す領土の方々の行政機関及び司法機関そして私企業に加えて教育機関や各種非営利団体からの報告で溢れ返っていた。時には活動家や革命家、それらの代理人、そして単なる奇抜な個人からの雄叫びも届けられた。立法府が収められた超高層ビルの最上階の、その遥か下方の地上から、時に組織され、時に組織されない市民の怒声が、ビルの鉄筋を揺らしながら這い上り、大統領の鼓膜を厳かに揺らした。黒々として騒めく黒点として以上には、彼はその誰もを視界に収めたことがなかった。
報告という言葉は中性的であり、雄叫びという言葉は肉体的に過ぎ、怒声という言葉は形式でしかない。その内容や実体は不満であり不平であり、折衝を装った強奪であり、よく言って陳情、そしてそれら全ての裏側にあるのはやはり不安であるように思えた。しかしそれらを唱える一人一人の人々は常に真剣な面持ちで、自分の意見や主張が客観や真実といったものに肉薄しているような印象を与えた。なので大統領がそれをそれとして聞き取れるようになったのは、皮肉なことに任期満了の直前であった。
こうして大統領はその座を退く少し前に、漸く、とんでもなく技術と制度が発達したこの世界帝国が、技術と制度が発達し切った末にとんでもない奇形を抱えてしまったこと、いや、発達し切った技術や制度というとんでもない奇形そのものになってしまったことに思い至った。それら夥しい奇形のそれぞれは複雑に噛み合い絡み合い、そうして全体として運動し続けているようだった。少なくともここ数世紀分の歴史はそのように単純化されるように思えた。彼の素朴な直感からすると、その運動こそがこの奇形の目的であり、そこで燃料となるは人間の辛苦であり疑似的な幸福であるように思えた。
この壮大な世界帝国で、公園といった素朴なものも含めて、あらゆる公共空間は義務と禁止で彩られていた。あらゆる場所が方向や行為について規定、定義されていた。それまでの社会が保持していた多くのスポーツや娯楽は、それ専用の空間でしか営めなくなっていて、それだけに偶発的な進歩を遂げにくくなっていた。結婚という習俗もまた同様だった。その目的が定義され、自動的に合目的的な行為とそうでない行為、そして違反に対する賠償やその背景にある責任が定義され尽くしていた。このような制度化、複雑化が急速に進み始めた当初は、幾分かの人々が反対してもいたのだが、上述した幾つかの概念(特に目的や賠償)が反対者の希望をも叶えるようになるまで制度が膨張してくと、どうしても反対者は消え去っていき、ただ制度の発達だけが残されて、結婚を筆頭としたあらゆる習俗は文言上、とかく制度として極限まで発達を遂げた。そしてその分だけ当事者である人間達は息を潜め、そのことに耐えられなくなると権利行使という形で制度通りに声を荒げ、それに飽きたり幻滅すると、同じくらい複雑怪奇なカウンタカルチャーを志向して、都市のモードとして人口に膾炙させてビジネスへ繋げたり、大陸から隔たった島嶼部で小規模なコミューンを流行らせては離散したりしていたが、長い目で見ると全ての反抗は、予定調和的に制度へと吸収されていくようだった。文化的レジスタントであった故人のドキュメンタリーが映画賞を受賞し、都市に巣食う不満を映画館という感情焼却場にて処理するまでが一連のスキームでさえあった。生まれ落ちた揺籠さえもがハイテクであった超過保護の世代にとって、本当の意味でのアナーキストになったり、実感や納得のある自由というものを思い描くことは困難だったのだ。
その他の側面においては、この社会は人々に、生活の様々な面で意識的なオプションを無数に提示してくれた。人間の想像力はそれらをどう駆使して、どのようにして(既に定義された)幸福を加算し不幸を減算していくかだけに注がれていた。品物を買う時には、期待に沿わなかった場合の対応オプションも選んで買うことが普通になっていた。生活必需品と呼ばれるような素朴な品々についてさえ、真面目な顔して訴訟オプションが提示されている始末であったが、この世界の誰もはこれを始末、終わりの始まりとは考えも感じもしなかった。終わりの始まりとは往々にしてそのようなものなのであろう。ちなみに、このようにして購買を複雑化した実際的要因としてよく挙げられるのは、情報の通信と処理にまつわる技術の異常発達であり、よってあらゆる訴訟や仲裁がアルゴリズムないしプログラムによって自動化されて、そのコストはかつての水道代レベルにまで低下していた。言い争うことはインフラとなっており、インフラの維持のために人々は争いの種を見つけたりばら撒いたりする必要が、少なくとも無意識下ではあったのかもしれなかった。環境と人間は組み合わさって発達し、一つの壮大な奇形を成長させつつあった、またはそれとして完成した。
物思いに耽りながら、大統領は自分が乗っかっている舞台装置を、漸く眺め渡しているような気分になった。当初は全てが、人間の幸福と快楽のために設計されていたし、そのように予想、期待されていたはずだった。しかしながら余りにも精巧で微細な構築物を設計し、そして実装する際に、往々にして人は視野狭窄に陥るのである。そのことを忘れる程に。そして複雑さを秘めたシステムが実際に発達していくに際して、人はどうしても視野狭窄による支配統制を加えてしまい、多様性や豊穣といった事態に進むはずであった可能性は、いつの間にか人為によってある種自然に、自己拘束や煩雑といった現状に陥って、誰もが身動きを失ってしまう。ということで誰もがよく喋り、その背景は常に不満や不安であった。社会的動物の進化を貫く素朴な真実として、私たちは状況に対して身動きが取れない時に、その分だけ負の感情を抱き、往々にしてその分だけよく喋る。立法府が収められた超高層ビルの最上階で、彼は地上の底辺から這い上がってくる全ての不平不満を頂点として吸い上げ、それを不安へと咀嚼して、誰にも吐き出せないままにハンコを押し続けていた。任期は一貫してこのような、抑圧され秘匿された心理過程と、機械のように期待された機械的反復〜陳情への是認と不満への了承〜に費やされた。この役職を経験した誰もが至った境地であるが、この世界からは偉大というものが消え去っていた。もう消え去ってから久しかった。その感触さえ忘れてしまった。偉大には多大なる余白が必要だったのだ。この世界帝国の最後の大統領となったこの人間は、最後にそれまでの先輩方から一歩だけ先を行き、余白がなければ作ればいいじゃないかと断定した。そして彼にしか押すことのできない、真っ赤で大きなボタンをぐいっと押した。物狂いは大火を謳う
・遊郭への来歴、娼婦としての規則原型の確立
この女は女になる前に少女として土を耕していた。この地方にはよくある出来事であったが、働き手として産み落とされた五人目の子供であり三人目の女児であった少女は、結局のところ食い扶持を減らしそして一時的な所得と交換されるために身売りされた。そして生まれ故郷から遠く遠く西にある都へと連れて来られ、女になるためにその日の内に女にされた。見知らぬ男に女にされて、その男とはそれ以来会うこともなかった。彼女が閉じ込められた時空間は遊郭と呼ばれており、そこではあらゆる快楽と擬似的な幸福が充溢していた。ここを訪れる人々は誰もが目を瞑ってこれを貪り、次の日には忘れてその翌日にまた来て同じことをし、同じ言葉を囁いていた。本来は難しい概念もここでは肉体により気軽に歌われていた。そのこと自体は女の気分を楽にさせた。どんな行為も現実も他者も、真面目には受け取らないこと、これこそは彼女が一番初めに体得した生存の鉄則であった。真面目に受け取るものは心を喰われて肉を腐らし、路上に眠ることになる。そのようなありがちなサイクルを最初の一週間で数個は見届けた。
・女による、遊郭への来歴への理解
この空間に善悪はないし、この時間に意味はないこと、は分かっていたが、自分がどうしてそんなことに気がついてしまうのかは分からないなあ、と思いながら股を開きその後に洗った。ここではないどこかへ行きたい、と思う自分がいるから、どうしてか鳥のように自分の居場所を眺め渡してしまうのだろうと思うのであるが、そんなことは生まれ故郷で鋤を振るっている時分からそうだった。そしてだからこそ母に疎まれていたことも。女とは一般に、あらゆる文脈において自分の手元を逃れ出る存在を、あらかじめ嫌うようにできている生き物であり、やはりそのことも含めて自分は、現在と微かな未来を含む過去からの流れの大体を把握しているように思えた。自分が初めからそうであったという性質と、今ここでこうしているという事実の迂遠なリンクに感嘆しつつ、しかしながらあまり運命論めいた思考に縋ることは避けたいし、避けた方が無難だろうとも感じていた。
・娼婦としての規則原型、の詳述、とその構成過程の記述
というのも、この場所で展開される運命の大抵は、ありきたりであやふやな悲劇であったからだ。女と同部屋であった娼婦の一人は、妊娠し、子の父親であると思われる客との駆け落ちを画策したことにより罰せられ、その最中に死んだ。その死について誰も、素朴な悲しみや弔いに暮れることができなかった。正直なところ、腹の子の父親がどの客であるかは不明であるはずだった。死んだ娼婦は沢山の客を取っていた。駆け落ちの相手となった客は自分が父親であることを途中から否定した。死んだ娼婦の腹から出てきた子は未熟かつ死んでおり、その似姿を確かめることはできなかった。女に加えられた罰は死をもたらすようなものではなかったが、女は途中で意識を失い、必要な介護をしようと折檻役が場を離れた間に死んでいた。折檻役によると女は静かに苦痛を受け容れていて、泣き叫んだり恨みを呟くこともなく、折檻はある種の確認作業として執り行われていた。しかし介護をしようと戻ったら死んでいて、縄を解くと力なく、女は目を開けなかった。死に顔は安らかなような気がした。どうも、全てはちょっとしたボタンの掛け違いで起こった出来事であるようだった。しかし確かに、少なくない人々の生命はボタンよりも軽く風になびいた。そしてこのような不透明さを孕む、人の世の気軽な誤作動は、ここ遊郭で日常茶飯事であった。当たり前だがそれにより、苦痛を受けたり不幸になったり死んだりするのは、ここ遊郭の重力に縛り付けられた人々、常に娼婦達であった。そしてこのような人の生の掛け違いや軽さと重さについて、真面目に受け取った者は暫くして何らかの理由で、遊郭から姿を消すことが多かった。そのことに何となく気が付いた娼婦達は、ここでの生存のために真面目に不真面目を貫徹し、いつもからからとした笑いに落ち着いていた。
・女の仕事振り、街と遊郭への意識
東から来た女もからからと笑うようになっていた。そしてそれなりに仕事をこなし、身のこなしや細かな所作は洗練し、いつの間にか花魁へと昇格し、客の内の幾人かは身請けを申し出さえしていた。しかし花魁は遊郭を出ることを心理的にも実際的にも拒絶していた。何故なら、彼女はここから見渡す世界像を愛していた、というか、この社会ではこの場所からしか世界や関係を見渡せないことに気がついていたから、彼女はこの低い水が流れる領域から出ようとしなかった。花魁の目に映る、水、客という人間の心理を通して感じられる社会は、一言で言えば過密であった。そしてここ、都という過密を核としてその周囲は巻き込まれ、これら全体が一つの運動を成しているように思えた。彼女が幼少に鋤を振るっていたのも、そもそもは都へ年貢を納めるためであり、更に言えば都自身が食料を賄えない程に過密しているからこそ押し付けられた義務であった。支配や統制といった事柄に関する複雑な議論を脇にして、いやその下を黙々と通底するような原理のみに彼女の意識は焦点を当てていた。全ての不快と罪悪は一部局所の過密によって生み出される業として感覚された。彼女の心理にあった整理はここまでのことであるが、そんなプロセスを単純化したものが後世の物理学において謳われているような気もした。
・女の仕事振り、意識の水準と焦点の在り方
花魁が仕事上意識していることはシンプルであった。彼女はテクニックというよりセンスで物事を熟していくタイプであった。都の過密と激烈な内部摩擦を感知していた彼女は、蛸壺より少し広いくらいのちょんの間にいる時から、男と寄り添う仕事場を、ただ男達の生活に対する余白として、雑音と摩擦のない空白透明な時空間として提供し、そこにほんの微かな温かみと、理解と呼ぶに相応しい若干の慈哀を混ぜ込んだ。肉体はその上で弄ばせたが、花魁の居る空間で男達は、往々にして花魁を優しく触り、外も中も傷つけるようなことをしなかった。自分が享受している余白、空白や透明は、彼女の中心から漏れ出ているものであることに、そしてその卵膜は非常に薄いものであることに、どれだけ無粋で粗野な男も何となく気がついたからだ。花魁の瞳には自分の過去と行く末が朧げに写っては消えていくようで、客の大半は数回の逢瀬を重ねると、もうその後の回からは花魁の静かな瞳を覗き込みながら少しの酒を舐めるようなことしかしなくなった。花魁にとってどこまで意識的であったかは謎であるが、花魁という余白、空白や透明を通して男達は、自分の輪郭や満足の形を探り当てようとしていた。見つかるということが重要なのではない、それを明確に求めているという意識が方向として、彼らの人生の推進を支えるのだ。そのためという訳でもないが花魁自身に方向は無く、彼女の人生は推進されない点としてそこに静止し、輪郭も満足も生まれる前から構成に失敗しているかのように思えた。
・女の客層、から感じられた街の作り
そんな花魁の客は実に様々であり、客層としてのまともな纏まりは存在しなかった。ある客は日銭を切り詰めて彼女の元を一度だけ訪れた。ある客は金銭を流し込むように費やしながら、それでいて生活に支障がないようだった。時に、前者のような客は後者のような客に雇われていて、一方はその奴隷のような境遇を花魁に語っては去り、もう一方は主人であることの孤独と空疎を花魁に語り続けた。花魁の目に映る、水、人間を伝っていく情報と金銭は、美しいほどに上から下へと流れ、そこからまた最上の一点へと流れ込んでいるようだった。人間の意識を貫く重力作用の中で、花魁は自分がその最下層にいることを意識していた。何より娼婦とは、その上にある構造への支えであることに気が付いてもいた。彼女らは街の全体と運動を保持するための基礎であり、殺されてはならぬ生贄であり、生贄としての優美な肉体を備えながらも、目に見えず手に触れることのない領域に存在していた。そのような領域に達した数ある娼婦の中でも、件の花魁は突出しており、それだけ奥底の一点として遊郭を支持しているようだった。花魁の存在は透明で、誰もが通り過ぎることができるが、誰も触れることはできず、そして誰もが心の痒さを、忘れることができなかった。そのような歯痒さはすれ違っただけの人の心にも生起した。なのでどの街角の蕎麦屋でも彼女の名が聞かれない日はなかった。無名の人々の語りの中で彼女は無数の顔を有していた。虹を越えた透明を名付けようとする人々の努力は可愛いもので、そんな街の雑踏に耳を傾けながら花魁は、自分の来歴と行末にふと思いを巡らせることがあった。
・花魁の壊れの始まり、予感
さてこの花魁の壊れと崩れは劇的であった。そこに神様の気まぐれが合わさって世界は変わり歴史が書き換えられた。終わりの始まり自体は些細であり、花魁本人にも感知されなかった。一つの行為の後に、無数の情報の偉大な旅が完遂され、終点として用意された始点から、一つの生命が複雑な発達を開始した。月経不順と思われたものは月経の停止であり妊娠の開始であった。食欲不振や情緒不定を感知した辺りから花魁は、自分のこれからと終わりを予想し始めていた。客の多くは離れ、何人かは身請けを申し出るだろう、申し出ることだけが目的である者もあるだろう、そして結局は最初から本当の意志で申し出た唯一の者の家に迎えられ、そこに閉じ込められるだろう。そこではまた多くの羨望と嫉妬、時に憎悪を浴びるだろうが、自分はそれを気にしないだろう、私の無関心は短期的には状況を悪化させ、しかし長期的には周囲を感化して雑音は消えるだろう。その頃には子は乳から離れ、私は初めての自由を実感し、恐らくはその家と街から消えるだろう。私の子はその家の者として大切に育まれるだろう。私の代わりに。私の代わりに?
・事件と壊れ、抽象
しかしながら花魁の予想は大きく外れ、多少のこと甘かったと判断せざる負えなかった。例えば、花魁の懐妊によって吹き出した都という過密の熱、それまでの摩擦によって極限にまで高められていた高密なエネルギーの強大さを、花魁は測り違えていた。強大さと言うより不条理さと言った方が適切であるかもしれず、であるならば花魁の読み違いも仕方のないことだったかもしれない。不条理さの不条理性とはまず持って予測不能性にあり、ここにおいて花魁の懐妊は、その後に引き起こされる陳腐な惨劇の一々の側面と、合理的な繋がりなど持ってはいなかった。全ては犠牲とタイミングについての恣意的な決定であるように思えた。それらすべてを決したのは、都の底に溜まりに溜まり、奥底の一点を通って外界へ吐き出されることを望んだ、濃密で強大な情念の塊であった。花魁こそはその奥底の一点、あらゆる水が地下へ潜り新たな循環に滑り込む直前の、唯一の通過点であった。それ故に花魁は、都の密と熱に冒された男達による不毛の争いの末に、腹を蹴破られ子を引き摺り出され、その上で看護されて死ぬこともできなかった。街に籠もった全ての情念が彼女の身の内を喰い破りながら通過することだけが重要であるようだった。
・事件と壊れ、具体、起こり
花街に吹き出した騒乱の中で、花魁の客の内の十数人が、我こそは花魁の腹の子の父であり、花魁の正当な身請け人であると主張した。その十数人は花魁の客層を反映しており、つまり社会的な立ち位置はそれぞれにばらばらであった。街のあらゆる蕎麦屋で粗末な予想と議論が繰り広げられ、事の進展を追う瓦版が出回ったりさえした。花魁その人は事の中心にありながら冷徹に冷静を突き通し、殆どの声や疑問をそのままに素通りさせた。膨らみかけた腹を拝もうと男達は、その権利があるかのように花魁の元を訪れては、自らの優位性と花魁への愛の真実性を歌っていたが、この花魁の耳に男達の歌は、ここではないどこかへ行きたい、今ではない何かになりたいという叫びとしか聞こえなかった。なので花魁は男達のそれぞれの、具体的な意見主張には耳を貸さず、ただそれまでと同様に空白で透明な時空を提供していた。膨れた腹の熱さと、この女においてさえ高められた母性本能に晒されて、男達は男としての本能と圧力を強くして家に帰った。このような不毛の逢瀬が何周も何周もされた。そうして街全体の熱と圧が最高潮に達した夜の、その翌日の朝に、十数人の身請け人候補の殆どが、それぞれの家で惨殺された状態で発見された。発見したのはそれぞれの妻であり、惨殺したのは身請け人候補の中の、最も無名な一人の男であった。この無名の刺客については事件当初、瓦版や井戸端会議でさえもが沈黙せざる負えない程に誰も何も知らず、事情を尋ねにやってきた奉行へ花魁がぽつりと語ったところによると、この男は、花魁との逢瀬に本当に何もしない不可思議な男であった。ただこの男を不可思議と評したのは奉行であり、不気味と言い合ったのは遊郭の侍従共や市井の人々であった。花魁その人はこの男に、自分と似たような空白であるという理解と感覚以外をあてがう事はせず、買い手と売り手として接していた時分にも、ただ何もしないという自由を提供していたようだった。客としての歴も長かったこの男に、かつて花魁はそれなりの好意、というより自然な寄り添いを抱いていた。同僚の娼婦や他の客を含む殆どの人間は、花魁の醸し出す透明と空白に、好みの絵面と言葉を充てがいながら目を瞑り手を伸ばしていたのだが、この男はただ花魁の透明を透明として、空白を空白として見通していたから、この男が身請け人に立候補した時には花魁以外の誰しもは意外に思い、花魁その人は珍しく少し心苦しそうにしていた。事件の後に語られたように、周囲の人々にとってこの男は多少なりとも不可思議か不気味であり、そのことはこの男の親族にとっても昔から変わりなく、多くはない月々の自由資産を遊郭通いに費やすようになってからは、この男に約束された孤独は色を濃くしていたようだった。特に、身請けの騒ぎが起こってからは、逢瀬の頻度を増したこの男にとり、花魁と、花魁と過ごす八畳間の空白は、まるで唯一の鏡であり現実の手触りであるかのようになっていた。そしていつしかこの男は花魁との、本当に何も無くなった時間のために生きて生活するようになっていき、一方、花魁に感じられていた自然な寄り添いは、花魁の心から色褪せ、消え去ってしまっていた。凶行が勃発し、十数の座敷が鮮血に彩られたのはこの頃だった。このようにして狂った男の凶行の、経緯や動機はあからさまに明らかでありながら、行き過ぎた結末の余剰エネルギーに街の人々は再加熱され、今にも誰もが踊り出しそうですらある祭りの熱気が、街の輪郭を外へ外へと押し広げるようにして鬱屈し始めた。当たり前だが、重ね塗りされた熱に最も激しく魘されたのは一夜にして寡婦となった十数人の女達であった。そして、街の熱の鬱屈が最高潮に達した夜に、この女達によって更なる凶行が強行された。誰もが実はそのような、更に激しい進行による、結末の上書きと更新を期待していたようだった。人は無意識にエネルギーの流れの姿形、物語を感知しつつ増幅しているものだ。
・事件と壊れ、具体、更なる起こり
寡婦となった女達の熱は、自らの夫を殺めた一人の狂者を素通りし、当たり前のように花魁へと流れ込んだ。寡婦達は遊郭に押しかけて花魁の部屋に押し入り、重くなった肉体を押さえつけて腹をどすりと蹴破った。中の子は潰れてから外に出てきたが、部屋の床の上で更に踏み潰されて窓から放り投げられ、その似姿は誰にも確認されなかった。寡婦達は更なる制裁と打撃を加え、花魁の肉体に薔薇が柘榴のように咲いた。しかしながら犠牲とタイミングは決定されており、花魁は刺殺ないし撲殺され切る直前に従者によって救出され、腹を縫われて救命された。意識不明の闇に沈みながら、この不条理に対して自分がどれほど関わっていると言えるのか、花魁には定かではなかった。原因や責任は自分に無い、という感覚がする、ということではない。不条理でしかない現実の全てに、いよいよ自分が帰属しているように思えなくなってきた。しかしこれは不条理の全体を意識に収めることのできる者特有の業であった。そんな業もこの世にはあるものだと、諭してくれるような老賢者が居合わせた訳でもなかったから、花魁が直面した不条理は、理解不同伴という条件も含めたより深刻な不条理であるようだった。現実への手触りが元々薄かった彼女の距離感は遂に完全に狂い始めた。目が覚めると花魁は大切に腹をさすり始めた。それまでよりもずっと強く丁寧に。そして誰にも聴こえない小さな歌を謳っていた。
・決、決への導き
それから幾つかの季節が流れた後に、花魁は都の大路を真夜中に、一人悠然と歩いていた。彼女はそれまで蔵に閉じ込められたいた。他の男達を殺した狂った男の、生家にある暗い蔵に、殺されるようにして閉じ込められていた。遊郭に対して引き取りを申し出たのは件の男の妻であった。男は凶行の後に自害していた。そのことからしても男は、花魁に具体的に何かを求めていた、というよりかは、現実に対して何も求めることができなくなっていたのだろうと、そして花魁の懐妊はそんな認識の蓋を開けて外してしまったのだろうと、少しでも感性というものがある人々は気がついていた。その男の妻もその内の一人であり、故に対抗的に発生した強大な憎悪と執着に身を委ね、傷の入った花魁の引き取りを申し出た。名目としては責任と道義上の救済、ということになっていたが、その下にどんな情念が渦巻いているのか、やはり少しでも感性というものがある人は気がついていた。しかしながら全ての感性を通過して、花魁は、最初に狂った男の生家に預けられた。何よりその頃にはもう、花魁自身が痴呆になりかけていて、遊郭としても対処に困り、脳梅毒に侵された者と同様に扱おうかと考えあぐねていた。そのような事情を尻目に、彼女の目と意識の焦点は無限遠に結ばれ始め、彼女の右手は腹を押さえ撫で続け、遠くを見ながら右手を音頭に小さな歌を謳っていた。時たま腹の方へ目を下げては、ねえと呟いてまた遠くへ視線を戻して謳い続けていた。壊れた花魁を引き受ける良心や余白は、都の何処にも、そして花魁を失った遊郭の何処にも存在しなかった。なので寡婦の憎悪と執着のみが彼女を受け容れたのである。
・終局と終滅
蔵を這い出した花魁は、都の背骨をなす大路を北に向かって、偶然にも満月であった夜の空の月の方へ、一人悠然と歩を進めていた。かつて花魁の唇には都で一番の紅が差されていたが、今は赤黒い血で厚く頬までが覆われていた。それは件の寡婦の静脈から流れ出た血潮であった。数ヶ月の幽閉の末の名も無い満月の夜に、寡婦は蔵に入り花魁の前に座り、誰にも聴こえない声で一つのお願いをした。誰にも聴こえない声を聞き取ることで生きてきた花魁は、正気を失おうとも願いを聞き届け、今回ばかりは積極的に完遂した。お歯黒を塗られることもなかった白く整った歯々がその時、薄い唇と共に静脈血に染められた。水を抜かれて乾涸びていた花魁の口腔は唾液を分泌しなかったので、蔵を這い出して大路に出てきた時には、花魁の顔面は、歯と舌に至るまでべたりとした黒紅に覆われていた。その乾いた断片をぽろぽろと道に落としながら花魁は、満月に向かってげらげらと笑い出した。そして走り出し、大路を駆け抜けながら自らの腹の傷を爪で抉り、中から子の代わりに臓物を引き摺り出して嚙み千切り、それを都の産物として大事そうに抱きしめながら、そして疾走し、物狂いとなりながら一つの歌を謳った。
・謡い、finale
大火よ、くい。大火よ、くい。すると時代錯誤の核爆弾が、ずるっと月の辺りから落ちてきて、都の過密とその周囲の過疎と辛苦と幸福の全てを押し潰し、焼き払い、風に流した。緑の上の白色の死
春、一頭の北極熊は陸地に辿り着いた。それまでに身を預けていた氷塊は溶けて消えていた。南へと進んだ分だけ、陸地は春として緑に覆われていた。その陸地の端に手を掛けたその時には、自分はこの陸地を去ることはできないだろうと予感していた。自分はもう、骨と皮だけになってしまった。大事なところ以外の筋肉は須く萎縮していて、狩人としては既に完全に死んでいる。自分はもう何も、追うことすらできない。咥えることすらできない。飢えの極地で本能さえ削り取られ、不可思議な感触の諦観だけが、彼の脳髄を満たしていた。そのようにして一頭の北極熊は、緑の陸地で祝福されるように、飢えて死んだ。骨と皮は冬のなけなしの雪に埋もれ、春に溶かされて風化しつつも、そこから数年は輪郭を保っていた。しかし今はもう全てが失われ風に流された。その土地を渡る鳥々の小さな脳髄に、薄い陸地の淡い緑と、その上に横たわる白色の死のみが記憶された。目覚めと涙と透明さ
ある文明の一時期を象徴するような幸福な家庭の、初めての子供である女の子は、生まれて初めて一人で起床し、しかも両親より早くベッドを抜け出した。得も言えぬ自尊心と覚醒感に身を震わせながら、彼女はまだ薄暗いリビングにそろりそろりと進出し、それまでは母親が独自に完遂していた事柄、つまり朝食の支度をやり遂げた。お皿にコーンフレークを盛ってその上からミルクをかけて、ワンスプーンのシナモンを振りかけて少しだけ混ぜた。その隣にコップを置いて氷を投げ込み、そこに嫌いなトマトジュースを注いだ。記憶にある中で最上の満足に駆られながらひとまずフレークを掬い、スプーンを口に運んだ。するとなぜだか涙が出てきた。氷を溶かしたような冷たい涙が、とめどなく両目から溢れてきた。達成感とは違う喪失感、その他彼女の未発達な意識によっては分別できない複雑な感情が、彼女のお腹に膨らみ始めた。コップの中の氷が崩れて音が鳴り、彼女は不可思議な腹痛の余りに手を添えて呻き、氷を溶かしたような冷えた涙を、床にぽろぽろと落とし続けた。それを尻目にぽたりぽたりと、椅子の脚を伝って鮮血が床に広がっていた。早すぎる血潮は少女の女を目覚めさせ、その朝から彼女は、自分と世界の間に横たわる余白と、自分の胸にある空白について考え始めた。
ae
