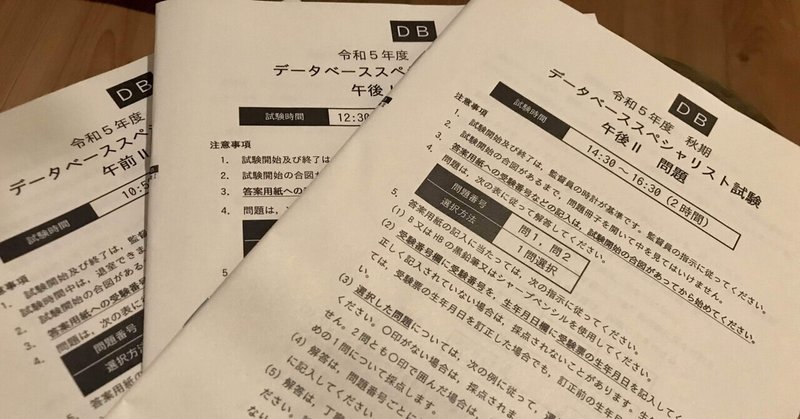
データベーススペシャリスト試験を受験しました
本日2023/10/08、
IPA情報処理技術者試験の1つ、
データベーススペシャリスト試験を受けてきました。
非IT企業の情シスとして、
日々「これもデータベース(Excelの表)があったらなぁ」という周囲の声が聞こえているので、業務をシステムに落とし込む訓練として受験するのが良いと考えたからです(あと部下に煽られた)。
あと、合格すると会社が受験料を払ってくれるはずです(ネスペの受験料の社内申請をまだしていない)。
AP、SC、NWのときは公式からの解答・合格発表が待ち遠しかったのですが、今回は午後Ⅰでしくじったのでおそらく不合格でしょう、なんか期待感がないですね。とは言え、不合格そうだったらNOTE書かないの?となるのも隠しているみたいでイヤなので、午後の答案をここに供養して来年に備えます。公式回答ではないし、反省ポエムの分量多め。
午前Ⅱは64点で危なかった。
「全然わからなくてもひねり出して何らかの文字を書く」がポリシーだったのですが、今回はそれが敗因でした。最優先すべきは「受験番号、生年月日、選択した問題番号に◯ 印」して確認(自分は大丈夫、が命取り)、次に優先すべきは時間を管理してわからない問題は後回しにすること。わからないなりに何か文字で埋めるのは時間に余裕があって戻ってきたとき、にするべきです。部分点がもらえる低い可能性に時間をかけて、簡単な単語問題にたどり着かないのはあまりにももったいないです。
午後1
配られた答案用紙を見て驚いたのが、問1で用紙の表面全部、問2で裏面3/4、問3が裏面右下に1/4というスペース配分。問1、2は概念データモデルと関係スキーマの完成、問3はデータベース設計。過去問では概念データモデルと関係スキーマをメインで訓練していたが、改めて答案用紙を見ると記入する気力が下がった。
そんな状態で問3の問題文を読むと、最近の情報処理技術者試験で目指しているような、農業IoTでDXな案件でめっちゃ面白そうな内容だっだので、物理設計あまりやってなかったけど農学部やからイケる、という好奇心優先で1つ目には問3を選択。その結果60分も費やして明らかに失敗。
正規化ならできそう、と2つ目は問1を選択したが組織が階層化されているあたりがわからなかったので何も解答せず、問2に変更。
問2
設問1
(1):概念データモデルのリレーションシップ補完 (予約エンティティに「自社サイト予約」「旅行会社予約」のサブタイプをつくったけど、いら ない?)
(2)
ア:客室タイプコード(外部キー)
イ:ホテルコード(外部キー)、客室タイプコード(外部キー)
ウ:予約番号(外部キー)、ホテルコード(外部キー)、客室タイプコード(外部キー)
エ:予約番号(外部キー)
設問2、3 ←時間切れのため空欄
問3
設問1
(1)
a:圃場ID、農事日時、AVG(分平均気温)
b:圃場ID、農事日時
(2)30字以内:当日日出から翌日日出までは毎日24時間とは限らないから
(3)
c:14.0
d:15.0
e:16.0
(4)
f:日平均気温
g:圃場ID
h:農事日時
設問2
(1)35字以内:分割索引を農事日時の年度に設定したいから(みたいなメモ)
(2)36,000
(3)30字以内:主索引が圃場IDではなく観測日時になっているから(みたいなメモ)
(4)35字以内:農事日時の12月31日は正午の日出1分前までだから(みたいなメモ)
(5)
イ:1
ウ:3
エ:1
オ:5
カ:4
午後2
あまりにも午後1を埋められなかったので帰ろうかとも思ったが、ちょっと早く帰ったところで仕方ないし、来年のデスペ勉強は今日が1日目だと思ったので令和5年秋期午後2の過去問をリアルにやっているという想定で参加。
回答用紙が配られ、問2の回答欄が表面の右下から裏面全部のスペースを覆っていて概念データモデルと関係スキーマの関係だけの問題のようだったので、どうせならあまり対策してこなかった方をやろうと、問1を選択。
やってみて思ったが、簿記みたいな問題(簿記3級は初回落ちて2度目で合格)。
問1
設問1
(1)25字以内:一つの生産拠点ては複数の商品を生産する
(2)
b:4
c:1,2,3
d:3
e:2,4
f:1,4
設問2
(1)
30字以内 累計出荷数量:22年10月から23年9月の出荷数量は月間約400件程度で一定
30字以内 移動累計出荷数量:21年10月から22年9月の出荷数量は徐々に減少していた
(2)
ア:1
イ:11行前の行
ウ:現在の行
エ:最初の行
オ:現在の行
カ:11
(3)
キ:COUNT(*)
ク:空欄
ケ:出庫回数
コ:出庫回数順位
(4)305と306
(5)倉庫内移動 行の挿入
設問3
(1)
g:210
h:85
i:260
j:85
k:150
l:90
(2)
a 35字以内:受払明細の摘要区分、数量、単位が一致する行を処理WTから選択
b 35字以内:空欄
(3)60字以内:空欄
(4)
m:減少
n:入荷
o:単価
(5)
受払残高:基受払#→ 受払明細
残高集計:年月、拠点→ 繰越残高
残高集計:商品#→ 商品
感想
部下に煽られて7/26の申し込み最終日に受験申込みし、期間中にコロナで倒れるなど、これまでの情報処理技術者試験とは異なる受験体験だった。
勉強については試験まで短期間でありながらDB全然わからないだったので、図書館でSQLの本を読むところから始めて、セキスペ、ネスペのときよりも過去問で対策をしたつもりになっていた。記録上されている勉強時間は23/07/27~23/10/08の4,955分(ネスペは22/10/25~23/04/25で4,481分)で、過去の午後2のデータベース論理設計問題を重点的に問いていた。しかし本番で論理設計を選ばないという選択をしたため、訓練の成果を発揮できず、平常心での対応もできなかった。来年への反省点は、訓練した問を選択すること、対策の分野を偏らせたとしてもそれ以外も最低限勉強すること、回答の時間配分を守ることの3つ。あと、論理設計対策しても、解けるようになってる感覚に乏しかった。
失敗したほうが学びは大きいというが、今回は自分について理解が深まった。回答可能性よりも面白そうかどうかで問題を選択すること、業務手続き系よりも自然科学系のデータ収集の方が明らかに興味がある(というか自分ごと感がある、業務フロー整理は正直誰か他の人にやってほしい)、面白そうだと思ってもわからないものはわからないしできない。だから仕事でもIoT案件に近いことを担当するように手を挙げるのが良さそう。
次の試験予定は11月末の技術士補なので、Azureのバウチャーがもらえれば何か受けたい(AZ-104が無料になるクラウドスキルチャレンジのバウチャーは受験期限9/27だったので受け損ねた)。春はSTかSAで初の論文試験を受けてみようかな。
2023/12/22追記
午前Ⅱ 64点
午後Ⅰ 40点
不合格でした。来年で合格できるように鍛え直します!
あと、煽ってきた部下が応用情報技術者に一発合格してたのがめちゃめちゃ嬉しかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
