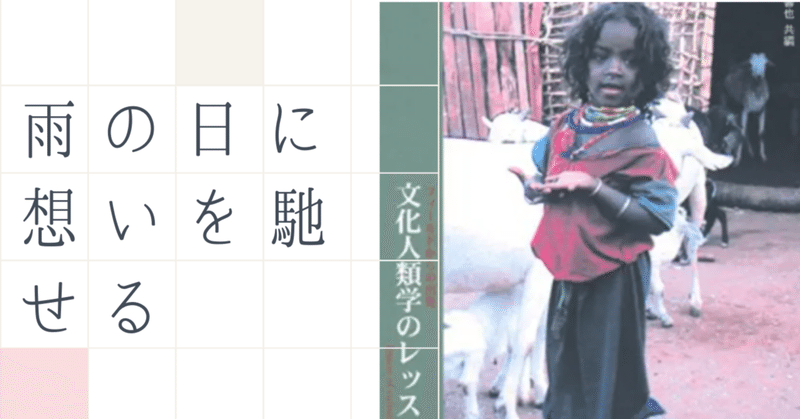
#4 雨の日に思いを馳せる“文化人類学”(台本公開)
文化人類学のレッスン―フィールドからの出発
奥野 克巳(著)
standfmをお聞きのあなたへ。おはようございます。一歩を一緒に作るブランドプロデューサーいっぽです。
今日は雨ですね。しとしと雨が降っていますが、この雨音を聞くと心が落ち着いて、今日はなんだかとっても穏やかな心持ちです。
6月に入って始めた朝活も今日で4日目。無事に三日坊主の壁は越えられたとホッとする気持ちもありつつ、なんだか新しい日常を受け入れる覚悟ができたのか「起きた!」「起きれた!」という喜び、非日常感はいい意味で薄くなってきたように感じます。
唐突ですがみなさんは雨の日に対してどんなことを感じますか?
ちょっと憂鬱だなーって思ったり、低気圧しんどいなーって思ったり。でも読書が捗るーとか、雨だからのんびりしようっていつもより少し自分に優しくできたり・・・きっと色々ですよね。
雨の日にはいつも思い出す話があるので今日はその話をしたいと思います。
私は大学の時に文化人類学と多文化共生というニッチな学問を専攻していたのですが、みなさん、文化人類学って聞いたことありますか?
私の通っていた学部では1年のときにみんな文化人類学を必修で受けるんですけどその初回講義は毎年「雨って、どう思う?」という問から始まるんです。
どう思うって・・・何?って思いません?笑
その問いを投げかけられた私は意味もわからずただなんとなく「気が滅入る」とか「学校に行きたくない」とか「なんかテンション下がる」ってマイナスなコメントを思い浮かべていました。
そんな学部生の様子を見ながら教授はそっと口を開き、こう言いました。
「雨が嫌だというのは一種の文化、世界には恵みの雨と言って雨の日が嬉しいというふうに考える人もいる。世界は広い。あなたが今思った雨に対する考えは自文化という自分の文化の考え方なんだよ。」とそんなことを教えてくれました。
一言一句正確に覚えているわけではないんですけど、この話は私にとって衝撃的でした。
言われてみれば当たり前で、頭ではすぐに理解できることなんですけど、いつもそう言ったスタンス、姿勢で異文化と対峙できるかという点ではまだまだひよっこなんですよね。
対峙と言うと言葉が強すぎるんですけど、文化人類学的に言うと「自文化中心主義」に陥っていないか。自分の文化中心に考えて相手の持つ固有の文化、習わしや価値観を否定してはいないかということを意識しようと思えたのは文化人類学のおかげなんです。
この考え方、世界観に惚れ込んだ私は文化人類学と多文化共生を学べるその教授のゼミに入りました。ゼミでは週によって異なるテーマに対して文献で理解を深めある文化や文化人類学の葛藤をどう解釈するか考えたり、どんなことを感じたかをA4、1枚のエッセイにまとめゼミのメンバーとディスカッションします。
例えばパプアニューギニアの成人儀礼についてや、ジェンダーについて、シャーマンの存在やアニミズムについてなど、幅広く色々なテーマで意見交換をしました。
教授はよく「成人儀礼で出てくるツールの名前や儀式の所作についてのルールなど、そんなものはきっと社会に出てからは1ミリも役に立たないだろう。ただそのプロセスを経て身につけた"異文化を見つめるまなざし”は文化人類学を通して全く違うものになる。」と言っていました。
一つの文化が出来上がる過程というのは非常に複雑で、様々な要因が複雑に絡み合い、影響しあい、成り立っています。気候や自然の恵み、人の多さ、他の文化圏からの侵略の歴史など・・・バックグラウンドが異なればそれだけ違う形の文化が出来上がるのですが、私はこの学問から「一人一人の価値観は異文化である」ということを学びました。
異文化と対峙した時、私とは価値観が合いませんねと言っってシャッターを閉めるのではなく、むしろ一歩踏み込んで「なぜそう思うのか?」「なぜそのような文化が生まれたのか?」「それを現代を生きる人々はどのように解釈して共に生きているのか?」そういった姿勢がこれからの多様性の時代を生きて行くには必要なんだと理解した時、この文化人類学というニッチな学問はなんて趣深くて人間の本質に迫る味わい深い学問だと感動したことをよく覚えています。
実は、この文化人類学から学んだ考え方のおかげで思わぬ恩恵がありました。
新入社員研修が終わり、現業部門に配属になった私は、バックグラウンドも価値観も様々な大勢の大人たちをまとめあげ、同じゴールに向かって進む日々を過ごすことになりました。
最初は今までの常識が通用しないことに戸惑い、誤解されることを恐れて思うようにコミュニケーションがとれないことがよくありました。
そこで文化人類学で身につけた異文化を見つめる眼差しと、フィールドワーカーとして同じ文化に思いっきり飛び込んで体感しながら分析するという異文化理解の手法を試してみようと考え方を変えました。
何か揉め事があった時はあえて大袈裟に文化人類学者になりきって「これはきっと文化摩擦が起きてるんだ」と解釈したり、「自分から歩み寄らなければ相互理解はできない」という考えをもとに積極的に自己開示をしながらコミュニケーションを取ろうと働きかけて行くことができました。
その後、徐々に信頼関係を構築することができ最終的にはベテランのスタッフにも「あなたがそこまでいうならやるしかないよね。」と言って動いてもらうことができたとき、本当に諦めなくて良かったし、文化人類学やっててよかった〜!と思いました。笑
人にはそれぞれの生まれ育った環境や家庭の価値観、文化的背景があります。極端ですが「一人一人の価値観は異文化である」と考えることによって、きっと人との接し方も変わってくるはずです。
雨が嫌だなと思うのは一つの文化の特性であって、私の価値観で「嫌だぁ」という感想を選んでいるということ。
雨の日には今ここを少し離れて、名前も知らない他の文化で懸命に生き、雨を感謝する人々へ思いを馳せる・・・そんな過ごし方も、いいかもしれませんね。
それでは、今日もあなたにとって素敵な1日になりますように。
いっぽのいっぽずつ、今日はこのへんで。
もし宜しければサポートよろしくお願いします。頂いたサポートはクリエイターの活動費にあてさせていただきます。
