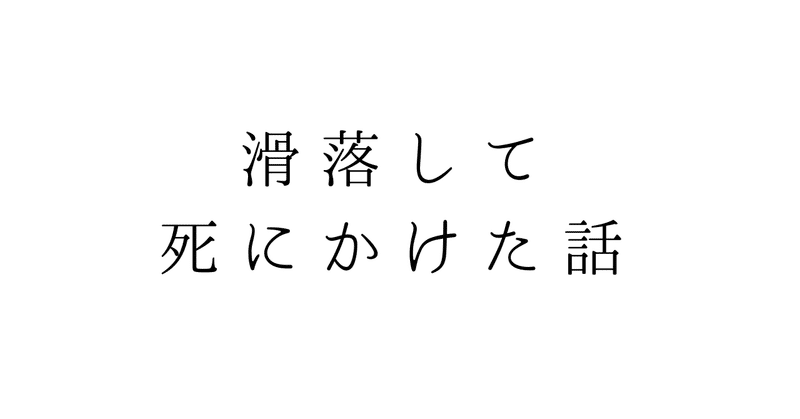
滑落して死にかけた話
頭をよぎったのは二つのことだった。
一つは「木にひっかかったら助かる、そうでなければ下まで落ちる」。
そしてもう一つは、「ああ、こういうふうに死ぬのか」だった。
丹波篠山市にある筱見四十八滝には、8つの滝が始終流れている。それらの滝のひとつ、「大滝」がすぐそこに見えてくるところだった。
9月24日、雨上がりの登山中、僕は滑落した。
13時を前にして空腹を感じ、体の力が少し抜けたところだった。一瞬のことだった。
急斜面で左足を滑らせ、そのまま谷底へ向かって体ごともっていかれた。濡れた木の根と落ち葉で滑り落ちるスピードが速い。前後左右の感覚がわからない。
落ちていく先に、木があれば引っかかることができるかもしれないが、そうでなければ落ちることに抗えない。
ゴツゴツした岩が重なる深い谷底へ向かって、容赦なく滑り落ちていく。速い。
咄嗟に何かを掴もうとした。掴めない。滑落の勢いが増す。体勢がわからない。持ち直すこともできない。額が何かにぶち当たる。
止まらない。(これで終わりか──)。長い時間を感じていた。
木の影が眼に入った気がした。ここを過ぎたら次はない。そんなことが頭をよぎったかもしれない。
止まった瞬間を覚えていない。直径10センチほどの濡れた古い木にからだを預けていた。
膝が痛む。折れてはなさそうだ。
額が重い。全身が湿った土と枯葉にまみれている。ポロシャツの袖、かろうじて泥のない場所を見つけて額を拭うと、うっすらと血が乗った。左の前腕からも濃い血がにじみ出ている。
どれくらい落ちたかわからない。その場に座り込んだまま、ひと呼吸置いた。体の痛みをリサーチする。あちこち痛みはあるがダメージはそれほど感じない。生きてた。
斜面の上にいる妻から声がかかる。座り込んだまま顔も向けずに大丈夫と返す。水がほしい。
リュックの左側に差し込んでいたペットボトルがない。自分を支えてくれた木の50センチほど下に転がっていた。
痛む膝を折り、慎重に手を伸ばして、ペットボトルをわしづかみする。泥を払ってキャップを回し、水を体に流し込んだ。
一息ついて立ち上がり、はるか上のほうに見える妻を見た。そしてズボンのポケットを確認する。左ポケットに入れたスマホは無事のようで、右ポケットに車のキーもあるようだ。スマホを取り出し、妻に向けて写真を撮った。
落下中、焦りも、恐れもなかった。
止まってからも気持ちは落ち着いてた。
興奮も恐怖もない。
下まで落ちていたら、少なくとも40メートル以上滑落していたことになる。命はなかったかもしれない。
足をすべらせないように気をつけながら、斜面をゆっくり上がっていった。
命拾いした、助かった、よかった、という安堵の気持ちには不思議とならなかった。危機が終わってただ落ち着いていた。
滑落の刹那、頭を通り抜けたのは、
「ああ、こういうふうに死ぬのか。こんな死に方、想像してなかった」だった。
心は死を拒絶するどころか、受け入れていた。
今回は助かったが、もし死んでいたら、あれが最後の意識だっただろう。
死ななかった。
だからこそ死を自覚できた。
あれが死だ。
古びた一本の濡れた細い木がなければ、その次の瞬間は、ブラックアウトかホワイトアウトして、この世から消えていただろう。
死に近づいて、まだ生きろといわれた気がした。
追伸:
あれからちょうど2ヶ月。
膝がまだ痛み、あちこち残った傷跡をみて、死を思い出す。
今日も生きている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
