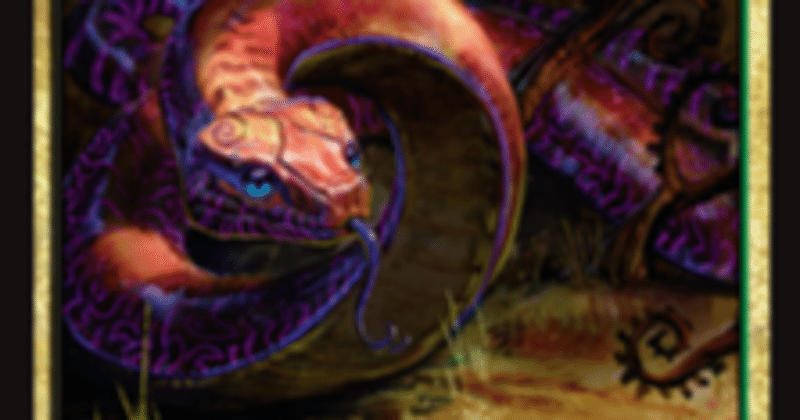
『巻蛇 先駆者日記』#1 ~オリジナルデッキを作るということ~
『1』【最初の出会いと、最初の別れ】
皆さんこんにちは。
突然ですが、このカードをご存じでしょうか?

巻きつき蛇 黒緑
クリーチャー 蛇
あなたがコントロールする、アーティファクトやクリーチャーの上にカウンターが1個以上置かれるなら、代わりにその個数に1を足した数のその種類のカウンターをそのパーマネントの上に置く。
あなたがカウンターを1個以上得るなら、代わりにあなたはその数に1を足した数のその種類のカウンターを得る。
マイナーというほどマイナーではありませんが、《稲妻》や《ラノワールのエルフ》みたいなカードほどメジャーではなく、
ご存じの方も、大部分の方は「カラデシュの頃のスタンダードにいて《新緑の機械巨人》や《リシュカー》のカウンターを増やしてた蛇」という認識かと思います。
実際、自分もその頃にスタンダードデビューをし、『チャレンジャーデッキ・怒涛カウンター』でMTGを始めました。
今回もMTG日本より画像を引用してまいります。

これ書いてるのは30周年です。思えば遠くに来たものだ。
【2018年 5月】
その頃、地域のカードショップの大会に通い、たまに3-0とかしていましたし、よく教えてくれる先達のプレイヤーや、今も付き合いのあるフリプ仲間と出会ったり、恵まれた初心者時代だったように思います。
【2018年 10月】
【ラヴニカのギルド】の発売に伴い、《巻きつき蛇》はスタンダードから落ちます。
そもそもチャレンジャーデッキ自体が環境で存在感を発揮しているデッキを調整したものを発売している商品のため、最新リストというわけではありませんからね。
《巻きつき蛇》。
思えば半年にも満たないほどの短い間でしたが、紛れもなく俺にMTGというゲームの楽しさを教えて、多くの友達や仲間を連れてきてくれた相棒でした。
その後も《巻きつき蛇》で培った緑という色への僕自身の信心でオリジナルデッキを構築し、スタンダードをエンジョイしていました。

初動ウン千円からズンドコ値段が落ちていきました。
最終的に僕以外に使ってる人はいないカードながら、長くお世話になりました。

《蛇》さえいれば探検でカウンターが1個が2回乗るのでそれぞれ置換。
2個が2回乗って6/5まで成長。《蛇》がスタン落ちしても使ってました。
しばらくはスタンダードを楽しんでいましたが、やはり心の隅には《巻きつき蛇》が住んでいました。
とぼけた目をしつつ、俺の心に巻きついている相棒。
別にスタンダードに不満があったわけではありませんが、それでも初めて一年を過ぎようともすれば、他環境にも興味は出てきます。
つまりモダンフォーマットに参入しようと、下環境で《巻きつき蛇》のシナジーカードを調べだした頃、新フォーマット制定の話が広がります。
パイオニアです。
『2』【先駆者(パイオニア)になるための戦い】
【2019年 10月】
パイオニア。
元々、モダンというフォーマットはスタン落ちしたカードの遊び場として制定されていました。
しかしながら制定から年月が経過し、カードパワーのインフレによってエターナル環境に近くなり、新発売されたカードが通じないことが多くなっていました。
モダン=近代的という呼称も、当初は新規カードを楽しむという趣旨だったものの、実態にはそぐわない形となっていました。
そして新たに制定されたフォーマット、それが“パイオニア”=先駆者でした。
高額二色土地であるフェッチランドが最初から禁止、かつ有力土地であるショックランドは既に概ね揃っていました。
当時はラヴニカのギルド・ラヴニカの献身がスタンリーガルで市場に溢れていましたし、そもそも、買おうとしても安めの《寺院の庭》なら600円、高額な《湿った墓》や《蒸気孔》でもセール品なら1000円を下回りました。
(2023年現在はどのショックランドも2000円前後)

そして意気揚々と繰り出したパイオニア黎明期、《巻きつき蛇》。
地元大会にも気軽に参加すれば、特に調整したデッキじゃなくても勝てたりしてました。
――思えばパイオニアにおける《巻きつき蛇》の黄金期でした。
この頃の《蛇》デッキは、《歩行バリスタ》によってアグロデッキの戦線を崩壊させ、コントロールデッキの残り数点を削れたりと、ドローが噛み合えば、どんな相手とも五分以上に戦えたように思います。
相手の妨害は《夏の帳》で避け、更に中核である《歩行バリスタ》は《むかしむかし》という反則カードでサーチ可能。
そのくせ、自分は《思考囲い》や《致命的な一押し》を有し、相手の戦術は崩していく。
大した研究や勉強もせず、気まぐれに参加しているだけの俺でも戦える、そんなレベルの、強いデッキだったように思います。
【2019年 11月】
そんな中、最強のサイドカード、《夏の帳》が禁止となります。

そりゃ反則だわこんなカード……。
緑1マナ立っている相手にハンデスや打消し、除去を打つと、なぜかテンポもハンドアドも失うという意味不明なカード。
当時の俺は「まあ、サイドボードの枠が空いただけ」程度に考えていました。
"自分の現状"が分かっていませんでした。
【2019年 12月】

続いて《むかしむかし》が禁止に。
パイオニアでも《王冠泥棒、オーコ》の猛威が振るう中、その弱体化としての禁止だったように思います。
とはいえ、その《オーコ》が続いて禁止になっても戻ってこない。
――この辺りから、僕と《巻きつき蛇》の大会やフリープレイをしても負け越しが多くなった気がします。
【2020年 7月】

【基本セット2020】にて、【巻きつき蛇】のそっくりさんが登場。
タフネスが2である、アーティファクトへ反応しない、プライチカウンターにしか反応しない、などの欠点は感じましたが、
《硬化した鱗》と違って、2ターン目にキャストすることで《実験体》や《生皮収集家》の効果を誘発させて3/3にできる魅力をまず感じていました。


それだけのために色を足すのかと考えつつ、運命の日は来ました。
『3』 【カードに勝たせてもらっていたことを知った日】
【2020年 8月】
《歩行バリスタ》の禁止。
ば、バリスタああああっ!
— 84g (@8844gg) August 3, 2020
俺のアブザン巻きつき蛇があああっ! https://t.co/AwfsSYs2Qu
運命の日。
マジで、俺のMTG人生において運命の日でした。
英語でいえばデイ・オブ・ディステニー。MTGでいえば伝説生物全体2点修整です。

さらば……さらばぁ……!

単独なカードパワーももちろん高かったのですが禁止級というわけではなく、最大の問題点は《太陽冠のヘリオッド》との2枚コンボでした。

ストーリー上での神とは思えない挙動からついた蔑称。
ヘリカス。マジヘリカス。
《ヘリオッド》の効果で《バリスタ》が絆魂を得ることで、プライチカウンターを射出して1点ダメージを与えるたびにライフ回復。
ライフを得たことで《ヘリオッド》の効果で《バリスタ》にプライチカウンターが乗り、それを射出して絆魂で回復、またカウンターが……と無限ループ。
無限ダメージコンボであり、2枚コンボによる即殺コンボがマナカーブに沿って動くだけで4ターン目までに実行可能なので、パイオニアというフォーマットでは不適当、というのは理解します。
ヘリカスを禁止にしろよヘリカスをよぉ このクソ神、エルズペスが槍をぶっさしたあとで良いから殴りたい。
当初、ただ単にデッキから《歩行バリスタ》を抜いただけのデッキを組みましたが、勝てない。
勝てなくなった。
面白いくらい大会にでても1-2や0-2で敗戦し、3マッチして0勝の日が増えていった。
フリープレイしても、1回勝っては2回負けるような時間が過ぎる。
当時の僕のツイートです。
パイオニアはしばらくやらないかもしんない。
— 84g (@8844gg) August 8, 2020
「歩行バリスタと巻きつき蛇で遊べる」と始めたフォーマットで、
今日、バリスタなしの鱗を回してみたらクソ弱かったし、楽しくもなかった。
スタンダード時代、ド素人の俺でも勝てていた《巻きつき蛇》が。
パイオニア時代、どんな相手にも勝ち筋のある対応力を持った《巻きつき蛇》が。
全く勝てない。
相手が事故ったときや、勝ちパターンを偶然防げたときだけ勝つだけ。
自分が強くなったと思っていたものが、全く通じなかった。
俺が強くなったわけじゃなかった。俺が戦えていたのは《歩行バリスタ》が強かっただけだった。
好きなカードが禁止カードになったから辞める、何も珍しいことじゃない。
勝てなくなった。辞めたっていい。ただそれだけのこと。
――俺の相棒は、《歩行バリスタ》だったのか?
違うだろ。俺は《歩行バリスタ》だけを使いたかったわけじゃない。

昨日から「パイオニアやりたくない」発言がでたりしましたが、
— 84g (@8844gg) August 8, 2020
「歩行バリスタの抜けた穴は、集合した中隊に懸ける……!」と一周して上がってるので、私は元気です。
スタンダードを最強として駆け抜けた無数のデッキたち。
それが更なる強化を受けて集結するようなフォーマット、それがパイオニア。
そんな、《歩行バリスタ》という最強のシナジーカードを失った《巻きつき蛇》は、スタン当時より弱くなっている疑惑すらありました。
歩行バリスタのない巻きつき蛇がパイオニアでは力不足なのはわかってる。
— 84g (@8844gg) December 12, 2021
けど、それでも俺はパイオニアではコイツを使うと決めてるし、
そして、「ファンデッキだから負けても仕方ない」というスタンスにもなれない。
大会に出るたびに無限に調整してる。
オワコン、ファンデッキだと直接言う人はそうはいない。
MTGは紳士のゲームだから。
ただ、負けるたびに俺の中で俺自身が言います。
「弱いカードを使ってるんだからしょうがない」、「カードが弱いんだ、俺が弱いんじゃない」。
それは事実や本音の一面ではあるかもしれないが、一面でしかない。
デッキ調整や環境理解のために、MTGアリーナでトップメタのデッキを回したりもした。
勝ちやすいと思うこと、苦労せずに勝てることも多かった。
ゲーム内のランクがスルスルと上がる。
しかし、勝っても俺のデッキであるという実感はありません。
これは、《巻きつき蛇》で勝てていた頃には、なかった感覚でした。
「強いカードで勝つ」。
「ならば強いカードとは何か」。
「強い構築とは何か」。
「敗因となったものは」。
無限に問うことができた。
一度の対戦ごとに勝因と敗因を考えるようになっていた。
漠然と漫然と勝てていたときとは、明らかに違ってきていた。
明らかに《巻きつき蛇》やカードたちによって、俺はカードゲームの楽しみ方をひとつ、理解した気がした。
元々、集合した中隊はルールス出た段階で注目してた。
— 84g (@8844gg) August 9, 2020
ただ、バリスタやハンガーバックとの仲の悪さで敬遠して。
今はバリスタが禁止、議事会の導師を得た。
中隊で蛇や導師と一緒にヨルヴォ出してぶん殴る。

白状すると、この《集合した中隊》型も、望む通りの結果は出せませんでした。
しかし、それでも、今もなお試行錯誤は続いています。
オリジナルデッキとしての《巻きつき蛇》を完成させるために。
もちろん、オリジナルではないデッキ、リストをコピーしたコピーデッキを使っても楽しい。
《巻きつき蛇》もスタンダード在籍時やパイオニア制定直後は当初はトップメタの一角として注目されていたリストだったし、それを否定する意図は全くない。
ただ、俺がやっていたのはカードで勝つではなく、「カードに勝たせてもらっていた」だけだった。
結果を出したリストをそのままコピーしようと、メイン60枚・サイド15枚の意図を解釈し、自分の全力を乗せることができたなら、それは紛れもない自分のデッキ。
ただ、俺にはそれが出来なかった。
“出来ていなかった”ことにも気づいてすらいませんでした。
過去の俺は、環境を理解しようともせず、カードの効果だけを見て、75枚の集合が持つ意味を考えようともしなかった。
それを勝てなくなったことで遅ればせながら理解できた。
リストに熱中する。
カード、そしてデッキと対話するように集合の強さを考える。
カードは単独の強さ、連繋したときの強さ、相手との相性による強さ。
カードには、デッキには、様々な強さがある。
それを読み解き、組み合わせたときに出来上がる一つのデッキ。
これを互いに戦わせて勝利を競う。MTGはそういうゲームだったんだ。
そんな当たり前のことを知らなった。
漠然と遊んでいた。それで十分だと思っていた。
もっと深い。もっと沼がある。《巻きつき蛇》の黒さが呼んだ沼があるんだ。
もっと楽しめる。もっと、もっと、もっと深く沈める。
このMTGというゲームは、《巻きつき蛇》と一緒なら、どこまでも面白くできる。
――本気でMTGを楽しめるようになったのは《巻きつき蛇》のおかげだった。
スタン当時、《巻きつき蛇》のおかげでMTGの楽しさを知ったし、仲間や友達もできた。
パイオニアをはじめてみようと思えたのも《巻きつき蛇》がいたから。
敗けたら運が悪い、カードが弱い、そんなクソみたいな言い訳をするよりも他に考えることはいくらでもあると教えてくれたのも《巻きつき蛇》。
このデッキと一緒に強くなる。強くなりたいと思えた。
俺は趣味でMTGをしている。楽しいから。
そして《巻きつき蛇》での勝利は、俺にとっては最高の勝利です。
最も気分よく、最も楽しく、最も俺らしい勝利であり、恩返しである。
対戦相手とその瞬間を築く。俺と《巻きつき蛇》の冒険。
《巻きつき蛇》と一緒に得る勝利は、そうでない勝利よりも強く輝く。
病気だ。そういう妄想だ。自覚はあるが治療法がない。治療する気もない。
自分の全力を注いだリストを、言い訳の余地のない“俺が一番強く使える”リストを、デッキリストを考案し続ける。
今、MTGアリーナでパイオニアもどきのエクスプローラーランク戦で勝率は5割を超え、ミシックランクでも戦え、実店舗のパイオニア大会に持ち込んでもそれなりに戦えるようになってきました。
しかし、まだまだ強いとは言えない。
トップメタと比べられるレベルじゃない。
しかしながら、確かに磨いてきた。カウンターを乗せてきた。
俺に乗る経験カウンターを《巻きつき蛇》は確実に増やしてくれている実感がある。
さあ! 一緒にパイオニアをやろう!
コピーデッキを使う? わかった! そのリストを誰より使いこなしてくれ!
オリジナルデッキを使う? わかった! かつてない破壊力を見せてくれ!
なんにせよ、俺と《巻きつき蛇》の経験カウンターになってくれ!
俺は先駆者になる。
いつの日か、『環境トップメタ:《巻きつき蛇》を黎明期から研究しているひとり』になるために。
今日も調整は続く。
そんなこんなで。
次回に続きます。
どの層に需要があるんだ?
当記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。
画像はMTG日本公式より引用しています。
ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。
題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。
©Wizards of the Coast LLC."
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
