
選挙で公費負担制度を使う場合
こんにちは、地方選挙専門の選挙広報プランナーhanaichiです。
今回は公費について簡単に解説したいと思います。
公費ってなに?
選挙に出るにはお金がかかります。立候補するだけでも供託金というお金が必要になりますし、ポスターなどの広報物を作るための費用、街宣車や事務所のレンタル、ポスター貼りのバイト代などなど。
選挙に際してなるべくお金がかからないように、また、お金持ちの候補者とお金がない候補者で選挙運動になるべく差が出ないように考えられたのが「公費負担制度(選挙公営制度)」です。この制度によって、選挙にかかるお金の一部が公費で助成されます。公費とは読んで字のごとく、「公的な費用」つまり税金のことになります。
本題の前に、ちょっとだけ自己紹介をさせていただきます。地方選挙専門で選挙ツールの制作をしています、hanaichiと申します。選挙ツールの制作を含む、企画・デザイン会社で勤務後、2021年からフリーで活動しています。
選挙ツールの制作については、2022年末現在で以下の実績があります。
※リピーターの方を含むため「人」ではなく「回」とさせていただいております
市長選挙 4回
県議会議員選挙 3回
市町議会議員選挙 20回
現在進行中の案件も含めさせていただいております。
また、国政選挙の経験も少しあります。
広報物で公費負担があるもの
公費負担制度には様々なものがありますが、当店で請け負っている広報物で公費負担があるものは2種類になります。
①選挙運動用ポスターの作成
②選挙運動用ビラ(政策ビラ)の作成
これらの作成費用については、全額または一部費用が公費にて賄われます。
①選挙運動用ポスターの作成
選挙になると、町中のあちこちに看板が立ち、候補者のポスターが並べて貼り出されます。これらのポスターは選挙運動用ポスター(掲示板ポスター)と呼ばれ、選挙期間中に貼り出されるものになります。こちらの作成費用に関しては、公費負担の対象になります。日頃、色んなところに貼ってある、国会議員や政党のポスターは別物になので注意が必要です。
公費負担が可能な金額は、ポスターを貼る掲示板の数と上限単価によって計算されます。掲示板数や上限単価は市町村、選挙区により異なります。また、市町村によっては掲示板数の1.15倍など、予備分も公費で認めていることもあります。
詳しくは、各市町の選挙管理委員会にお尋ねください。
②選挙運動用ビラ(政策ビラ)の作成
政策ビラは選挙期間中に配布できるビラになります。選挙事務所に来られる方に配ったり、街頭演説中に通行人に配ることができます。新聞折り込みも可能です。
政策ビラは発行できる枚数が決まっています。市長選・県議選は16,000枚まで、一般市議選は4,000枚(政令市は8,000枚)です。政策ビラには1枚1枚に「証紙」と呼ばれるシールを貼る必要があります。証紙は通常、立候補を届け出た際にもらえます。
こちらも公費負担制度の対象です。金額は市町村、選挙区によって異なりますが、ポスターに比べるとかなり低く設定されています。"一部補助がある"程度にお考えいただくと良いと思います。
注意点として、公費負担制度は当店のような業者と有償で作成契約を結んだ場合に対象となります。そのため、政策ビラを候補者が自身で作成し、自宅のプリンターで印刷した場合、対象にはなりません。また、支払については選挙後に候補者ではなく業者に対して選挙管理委員会から支払いがあります。
公費負担を受けたい場合
様式の種類
公費負担を受けたい場合はそれぞれ書類を揃えて、選挙管理委員会に提出する必要があります。ポスターと政策ビラで様式はほぼ一緒です。
①作成請負契約書
②作成枚数確認申請書
③作成証明書
④作成契約届出書
⑤請求書
⑥請求内訳書
以上の6種類になります。市町によって細部は異なるかもしれませんが、基本的に上記6種類になります。
①は候補者と当店のような業者で結ぶ契約書になります。そのため、他の書類と違い、選管に提出するのは印紙、両者押印したもののコピーになります。
②〜④は記入主体が候補者、⑤〜⑥は記入主体が業者になります。
これらの様式については、基本的に立候補予定者説明会時に他の公営書類(自動車関係やはがき、公報関連など)と合わせて配布されます。立候補予定者説明会は概ね選挙の1〜2ヶ月前に行われますので、忘れずに出席しましょう。一部自治体ではウェブサイト上にアップしている場合もあります。
様式を入手したら記入した上で事前審査に提出します。事前審査は選挙の概ね2週間前にあります。各種の書類やポスター、政策ビラなど膨大な資料を確認されます。
当店をご利用の場合
当店の場合、以下の流れで対応しております。
①様式の入手(候補者)
まずは、様式の入手をお願いします。
②様式の送付(候補者→当店)
紙の場合はスキャンしてPDFでお送りください。データの場合はそのままメール添付でお送りください。
③様式の記入(当店)
当店にて記入、印紙の貼付などを行います。候補者の方は契約書に押印いただくだけの状態まで仕上げます。
④様式の郵送(当店)
候補者のご指定の場所へ、それぞれ2部ずつ郵送します。
⑤様式の記入・返送(候補者)
ご自身の署名・押印をお願いします。
それぞれ1部は当店の控えとなります。記入後、当店まで返送をお願いします。
⑥選挙管理委員会への提出(候補者)
事前審査にて提出をお願いします。選挙後、請求書・請求内訳書の提出をお願いします。
候補者への公費分の入金について
当店では校了時(印刷前)に料金のお支払いをお願いしております。公費が当店に入金されるのは選挙後のため、一旦全ての料金を校了時にお支払いいただき、公費がある場合は当店に公費入金後、候補者へ当店から入金させていただいております。
公費の入金は市町によって異なり、選挙2ヶ月後になる場合もあります。また、振込手数料は候補者にご負担いただいております。予めご了承下さい。
公費が出ない場合
各選挙には供託金没収点が設定されています。
供託金とは立候補時に選管に預けるお金になります。選挙によって決められた金額を預け、一定以上の得票(供託金没収点)がない場合、預けたお金は戻ってきませんよ、という制度です。これによって、売名や泡沫候補の乱立を防いでいるということになります。
この、供託金没収点以上の得票がない場合、供託金が戻ってこないだけでなく、公費も出ません。供託金没収点は市議会議員選挙の場合、有効投票総数÷議員定数÷10になります。
以上、公費について簡単に解説しました。
選挙には独特な制度や決まり、書類などが多いため、初めて出る方は特に大変かと思います。当店ではできるだけサポートもさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
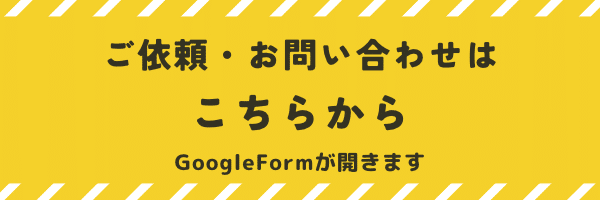
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
