
「届いているのに、届かない」状況をファントム理論で考えた その①
※長くなったので、2部構成に分けました。
「届いているのに、届かない」
痴話喧嘩をしているカップルは、雑踏でも目立つくらい声がデカい。むしろ、声がデカいゆえに目立っている。
別にカップルに限らず、我々は泣いたり怒ったり、感情的になると声が大きくなるものだ。
物理的な音の伝達という点では、十分に聞きとれる射程範囲にあるのに、声を張り上げるのはなぜかというと、そこには音声としての「コトバ」の背後にある主体の「ことば」を「聞き取ってもらえた」という実感が欠けているからである。
我々は、意味を伝達するためだけに話すのではない。発話を通じて、「この私」が承認されることを求めている。
例えば、いわゆるおしゃべり、というか一般的なコミュニケーションは後者の機能を中心に成り立っている(そのため、共感が必要とされる)。
明らかに聞こえているはずなのに、それに対応する何かしらのフィードバックがなければ当然不安になるだろう。あまりに手応えのない反応をされると、不満や苛立ちも募ってくる。
つまり、「(音として)届いているのに(心に)届かない」状況は発話主体にとって非常に居心地が悪いものである。
したがって、駅で喚く彼女は自分の言い分、すなわち自分自身が「聞き届けられない」ことに不満を募らせて、そのことに喚いているのであり、彼女の主体が認められない限り、彼氏はペコペコ謝ろうと別のことで気を引こうと徒労である。
「パターン」とは何か
唐突だが、発せられた言葉の「主体を凝縮した言霊としての主観的・精神的側面=ことば」と、「音声としての客観的・物理的側面=コトバ」の関係性はウォーコップ、および安永浩先生のいうパターンA/Bに当てはめることができる。
「パターン」について、簡単にいうと、対をなすカテゴリーのことである。
定義としては、
相対的不可欠性:両項はそれ単独で成立せず、互いを必要とする
非対称性:両項の相対性は、男と女、右と左のように平等ではなく、置き換えができない。パターンにおいては、前項の自明性、および後項の従属性が前提とされる。
代表的なパターンの例として、「自/他」がある。この関係性は、常に自が優位にあり、自から始まらなければならない。このことは、「体験世界は自我と非・自我からできている」と言うことはできるが、「体験世界は他と非・他からできている」と言うことはできない、ということから理解可能である。前項をA、後項をBとすれば、両項の関係はA>Bと示される。(なお、その他のパターンとして、質/量、精神/物質、生/死などがある)
すなわち、今回ではことば=A、コトバ=Bであり、健全な通常の対話の場合、ことば>コトバとなっている。
パターンの発案者であるウォーコップはAを「生きた挙動(living behavior)」B を「死-回避行動(death-avoiding behavior)」と説明する。生きた挙動は無・合理的、それ自体に喜びがあり、実用的見地からは無用に捉えられる行動である。一方、死-回避行動はその名の通り「死なないために渋々やっている」行動であり、意味や目的、合理性に支配されている。
イメージとしては、Aは生命エネルギーに満ち満ちた天真爛漫な子どものそれで、後者は心底不本意でやっている、「本当はやりたくないけどやるしかない」、死んだ魚の目にならざるを得ない行動である。付き合いのために重い足取りで行く死ぬほど嫌な飲み会は死-回避行動である。
余談だが、安永先生は両者のエネルギーの増減を以下のように図表化しているのだが、これがあまりに実感に即していて面白い。グラデーションのように、じわじわ音もなく変化していく感じが生々しくってもうなんとも…

「ファントム理論」について
さらに、安永先生は以上のパターンを応用化して「ファントム理論」という体験世界の図式化理論を展開している。
これは非常に面白いので、詳細は「精神の幾何学」および「安永浩著作集Ⅰ」、手に入りにくいけど一番読みやすいのは「精神科医のものの考え方」を参照してもらいたい(ちなみに、Wikipediaの説明も謎に充実しているhttps://ja.wikipedia.org/wiki/安永浩)。
最近これにハマっている手前、自分自身でもファントム空間をいじってみたくなった。そこで、例の「届いているのに届かない」状況についてファントム理論を借りながら考えてみた次第である。
本題に先立ち、まずその①ではファントム理論について、とりあえず必要そうな部分だけ頑張って説明を試みる。
【⑴基準体験線について】
・先程のパターンA/Bは直線上に図示することができる(図Ⅰ-1)。これは、主体Aから対象Bに向かう矢印である。

・主体側はさらにeとEに分化する(図Ⅰ-2)。
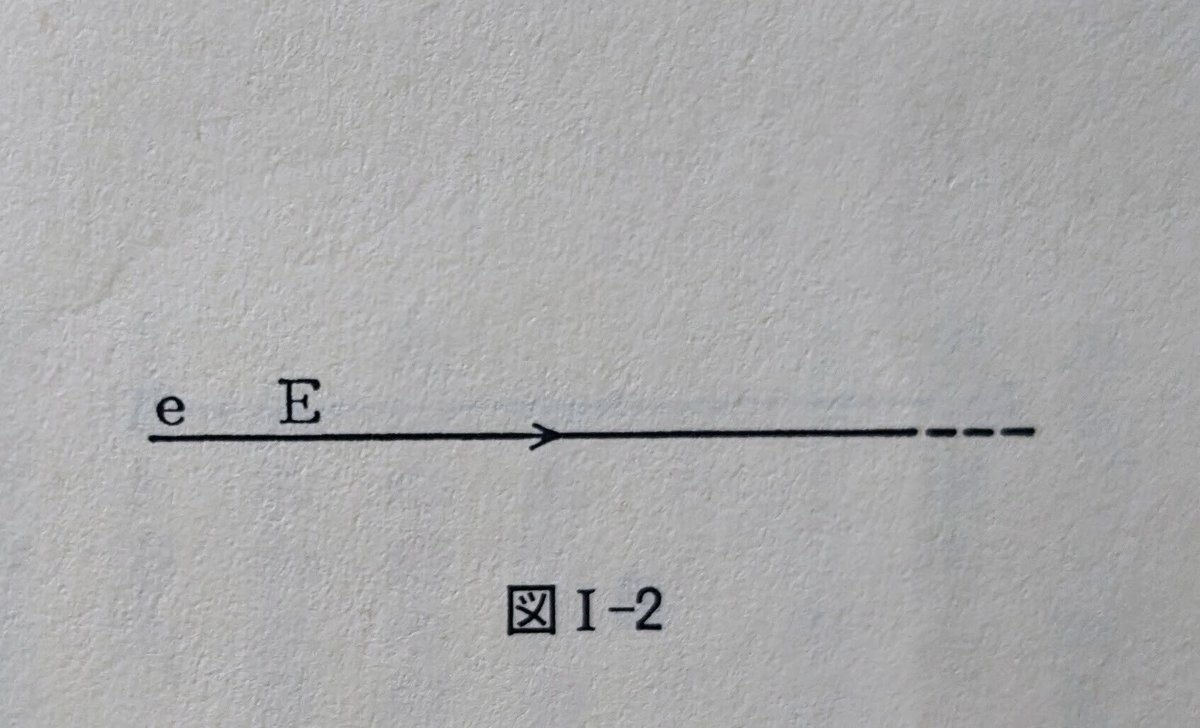
これは、より本質的主体である「私は」をe、二次的な「自我」をEとして、eはEを対象化し得ると言うことを意味する。私感では、eは西田幾多郎が「真の我は知る我ではなくして働く我である」と言うところの「働く我」であろう。eをノエシス的自己、Eをノエマ的自己というとわかりやすい。なお個人的には、eは「私は」よりも平仮名で「われ」とする方がしっくりくる(語感の柔らかさ、まろやかさ、字面の丸みが生命を感じさせる為?)。Eの「自我」はその凝り固まった感じ、融通の効かない感じがよく表されていると思う(非常にB的!)。
また、西田は「働く我は考える我を含むが故に、働く我の立場において現れるものは、思惟の範疇を含んだものでなければならぬ」(引用:「西田幾多郎哲学論集Ⅰ 」から「直接に与えられるもの」)と言っているが、そうするとeがEに先行している(安永語では「下流に置かれる」)のにも合点がいく。
・対象側もFとfに分化する(図Ⅰ-4)。

実際に主体が確認できる見え方を対象図式Fとし、決して体験されない絶対客観(物自体)をfとする。わかりやすくは、単純にEはF、eはfに対応する(かかる)と捉えればよい。個人的な印象では、EF関係は「私の本来性とはずれた、形式的で乾いた出来事」で、他人事、e的自己が及ばないため信頼できない感じ。対するef関係は「私の瑞々しい感覚が及ぶ範囲の出来事」で当事者性が強い感じ、と捉えている。EF関係がくぐもっていて実感がないのに対し、ef関係の方は澄んでいて、キラキラしている。総合的に見て前者はB的、後者はA的である。
【⑵二重の体験強度について】
主体側Aは、「生きた挙動」と言う位であるから、その実態はエネルギーである。このエネルギー量を「体験強度」という。体験強度も、生命がメラメラと発出するほとばしりとしてのa強度と、それを外界、対象側から制約するb強度とから成り立っている。最終的な体験強度は両者の拮抗関係によってほどほどな感じに落ち着いている。
体験強度に関しては、本当はここからさらに説明する必要があるが、ひとまずこの辺で理論の説明は区切りとする。
完全に独断、独りよがりな理解のため、誤解している点もあると思う。が、パターンひいてはファントム理論は現実世界をうまいこと捉え直すための現場的な道具であり、まさしく「ものの考え方」としてのあり方が本来的であると同時に、積極的に日常生活に汎用することで理解が深まると考えるため、お構いなしにどんどん使っていく。
※その②に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
