遅れてきたGS 6
昭和40年(1965年)夏 3人@金沢
「あー、3人とも汗びっしょりやね。……ほうや、お風呂屋さん行ってくるか?お父さん、悪いけど連れてってくれる?」
麦わら帽子をかぶって、捕虫網と虫かごを持った博臣と明と由美は、犬みたいに舌を突き出して、ハアハア言いながらもニコニコしていた。
虫かごの中で、この日の収穫である油ゼミがジージーやかましく鳴いている。
博臣と明はランニングシャツにサンダル、由美はシュミーズ姿。
夏の子どもの典型的な姿である。


「おーっ、いいぞ、じゃ、ヒロも由美ちゃんも明君も先に水、飲みや。そしたらお風呂屋さん、行こ」
博臣の父親は快諾し、明と由美の分も含めた3人分の着替えを母親から受け取る。
そして、自らは洗面器にせっけんを入れ、首にタオルを巻いただけの用意をした。
夏の夕暮れ。
三人はお互いの影を踏みあいながら走っていく。
「転ばんようにな!」という父親の注意などろくに聞きもしない。
夕立の後に出来た水たまりを見つけると、我先にと飛び越す。
興が乗ってくると、わざとビシャンと水たまりにはまる。
そして嬉しそうにキャハハと笑いあう。
父親は
「あーあー、ビショビショになってからに……でも、風呂入ってどうせ着替えるんやから、まっ、いいか」
とお気楽に思うのだった。
「あっ、3番あった!僕、長嶋!」
競争で銭湯に着くと、博臣が大急ぎで「3」と書かれた木の下足札を手に取る。
あいにく、王の背番号の1番はなかったけれど、長嶋の3番が残っていたのだった。
博臣は御多分にもれず巨人ファンで、王や長嶋の背番号と同じ下足入れが空いていると嬉々としてそこに「鉄腕アトム」が描かれている自分のサンダルを入れるのだった。


「巨人・大鵬・卵焼き」と言われていた時代。1番や3番は人気が高く、めったに空いていなかった。

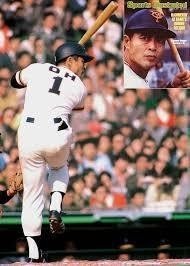
「ほら、明君。12が空いてるよ。柴田だよ」
おせっかいにも博臣は、明に当時の柴田の背番号を勧める。

明は全く野球に興味がなかったが、それでも勧められるままに「12」に「狼少年ケン」のキャラクターのついた黄色のサンダルをしまった。
一緒にいる由美には勧めない。
おせっかいは由美が一番嫌がるということを、博臣は既に学習していた。
今日は4人で男湯に入る。
父親が桶でお湯を汲んで来ては、順々に頭からザブンとかけてやる。
そして、石鹸をつけてゴシゴシ髪を洗ってやる。
それが終わると一人ずつ立たせ、タオルに石鹸を泡立てて今度は体中をゴシゴシ洗う。
最後にまた桶にお湯を汲み、一人ずつザブンと何回も頭からかけてやった。
シャワーは、立って使うのが一つあるだけで、桶を使って流すのが通常だった。
ちょっと前までは、仰向け抱っこして髪を洗ってやらなければならなかったのだが、3人とも座ったままシャンプーできるようになったので、大人一人だけで銭湯に連れてこられるようになったのだ。
シャンプーが目に入ると泣きわめいたり、頭からお湯をかけるのを怖がったりして、中々スムーズにいかないのは、例によって博臣だった。
でも、自分以外の2人が出来るようになると、「僕もがんばる」と言って少しずつ出来るようになった。
兄弟のいない博臣を鍛えるためにも、両親は由美や明と一緒に行動させたがった。
「ほら、3人で上がり湯に入っておいで。肩まで浸かって百まで数えてくるんやぞ」
そう言って、3人がお湯に浸かっている間に、父親は急いで自分の体を洗う。
そして、洗い終わると慌てて自分も湯船に体を沈めた。
興がのってくると、タオルを湯船に広げて浮かべ、風船を作ってブクブクと泡を出しては子どもたちを喜ばせた。
当時は、タオルを湯船につけるのに目くじらを立てる大人はいなかった。
「お父さん、もう出ていい?」
すぐに子どもたちがそう言うので、父親はいつも「カラスの行水」だった。
お湯から上がると、使っていたタオルを絞って3人の体を拭いてやる。
バスタオルなどという洒落たものは持ってきてないので、3人に服を着せ終えるころには、父親はまた汗びっしょりになっていた。
次はお待ちかねのドリンクタイム。
「白牛乳なら飲んでいいよ」
父親はそう言うが、三人は共同戦線を張って抵抗する。
結局、父親が折れて、由美がコーヒー牛乳、明と博臣がフルーツ牛乳をチョイスした。


牛乳ケースの脇にひもでぶら下げられている専用の道具で牛乳の「ふた」を開けるのだが、博臣だけは中々うまく出来ない。
「お父さん、開けて」
と差し出すと、明が
「ヒロ君、貸して。アキが開けてあげる」
と言って、器用に牛乳キャップを開けてやった。
続けて、明が
「由美ちゃんも開けてあげる」
と言ったものの、
「いい。わたしは自分で開ける」
そう言って由美は自分で開けた。

3人で腰に手を当てながらお風呂上りにコーヒー牛乳やフルーツ牛乳を飲むのは、楽しかった。
家に帰った父親は、子どもたちを銭湯に連れて行ったご褒美につけてもらったビールを一息に飲み干す。このために今日も一日頑張ったのだと思う。
「おい、明君も由美ちゃんもちゃんと自分で牛乳のふた開けられるぞ。ヒロだけ出来んかったわ」
ふと思い出して母親に伝えるが
「明君も由美ちゃんもお母さん忙しいから手をかけてもらってないんやろ。かわいそうに」
とトンチンカンな答えが返ってくる。
「そうじゃなくて、ヒロだけが遅れているんじゃないかと……」
「そんなもん、もうちょっと大きくなったら自然に出来るわぁ。牛乳のふたなんか取れんでも死にゃあせんわぁ。第一、博臣はえらいもんになって、全部、お手伝いさんがやってくれるようになるさかい大丈夫や」
「……」
「末は博士か大臣か」という思いから「博臣」と命名した母親は、気合を入れて鼻の穴を膨らませるのだった。
博臣の父親が3人を銭湯に連れていくことが多かったが、交替で母親たちが銭湯に連れて行くこともあった。
明の母親が連れて行ってくれる時には、博臣は何だか嬉しい。
「明君のおばちゃんって綺麗だな」と密かに憧れているからだ。
「髪、洗います」
そう言って明の母親は、番台で余分にお金を払う。

不思議に思った博臣が訊いてみる。
「どうしておばちゃんだけ、頭洗うのにお金がかかるの?」
「それはね、女の人は髪の毛が長いでしょ。だからたくさんお湯を使うから、その分お金がかかるのよ」
「でも、おばちゃんの髪の毛短いよ。男の人と同じだからお湯使わないよ。僕言ってあげようか?」
明の母親は、自慢のセシールカットに手をやってコロコロと笑いながら
「ありがと」
と言った。
騎士ぶりを発揮して、お礼を言われた博臣は、
「やっぱり明君のおばちゃん、綺麗だな」
と鼻の下を伸ばしてデヘヘヘと笑う。
「髪の毛洗いますって言わないで、内緒でお金払わない人っていないの?」
今度は由美が別のことを訊く。
「そんな人いないわよ」
由美の母親は笑って取りあわなかったが、由美はそのくらい厚かましい人も中にはいるだろうと、お金を払わずに洗髪を始める女性がいないか見張ることまでした。
「今日は髪洗いません」
と言おうものなら、その女性はお湯から上がるまで、ずっと由美に監視されることになった。
明の母親は「天花粉」(今でいうベビーパウダーのこと)をわざわざ持ってきて、風呂上りの3人にパタパタとはたいてくれた。

博臣はくすぐったくって仕方がなかったが、大好きな明のおばちゃんに全身を叩かれて幸せな気持ちになる。
そして、博臣は脱衣所の隅に置かれている冷蔵ケースに目を向ける。
ラムネを飲んでみたいのだ。
ラムネは博臣にとってあこがれの飲み物だった。
まず、開け方が難しそう。牛乳よりずっと。

牛乳のキャップと違って、専用の蓋を上から押し付けて開けるみたいだった。
この間は、ジュワーと泡がこぼれて、若いお兄さんが大笑いしていた。
それから飲みにくそうでもある。そのお兄さんが「ビ―玉、邪魔!」と言いながら飲みにくそうにしていたからだ。その様子を見て、
「へぇ~、ラムネって、中にビー玉が入っているんだ」
ますます興味が湧いてきた。
博臣の父親も明の母親も、牛乳が入っていればコーヒー牛乳でもフルーツ牛乳でもOKだったが、ラムネだけは絶対に許してくれない。
お金がかかるので、銭湯に行くのは週に1~2回というところだった。
だから、暑くなってくると、庭先で行水をする。
お風呂屋さんにはおもちゃを持って入ってはいけないが、行水はおもちゃでいっぱい遊べるのが楽しかった。
野良猫がそばにいると、カエルのおもちゃを目の前で動かしてからかってみたりもした。

しかし、男女を意識することなく何事も一緒に出来たのは、この年をもって終わりを告げることになる。
銭湯や行水が終わって帰る頃になると、バイバイと手を振る代わりに、3人はそれぞれ「シェー」のポーズをして帰途に就くのだった。
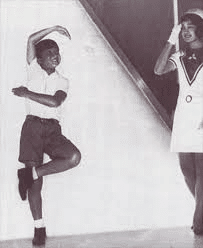

(続く)
この物語はフィクションです。実在する人物、団体とは一切関係がありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
