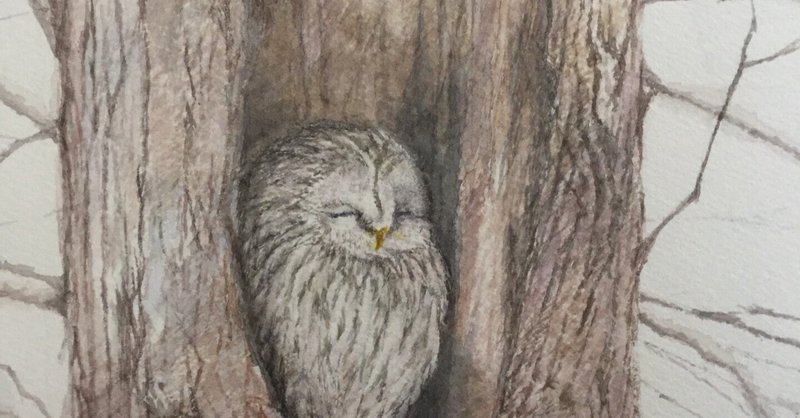
幸田露伴の随筆「折々草36」
三十六 わが失敗
去る午年(うまどし)の病後のことである。弱り果てた身を早く元の体に戻したいと少し運動をと思い立ったが、見慣れた我が家の周りを歩くのも、愚かな男が落とし物を拾うようでツマラナイと考えた末、細工事(さいくごと)などの適度な労作業をして自らを慰めようと心に決めた。サテ、何をしようかと考えたが、出来そうに思えることは運動の目的に合わず、運動になることは容易ではなさそうなので、少時(しばし)迷ったが、運動になればそれでよい、出来なくてもそれほど悔やむことでも無いと悟って、小さな箱を作ったり煙草盆を作ったりする簡単な木工(もっこう)を私の日課にしようと決めた。物が完成しなくても構わないとは思うものの、出来ないのも口惜しいので、心の底では密かに、必ず小さな箱を作りたい、煙草盆を作りたい、本箱も文机(ふみづくえ)も作りたいと多くの望みを懐き、かつ又、その望みを空中の雲のように消え果てさせたりしないぞと、強い念(おもい)を燃やした。
しかしその作業については、その当時は知らないだけでなく経験もしたことがなかったので、ただ鋸(のこぎり)で木を切って鉋(かんな)で削って釘を打ち付ければ小さい箱が出来るハズ、と云うこと以外は何も知らなかった。さらに闇夜の盲人が眼のある人より却って大胆なように、無知無経験な者は却って経験者より大胆になる理屈で、私は憐れにも大胆になっていたと云える。
こうした無知無経験が与えた胆力に誇り昂ぶった私は、寺島から浅草へ出て、鋸を買い曲尺(かねじゃく)を買って、意気揚々として家に帰ったが、その時の心中はいうに云われない愉快で充ちていた。それは云う迄もなく無知と無経験の二人がもたらした空想という者が贈って来た物である。
槌(つち)や鉋などは家にあるので、それを取り出して埃(ほこり)を払いマズ鉋を検(あらた)める。少し錆びていたけれど刃は幸い欠け損じ無く、砥石を出して研ぐと刃は表裏とも光り輝いて鋭く見えたので、試しに紙片や竹の葉などを切ると簡単に切れた。道具はととのった、イザマズ手始めに小箱を作ろうと、有り合せの板を取り出して勢いよく削りかけたが、心地よく板が刃を迎えて削られる音を立てて、クルクルと巻いた鉋屑が風にあおられて飛んで落ちると思っていたのが意外にも、ガッチと音がして板の一端に緊乎(しっか)と食っ付いたまま、曳いても曳いても一向に動かない。これはいけない、私の腕に熟練の冴えがないのでコウなったかと、再び鉋を持ち直して、今度は前より猶も力を込めて曳いたが、同様に思うようには削れない。刃が出過ぎているためかと思い、刃を少し後ろへ引っ込めて削ると、板の上を無駄にすべるだけ。やり損なってはやり直し、やり直してはやり損じ、ついにその日は削れずに力も疲れておもしろく無く終わった。
初日の失敗はそれほど私の心に響かなかった、次の日はゆっくり急がずに事を成そうと思い、一時間余りも鉋を研いだところ、その切れ味は濡れ紙を切るのも簡単なほどになった。コウなれば仕損じることも無いだろうと板に対(むか)って削ってみたが、昨日と同様の失敗を繰り返すばかりで何の効果もなく、その日も同じく不快なままで終った。
二日の失敗は私の心に響いて、三日目は流石に鉋を研ぐ勇気は無く、木工を中止して、単に本来の目的の運動のために浅草辺りを散歩したところ、ある家の修繕仕事をしている大工が、簡単そうに板を削っているのが眼に留まり、帰る道々、昨日一昨日の失敗をどうしても明日明後日には成し遂げたいとの考えに思い耽った。
砥石が水平で無いのが、鉋を研いでも成功しない原因ではと思い付いて、次の日は沓脱石の平らな面でマズ砥石を平らにしようと試みたが、コレは極めて短時間で出来た。些細な事だがこれに勇気を得て、今度は必ず成功するだろうと丹念に例の鉋を研いで一日を終え、その次の日も午後四時頃から研ぎ始めて夕方になると、見たところ前よりも鋭さが増したようなので、明日はおそらく快く削れるだろうと楽しみにした明くる日、十分に自信を持って例の板に対したが、訳も無くまた私の親友とも云える失敗者の来訪に遇って、鉋を投げ捨てて綾瀬の辺りを逍遥し、その事を忘れた訳では無いが、その事には関わらないで、或いは庭を掃き、或いは魚を釣り、或いはまた例の散歩などをして日々を過ごした。
ある日、散歩の途中で一人の大工が鉋を研いでいるのを見て近寄って見ると、彼は私の家で使っている類の砥石でない砥石で急がず滞らず研いでいる。その傍らには既に使い終わった思われる砥石が捨て置かれて在ったが、それは私の知っている砥石と同じものであった。これで白い砥石で研いだ後に更に緻密な砥石で研ぐべきことが分かったので、家に帰って例の鉋を研ぐと、今度は鉄の色もいよいよ澄み徹って秋の水のようになった、コウなればと心に三分の悦びを得たが、その悦びもつかの間に消えて例の失敗の親友が訪れた。
次の日、某と云う男が来て雑談に時を過ごしたが、私が「鉋はどうすれば物をよく削れるだろうか」と訊くと、「刃は少し丸みをおびたのが良い」と答えたので、その説に従ったが、その結果は今までの結果と比べて勝るところは無かった。
その後数日過ぎて或る老人が家に来た。老人であれば永い年月の間に積み蓄えた豊富な経験の中に、このような事もあったのではと密かに思って訊くと、「それらは能く知らないが、鉋は台木によって好くも悪くもなると聞く、それほど研いでいるのなら刃の鈍いことはないだろう、台木を吟味した方がよいかも、ただし私は鉋と云うものを手にしたことがないから精しいことは知らない」という。コレは真(まこと)に道理、台木が悪くては刃が板に触れる面に平均に当たらないハズで、従って使用に支障をきたす原因となろうと思って、その後、鉋の台木を定規で見ると、甚だ不規則にゆるやかに凹凸しているのが分かった。このために無駄な働きをしたのかと思ったものだから、急に面を水平にしようと思い立った。しかし他に鉋が無いので水平にすることが出来ない、しばらく考えていたが、愚かにも鮫やすりや木賊または金剛砂布を使おうか、それとも砥石の類を使おうかと考え出した。
この時、新しい鉋を買おうと思わなかったことも無かったが、今使っているこの鉋を使えずに終えるようでは、いくら新しい鉋を買っても使えずに今のようになるのは必定、今日の難儀を明日に伸ばすだけの話、であれば、成功は難しくても遅くても、今の鉋を使えるまでは新しい鉋は買わないでおこう、今の鉋が使えるようになった後に必要があれば買えばよい、また鉋の質が悪くないのに使えないのであれば、箱を作ることも煙草盆を作ることも私は出来ないと云うことであり、自ら愧(は)じて木工作業を止(や)めなくてはならない、ただしこの鉋が使えないと決まったわけでは無いと、頑固にも執拗にも自ら思い返して、新しいものは買わずに鮫やすりや木賊の類を買って、心を落ち着けて捗(はかど)り難い作業をやり始めた。
多くの日を費やした結果台木の水平は直せたが、木を削り始めると、折角の苦心の結果は例の親友を招く準備の茶菓(おまけ)に過ぎなかったことを知って、私は泣かんばかりに力を落とした。
その後は運動に決めた時間も他の事に費やし、口惜しい鉋には見向きもしないで過ごしたが、年長の某氏を訪れた時にこの事を話して、「簡単に見えることもやってみると難しい」と云い出すと某氏は笑って、「私は聞いたことがある、鉋は裏が切ると云って、素人が永年使った鉋はたいてい裏刃の刃口が知らないうちに中凹(なかくぼ)みになっていて、砥石の面に密着できないようになっているので、どんなに研いでも削れるようにはならないという、私のところに一ツ鋸がある、君に貸してあげよう、これは以前露店(よみせ)で買った物だが、この鉋を買った時は、家を出る前に隣の大工に、今夜鉋を買おうと思っているが、鉋は誰の作が優れているかと訊いたところ、誰の作でも火事に遇った物以外は刃のある物で切れないものは無い、ただ裏の欠けてないのを買いなさいと教えてくれたので知ったのだ、私も暇つぶしに小細工をすることが好きなので、教えられた通り裏の欠けていないものを買って来て直ちに使ってみたが、貴方の失敗のような失敗をしたので、ムッとして教えてくれた者を責めたところ、教えてくれた者は笑いながらコレは台が悪いと云って、鉋の台の裏を二三度削って私に返してくれたが、長い間使っていないので今はどうか分からないが、今までは快く削れていた、貴方、持ち帰って使って見なさい」と気の好い人なので私に鉋を貸してくれた。これに失った勇気を再び得て心嬉しく家に帰って鉋を調べると、果して裏刃が欠けていた。水平な物の上に刃を当てて透かして見ると、中央の部分が全く面に触れていない。サテはこれが失敗の原因かとマズ悦んで、急いで砥石を取り出し高い部分を減らそうと研ぎ始める。
昨日も研ぎ今日も研いで、日々怠らず腕が萎えるまで研いだが、終いには全く疲れ切っても思うように研げてはいない、変化も面白味も無いこの労働に精も根もさすがに尽き果てて、ある日、歯を食いしばって自ら堪えて研いでいる中(うち)に、愚かなことに力を尽くすことに、自分自身を嘲り罵り非難冷笑する心が起きて、その後はそれほど長くは堪えることが出来ないで、ついには自ら止めてしまった。
同じ寺島に住む文士の某翁を訪れた時のこと、私が愚かしい実際のところを打ち明け話して、単に刃物を研ぐことの難しいことを云って我知らずコボしたところ、翁も気安い人なので、「そうですなア、人の性分と云うべきか天稟(てんぴん)と云うべきか、別に木工など仕た覚えもないのに、チョット研いでも直ぐに能く切れるように研げる人もある、また盆などの器を拭くにも不思議と或る人が拭いた後は漆などを塗ったかのように光沢(つや)を発し、また或る人が拭いた器は汚れていないというだけで光沢は無いというように、俗に「きれ手」「つや手」というのもがあるのも強(あなが)ち否定できないようです」、と真率(しんそつ)に語られて、後は余談に入った。まことにそう云うことも有るだろう、私の祖母は所謂(いわゆる)「つや手」で、我家の他の者は「つや手」でないのが実際なので、私は自ら私は「つや手」でない男であるかと密かに自分を憐れに思うのを禁じ得ない、その時は最初に紙片や竹の葉を切った時の自負の満足の影が胸に浮かぶのに任せて、私は恐らくいわゆる「きれ手」のほうでしょうと口走ったけれども。
身体が次第に元のように丈夫になってきて強いて運動をする必要もなく、また面白味のない労働を引き続いてやるのも面倒くさくて、他の種々のことに紛れて何時の間にかあれほど熱心にしていた鉋のことも忘れたように止めて、その年は暮れた。
未年(ひつじとし)の春の初めに芝に引っ越したが、近くに西洋家具を製作する職人が多く住んで居ることから、交際の度に寺島で一度起こした念(おもい)がまた燃やされて、五月頃からその念が私を駆り立てて再び遺恨の鉋を手にさせた。同じような種々の失敗が記(しる)すのも煩わしいほど繰り返された。種々の人によって説かれた種々の教えは、確実にその一半は私を将来の成功へ近づけ、その一半は私を現在の失望に留めている。このよう私は今や単に鉋については殆んど知り尽くしている。しかし今なお私は小箱一ツ煙草盆一ツ作ることが出来ない。それは云うまでも無く、鋸や錐(きり)や鉄槌(てっつい)や卦引(けび)き等について失敗を重ねていないからである。アア、鉋だけにもこのように月日を重ねる。書棚や文机を作れるのはソモソモ何時の日のことだろうか、遠いかな、遠いかな。
注解
・鮫やすり:鮫の皮を板に貼りつけた研磨用品。
・木賊:硬くザラザラした茎を使って木材などを研磨する。
・金剛砂布:柘榴石を粉末にしたものを貼りつけた研磨用の布。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
