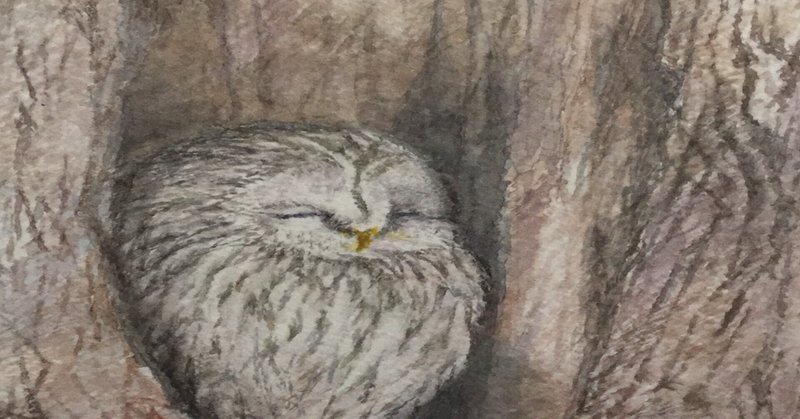
幸田露伴の考証「酔眼纈」
酔眼纈(すいがんけつ)
唐の李長吉の詩、胡蝶飛の曲、
楊花 帳を撲(う)ち 春雲爇(やける)
亀甲の屏風 酔眼纈(すいがんけつ)
東家の蝴蝶 西家に飛ぶ
白騎の少年 今日帰る
この詩の題は、現今本の王琦が注記するものでは蝴蝶舞となっているが、そうではない。第三句に蝴蝶飛とあり、明の姚佺の「昌谷詩箋」や清の姚文爕の「昌谷詩」に蝴蝶飛とあるのが正しい。詩は今体の七言絶句ではなく、第一句・第二句に爇纈九屑の韻を用いて、第三句・第四句に飛帰五徴の韻を用いている。蝴蝶舞ではなく蝴蝶飛であることを知るべきである。
春雲爇の爇は、諸本は皆熱に作る。爇に作るのは私の意見である。熱は如列切れで、爇である。であれば熱でも爇でも無論通じるが、熱は冷熱の熱として用いられて来たので、三月熱・五月熱・春心熱・山雨熱と云うには可(よ)いけれども、春雲熱では少し奇妙すぎる。爇は陟列切れで、焼である。楊(やなぎ)の花が乱れ飛んで帳(とばり)を撲(う)つ、春たけなわの頃の天日麗らかに空輝く暖かな時に、雲の端が光を帯びてやや紅く黄ばむのを、春日爇(や)けると云うのである。宝香爇ける、沈烟爇けるなどと云う爇の字のかたちは、一見した景色を表わすのに適していよう。春日熱しとして想像する情景よりも佳いと思う。しかし熱も爇もお互いに通じる字なので、どちらにしても読者の取りようで、強いて論じるには及ばないことである。諸本が熱とするのであれば、熱のままでもよい。何れにしても佳句である。
第二句の、亀甲屏風酔眼纈は難解の句ではなく、そのままに読んでも通じる句である。しかも長吉の詩詞は、描写に優れ、心中を抉り、快い気持にさせるものなので、細かに詩味を味わうには、この七字を軽々に呑み下してはいけない。先ず亀甲の屏風と云う。此の屏風は我が国の屏風とは異なる。屏風の古(いにしえ)のものは扆(い)である。扆は依で、依存するところである。「礼記」の「天子扆に当って立つ」の鄭玄の注に、「扆は屏風なり」とある。扆には斧の模様がある。それなので「礼記」に「天子斧扆(ふい)を負う」と云う文がある。屏風は障風である。能く風露を遮ることで屏風の名が出る。我が国で一般に云う障子や衝立や屏風等は皆同類のものである。現今の紙を一重(ひとえ)貼ったものは明かり障子、それに腰板が付いたのが腰障子、絹布などを貼ったものが衾(ふすま)障子、唐紙を貼ったものが唐紙障子である。衾とか唐紙とか云うのは障子を省略した名である。脚が有って何処にでも立てられるものを衝立障子と云うが、これも略して衝立と呼んでいる。古の賢聖障子とか荒海障子などは、衝立と云わずに直に障子と云うのが正しい名である。衝立は単一の障子で硬い屏風とも云えるものである。後世に此れを折りたたんだり引き延ばしたりする屏風が出来たので、此れを軟屏風と云って、昔からの単一のものを硬屏と云うようになったが、その初めは衝立障子のようなものであったろう。それなので、石屏風や玉屏風や雲母屏風や紫琉璃屏風や楠瘤屏風等の語があって、後世になって書画を屏風上に画くようになった。長吉の詩の亀甲の屏風とはどのような屏風か。「初学記」に「郭子横洞冥記」を引用して、「天子、神明台を起こす、上に金牀象席有り、雑玉で亀甲牀の屏風を作る、」と云う。玉琢崖は注書して、「思うにその模様が亀甲の模様に似ていることで云うのであろう、」と云う。郭の文や王の注は明解とは云えない。亀甲の模様は斑(まだら)に光り輝いてボヤケテいる。どうして雑玉を用いてそのような模様が出来ようか。これとは別に長吉の悩公の篇中に一聯があって、「亀甲開屏渋り、鵞毛滲墨濃やかなり」とある。屏を開く渋りとあれば、この亀甲の屏風は開閉できる二曲もしくは六曲等のもののようで、且つ渋の字を用いていることを考えれば、スラリと滑らかに開かないで聊(いささ)か渋るようである。雑玉等で亀甲の模様のように見せたものとも思えない。同じ作者が同じ亀甲の屏風をこのように云うのであれば、王琦が長吉詩の亀甲屏風を解釈して、時代が遥かに隔たった「洞冥記」の天子の神明台の屏風を引用するのは甚だ適当でないと思う。洞冥記の亀甲の屏風は雑玉を用いて作ったその模様は亀甲に似ているかも知れないが、長吉詩の亀甲の屏風はそういうものではないであろう。長吉詩の屏風は細木や篠を用いて亀甲状に組み立てたものではないだろうか。およそ細木や篠を組んで模様とするものには、井字を作るものがあり、亜字を作るものがあり、囘字を作るものがあり、その種類は甚だ多い。六角が繫がり合って模様を作るのが即ち亀甲模様である。亀甲は中央に五片、左右各々四片の計十三片で、片と片は皆六辺でそれぞれ接する。それでその名がある。亀甲屏風の名は漢の武帝の時代に始まったもののようだが、後になって細木や篠でその模様を形どったものが出て来て、それを亀甲屏風と云ったことも有り得ることである。屏風も初めは組子模様のものでは無いことは明らかだが、後になって細木や篠を組んで繒(そう)や帛(はく)や紙などを貼るものが多く出来るようになった。また早くから既に帛や紙を用いないものがあったことが晋の呉隠之の伝記に出ている。晋書に云う、「呉隠之は字(あざな)を處黙と云う。清貧である。劉裕太常卿に拝謁する。竹篷を以て屏風と為し、坐に繵席無し、」と。竹の篷(むしろ)を用いて屏風とすると云えば、ただ座席を隔てるだけであるが、それでも屏風の意味は無くは無い。我が国の組子の衝立に同じようなものがある。繒も紙も無い我が国の組子の衝立も、思うに彼の国の形式から出たものであろう。我が中世に通屏風と云う名のものが「掃部寮式」に出ているが、これは今の簾(すだれ)屏風と云うものに近いものである。ずしょうじと呼ばれてきたことでも、彼の国の様式に倣うものであることが推測できる。それなので李長吉詩の亀甲屏風は、現今の亀甲つなぎの組子の衝立のようなものと思っても間違いではないだろう。亀甲開屏渋もこのようなものとすれば、その状態は善く理解できる。開屏渋の屏風は両端の連なる屏風であろう。人間の巧緻は日進月歩に進むので、長吉の時代には既に六曲の屏風さえあったのである。何で両端のある屏風があったことを疑えよう。同じ人に屏風曲の一篇がある。云う、
蜨(ちょう・蝶)は石竹に棲む 銀の交関、
水は緑鴨を凝(こお)らす 琉璃の銭、
団廻せる六曲 膏蘭を抱く、
鬟(かん)を將(とき・解)て 鏡上の金蝉(きんせん)を抛(なげう)つ、
以下略。
銀交関は銀で造った今の鉸鏈(こうれん・蝶番)であると玉琢崖は注記している。団廻六曲抱膏蘭は、六曲屏風の中に蘭灯のほのかなことを云うのである。これで亀甲屏風の四字はどうにかこうにか解釈を仕尽したことになるが、此処になお疑問が一ツある。それは我が国の精美な屏風に亀甲の模様が時に見えることである。大層美しい金銀七彩などを用いた絢爛とした画屏風などに、例えば画のない金箔で雲形を押してある部分をよく見ると、その雲形の中にかすかに細かな亀甲模様が見えるものが有る。このようなものは無論ありきたりのものでは無いので、これを目にしたり、これに気付いたりした人も稀ではあろうが、時にこのようなものを見た人もあろう。その亀甲の模様を必要も無いのに加えた理由は何だろう、大層疑問だ。また例えば画も無い素地のところに全体に毘沙門亀甲などを現わしたのを見たことがある。そのような煩わしい工作を敢てする理由が分らない。青海波・紗綾形・菱つなぎ・亀甲蜀紅などは皆ありふれた模様なので、器物の装飾に用いられても不思議では無いが、特に亀甲が屏風に用いられることは、古くからあった事なのか、長吉詩の句もあって聊(いささ)か不審に思う。なお考えたい。それとはまた別に、屏風について疑問がある。この長吉詩には関係ないことであるが、我が国の唐紙屏風の中には中世以来近頃まで、多くは雀が両翼を張って煽った雀形と云う紙を用いているのが定例であり、古いものほどその雀は大きい。屏風の中に必ず雀形を用いるのは何故なのかが分からない。これも彼の国から伝わった唐紙の模様にあったものを、後に我が国でも真似て作ったものなのか。窠(か・巣)の紋も「主計寮式」に出ていて、古く彼の国から我が国へ伝わったと思える。窠は帽額と云い木瓜とも云う。御簾の上に添えて引く帛の紋は窠である。古い屏風などにはその縁にこの紋を置くものもある。すべて屏風の類のことは我が国からは出ないで、彼の国から伝わったものと思われる。彼を調べて我を知るべきである。ただ雀形は彼の国には未だその記事を見ない。亀甲雀影、アア何と古(いにしえ)の詳らかに仕難いことよ。
酔眼纈の三字は、ただ一名詞としてこれを理解すれば難しいところは無い。纈(けつ)はくくり染のことである。纈は玉琢崖が胡三省の「通鑑註」を引用して、「纈は布を摘まんで紐で之を結び、その後に染色する。染色したら結んだ紐を解く、すると結んだところは原色のままで、その他は染色される。そのため染色はまだら模様になる。これを纈と云う」と云っている。これで明らかである。酔眼の眼とは、纈の状態は自然と中央に染色の最も濃い処と無色の処を生じる。まるで眼のようなのでこれを眼と云う。酔は中央から放射状に染色の濃淡深浅が生じるところが、人が酔った時に顔に紅が射すようになることに喩えて云うのである。次第に紅色を増す木芙蓉を酔芙蓉と云うような酔の字の用い方である。なので、眼の字を省略して酔纈(すいけつ)と云うのもある。同じ長吉の詩に、
酔纈紅網を抛ち、
単羅緑蒙を挂く、
という句がある。紅網を抛(はな)つの三字は、まことに紅纈の美しくあでやかな状態(さま)を形容して、酔の一語は活きて躍々とすると云える。これで酔眼纈の解釈は済んだが、しかし上の亀甲屏風と酔眼纈とはどんな関係があるのか、ただ二ツのものを並べただけなのか。葡萄美酒夜光杯と云うのは葡萄美酒と夜光杯の二ツのものを並挙したものであるが、酒と杯との緊密な関係があることで、そこに詩情の生まれるところがある。亀甲屏風と酔眼纈とがただの並列で、何も関係が無ければ、骨董店を一瞥するようなことで何の味も生まれない。「鄴中記」には、晋の石季倫は金鈕屈膝の屏風を作り、それを装飾するのに白縑(はくけん・白い固布)を用いて義士・仙人・禽獣を画かせたと記されている。季倫は晋の時代の富豪で、屈膝屏風は高くも低くも出来るように作られた屏風である。これを装飾するのに白縑を用いるとあるその白縑に代えて、酔眼纈を用いることを想像すれば、亀甲屏風酔眼纈の七字はハッキリ理解出来て情致あると云える。酔眼纈の三字を死字として解釈すれば、このようなことに尽きる。
しかし、三字皆佳趣がある。これを活解すれば、酔に紅の意があり、暈の意があり、熱の意があり、乱の意があり、不定の意があり、眼に中心の意があり、情の意があり、義の意があり、我の意があり、纈に集の意があり、散の意があり、紛の意があり、凝の意があり、解釈を拡大すれば三字おのおの霊妙な感が無いことも無い。ここにおいて纈の字が蘇東坡の雪を詠ぜる詩の句に、
未だ嫌わず 長夜衣稜を作(な)すを、
却って怕(おそ)る 初陽眼纈を生ずるを。
というように用いられることがある。また同じく蘇東坡の独覚の詩に、
浮空の眼纈雲散じ、
無数の心花桃李発(ひら)く、
と云うように用いられることもある。ついに酔眼纈の纈は、もとは死字に疑い無いが、酔眼纈(しぼ・絞)ると活字として読んでも興趣がある。倪璠は庾子山の夜聴擣衣の詩句の花鬟酔眼纈を解釈して、「涙眼は酔うようで、砧(きぬた)を打つに際し乱髪は下に垂れて眼と繫がるようだ」と解釈するようにもなった。倪璠の解釈は無論ただの解釈に過ぎないが、このように解釈してもまた自然と情趣があって人に共感させるものがある。元来詩歌は、盲人が丸木橋を渡るようにただ一本の道を恐る恐る行くものでは無い。算数や法律を述べる文字とは大いに異なり、比興や譬喩や暗示や反語等は初めから許されることで、一情一辞が自他を溶融して、彼の中に此れがあり、東を写して西を帯びるところに詩歌の妙境も現われるのである。簡単な例を挙げれば、春の静かな平和な夜の草堂の上に柔らかに星の照る優しい景色を、杜甫が春星帯草堂と描写したようなことである。春の星なので、細く長いものではない、草堂の棟の上の空に在っても草堂を帯びるということは有る筈も無い、数学的法律論的に云えば理屈の通らないことであるが、此の帯の一字があることで、帯の本来の連帯の字義が働いて、いかにも春の星らしく草堂の余り高くないところに、秋や冬の星のように凄涼燦爛には照り輝かないで、ゆるやかに睦まじ気に草堂の上に在る状態が想像されて、春の夜の情景が人の身に浮かびまた浸みるのである。理屈や効率を云う人は、帯字は自動か他動か、春星が草堂を帯びるのか、春星が草堂に帯びられるのかと云うかも知れないが、この帯字は切って自他を云う字では無い。合して春星草堂を云う字である。春星があり草堂があり、そこに直ちに詩人の身中から湧き出して二者を融合一連する字である。若し強いて春星草堂を帯びると云えば、春星は天龍や山の雪線のようなものになってしまう。また若し強いて春星草堂を帯びられるとすれば、草堂は高灯籠のようなものになってしまう。どちらの情景も笑うだけである。この帯の一字は一にして二に亘り、二にして一二帰し、渾然と融け合い、理を離れ実を超えたところに霊活無限の作用があって、ありのままの春の情景はありのままに人の心に映じるのである。子供がオモチャに対するようにイジクッテこの帯字を理解しようとする時は、字霊は忽ち死んで語屍が空しく横たわるだけである。詩歌の極致はおおむねこのようになることがある。此処の酔眼纈は、ただこれ酔眼纈である。活用があるのではない。酔眼が纈(絞)られるのではない。であるが機微の間に酔眼纈の三字は、何となく動くような暈彩(うんさい)を生じる気味も無いではない。しかしこれは考慮外の事である。論じるようなことではない。拘(こだわ)れば即ち失敗すると云うものである。表はあくまで酔眼纈の纈であるとして、倪璠が庾句を解釈したような枝葉な言を為さない方が善い。
第三句の、東家蝴蝶西家飛は何のことも無い。ただ第一句第二句を受けて、春暖の季節のその場の情景を云ったものであるが、蝴蝶には本来東家も西家も無いが、前二句が打開けた家の状態を云うので、このように云うことで却って真実味が出る。第四句の、白騎少年今日帰は白馬に跨った少年が貴公子であることを暗示するのである。第三句の蝴蝶、第四句の少年、蝴蝶と少年は別に因縁があるのではないが、第一句から云い下して来て、この温和な春に今日帰ろうと結んだところに、一篇の情景はことごとく活動すると云うものである。この家はこれ何の家か、士人の家か、文武官員の家か、貴冑華族の家か、イヤイヤ、実はこのような家では無く、竹葉柳影の聊か媚(なま)めいた家なのであろう。この家がどのような家か露わには云ってはいないが、そこを覚り得てこの詩の巧みなことを知るべきである。
長吉の詩も佳ではあるが、李白や杜甫には比べられない。ましてこの一篇においては深く論じることも無い。たまたま人が粗雑にこの詩を論じて帰ったので筆を執って記す。閑筆一笑するだけである。
(昭和十七年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
