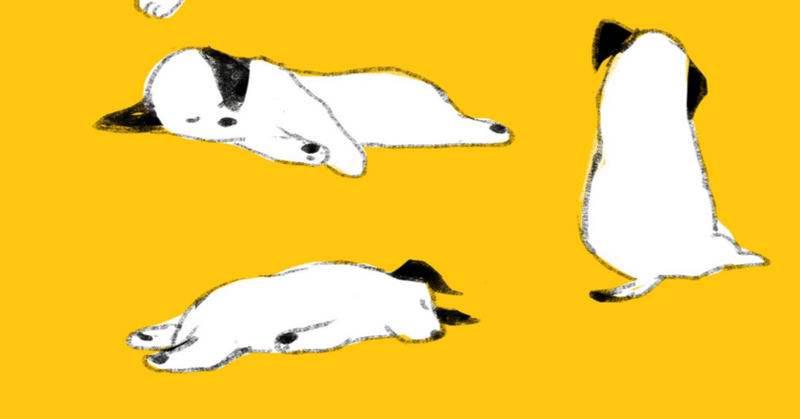
短編小説:いぬのかぞく
「なあモリさん、俺にはな、娘がおるんや」
霧雨の降る日曜の午後、朝からずっと落ち着かない様子で家の中を秀さんは、床に寝そべるおれの顔を覗き込んで言った。
「子どもなんて、スグきるもんやろと思てたんやけど、1年たっても2年たっても3年たってもどうにもでけへん、それで病院で調べてもろたら、里佳子さんは健康そのもの、いつでもママになれますてことやったんやけど、俺があかんかった」
ニンゲンの繁殖事情はよくわからないが、ともかく秀さんは細君の里佳子殿との間になかなか子が授からなかった。そしてそれの原因は秀さんにあったということらしい。医師から
「自然に子どもを授かることは不可能」
そのように聞いて落胆する秀さんに、細君である里佳子殿は子どもがない夫婦など世の中にはいくらでもいるのだし、子どもを持つことはこの結婚の絶対条件ではないはずだと秀さんに言ったそうだ。しかし秀さんはお子を諦めることができず、最終的に自身の体にメスを入れ体の改善を図り(子種の通る道が閉塞していたのだとか)、結婚10年目にようやく里佳子殿との間に待望のご息女を授かった。
「なにしろ可愛いんや、目に入れても痛くないって、ああいうことをいうのやろなァ」
秀さんの自宅のリビングのあちこちには赤ん坊の頃から成人した現在までのご息女の写真がいくつも飾られている。どの写真も輝くような笑顔で、写真のご息女の傍らにはいつも秀さんか里佳子殿、もしくは双方が寄り添う。幸福な家族だ、いや家族というものは一般に幸福なものと定義されているものか。
「秀さん、モリさんに近づきすぎやわ。モリさん困惑しきりですって難しい顔してはるもん、第一なに言うてるんかがわからんやんなァ」
「いや、モリさんは人語をわかってる、あの兄ちゃんの犬やぞ。せやからこうやって俺が俺のことを色々話して聞かせてたら、おれの人となりを分かってやな、安心してメシも食うようになるかもしらん」
「せやな、このまま全然食べへんかったらもう点滴や。なあモリさん、うちらはあんたの新しい家族なんやで。怖いことあらへんし遠慮もいらん、安心してご飯を食べなさい」
里佳子殿はおれの前に膝をつき、おれの頭を優しく撫でたが、おれは里佳子殿を上目遣いにちらりと一瞥して、返事をしなかった。
「モリさん、治彦さんはもういてないのよ。寂しいやろうけど、これからはうちらがモリさんの新しい家族やで、治彦さんの代わりにあんたを一生大事するさかい、このままうちらと一緒に暮らそう、な?」
秀さんと里佳子殿はおれを『かぞく』だと言う。以前おれとかぞくだったハルヒコの代わりに、自分達がおれのあたらしい『かぞく』になるのだと。しかし申し訳ないが里佳子殿、おれにとってハルヒコとはかぞくではなく主人であったのだ。そしておれにとっての主人は生涯、ハルヒコただひとりなのだ。
ハルヒコは、キョ―ジュというものを生業にしていた。
キョ―ジュというものが一体何をするものであるのか、おれにはよく分からない。ただ生前のハルヒコは毎日寝ながら本を読み、パソコンをぼうっと眺め、時々何かを冷蔵庫から出して立ったまま食べるという、おおよそ勤勉とは対極の怠惰な生活を送っていた。勤め先に足を運ぶのは週に数回程度、それも随分と陽が高くなってから普段着で出かけ、夕餉の頃に帰宅しておれの散歩と食事をすませると、また深夜またふらりとどこかに出かける、大変に気楽そうな毎日だった。
ハルヒコは秀さんと違って子どもがないし妻もない。遠い昔、おれがまだ仔犬から若犬だった時期には一緒に暮らしていた人がいたが、その人は冬の雨の日の朝まるで煙のようにハルヒコとおれの元から消え去ってしまい、それ以後おれたちはひとりと一匹で暮らしてきたのだ。
しかしおれは、常日頃夕餉として白飯になめたけを乗せたものだけを食すとか、仕事の合間の昼餐に蕎麦にフライドポテトを乗せて食べるとか、昼前に「遅い朝食」と称して小倉あんとバターを挟んだ食パンとマヨネーズに七味を振って焼いた食パンを交互に齧るなどという、偏った食生活を送るハルヒコの体が心配で
(ハルヒコ、誰かと一緒ならないのか、男やもめは寿命が短いと聞くぞ)
そのようなことを進言していた。ハルヒコと違う嗜好の人間がひとりでも家にいれば、ハルヒコの偏食を窘め、矯正してくれるのではないかと期待したのだ。しかしハルヒコはそんなおれの気持ちに気づくことなく、ひとりと一匹の暮らしを続けた。ハルヒコは毎晩ウイスキーをちびちび飲みながおれの肩を抱き、もしくはおれのタプタプとしたマズルの皮を弄びながらこう言ったものだ。
「俺はもうモリがいればそれでいいんや、モリは長生きしてくれ、俺は大切な人を見送るなんてことは2度とやりたくない」
戦後すぐ建てられた古い木造家屋に時折家鳴りだけが響く夜、酔って赤い顔をしたハルヒコは、いつもどこか寂しそうだった。
(しかしな、おれたち犬族の平均寿命はだいたい10年から15年、かたやハルヒコ達ニンゲンは人生100年時代と言うではないか、おれが7たび生まれ変わろうとハルヒコ達ニンゲンの命の長さを凌駕することはできないんだ)
「長生きしてくれモリ、オマエがいなくなったら俺はこの家にひとりぼっちや」
(そこは、おれも鋭意努力はしてみるが)
おれは返事をする代わりに、尻尾を振った。ウイスキーがハルヒコの体を巡り、やがてハルヒコの呂律が回らなくなってくると、ハルヒコは今度おれの腹を枕にしてごろりと床に横になり、家族の定義についておれに話しはじめる。ハルヒコはダイガクというところで家族社会学というものを教えていた。
家族:それは最も小さな共同体である、本来的な意味としては夫婦や親子を中心とした結びつきであるが、現代の家族はそこに限定されない、同性同士が夫婦となり、種族として全く別の生き物を家族と呼称することもある、例えば猫、例えば鳥、そして犬。
「おまえだけが俺の家族や、それでいい」
ハルヒコは俺の腹を枕に仰臥しながら手を伸ばして俺の鼻先をこしょこしょとくすぐる、俺はぶしゅんとくしゃみをする。
(やめろハルヒコ、いまおまえの顔におれの鼻水が飛んだぞ)
「うわ、これよだれか?モリ腹減ってんのんか、さっきようさん食うたやろ」
(いや、だからそれは鼻水だ)
おれの鼻水をよだれと勘違いしたハルヒコは笑い、おれはハルヒコが床の上でいびきをかき出す前にすっと立ち上がって、ハルヒコに布団に入るようにと鼻先で促した。以前、夕餉のあとにリビングの床の上で朝まで寝てしまったハルヒコは風邪をひいてその後1週間高熱を出して寝込んだことがあるのだ。以来おれは酔っ払って床に仰臥するハルヒコを起こし、布団に入るようにと鼻先でつついて促すようになった。ハルヒコ、床で寝るな、また風邪をひくぞ。
ハルヒコの最期の日も、ハルヒコはいつものように酔いに任せて床に寝転び「マイノリティとは誰のことか」という講義を朗々とおれに語り、そののち俺に促されて布団で入眠している。この国で少数派であるということは『最大多数の最大幸福』に抗って生きることであり、それは常に生きづらさと共にあるものだ、しかしそれは不幸という言葉とは意味を異にする。
「俺はそういう場所から世界を見ているんや、犬のおまえにはどう見えるんやろうなァ、世界」
ハルヒコはそう言ってから静かに寝息を立てはじめた。おれは立ち上がって体高61㎝の視座で部屋の中を見渡してみたが、そこにはハルヒコの蔵書がうずたかく積み上げられているいつものハルヒコの寝室だった。まあいい、明日起きたらハルヒコと散歩に行こう。世界がどんな姿かたちをしているものであれ、晴れた日の淀川堤防は川の水面がきらきら美しくたいへんに気持ちが良いものだ、ハルヒコ、明日もおれと歩こう。
おれが淀川堤防で風に揺れるセイタカアワダチソウを想いながら眠りに落ちた翌朝、ハルヒコは目を覚まさなかった。
(ハルヒコ、どうしたんだ、朝だぞ)
前足で頭を小突いても、顔をぺろぺろと舐めても、ハルヒコはひとつも目を覚まさず、ハルヒコの体が弛緩した状態から徐々に硬直してゆく様をひどく奇異に感じはしたものの、それが一体何なのかおれには皆目分からなかった。おれはペットショップ育ちの箱入り犬で、命の理をよく理解していなかったのだ。そしてそのまま2日間が過ぎた。
ハルヒコが動かなくなってから3日目、ハルヒコから床板の張替えを頼まれていたという工務店の主人によっておれとハルヒコは発見された。第一発見者となった工務店の主人の手によって諸々の手続きを経てハルヒコは荼毘に付され、そしてその工務店の主人がおれの身柄を引き取ることになった、それが秀さんだ。
秀さんは、目を覚まさないハルヒコの傍らに座るおれの前に膝をつき、自分はハルヒコの血の繋がらない弟だとおれに言った。人間とは大変に不思議な生き物だ、時に全く血縁のないものを兄弟と呼ぶことがあるらしい。
「俺が9歳か…アレ10歳やったか?そんくらいの時に、俺の母ちゃんと、兄ちゃんの父ちゃんが再婚したんや、子連れ同士の再婚ってヤツやな」
秀さんとハルヒコは、秀さんの母親とハルヒコの父親がそれぞれ子連れ再婚をして発生した後発的兄弟だった。母親から「この子がお兄ちゃんやで」と紹介された時のハルヒコは、付属中に通う大変聡い子どもであったらしい。成績は飛びぬけて優秀で学級長などをしばしば拝命し、そのまま付属の高校に上がり、ダイガクとダイガクインというところを出て、その後しばらく外国で暮らしていた。一方の秀さんは悪戯ボウズで筆箱には折れた鉛筆が1本転がっているだけの勉強嫌い、公立中から這う這うの体で入学した工業高校も、理不尽な理由で友人を折檻した教師をぶん殴り、放校同然で自主退学している。
「俺な、兄ちゃんが俺とあんまりなんもかも違うもんで、俺のことアホやと思てんねやろなて、その…互いに分かり合えることなんかないのやろなて勝手に思ってたんや」
ハルヒコの躯を見送りながら、秀さんはハルヒコとの思い出をぽつりぽつりと、おれに話してくれた。
ハルヒコが将棋でわざと秀さんに負け、神妙な顔で「参りました」と頭を下げてくれたこと、悪い友達にそそのかされて近所の駄菓子屋からフーセンガムをひとつ盗んだ日に、店に代金を払いに行ってくれたこと、自分がひと晩考えてひとつも分からなかった算数の宿題を解いておいてくれたこと。
そんな兄のことをいつしか自分とは学歴も嗜好も考え方も、何もかも違う人種なのだと、避けるようになっていたこと。こうして兄を亡くしてしまった今、それをとても後悔していること。
「でもなモリさん。ちょっと前に突然兄ちゃんが床板が犬のよだれのシミやらひっかき傷だらけなもんで、貼り替えを頼めへんかって電話してきたんや。兄ちゃんに頼みごとされるなんて初めてや、俺嬉しくてなァ、そんなら一番ええ板を超身内価格にしたるからまかしとけって言うてたんや。それが突然こんなことになって…なァ、人間て、ほんまに死ぬんやな」
(そうだな秀さん、いのちとはとても儚い、そして尊いものだ)
おれは返事をする代わりに、ちいさく鼻を鳴らした。
それから、たくさんのニンゲンが、黒い衣装を纏い小さな包みを片手にぐずぐずと鼻を鳴らしながらおれとハルヒコの家にやって来ては去った。その列がすべて途切れ、おれの家に再び静寂が訪れた晩、秀さんはおれに言った。
「なあモリさん、俺の家で暮らそう、俺にとってオマエは兄ちゃんの形見なんや」
(秀さん、それはできない相談だ)
「な、行こう、俺の家もそこそこ広いで」
(いや、おれはここに残るつもりなんだ、申し訳ないが)
おれは秀さんの申し出を断ったのだが、おれの言葉を理解しない秀さんはおれのことを抱えて車に乗せてしまった。秀さんが仕事で使っているらしい大きな車の中で、おれは自分をハルヒコの躯と共に焼いてほしいとピィピィ鼻を鳴らして訴えたが、秀さんはよしよしとおれの頭を撫でて、そのまま車のエンジンをかけた。
「モリさん、そんな哀しい声出すな、なんも心配いらんのやから」
道中一度、秀さんがトイレ休憩だと言って5分程おれを淀川の堤防に降ろしてくれた。おれがいつもハルヒコと歩いていた淀川だ。しかしそこには川の音も草の匂いも、セイタカアワダチソウの中に潜んでいる猫の気配も、すべていままでどおりそこにあるはずなのに、おれはそれを感知しなかった。ハルヒコの死と同時におれの世界も終わったのかもしれない。なにもかも変わってゆく、いつかハルヒコの言っていた仏陀の最期の言葉のように。
「諸々の現象とは過ぎ去るものだ」
そうして秀さんの家に身柄を移してから1週間、おれはまともに食事をとっていない。
その間、秀さんが獣医や知人に聞いて購入したフードは5種類、それ以外にもささみを湯がいたもの、牛肉の赤身を焼いたもの、チーズ、タイのアラを茹でて身を丁寧に剥がしてほぐしたものなど。おれにとってはすべて魂いの飛ぶようなご馳走であったが、おれはその一切をほんのすこし舐めただけで咀嚼も嚥下もせず、この体が飢えて衰え、魂がハルヒコの元に旅立ってゆく日を待っていた。
楓の床材の敷かれた広いリビングに、中庭の風景をすべて見渡せるよう誂えた一枚ガラスの大きな窓、丸窓障子の設えられた畳敷きの小上がり、工務店の社長宅らしい凝った造りのリビングの一角にペットシーツを敷き、大型のペットケージを置いた場所がおれの当座の居場所となった。おれはそこに這いつくばったまま動かず、そんなおれを見て秀さんも里佳子殿もひどく困惑し、毎日ため息をついていた。
しかし、1週間目のこの日は少し様子が違った。どうやら今日、件の秀さんのご息女がこの家に帰ってくるらしい。おれの目の前に座り込んだ秀さんが、いかにも工務店の親方といった屈強な体躯と風貌に似合わないひどく情けない顔をしていた。
「なあモリさん、おれどんな顔してアイツのこと出迎えたらええんやろ」
(件のご息女か、ならば普段のように自宅に迎え入れ、ともに食卓を囲めばよいではないか)
「あんなあ、俺の娘、佳乃子ていうねやけど、そのかのちゃんが紹介したひとがおるから、今日うちに連れて来るて言うねん」
(会うがいいさ。80億人ものニンゲンのいるこの世界で人が出会うことは奇跡みたいなものだと、死んだハルヒコも言っていた)
「紹介したいひとがおるていうのは、アレやんな、その…結婚しますとか、お嬢さんを僕にくださいとか…つまりそういうことなんやろ」
(はて、佳乃子殿はモノではなくニンゲンだ、くださいとかやるとかの文言はおかしくはないだろうか)
「なあ俺、どないしたらええと思う?兄ちゃんの代わりになんか言うてくれモリさん、ラブラドールレトリバーて賢い犬なんやろ」
(賢いかどうかは、他の犬種をあまり良く知らないおれにはなんとも。ハルヒコが生きていれば、まず相手に会ってみよ、それから考えろと言うだろうが)
おれにしきりに話しかけていた秀さんは、傍目には無反応であるおれを前に、がっくり肩を落とし深いため息をついた。そんな秀さんの背後でこれからやって来るご息女と、もうひとりのニンゲンのためだろう、昼過ぎから一心に料理をしていた里佳子殿は笑った。
「秀さんもういかげんにし、かのちゃんも今年で30やねんから、付き合うてる人くらいおるし結婚かてするやろ、第一結婚はせえへんのんかて散々あの子に言うてたんは秀さんの方やないの」
「そんなん俺、言うてへん」
「言うてたわ、ウチに帰省するたび誰か好きな男はいてへんのかて、そんでかのちゃんがそんなんいてないて言うたら、ほんなら職場にええなってやつはおらんのかて言うてたわ、かのちゃんがそれもいてないて言うたら、終いには一体どんな男ならええんやて言うてたやないの」
「いや、言うてないて」
「言うてました、その待望のお相手がやっと来てくれるのやで、観念して着替えてきたらどうやの」
おれのケージの中に半身を突っ込み、世界の終わりといった表情をしていた秀さんはしぶしぶ立ち上がると、黙って2階に上がっていった。ニンゲンは面倒な生き物だ、ただ自宅で人と会うだけのことに身なりを整えなくてはならないとは。おれの換毛期は非常に面倒なものだが、毎日着替えるよりマシなのかもしれない。
里佳子殿が用意したらしいポロシャツとチノパンツに着替え、リビングをノイローゼのシロクマのように(ハルヒコがそんな気の毒なシロクマの話をしていたことがあるのだ)ひたすら往復していた秀さんのもとに、佳乃子殿とそのお連れ合いになるひとが到着したのは、遠くの山の端に夕陽がほんの少しかかるかかからないかの頃合いだった。
どうやら東京駅から乗ったシンカンセンとやらが遅れたらしい。「あんたらご飯は?」「朝おにぎり食べたきりやねん」という普通の親子らしい会話の交わされている玄関の様子に、秀さんは臆病な野良猫のような表情になり、また2階の自室に引っ込んでしまった。
「モリさん、あとは頼んだで」
(そう言われても、おれは犬だ、どうにもできない)
おれが秀さんの言葉に戸惑いながら玄関の人影を注視していると、里佳子殿に伴われて佳乃子殿と、そのお連れ合いになるひとがやってきた。ふたりはまずこの家の居候であるおれのケージの前にきて、そっとケージの中のおれを覗き込んだ。
「お母さん、この子がモリ?」
「そう、モリエールのモリやて」
「伯父さんらしい、モリエールて17世紀の喜劇作家やろ」
「さあ、お母さんはしらんけど、なんかな、5年前に亡くなった治彦さんのお連れ合いさんがペットショップで売れ残ってたのを買って、それで飼い始めた子なんやて。その人がモリって付けたらしいわ。せやから治彦さんにとってはお連れ合いさんの形見みたいなもんやったんやろね、ものすごかわいがってはったみたい」
「そうなんや。元気ないなァ、伯父さんが急に死んでしもて辛いんやな」
「せやねん、見てるこっちの胸が痛くなるくら落ち込んでて、ご飯も食べんへんし、ホンマに困ってるんよ」
「あのう…この子、ずっとこのケージの中にいるんですか」
「え?あ、そうなんよ、この家はこの子にとっては全く知らんとこやし、慣れへんうちは落ち着かへんかなと思って」
「もしかしたら、ケージから出して、落ち着く場所をワンちゃん自身に探させてあげるといいかもしれません、亡くなった伯父様が普段おうちの中で自由に過ごさせていた子なら、そっちの方が落ち着くかも」
「そうやろか」
「お母さんアキラの実家にも、モリと同じゴールデンちゃんがおるねん、元保護犬の子、モリよりもう少し白っぽい色の女の子やねんで」
「へえー、やっぱ大きいん?」
「メスだからモリ君よりひと回りほど小さいかもしれません、でも人懐っこい子で、今4歳です」
アキラ殿に促されて里佳子殿はおれのケージの扉を開けた、おれはもうこの狭いケージの中で朽ち果てる覚悟ではあったのだが、扉を開け放たれると外に出てみたくなるのが生き物の本能というものか、おれは里佳子殿と佳乃子殿、そしてアキラ殿の3人に「おいでおいで」と笑顔で手招きされ、おそるおそるケージの外に出た。
「歩いた歩いた、立つと大きいなァやっぱり」
「この子、何キロですか?」
「ウーン、お父さんが40キロくらいて言うてたかな」
「なあ、立ち上がったらお母さんの背丈とそう変わらへんのんちゃう?」
ハルヒコと暮らしていた頃も時折、かれらのような若者がおれの家に遊びに来た。皆ハルヒコのゼミの学生で、ハルヒコの家の庭や、淀川の河川敷でボールやらフリスビーやらを投げて存分におれと遊んでくれたものだった。目の前の若いふたりを見ていると、あの頃の優しい若者達を思い出す。
「あ、モリ尻尾振ってるで」
「ほんまや、やっぱりアキラちゃんの言う通り、閉じ込めてたんがあかんかったやなァ」
どんなに気持ちが沈んでいても、過去の楽しく美しい思い出は色あせない。おれはつい、尻尾を振って佳乃子殿の掌に頭を擦り付け、鼻先に差し出されたアキラ殿の指先を舐めた。アキラ殿の指先からは微かに甘いバニラエッセンスの香りがする、聞けばアキラ殿は菓子職人であるらしい。アキラ殿がこの日持参した手土産はアキラ殿の焼いたチーズケーキで、それは秀さんご自慢の欅の一枚板でできたテーブルの上に置かれていた。
「お父さーんフテてないで降りてきてみ、モリさんが2人にえらい懐いてるで」
「はァ?おれは別にフテてなんかない、ちょっとアレや、急ぎの仕事があったんや、ほんで佳乃子が連れて来たんはどいつや」
おおよそ踊り場あたりで階下の様子を伺っていたのだろう、里佳子殿に呼ばれた秀さんがばたばたと駆け下りてきた。
「どいつもなにも、ここにいてはるやないの、滝本晶ちゃんよ、なんなんお父さんたら挨拶もせんと『どいつや』なんて」
「晶ちゃんよて、え…このお嬢さんがか?」
「そうや、滝本晶ちゃん、東京の西荻窪のケーキ屋さんで働いてはるんよ」
「だって…この子は女の子やぞ、かのちゃんの…お友達なんちゃうんか」
「あたし晶と結婚するねん、今日はそれをお父さんに言いに来たんや」
「なにをアホな…えっ、その、里佳子さんはこのこと知ってたんか?」
「そうや」
「そうやて、ほしたらなんでそれを俺に言わへんねん」
「だって秀さん、これとよう似たことが昔あったやろ、そん時秀さん自分がなに言うたか覚えてへんの?相手さんに随分なこと言うて、それでそのまま疎遠になってしもたやないの」
「それはあれや、あん時はちょっと驚いただけていうか…いや、それはそれ、これはこれや。大体いくらなんでもこのやり方は乱暴ちゃうか、突然娘が女の子を家に連れてきてやな、あたしたち結婚しますやなんて」
語気を強め鼻息を荒くした秀さん、冷静な表情の里佳子殿、一歩も引く気配のない佳乃子殿、困惑しているアキラ殿、4人の間に緊張した空気が流れた。そして全員の視線がおれから逸れた瞬間、おれはテーブルに飛びつき、そこにあったチーズケーキにかぶりついた。
「うわ、モリさんなにしとんねん!やめやめ、ストップや、あかんて、オスワリ!フセ!フセ!」
秀さんはおれに飛びついておれを止めようとしたが、おれを止めることはできない。おれがテーブルに前足を掛けて飛びついたチーズケーキはそのまま床に落ち、おれは床で粉々に砕けたチーズケーキを無我夢中で飲み込んだ。
「この子、治彦さんが亡くなってから、ホンマになんにも食べへんかってんけど、ホンマはお腹減ってたんやろなァ、ゴメンな晶ちゃん…」
「いえ、またいくらでも作りますから。でもフフッ、ゴールデンって、すっごい食いしん坊の犬種なんですよ、うちの子も油断してるとやります、朝ごはんの食パンとか、パクッと咥えて持って行っちゃうんです」
「まあチーズケーキやし、チョコとかお酒の入ったお菓子じゃないから大丈夫やろ?」
「ワンちゃんの害になるものは入ってないけど、ホントはダメだよ。次からはワンちゃん用のも作ってくるね、モリ」
「やって、良かったね、モリ」
「良かったねやあるか、すました顔して何ちゅう犬や」
心づくしの手土産をおれに急襲され、食い散らかされたアキラ殿は「むしろ食欲が戻ってよかった」と言っておれを許してくれた、秀さんはおれのことを叱って、軽く小突いた。
しかし、そもそもこれはハルヒコがいけないのだ。生前のハルヒコはおれがちょっとでも欲しがると「モリ、これ食べたいんか?しょうがないなァ、ちょっとだけやぞ」と、たちまち食パンの耳やら、苺タルトの土台やら、煎餅のノリやら、そういうものをしょっちゅうおれに与えていたのだから。
おれがまだ若犬だった頃、すなわちハルヒコの同居人が生きていた頃は「ハルヒコそれはダメ、人間の食べ物は犬の体に良くないし、盗み食いする犬になるよ」と禁止していたニンゲンの食べ物を、同居人がいなくなってからのハルヒコはおれによく与えていた。お陰で品行方正、どこに出しても恥ずかしくない利口な犬だと口々にほめそやされてきたおれの唯一にして最大の欠点が「人の食べ物を闇雲に欲しがる」になってしまったのだ。
やはりハルヒコがいけない。
「ちょっと早いけど晩ご飯にしよか。お母さん今日ちょっとええ肉でローストビーフを作ったんやで。お父さん、モリさんのお散歩のついでにお買い物行ってきてくれへん?張り切ってローストビーフ作ったのに、肝心のホースラディッシュを買い忘れてしもたんよ」
アキラ殿のケーキを食い散らかしたおれのことを秀さんは平身低頭アキラ殿に謝罪した。しかしアキラ殿は天女のように優しく「また焼いてくるので次は是非召し上がってください」などと言い、おれの耳の上を掻いてくれたもので、おれは嬉しくなってさっきの2倍速で尻尾を振り、アキラ殿に感謝と親愛の気持ちを示した。
「滝本さんやったか、きみ、いい子やな」
秀さんはおれがアキラ殿にしきりに尻尾を振る様子を見て、アキラ殿にぽつりとそう言うと「ほなそのホースなんとか、モリさんと一緒に買うてくるわ」と言って、おれにハーネスを装着して夕の茜が夜の藍に変わりかけている家の外に出た。透明な月が空に映る、南東から吹く風の優しい5月の夕暮れだ。
「モリさん俺なァ、長いこと兄ちゃんと仲違いしとったんや。いや、仲違いとは違うな、兄ちゃんが一世一代の勇気を振り絞って俺に打ち明けた秘密を、俺が受け入れへんかったんや、ずいぶん酷い事も言うた、兄ちゃんが怒って当然や」
(はて、ハルヒコは他人に腹を立てることの稀な、穏やかで鷹揚なニンゲンだったと記憶しているのだが)
「モリさんは覚えてるやろ、吉瀬禎治さん、兄ちゃんのパートナーやった人や。あの人を兄ちゃんの身内で最初に紹介してもろたんは俺なんや、法律上の結婚はできへんけど、連れ合いとしてずっと一緒に暮らす人やし、もし自分になんかあった時は、家族の一員として自分を見送れるように、弟の俺にパートナーの存在を知ってて欲しいって」
(そうだ、サダハルだ、ハルヒコの恋人のサダハル。とても優しい男だった、ペットショップで廃棄寸前だったおれを有り金叩いて買い取ってくれた。ハルヒコより5つ若い売れない物書き、いいやつだった、おれのことを愛してくれたし、ハルヒコのことも、とても愛していた)
おれは、秀さんに出会ってから初めて大きな声で「ワン」と吠えた。覚えている、覚えているとも。秀さんは「なんやおまえ、そんな大声がでるんやないか」と言って笑った。
「なあ、俺かて別に男同士の恋愛があかんとか、同性愛がおかしいとか、そらちょっとびっくりはしたけどやな、そんな風に思てる訳ではなかったんや。それやのに、兄ちゃんに吉瀬禎治ていう男が自分のパートナーなんやて言われた時、気色悪いこと言うなて兄ちゃんに言うてしもたんや、そんなん俺は認めへんぞって。あん時の兄ちゃんの哀しそうな顔、俺一生忘れられへんわ」
(後悔しているのだな、でもそれは秀さんの本心ではなかったのだろう?)
「勿論、ホンマに兄ちゃんを気持ち悪いやなんて思った訳ではないねん、禎治さんかてええ人なんやて顔見てすぐにわかった。まあ…今思えばあれは、アレやな…」
(アレ?アレとはなんだ?秀さん)
「嫉妬てヤツや」
(ほう)
「おれはあん時もういい年のオッサンやったのに、禎治さんに兄ちゃんを取られてしもたみたいな気持ちになったんや、アホやな、いや知ってたけどな」
(そんな風に自身を卑下するのはよくないな、秀さん)
秀さんの顔をふいに見上げると、秀さんの瞳の上では涙が表面張力を起こしかけていた。そうだ、秀さんも大切な家族を亡くしたばかりなのだ、哀しみがそこに発生したまま停滞しているのだ。おれは秀さんの手をぺろりと舐めた。
(秀さん、おれの主人は生涯ハルヒコただひとりだが、家族はひとりに限定されないはずだ、同性同士も夫婦になれるし、犬と人も家族と成り得る。であればおれは秀さんの勧めに従って秀さんの家族になろうではないか、秀さん元気を出せ、ハルヒコは聡い男だ、何もかもわかっていたさ)
秀さんはおれの頭を撫で、黙って頷いた。秀さん、おれの言ったことが分かったのか。
「帰ろか、モリさん」
(そうだな、帰ろう)
あたりは薄暗く、空には冴え冴えと白い月が出ていた。世界とは美しいものだな、ハルヒコを欠いてはいてもやはり美しいものだ。秀さん、帰ろう、おれの新しい我が家には、秀さんの妻と娘と、そしてもうひとりの、秀さんの新しい娘が待っている。
サポートありがとうございます。頂いたサポートは今後の創作のために使わせていただきます。文学フリマに出るのが夢です!
