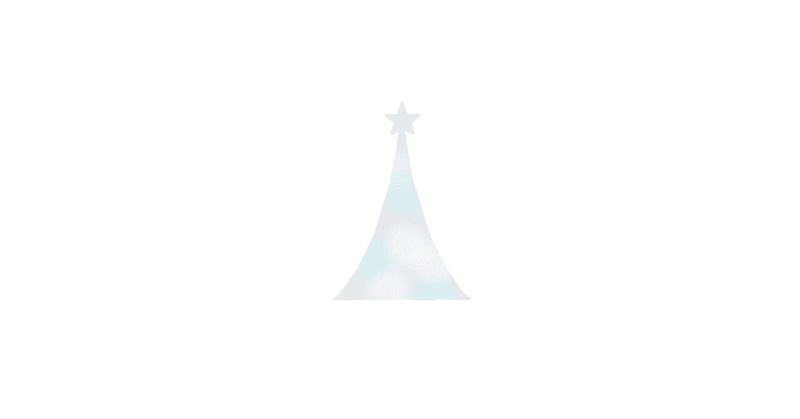
初恋がほんとうに終わった日
奇跡と運命を両方合わせた言葉ってあるだろうか。そんな言葉があるのかは分からない。でも私は奇跡と運命を合わせたような経験をしたことがある。奇跡と運命が同時に私の目の前に現れた日が私の人生でたった一度だけある。
ただそれは私に朧げな奇跡かつ運命をみせて、スパークリングワインの泡のようにあっという間に消えていった。
あの時、私はあなたに何を言えば奇跡かつ運命を、あなたと私の未来に変えられたのだろう。
奇跡かつ運命を感じた日に、私は何をあなたに伝えれば良かったのかとクリスマスがくるたびに思う。
私があなたに出会ったのはとある地方都市の中学校だった。
あなたとは中学2年生で同じクラスになり、10月という中途半端な時期に、担任の単なる気まぐれにより行われた席替えで、たまたま隣の席になった。
その時まであなたのことはほとんどよく知らなかった。
でも隣の席になれば、いろいろと気がつくことがある。ある日、私はあなたの筆箱の裏にブランキージェットシティのステッカーが貼ってあることを発見した。
ブランキージェットシティは当時、すごく売れているわけではないもののかっこいいバンドだった。
私はブランキージェットシティーのボーカル・ギターの浅井健一さんに憧れていた。
中学生の当時は奥手で、女子に声をかけるのは苦手だったが、この時はブランキージェットシティの話ができるかもという好奇心が勝った。「◯◯さん、ブランキージェットシティ好きなの?」とおもいきって私はあなたに話しかけてみた。
あなたはちょっと驚いたようだったが「うん、◯◯くんもブランキージェットシティ聴いてる?」と答えてくれた。
この時の胸の奥からくるじわっと広がる喜びは今でも覚えている。あなたとなら分かり合えるかもしれないという期待感。
あなたとブランキージェットシティのことをちょっとずつ教室で話すようになった。どの曲のどのフレーズが好きかなどといった他愛もない話だったが、まさか同じクラスの人とブランキージェットシティの話ができると思わなかったから嬉しかった。
当時、私の通う田舎の中学校ではブランキージェットシティのことをよく知っている生徒はほとんどいなかったように思う。
私たちだけが共有している秘密の話みたいな感じで、とても楽しく話ができた。
ただ、私が通っていた中学校は男女が教室内で話すのはなんとなく照れ臭く、からかいの対象となるような雰囲気があった。
ある時、クラスの派手なグループの人たちにあなたと私が仲がいいということをだいぶからかわれた。
私はそれについて派手なグループの人たちにやり返せるほど強くはなく、あなたを守れなかった。
あなたはじっと下を向いてからかいに耐えていた。
これでもうあなたとブランキージェットシティのことを話すこともできない。
派手なグループの人に対して、言い返せなかった私にあなたは幻滅しただろうなと私は落胆し、自分の弱さに失望した。
でもあなたはその日の放課後、派手なグループの人たちがいないところで「明日、7時40分に体育館裏のけやきの木の下に来れる?もっと話したいから」とこっそり誘ってくれた。
嬉しかった。
わざわざ時間を作ってまで、私と話したいと思ってくれている。そんな気持ちが分かって、心が躍るようだった。
次の日は緊張しつつ体育館裏のけやきの木の下に行った。
中学校の敷地に生えている木には、ご丁寧に一つずつ木の名前の看板がかけられていたので体育館裏のけやきと言われたらすぐ分かる。
親には係活動があるからと、小さな嘘をついていつもより早く出かけた。
私はけやきの下に7時30分くらいについた。
あなたはまだいなくて、あなたが来るまでの時間はとても長く感じた。
7時40分ちょうどにあなたが「おはよ」って言って微笑んでくれた顔は今でも鮮明に覚えている。身体がふわっと浮くような気持ちがしたことも。
待っていた10分間は長かったが、ブランキージェットシティについて話していられる時間はあっという間に過ぎようとしていた。
他の生徒たちが登校してきていて、二人きりで話しているところを誰かに見られてしまうかもれないから。
でもこの時間を失うのは惜しすぎる。今の歳になってもこれほど勇気を出したことはないが、この時の私は「もし良かったら明日も同じ時間にここで会いたいな」と言えた。
あなたは「うん」と答えてくれた。全世界を祝福するような微笑みとともに。
それ以来けやきの木の下で毎朝話すことは、あなたと私の秘密の日常となった。
毎日、あなたと7時40分にけやきの木の下で待ち合わせておしゃべりをするようになった。
あなたとはたくさんの話をした。ブランキージェットシティのことはもちろん、クラスメート、先生、将来の夢の話。毎日10分程度の時間だったが、その頃の私はけやきの木の下のあなたとの時間が喜びの全てだった。
あなたと毎日一緒に話して、可愛らしいあなたのことがごく自然ななりゆきで好きになっていった。
そしてあなたもきっと私といる時間が大切だと思ってくれているのだと実感することもできていて満たされた気持ちでいた。
しかし幸せは儚い。幸せのすぐ先には絶望が姿を隠して待ち構えている。
そしてそれは当然のような顔をして、あなたと私の前にもやってきた。
11月末のある日、あなたは二学期いっぱいで転校することになってしまったと私に告げた。
けやきの木の下で話す日々がこれからも続くと信じて疑いもしなかった私には絶望的すぎる事実だった。
それでも転校までの残った毎日を大切にしようと私たちは毎朝どうでもいい話を熱心にした。
あなたと私は、恥ずかしくてお互いの好意を素直に言葉で伝え合うことはできなかった。
その代わりあなたと私は、とりとめもない話をたくさんすることが、相手に好きだという気持ちを表すことになると信じて夢中で話をした。
最後の日はあっけないほどの早さでやってきた。二学期の終業式はクリスマスイブの前々日だった。
あなたと私はその日が最後だということは痛いほど分かっていたが、いつも通り普通に話をした。先生や友達のモノマネをしたり、誰かの失敗話をして笑い合ったりした。
まるでこの日々は明日以降もずっと続くようなテンションで話を続けた。きっとそうしなければ、悲しみが受け止めきれなかったから。
ただその日のあなたは勇気と好意を私に直接的な表現で示してくれた。
それは私からするべきことだったのかもしれないが、あなたは私にしてくれた。
そろそろ話をやめて教室に向かおうかというところで、あなたは目を閉じて顔を私に近づけた。
それは私のような鈍感な男子でも、キスをしてくれようとしているのだと気付く仕草だ。
私も目を閉じて顔をあなたに近づけた。
あなたと私のはじめてのキスは、サイダーのようでもレモンの味でもなかった。
前歯が、がちっと当たってしまったから。二人ともキスのやり方が分からなくて、唇が触れるというより前歯が当たり、切なくもなんともないはじめてのキスになった。
あなたと私は二人のキスの不器用さにちょっと笑って、あなたは少しだけ涙を流してバイバイと言って教室に向かった。
当時の私が住んでいた地域は携帯電話が中学生には普及していなくて、高校生がやっとポケベルを持っているような時代だった。
だから私は引っ越したあなたと簡単に連絡を取ることができなかった。
あなたの新しい住所は教えてもらったものの、手紙を書くことはなんか恥ずかしく、いつしかあなたとの関係は途切れて、私の大切な思い出して心の奥にしまわれた。
しかし、中学生時代の別れのちょうど10年後、あなたと奇跡かつ運命と言って大袈裟でないような再会があった。
私は上京して大学に入り、一年留年した後、大学院に入学した。大学院に入ったばかりのころにコンビニでバイトをしていて、クリスマスイブの日、人が足らないからとパワハラ気質の店長に「お前はどうせ彼女もいないんだからイブの日に入ってくれ」と言われていた。
悔しいが店長の言う通り彼女はいないし、クリスマスイブの楽しい予定もないので、サンタの帽子を被らされて浮かない気持ちで店長の言われるままにバイトをすることにした。
その日はクリスマスイブだったからか、それほど忙しくもなく、家にいて暇を持て余すより良かったと考えながらのんびり働いていた。
しかしある瞬間レジに入った時、奇跡と運命が一度にやってきた。
あなたが目の前にいた。
そこには会計を待つあなたがいた。
あなたが東京にいることすら想像もしていなかった。それがまさかバイト先で出会うなんて。
「あと1時間でバイト終わるから待ってて欲しい」私は10年ぶりの再会に興奮して思わず声をかけてしまった。
あなたも私に気が付いて「じゃあそこのデニーズにいる」と言ってくれた。
心ここにあらずという感じで、1時間なんとか働き、私は着替えてあなたが待つデニーズへと急いだ。もっといい服を着てくれば良かったと後悔したことを覚えている。
デニーズに着き、あなたを探して席に座ると10年という会えない時間はなかったようにあなたとの話は弾んだ。まるでデニーズがあのけやきの木の下のように思えたほど。
あの頃どんな話を二人でしていたかということ、ブランキージェットシティは解散したけどまだ浅井健一さんはかっこいいままなこと。
時が戻ったかのようにあなたと私は夢中になって話した。
デニーズを出て、お酒が飲めるお店に入り、あなたと私はスパークリングワインをボトルで一本オーダーして再会に乾杯をした。
あの時にあなたと飲んだスパークリングワインより美味しいお酒を私は今でも知らない。
アルコールが入り、さらに気持ちがほどけて思い出話で盛り上がった。先生や同級生の面白かった話、中学生の頃に地元であったこと。
ただそれが当然のルールであるかの如く、あなたは現在の話をしないので、私も今自分がどのような生活をしてるかということは話さなかったし、正確に言うなら話す雰囲気にあなたはしなかった。
国語の先生がいつもしていたつまらないギャグ話をしている最中に、スパークリングワインのボトルが空になった。
私は10年ぶりの勇気を振り絞って「パワハラ店長に残り物のクリスマスケーキを無理やり買わされて、一人じゃ食べきれなさそうなんだよ。うちで一緒に食べない?」と言ってみた。
あなたのその時の顔は忘れられない。一瞬嬉しそうになり、すぐに悲しそうになった。そしてしばらく考えてこう言った。
「思い出はきれいなままにしておこう」
店を出るとあなたはまた、どんな鈍感な男でもキスをしようとしてくれていると分かるような仕草で、私に顔を近づけてきてくれた。
今回は歯は当たらなかったし、あなたとの二度目で最後のキスはスパークリングワインの香りがした。
でもその香りはすぐに消えた。泡のように。
あなたはまたバイバイと言っていなくなった。
連絡先も交換せずに。
もう二度と私のバイト先に来ないつもりだということも、なんとなく分かった。
この日、私の初恋はほんとうに終わり、私は一人きりの自分の部屋に戻りちょっと笑って、そのあとすごく泣いた。
こんな運命かつ奇跡の日に私はどうすれば良かったのか今でもまだ分からないし、今後もし分かる日がきたとしてもあなたはもう私のそばにはいない。
でもあなたが残した、あなたがきれいなままにしておいてくれた思い出は、クリスマスが近づくたびに蘇る。
今年もあなたはきっと幸せなクリスマスむかえていると私は信じている。
私はあなたと離れてクリスマスを過ごしても、あなたとのきれいな思い出は決して忘れない。
思い出のあなたはいつもけやきの木の下で笑っている。これからもずっと。ずっと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
