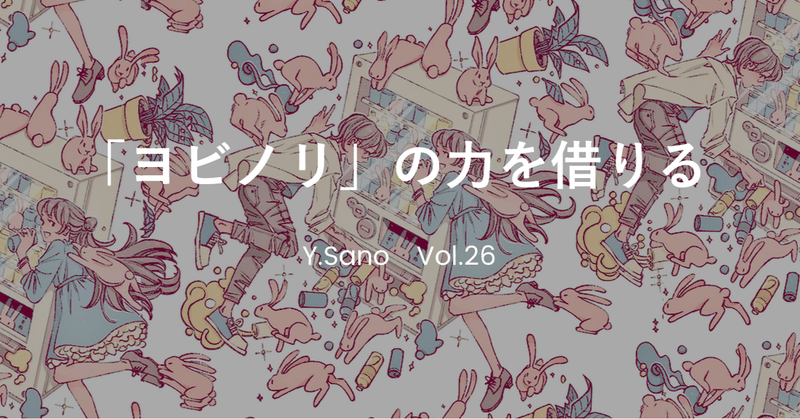
「ヨビノリ」の力を借りる
ヨビノリってすごい!という話と,教授の立ち位置的な話です.
現在,大学生の私が受講している講義に,工業数学というものがある.最小二乗法に始まり,フーリエ解析,ウェーブレットまでを対象として進めていくものなのだが,最近心が折れそうである.
第一に,とっかかりが付きにくい.この言葉が何を意味するのか,どのような手法なのか,そして何に役立つのか...恥ずかしながら,私は理系を名乗れないほどに数理の出来が悪いため,このあたりの知識などまっさらである.
そして第二に挙げるのが,この講義を担当する教授の分かりにくさ.
本当に,説明が分かりにくい.最初から最後まで,結局何を言いたかったのか不明なままに講義が終わってしまう.教室を見渡せば,机に突っ伏している人がかなりの数で見受けられる.弊学科は居眠りする人の少ないイメージがあったが,ここだけ例外的にみんなダウンしていく.
まるで教授が呪文を唱えるかのように話をするからだろう.いやもしかしたら,本当に催眠術をしているのかもしれない.ラリホーマ.
大学の講義に質を求めるのは間違っているのだろうか
当然ではあるが,教授はあくまでも研究職であって,教えることに必ずしも長けているわけではない.日夜問わず研究に勤しんでおられる方々が,授業の準備といった手間のかかる作業に時間をかけられるはずがなく...
しかも,本業に関係のない話をするとなれば,教授のモチベもダダ下がりであろう.講義資料やテストの作成,出席・課題の確認といった作業は最低限にとどめるのが現状だと思う.
「ただでさえ手間がかかるものに,心血注いでやってらんないよ!」
前期の講義で,ある教授がつぶやいていたのを思い出す.
よって,講義に質を求めるのはやや無理がある話だといえる...だろうか?私たちはなぜ大学に行くのか.そうだ,学ぶためだ.入学した学科に沿った授業を聞き,ノートをとり,教養を広げ,深めていく.この一連の流れをしたいから入ったのだ.
大学に入学するまでの理系知識は,それなりにだがやってきているつもりはある.そんな悩みを解決してくれるヒーロー,ひいてはアンパンマンみたいな存在はいないものか...
改めて気づかされる,ヨビノリの授業の分かりやすさ
かつて,大学受験の時にヨビノリのチャンネルにはお世話になった.高校数学(特に微積分学)で行き詰ったところがあったとき,この方の解説動画を見て疑問が解消したり,さらに理解が深まったことがあった.
(自身の成績は無視するにしても,)理系科目に対する苦手意識がさほどないのは,この方のおかげだと思っている.
そんな日々をふと思い出し,YouTubeで「ヨビノリ フーリエ解析」と調べた.おお,出てきた.そして,めっちゃ分かりやすい.一気に全5編の動画を見終えた.
自分で演習を加えつつ,入門的な部分への理解をしていく.ようやく入り口に立てたというか,この分野で何をすれば良いのかが分かった気がする.大学の講義でとっていた遅れをとりもどすことができた.
教授に共感する気持ちと,それでもなお湧く不満.
1年のころはそれこそ専門性の低い基礎科目ばかりで,それらの講義ですら分かりづらかったものだから不満が勝っていた.最近は,専門的な分野に足を突っ込むにつれて生き生きとした教授が増えてきたためか,共感するケースが多い.きっと,専門分野を語ることなら,理解も進んでいることなので要領よく教鞭をとることができるのだろう.
インターネットの発達するこの時代,教育のスペシャリストがコンテンツを提供しているのであれば,それを最大限に活用していくのが私たちの勉強法の1つであり,これを自主的に取り組めるのが,私たちに求められるリサーチ力の一角なのかもしれない.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
