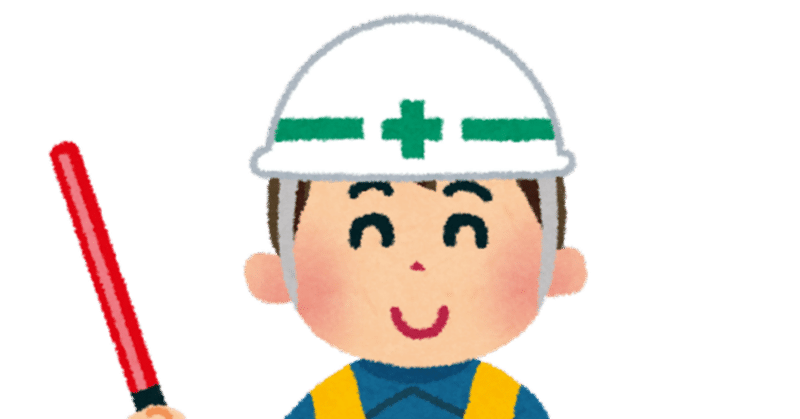
警備員という仕事
まえがき
これは私が2023年夏頃から約4ヶ月に渡って務めた警備員の仕事に関するあれこれをまとめた記事である。
僅か4ヶ月の職歴で経験者としての語り口をとるのが烏滸がましいことは百も承知だが、警備員は市街地では毎日どこかしらで見かけるほど生活に身近な仕事である反面、その実態や内情に関しては知らない人が大半であろうから、この記事が少しでも彼らの仕事を知る助けになることを願って執筆する次第である。
なお、内容が多岐に渡ることもあり、全てを順番に読み進めずとも、目次を参考にしながらご自身の興味に合わせて読んでいただければ問題ない。
警備員という仕事 〜仕事内容編〜
まず初めにお断りを申し上げたいのだが、一口に警備員と言ってもその職務内容は様々である。警備業法では警備業務を第1号〜第4号の4つに分類しているが、大分類の中だけでも、施設において不審者の侵入などを防いだり(第1号)、現金など貴重品の輸送を担ったり(第3号)、要人を取り囲み彼らを襲撃から守ったり(第4号)と様々に分けられる。
私が務めたのはその第2号である雑踏警備業務、特に公道上における交通誘導警備である。私が見聞き経験したのは、数多ある警備員の仕事のうちほんの一部に過ぎない。
交通誘導警備は、工事等によって通常より通行しにくくなったり安全性が劣ったりしている道路において、車両や歩行者などへの影響をなるべく小さくし、安全かつ円滑な交通を実現することが職務である。
たとえば道路工事で道の半分が通行不能になっている時、片側交互通行(警備員は専らこれを片交:カタコウと略して呼ぶ)によって車の発進を制御したり、歩行者や自転車に注意を呼びかけたり、これが狭い道の場合は通行止めとして迂回してもらったりするわけだ。工事は基本的に空中に架設された電線や地下の配管、道路の舗装などに手を加えるもので、新しい道路の建設のような大掛かりな工事に関わることはなかった。そのため現場は日によって変わり、ただ立っているだけの時もあれば、警備員同士が連携しながら懸命に交通を捌く時もある。
警備員という仕事 〜ルール編〜
警備員の仕事は警備業法という法律によって細かく規定されているが、その中で興味深い規定を取り上げていく。また、法的拘束力を持つものに限らず、警備員を取り巻く様々な規則を取り上げていく。
○警備員は警備業務において、特別な権限を何ら持っていない
これは警備業務実施の基本原則であり、新任研修の際には何よりも口酸っぱく言われた。警備員は交通の安全と円滑のための判断や注意喚起を担っているが、あくまで警備員からの指図は「お願い」にすぎない(勿論無視しても法には反しない)。いかにも何か権限のありそうな風貌をしているだけで、実態はただそこら辺のおじさんが道ゆく車の邪魔をしているのと何ら変わりない。
ちなみに、私が務めたのは交通誘導の仕事だが、警察官などが強制力・法的拘束力をもって行うものは交通整理と呼ばれ、明確に区別されている。
○警備員になろうとする者は20時間の、現職の警備員は1年に1回10時間の研修を受けなければならない
警備員は一定の知識・技能がないと、自身や周囲を危険に晒す恐れのある仕事である。そのため、警備員になる前に新任研修として20時間、またその後も基本に立ち返る機会としてだろうか、1年に1回10時間の現任研修受講が法律で定められている。法定研修が定められた仕事は他にも多々あるが、警備員のような(あまり専門的なスキルが必要とされない)仕事において、現任者に対する研修を必須とするのは特筆すべき点と呼んでもよいのではないか。他に似た例があったらごめんなさい。
○警備員の制服は警察官・海上保安官などと明確に区別できるものでなくてはならない
上述の通り警備員は何ら特別な権限を持っていないため、権限のある人間を装うことも禁止されている。制服の色や形は公安委員会に届け出る必要がある。
私は正直警察官と見分けが付きづらい警備員を見かけたことが何度もあるが、公安委員会の届出を経て営業しているということは実質的に権力者のお墨付きを意味するから、彼らも堂々と着用してよいのだ。
装備品に関しても、「護身用具」に関して届出が求められている。ただ、私が貸与されていた装備品の中に届出が必要そうな護身用具はひとつも無い気がする…
○欠格事由
警備員になってはならない人間というのが定められている。18歳未満の未成年者の他は、他の業種にもありがちな欠格事由(例:暴力団員、刑の執行終了後5年以内の者、破産者など)である。特別なスキルが必要ない職であるがゆえ、出所者などの雇用の受け皿としての機能も期待できそうに思えるが、ここは信用が鍵を握る業界らしくしっかりしている。
○30分前集合
これは法律でも何でもないのだが、警備の仕事は始業の30分前に集合することになっている。始業時刻は大抵9時であるため、8時半には集合場所(大抵は工事箇所付近のコンビニ)に着かなくてはならない。ただ、工事業者に関しては、資機材を運んでくることと道路使用許可の時刻の都合があり(つまり、始業前には工事箇所に車を停められないが、他の場所に車を置くとその場所を占拠してしまう)、集合場所に来るのはギリギリが望ましい。渋滞に嵌ったのか、始業時刻になって工事業者が到着していないことも偶にある。毎日30分貴重な時間を無駄にしている気がしてならないが、警備業者から見れば工事業者は大切なお客様であり、万が一お客様を待たせることが無いように…との決まりなのだろうか?
おかげで朝5時台に起きなくてはならない日も多々あった。
他にも興味深いルールは多々あるのだが、紹介しているとキリがないのでこの辺で止めさせていただく。
警備員という仕事 〜社会編〜
警備員、中でも特に交通誘導警備というのは、明らかに「国家権力に守られた仕事」である。このカラクリを簡単に説明しよう。
まず、工事業者が道路で工事をするには、先に名前だけ触れた「道路使用許可」というものが必要になる。本来道路は交通の用に供する場所であり、工事をする場所ではないからだ。
この道路使用許可には「許可条件」が付き、道路使用の際には示された条件を守らなくてはならないのだが、その中には必ず「警備員○人以上」という条件が付される。これが警備員の雇用を生んでいるのだ。
学もスキルも本当に何もない人間でも社会の中で生きていけるような手段を国家権力が用意する(しかも電気・通信工事では民間の資金で!)というのは、かなり巧みな治安対策にも見えてくる。
また、街中で仕事をするということは当然、周辺住民や通行人との関わりも存在する。
あなたは、道路上で働く警備員を見かけて何を思うだろうか。実際のところ、私は(あくまで警備員の中では)比較的真面目に誘導や声掛けを行っていたこともあり、夏の暑い日などは地域住民の方から優しい声をかけられることもあった。
しかし、やはり私が経験した他の仕事に比べると、警備員に対する風当たりは強いように感じる。工事現場には大抵「ご迷惑をおかけします」のような看板が立っていることが多いが、交互通行で渋滞しているとか、家の付近での工事で出入りに苦労するとかになれば、イライラしてしまうのが人間というものなのだろう。警備員はその「工事に対する苛立ち」を一手に引き受ける役目でもある。
誰が悪いでもなく、それどころかそこの住民の利便のためであるにも関わらず、「申し訳ございません」と頭を下げて工事をするのは、どうも腑に落ちないものがあった。
警備員という仕事 〜内情編〜
警備業は決して優秀な人や真面目な人が集まる業界ではない。正社員として長年働き、定年を迎えたのちに警備に行き着いたような人はまだマシな方だが、若くから職を転々としているような人は、ゴミや吸い殻をポイ捨てしたり、交通ルールを守らなかったりというのも珍しくない。
ひとつ私の印象に残っているのは、そうした「倫理観のない人達」を見てみた時、彼らはルールを好きに破って勝手な行動をするのではなく、守るルールと守らないルールがあり、その線引きが皆似ているということだ。あるルールを誰かが破っているのを目撃すれば、そのルールを破ることの抵抗感は小さくなると考えられるが、今はその状態を長年繰り返して生まれたある種の均衡状態なのかもしれない。
警備員という仕事 〜学んだこと〜
私は警備員として働いたことで、得たものが大きく2つある。
ひとつはあらゆる経験に共通することだが、世界の解像度を上げられたことだ。自分と異なる人間に多く触れることで得る驚きや感銘などは、他者への理解の種、そして豊かな人生の種になると思っている。往復の車移動で人と話す機会が多くあることもあってか、広がった世界の幅は、1週間の旅行に比べても大きかったと感じている。
もうひとつは、人生における挑戦意欲を高められたことだ。
私は「やってみたいこと」がたくさんあるが、その中には失敗した場合にリスクを負うものもある。
私はネガティブで現実派で論理的だから、失敗した時に飯が食えなくなると思うと、やってみたいと思いつつなかなか踏み出せない事ばかりである。しかし、何かに挑戦し、失敗して借金だけが残り、本当に何もない何もできない人間になってしまったとしても、警備員という形で、社会の一員として誰かに貢献する道が残されていることが分かった。
辛いことがあると視野が狭くなり、「自分なんて…」という考えに陥りがちだが、「何もできない自分」でも社会に居場所を作れるのだという実感は今後の生きる上での下支えになると思っている。
あとがき(という名のポエム)
あらゆるものには多面性がある。精神の下支えができたことは素晴らしいのだが、違う視点から見れば、自分を追い込まなくても良い、頑張らなくても良い理由ができたともいえる。この仕事を卒業ギリギリまで続けず退職することに決めた理由は、やはり来春からビジネスの世界に飛び込んでいく人間であるという自覚を忘れないためだ。人に対してはもっと友好的にならないといけないし、適切な礼儀作法を備え、素直にならないといけない。
将来の自分が、合格最低点でないように、日々具体的な行動を重ね、成長しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
