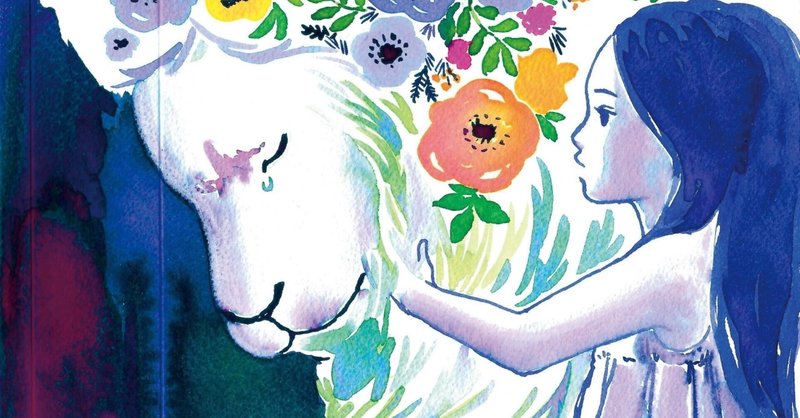
不登校になっちゃった子どもたちのへっとへとな伴走者さんへ
あくまでもさらっと明るい感じで妹が発表したのを覚えています。
夏休みの盆パーティーの後片付けが終わり、子ども達はリビングでゲーム、私達姉妹3人はリビングの横の和室で寝そべりながら話していました。その時に妹が、ふと、なんとなく言っちゃった様子で発表したのです。
「炭治郎くん(仮名)、学校に行かなくなりました!」
「へ?!」
賑やかに喋っていた私達は一瞬で静かになりました。
面白おかしく話す姉達の会話の中にいて、妹はどんな気持ちでいたのでしょう。
最後にゴールデンウイークに会って以来、妹と息子の炭治郎がどのように過ごしてきたのか知りません。「言えなかった」のかもしれません。
「ごめんね。知らなくて。一人で抱えてたんだね。今日まで長かったね」と私達から言われると、妹の目から、初めてポロポロと涙が落ちました。
こちらの企画に参加しています
JOYさん発の不登校さんへ向けた温かい企画です。
私は遠い過去に自分が当事者になりかけたことがあります。そして、不登校少年の母である妹がいます。彼女がもがいてもがいてトライandエラーしているのを見ていて、思うことがあり、筆をとりました。私は、学校をお休みしている少年少女のおかあさんにエールをおくりたいと思っています。
コンテストの締め切りには間に合っていないので、参加だけさせてください。
今回の記事は、当事者の妹に聞き取りをして、『なりきって』書きます。今回に限り『私=妹』です。お休みしているのは中学生です。
理解が浅いところや表現が拙い所があるかもしれません。
勉強不足をお許しください。
0.不登校を段階に分けて捉えてみよう
「うぉぉおおおー!ふんぬーーーーー!」
と大音量で叫びながら、雷様が背負っているような太鼓を叩きまくる。
ドコドコドコドコドコドコドコドコ
ドコドコドコドコドコドコドコドコ
脳内で。
学校へ行かない状態、親にとっては突然にはじまるし、あしたにも行くような気がするし、自分の中に「あぁコレが!」と受け入れられなくて。
赤い線がある。学校を否が応にも意識してしまう時間帯。
息子にも。
親である私にも。
最初は毎日の登校時間。
次は毎週の月曜日の朝。
長期休暇の終わった新学期。
学年が変わった新学期。
でも、行けるようにならなかった。
見通しが立たない状況は、苦しい。暗闇の中でもがくような。酸素のない水の中で息ができないような。
心理学では受け入れられない告知や事実を突きつけられた時、人は「拒絶→諦め→受け入れ」のプロセスを経ていくそうだ。学校に行けない子供たちも、いくつかのプロセスを経て、段々と安定した状態になっていくと考えられる。
お子さんがそのプロセスのどの段階にいるのかに分けて、親御さんに必要なことを考えてみようと思った。子どもたちが皆、同じ経過をたどるわけではない。プロセスがスキップしたり、後戻りしたりすることもありえる。
このプロセスの時はきっと、おかあさんはこう思ってるよね…、と寄り添ってみたい。並走している親だって、へこたれているんだもん。
1.不登校はじまり期 〜気持ちを吐き出そう
お子さん本人も「行かねばならない」と思っているけれど心と体がついていかない状況です。お子さんのなかで何かが起こっていて、やっとお母さんに「休みたい」と言えるようになったのです。学校へは行ったり行かなかったりしながら、徐々に休みの日が多くなっていく時期です。
「行かなくてもいいよ」
「大丈夫だよ」
黙ってそっとしてくれる感じ。それらがお子さんの心に安心をもたらすことでしょう。お子さんを責め、理由を問いただしたり、無理やり学校へ連れて行くことはNGとされています。
↑一般論
分かってる。しかしながら、私には、これが辛い。息子を支え、いつもニコニコして余裕の対処をせねばならないと思えば思うほど苦しくなる!
誰か、誰か、気持ちを吐き出させて。
どす黒いこの胸の内をくまなく放出してしまいたい。そして改めて強い心で、息子と対峙させて欲しい。
そんな時、助けを求める先の見極めはとても大事である。親、兄弟姉妹、友人、クラスメイトのママ友、同僚、学校の担任の先生、学年主任、教頭、校長、スクールカウンセラー・・・。私の周りにはたくさんの人がいるけれど、自分の息苦しい肺の中にどうやったら楽に酸素が行き渡るようになるのか、人を選んだ。
ただただ気持ちを聞いて欲しい時、
情報を集めたい時、
迷っていることにアドバイスがほしい時、
に分けて、助けを求めた。
大事なのは、合わない人からは離れること。
それが先生であっても。スクールカウンセラーであっても。
「生きてるだけでいいじゃない。」と言った人がいた。「学校行かなくても大丈夫だよ。大学行けるよ。」と、すごく未来のことを言われて慰められたこともあった。
そうじゃないんだ。
いま、今、行かない子どもがいてそれを受け入れられない、どう接したらいいのかわからない。
そう思っていた。
一人で考え込んでいるよりも、話していると、頭が整理されて新しい切り口が見えたりする。息子を見ていてどす黒い気持ちが湧いてきても、打ち消さず、そのままでいられる人を探した。
・・・そして、ハッとした。
息子だってつらくて苦しくて、もがいている。傷だらけそのままの姿でいられる家と家族を求めている。
そう気がついた。
2.ぐったり期 〜おかあさんにも避難場所を
お子さんが枯渇したエネルギーを補充している時期です。
ずっと頑張ってきて頑張りすぎてエネルギーを使い切ってしまっているので、休息が必要なのです。動きたくても動けずただただ眠っています。そして部屋を真っ暗にして閉じこもるタイプのお子さんもいます。そんなになるまで学校で頑張ってきたのです。そして、行けない現実を受け止めている真っ最中です。こもる自分と向き合っています。本人も自分にショックを受けているので、そっとしておきます。なにもしないという応援です。
↑一般論
この時期はとにかく動かない、風呂に入らない、部屋に入らせてくれないから掃除できないという、母としての葛藤が渦巻いていた。
カタリとも音をさせず、カーテンも閉めて薄暗い部屋でじっとしている息子を思う。息子の傷ついた心が癒え、土が耕され、水が入っていく。その途上にあるんだろう。そして、やる気の芽が出てくるまでには時間がかかるんだろう。
でも、その状態になるのに、どれだけの夜を明かせば良いのか。どれだけ寝返りをうって、ため息をついて。私も息子も。
私は専業主婦なので、24時間、四六時中息子と顔を突き合わせなければならない。息子のコンディションが良い時も悪い時も。私のコンディションが良い時も悪い時も。
閉塞感ったらない。
だから、息子から物理的に離れて落ち着ける場所を探した。家から出て私がカウンセリングを受けたり、支援組織(親の会)と繋がりを持ったのもこの時期だった。自分と息子は特殊なケースではないし、他にも同じ悩みを持つ保護者さんがいると感じることで力が湧くこともあった。
⒊充電完了期 〜ゲームでもいいんだよ
元気が回復しエネルギーが溜まってきた段階では、家事をルーティンでやらせてみて、徐々にやり遂げる体験や達成感を積み重ねて行く時期です。
そして充電が完了すると、ついには外に目が向き始めます。「ひまだ」という言葉が出てきたら、アルバイトやスポーツなどに参加する提案をして、外の世界につなげましょう。
↑一般論
確かに、息子にはある時期を過ぎると活気が戻ってきた。部屋から笑い声が聞こえてくる。オンラインゲームにはまったのだ。ずっとやっている。
ここで重要なのは、何かをしたいと言った時の芽を摘まないことだ。それが例えゲームでも。バーチャルな場所でお友達と待ち合わせしている。お友達と話している。私は、ボソボソという話し声と笑い声を聞いた時、少し涙が滲んだ。
社会との細い繋がりができた瞬間だった。
その後、そのゲーム友に誘われて、同学年の鉄男子数名で鈍行電車だけを乗り継いで他県の目的地まで行くという企画を実行していた。少しづつ事態が好転して行くように思った。
4.活動再開期 〜ゴールはそれぞれ
この段階になると、不定期ですが学校に行き始めるようになります。遅刻早退をし、欠席を繰り返して徐々に復帰していきます。
↑一般論
結論からいうと、息子は未だ、学校へ行っていない。
この春、中学を卒業する。
この一年で適応指導教室には少しだけ行くようになった。この教室は教育委員会がやっているので無料だし、行った日は出席にカウントしてもらえる。そこから家に派遣されてくる指導員さんが学習指導をしてくれることもあった。
私は思う。学校へ行き始めること、進学すること、それがゴールではないかもしれない。息子は入学して、また、行けなくなる日が来るかもしれない。
あくまでもプランAがうまくいかなかったに過ぎない。ではBで行こう。
そのプランは、私の希望やこうあるべきや世間体ではなくて、息子がやりたいことや苦しくなくて実現可能なことは何か、それが根底になければならない。
私はどれだけ世界を見せてあげられるだろうか。
どれだけ多様な価値観を見せてあげられるだろうか。
自分の人生をかけて息子にプレゼンする。
悪口を言われたときの切り抜け方
風邪をひかないコツ
どうやって素早く着替えるか
落ち込んだときの気晴らしの種類
そして、自分のあり方、どうありたいかのビジョンを常に持たせたい。
突き詰めると、子どもには、
より良く生きて欲しいし
「生まれて良かったなあ」って思って欲しい。
生きて生きて生きて欲しい。
サバイバルしていって欲しい。
切に願う。
おわりに
途中、親の感情が暴走してしまいました。
へっとへとな伴走者さんへ少しでもエールを送ることが出来ていれば幸いです。
ハトちゃん(娘)と一緒にアイス食べます🍨 それがまた書く原動力に繋がると思います。
