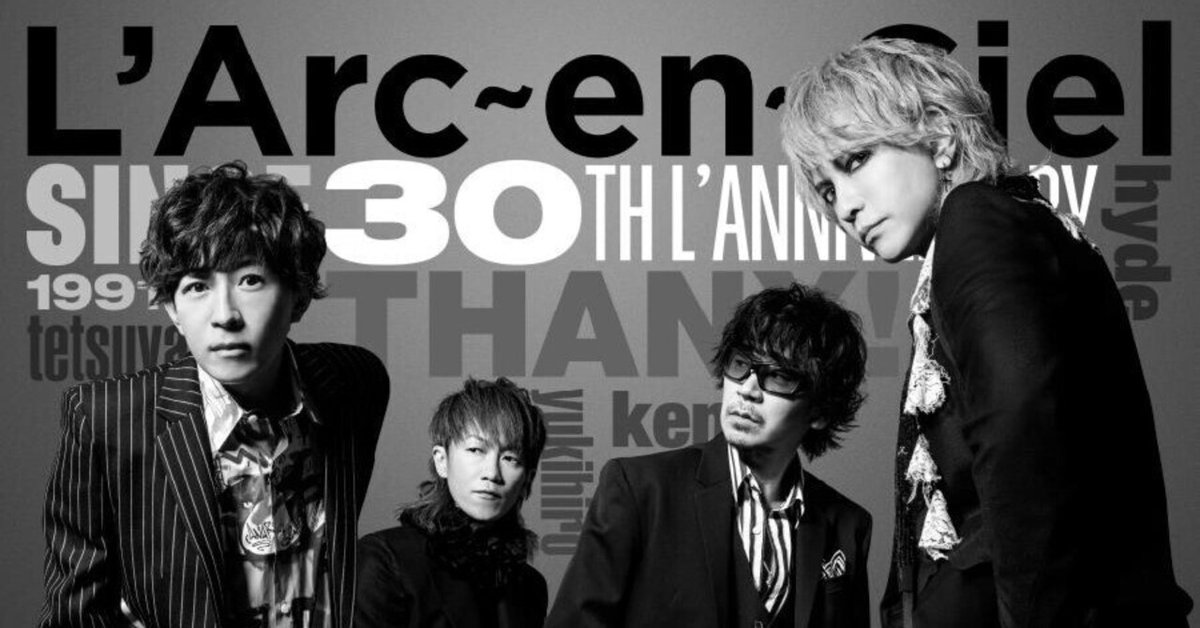
「L'Arc~en~Ciel 30th L'Anniversary LIVE 5/21」感想~果敢に孤独と戦う人へ~
後楽園駅から階段を登り、東京ドーム前に着くと、そこは雨だった。
既に人はたくさんいて、過去のツアーTシャツを着た人達が再開を喜びあったり、円陣を組んだりしていた。もちろんカジュアルな服装の人も大勢いた。

私は十七時から入場できるとの通知を受け取っていたが、「全員会場に入れる。できるだけ早めに入場して欲しい」というアナウンスが聞こえ、感染対策もあり、さっさと入る事にした。ドーム周辺はとかく人が集まりやすい。
アナウンスをしているおじさんが少しユーモラスであった。渋谷のDJポリスを思い出した。

入場すると、既に多くの人がドーム内にいた。外国の人もちらほらいた。元々日本に住んでいるのか、来日されたのか分からないが、ファン層の広さを実感した。
二階スタンド席の後方。ステージと真向い。東京ドームに来たのも久々で、巨大だがどこか低く見える天井が懐かしかった。
ステージ左右の画面に、かかっているSEの曲名、アーティスト名が載り、最後にメンバーの誰がセレクトしたのかが載った。「東京」をテーマにした洋楽が多かったが、GASTUNK、マイケル・ジャクソン、coldrain等「お!」と思う曲もかかっていた。前日に一部座席のレイアウトが変更されるという問題があったみたいが、全体を見渡すと、ほぼ客席は100%埋まっているようだった。

定刻を少し過ぎ、ライトが落ち、洗練された映像でバンドの歴史を振り返った後、長い音楽の旅が幕を開けた。
ここでは、①現場での演奏、演出の感想②三十周年という厚み③まとめ、の三つの要素で、ライブの感想を書いていきたい。(演出、セットリスト等への言及あり。またMCの内容は記憶上不正確な可能性あり。人物名は敬称略とさせて頂く)
①現場での演奏、演出の感想
演奏はもちろん素晴らしかった。曲に合った照明、映像が映し出された。ファンが抱いている曲へのイメージを最大公約数的に表現していたのでは無いか。風景や多彩なイメージは、多種多様なジャンルが盛り込まれた曲と相まって、壮大な旅行をしている気分にさせてくれた。
tetsuyaのベースのうねりや、スコーンと突き抜けるyukihiroのドラム、曲の空間を彩るkenのギターとキーボード、コーラス。音響のバランスもほぼ完璧で、ライブが進むにつれ更に改善された印象を受けた。
hydeのボーカルは、正確な演奏に対して、基本は合わせつつも、要所要所で「敢えて」逸脱し、暴れまわっていた。「いばらの涙」からは特に、感情をむき出しにして歌い上げ、コロナでの閉塞感や孤立感を打ち破る「パンク」なパワーを感じた。
hydeは年齢を重ねるとどうしても衰えるであろう声の伸び等を、難しい高音でもサラッと出せる発声法でカバーしていたと思う。それにしてもよくステージの隅から隅まで走り回りながら歌えるものだ。特に「GOOD LUCK MY WAY」で駆けながら、難しいサビが普通に歌えていた時は驚いた。
(複雑なベースラインを弾きながら走り回るtetsuyaも凄いが)
セットリストも大変良かった。工夫に工夫を重ねたのだろう。hydeは著書『THE HYDE』(①)の中で、「ライブでは三つの山を作るようにしている」と書いていたが、後でセットリストを見返し、ライブを振り返っても、山が四つも五つもあったような気がして、分からなくなった。私が見つけられてないだけで三つの山があったのかもしれないし、hyde達メンバーの考え方自体がアップデートされたのかもしれない。
一つ一つの山の中でも、盛り上がる曲、美しい曲、マイナーな曲等をバランスよく散りばめ、山の中に更に小さな緩急が作られていた。構成の小宇宙。
後半にやりそうな曲を前半にやったり、終盤でも初期のマイナー曲が演奏されたりと、徹底的に「マンネリ化」を防ぐ形で意外性を持たせつつ、後述するようなテーマ的統一性が感じられたりして、三十年間は伊達じゃないなと思った。
今回はコロナ禍でのライブでもあり、入退場にかかる厳格な衛生対策や管理はもちろんの事、ライブ中も「ハミング」以外は声を出せなかったりと、「統率された」ライブとなった。(ほぼ9割以上、ファンからも感染対策は守られていた印象だった)
コロナ禍でもツアーを積み上げてきた実績からか、バンドとファンの間で信頼関係が出来上がっており、hydeもいつも通り煽り、それに対しファンが声を出す以外の方法で応える事が確立されていた。コロナ前ならファンに振っていた箇所をhydeが歌い上げていたのも新鮮で、「Blurry Eyes」の高音サビを余裕そうに歌うhydeの実力に感動したりした。
コロナのせいもあり、「ケア」的な側面が出たライブで、hydeがMCで「演奏しなくても、ここにメンバーと皆が集まれただけで素晴らしい」と言ってtetsuyaから「演奏しないの」と突っ込まれたり、メンバーに感染者が出ず、ファンが厳しい感染対策を、家に出てライブに参加し、そして帰宅するまで徹底している事に感謝してねぎらったりと、要所要所で優しさが目立った。
演出でも、曲間で長めの「休憩時間」が何回か取られ、トイレ休憩や水分補給、体調管理がしやすかったのでは無いか。(長丁場のライブは参戦するだけでも体力、気持ち面で結構パワーを使う)
もちろん「ケア」的側面が、ライブの質の「手抜き」に繋がる事は一切無い。逆に「ケア」が新たな演出を創造する。突如ステージ脇から登場した宇宙船「ark号」。皆が座ったり休憩している間にドーム上をゆっくり飛び、最後に後方のもう一つのステージ横に着陸し、メンバーが登場するというサプライズが仕掛けられる。
また、「wave game」では、画面に映し出される座席表の上を動く矢印よりも速く、観客が立ち上がってウェーブし、ゴールしなければならず、矢印に抜かれたり追いついたりしながら、自分がウェーブする番を待ち、ファン同士の一体性を感じられた。
ここまで練り込まれ、緻密かつ大胆なライブが何故できるのか、その背景を考えるべく、三十年間の活動が生み出したものに迫って行きたい。
②三十周年という厚み
・アングラツアーができるバンド
三十年間の活動は多くの曲を生み出した。大ヒットした曲もあればコアな曲もあり、演出や照明、前曲から、「次何の曲演奏するかな」と予想するのは楽しい。想像のゲームが当たるか外れるかは、大きな問題じゃない。もし当たったら、じんわりと涙が出てしまうが。
前段でコアな曲と書いたが、L'Arc-en-Cielの大きな魅力の一つに、「アンダーグラウンドをパックツアーみたいに見せてくれる」事がある。
演出も、凝っているが、凝り過ぎて伝わりづらくならないようになっている。曲もまた同じで、奇をてらった曲は基本的に無い。歌詞にしても、美しい比喩や捻りは多用されているが、何度か読み返したり、曲になじむうちに深い意味が分かる事も多く、難解さが目的にはなっていない。
音楽でも何でも、文化の世界は、移ろいやすい流行の奥底に、アンダーグラウンドの濃い流れがあり、流行と時に繋がる事もあれば、流行と断絶する事もある。
しかしL’Arc-en-Cielのポップさや分かりやすさが散りばめられた道をしばらく歩くと、そのまま奥底の流れに着く事ができる。親切なバンドである。
今回のライブでも、後半で最新曲の「FOREVER」が演奏された後に、デビュー前の初期曲である「予感」が演奏されたが、「FOREVER」演奏中は、ステージ上の画面に最新のレタリングで「L'Arc-en-Ciel」と映し出され、「予感」が始まった途端に、デビュー前のレタリングでの「L'Arc~en~Ciel」へと切り替えられた。(何となくイメージは付く方も多いだろう)
演出一つで、ポップからアンダーグラウンドへスルッと入る事ができるのだ。
もしL'Arc-en-Cielを聴いて、更にアンダーグラウンドなシーンへどっぷり浸かりたくなったら、各々メンバーのインタビュー等を手掛かりに、新しい音楽を見つけに行く事ができる。「GASTUNK」等がかかっていた、開演前のSEも良い手掛かりだったと思う。
・戦争と平和
三十年間バンドを続けて来た過程で、世の中も世界も様々に変化し、バンドとしても対応を迫られる時もあったはずだ。向き合い続けてきたからこそ、深刻な問題をテーマにしても、説得力が出る。
今回のライブを通し、目立つ形では無いが、「戦争と平和」がテーマとされていたと、私は考える。
「星空」の演奏前、大勢の観客のスマホライトに囲まれながら、hydeは言った。
「こんな綺麗な星があるのに、コロナも収束に向かって来ているのに、世の中が物騒なのは残念に思いますが、星空をどうか取り戻せたらと思います」
歌詞を見れば「星空」は平和を希求する歌と分かるが、ウクライナ情勢を踏まえたのだろう。最後の曲、「虹」の前にもhydeは言った。
「世界が大変な中でのライブになってしまいましたが、虹は雨が止んだ後に出るから」
東日本大震災後のライブMCを彷彿とさせる表現だが、「世界が大変」は、コロナもあるが、戦争も指していると思われる。
ここで何よりも強調したいのは、マスコミ報道やSNSを通した情報の濁流に流され、安易に「戦争と平和」を語っている訳では無いという事だ。
推測が混じるが、セットリストを振り返ると、「星空」のような平和を希求する歌だけで無く、「いばらの涙」のような信仰や思想を推し進める事への懐疑を示したと思われる歌(演出もどこか戦場を表している気がした)、「LOST HEAVEN」「SEVENTH HEAVEN」のような「理想の楽園」を無効化し、地上で生きて行く事を伝えているような歌(hydeは「SEVENTH HEAVEN」の演奏前に「楽園はどこにあると思う? ここにあるんだよ!」と叫んでいた)が演奏されていた。
「戦争駄目。平和が良いよね」だけでなく、戦争を生む要因まで、曲を通して問題定義していたと言えないだろうか。
更に言えば、「new world」のサビで、ステージ後方の画面に世界中の言葉で「愛してる」と出てくる演出があった。これも世界平和を願っているような気がするし、「MY HEART DRAWS A DREAM」もそんな気がして来る。1曲目に演奏された「ミライ」ももしかしたら……こう考えていくと、全てが平和を願った曲に感じてしまう。考えてもキリが無く、分からないなりに、無数の曲が私の中で、平和に向けて飛び立っていく。
上で取り上げた「new world」「LOST HEAVEN」「星空」は全て、2005年のアルバム『AWAKE』の曲で、丁度イラク戦争後であり、米国が世界の混迷に更なる混迷を上塗りしている頃だった。
今回のライブで、ステージ上の画面に映し出された「星空」の英詩が、大変印象的である。
「Nobody knows. Nobody cares. I have lost everything to bombs.」
「Nobody knows.Nobody cares. They just took everything I had.」
正直イラクよりも、今回のウクライナの方が、社会の共感を集めている事は否めない。それどころか、イラク戦争に反対する活動をしたGLAYのTAKUROは脅迫等を受け大変苦労したという。(②)
今回もアジア、アフリカ等の紛争は何故注目されないのか、と問われたりした。
また、ウクライナ情勢でも、現地で苦しむ人や難民、ロシアで戦争反対したり、日本等に住んで肩身の狭い思いをするロシア人といった存在を、我々がいつまでも忘れずにいれるか、という問題もある。
そういった諸々を考えながら、上の英詩を読むと、30年間活動し、同時代の出来事を見つめて来たhydeの思考の鋭さが分かる。
(彼の著書「THE HYDE」には、宗教や思想への懐疑が具体的に綴られている。また、出版当時問題になっていた「韓流へのヘイト」への批判と背景への考察や「アメリカという国は嫌いだが文化は好き」という記述もある)
色々書いたが、結局「浮かれた報道で流されても、更なる戦争に向かうだけで、一人一人が地に足付けて生きて行く事でしか、平和は達成されないんじゃないか」というのが、ライブでのメッセージではないかと、私は勝手に思っている。
③まとめ
・懐かしい香りがする「空気」
今回のライブで改めて、L'Arc-en-Cielというバンドが、高クオリティで多様な表現を出し続けているバンドだと実感した。また、物凄く明確なメッセージを伝えるバンドでは無いとも再確認した。(決してファンを突き放す訳では無いが)
そうなると困った事(?)に、想像力次第で、何とでもバンドの特徴を定義付ける事ができてしまう。他のミュージシャンに無い絶対的な個性や特徴を見出す事が難しい。もっと言ってしまうと、L'Arc-en-Ciel的なものは、「空気」のように、世界中に偏在している気がする。他のアーティストの曲を聴いても、L'Arc-en-Cielのライブを思い出し、余韻に浸り、切なくなったりする。これは決してどちらかがどちらを真似しているという話では無い。
L'Arc-en-Cielは不思議な宇宙空間なのだ。
普遍性があり過ぎるバンドで、それが鬼才たる所以かもしれない。
バンドに普遍性があり過ぎると、ファンの特徴を捉えるのも難しい。
結果として「私にとってのラルク」というのが一人一人、全く違う状況で存在し、そこを突き詰めてこそ、バンドの特徴に行き着けるのだろう。
究極の個別性が、究極の普遍性と行き来する。
バンドの三十年間の巨大な歩みは、ファンの無数の足跡を受け入れ続けた。そしてこれからも歩みは続き、新たな足跡も永久に受け入れる事になる。
だからこそ、ほぼ確実な動員で大規模ライブをいつまでも続けられる。
・果敢に孤独と戦う人へ
最後に一つ「逸れた話」をして、ライブの感想を終わりたい。hydeはインタビューで日本人の特徴について以下のように語った。(③)
「国民性として人の気持ちを思いやる人が多いなと思います。悪く言うと押しが弱いんですけど。例えば、中国とかほかのアジア圏の人はちゃんと自分をアピールできるけど、日本人はできない人が多い印象。シャイな部分もあるけど、まずはその人の意見を聞こうとする気持ちが先に来る。鍵のない襖の文化とか象徴的ですよね。鍵がなくても、襖の向こうにいる人を察して入るか入らないか考えたりするじゃない?」
多少日本人の特徴をデフォルメし過ぎな印象は受けるが、かなり当たっていると思う。(日本人だけでなく、日本で生まれ育ったり、長く日本にいる外国の人も、そうなるかもしれない)シャイだけれど、人の意見を聞ける。気持ちを思いやれる。これは何故なのだろうか。ざっくり言ってしまうと、「意外と孤独な民族だから」では無いだろうか。
宗教、政治、地域といった、個人と、国や世界の間にある中間地帯が機能していないもしくは分解してしまい、多くの人々がバラバラに街で生きている。だからこそ学校や会社が疑似家族的に感じて同調圧力に苦しんだり(逆に同調の中で無いと生きられない人もいるのだろう)辛うじて作った核家族で縛り合ったりする。怪しげな集まりに絡めとられてしまったりもする。
しかし、こうした日本的な在り方は長所もある。見ず知らずの人同士で知り合っても、何とかお互いを理解しようとする。(気の使い過ぎや新たな縛り合いになる可能性もあるが)そして、お互いの生活を理解し合う中で、それが一気に巨大な世界に接続されたりする。
たまたま教室で知り合った学生同士が、世界の存亡に巻き込まれるアニメ作品は、その反映では無いか。
最近では、いきなり巨大な世界に接続するのでは無く、中間にある政治等について、お互い理解し合い、ケアし合いながら、初対面の人同士で学び合って行こうというコミュニティが複数、出来始めているようである。
結論はシンプルである。L'Arc-en-Cielこそが、孤独を抱えながらも、果敢に他者と繋がろうとする一人一人を理解し、何かを伝えながら歩んで来た「ケアセンター」だったのでは無いか。
そしてそれは先に書いたように、明確なメッセージを敢えて打ち出さず、「空気」のような普遍性を持ったからこそ、得られた立ち位置なのだ。

(参考)
①
Amazon - THE HYDE | 寶井 秀人 |本 | 通販
②
胸懐 | TAKURO |本 | 通販 (amazon.co.jp)
③
HYDEソロ20周年記念インタビュー|筋書きのない道を歩いてきた20年……6つのテーマでたどるその足跡 (2/3) - 音楽ナタリー 特集・インタビュー (natalie.mu)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
