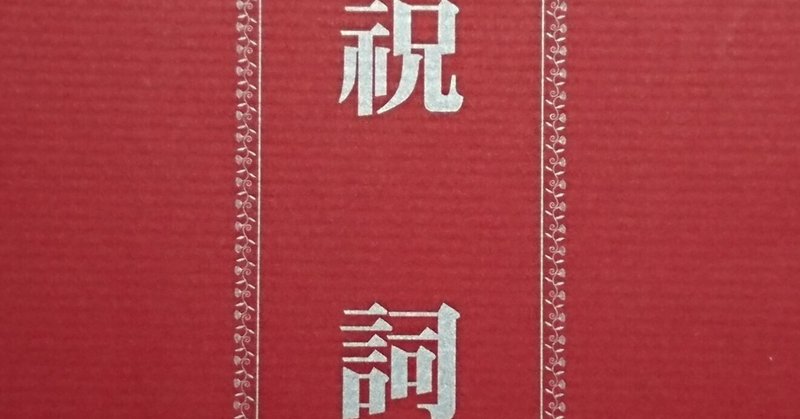
大祓詞/千木(ちぎ)
『 下(した)つ磐根(いわね)に 宮柱(みやばしら)太敷立(ふとしきた)て 高天原(たかまのはら)に 千木高知(たかし)りて 』
( 意訳 )
『 地の下にある岩盤に宮殿の柱を太く立て、高天原に向けて千木を高くそびえさせ 』 國學院大學博物館 企画展 祓 儀礼と思想 図録より
日本書紀 巻第三 神武天皇 元年正月
『故(かれ)、古語(ふること)に称(たた)へて曰(まを)さく、「畝傍(うねび)の橿原(かしはら)に、底磐之根(そこついはね)に宮柱(みやばしら)太立(ふとしきた)て高天之原(たかまのはら)に搏風峻峙(ちぎたかし)りて、始馭天下之(はつくにしらす)天皇(すめらみこと)」』
⇒ 『そこで古伝承に、天皇を讃えて、「畝傍の橿原に、大地の底の岩に宮柱をしっかりと立て、高天原に千木を聳(そそ)り立たせて、初めて国をお治めになったという始馭天下之天皇』新編日本古典文学全集2 日本書記1 より
千木 詳しくは ↓
社殿の建築|神宮について|伊勢神宮 (isejingu.or.jp)
*高知りて 高大に造り営んだ
古事記 上巻 忍穂耳命と邇々芸命
『是(ここ)に、詔(のりたま)はく、「此地(ここ)は、韓国(からくに)に向ひ、笠沙(かささ)の御前(みさき)を真来(まき)通(とほ)りて、朝日の直刺(たださ)す国、夕日(ゆふひ)の日照(ひで)る国ぞ。
故(かれ)、此地(ここ)は、甚吉(いとよ)き地(ところ)」と詔ひて、底津石根(そこついはね)に宮柱ふとしり、高天原(たかあまのはら)に氷 椽たかしりて坐(いま)しき。』
底津石根~ 大磐石の上に宮柱を太く立て、高天原に千木を高くそびえさせてお住まいになった。 新編日本古典文学全集1 古事記より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
