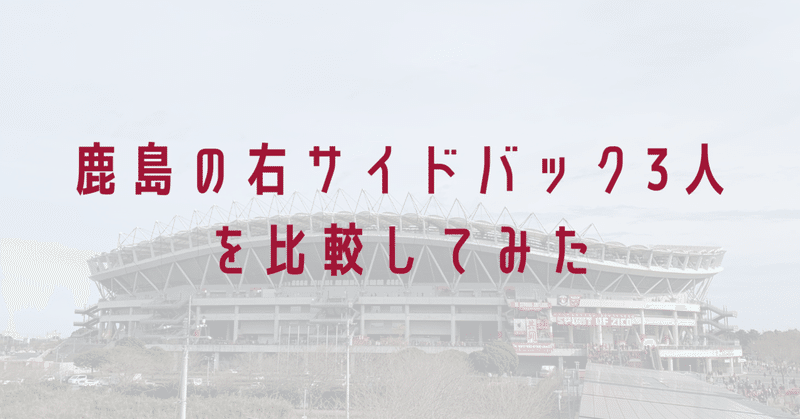
鹿島の右サイドバック3人を比較してみた
今シーズン、鹿島では小泉、広瀬、常本の3人が右サイドバックとして起用されている。この3人はそれぞれ特徴が異なる。今回はその特徴をJリーグのデータサイト「Football LAB」を参考に比較してみる。
■出場状況
まず、現在までの出場時間について。リーグ戦において一番試合に絡めているのは小泉。右サイドバックでの先発出場を見ても、小泉→常本→広瀬の順で直近リーグ戦では常本がスタメン起用される機会が増えているという状況。3人のポテンシャルを考えれば、シーズン終盤までかなり激しい競争が予想される。
小泉:478分(7試合)
常本:311分(4試合)
広瀬:203分(4試合)
右サイドバックでの先発
小泉:5試合
常本:4試合
広瀬:2試合
■比較方法
先述の通り、Football LABのチャンスビルディングポイント(CBP)を参考に比較する。
>CBPとは、「選手(またはチーム)が試合を通じてどれだけチャンス機会を構築することができたか」を独自のロジックにより数値化した指標です。選手(またはチーム)に対する評価方法が様々ある中で、「シュート機会への貢献」という観点での評価に軸足を置いています。
>フィールド上で発生するプレーを「プレー項目(パス、ドリブル、クロスなど)」と「エリア」で定義し、①そのプレーがどの程度シュートに結びつくか、②そのプレーがどの程度難しいか、という2つの視点に則った算出式を用いてスコア化します。すなわち、フィールド上で発生する全てのプレーにポイントを与えます。
そのプレーがどの程度シュートに結びつくか
=該当プレー×エリア別シュート到達率(当該エリアでのプレーが、最終的にシュートに到達する確率)
そのプレーがどの程度難しいか
=該当エリアにおけるプレーの難易度(当該エリアでのプレーが成功する難易度を独自ロジックでスコア化)
・守備
>相手のプレーの成功(味方へつなぐ、もしくはゴール)を阻止した場合に、成功していれば攻撃側に付与されていたポイントがそのまま守備側に与えられます。よって味方ゴールに近い方が高いポイントが付きます。奪取と違いマイボールにならなかったとしてもポイントとなりますので、クロスボールをクリアして相手にコーナーキックを与えたとしてもクロスを阻止したポイントが加算されます。
常本:2.45
広瀬:1.57
小泉:1.50
守備というと小泉のイメージが強いかもしれないが、この項目における数値は常本が抜けている。個人的にこの項目の基準のように味方ゴール前での守備に特徴を出しているのが常本で広瀬、小泉はもう一つ前のエリアで守備に成功している場面が多いような気がする。また、常本の場合カバーリングの感度もいいように見えるので、ギリギリの局面(ゴール前)での守備対応は彼の特徴と言っていいだろう。これは大学時代にCBをやっていたことやアジリティ能力も影響しているかもしれない。
・奪取
>相手のパス、クロス、ドリブルなどのアクションからボールを奪い自チームの攻撃につなげたプレーに対してポイントが付与されます。ポイントは相手のパス、クロス、ドリブルなどのアクションの失敗確率から算出されるため、相手チームがパスを通しやすいはずの高い位置でボールを奪うと高いポイントがつきやすくなります。
常本:13.44
広瀬:9.77
小泉:8.13
「守備」の項目とは違い、「奪取」では攻撃に繋げられたかがポイントに影響する。ここでも常本のボール奪取能力の高さが伺える。大卒ルーキーとはいえ、キャリアを重ねてきた2人よりも明確に違いを発揮できるあたり、相馬体制で起用されるのも納得できてしまう。
・攻撃
>パス、クロス、ドリブルのポイントの合計値を攻撃ポイントとして掲載しています。
広瀬:2.55
常本:1.61
小泉:1.31
続いて攻撃。この項目は総合的な観点となるようなので、広瀬が一番数値が高いのは予想通り。昨シーズン終盤にザーゴが攻撃の交代カードとして使っていた大きな理由だろう。
・パス
>味方にボールをつなぐことを意図したプレーをパスとしています。クロスは別途ポイント化しているためこちらには含めません。セットプレーは除かれます。
広瀬:2.55
常本:1.66
小泉:1.23
ここでも広瀬がダントツの数値。小泉の数値の開きは2倍。こうみると、改めて彼の起用法は攻撃に転じたい展開や試合が適しているのかもしれない。例えば、ボール保持の時間が長い川崎に対して三苫薫に常本をぶつけるのではなく、自ら保持してボールを取り上げる戦いで広瀬を頼ることもありなのかもしれない。逆にこれだけ違いの見せられる広瀬が常本並みに守備が改善されれば、スタメン確保できる可能性は高くなる。
・クロス
>グラウンドの3分の1を越えたペナルティエリア両脇の延長線の外から出したパス、もしくは、ペナルティエリア内でもゴールエリアの縦のラインより外側から出し、ペナルティエリア中央付近を狙ったパスをクロスとしています。パスと同様セットプレーは除かれます。
常本:0.30
広瀬:0.24
小泉:0.08
エヴェラウドや上田といったヘディンガーがいる鹿島において、クロスを上げられるかはとても重要である。その点、数値的には小泉の課題かもしれない。
・ドリブル
>相手を抜こうとする、もしくはかわそうとするプレー。相手と対峙していない状況下でボールを運ぶプレーはドリブルとしていません。
広瀬 0.08
常本 0.06
小泉:0.00
小泉の数値にはかなり驚いた。たしかに、運ぶプレーはあっても小泉が強引に抜きにかかる場面はあまり見たことない。
・シュート
>足(キック)、頭(ヘディング)、その他の部位などを使い、得点を取ることを目的としたプレーをシュートとしています。その中から枠内へ飛ばしたシュートがポイントの対象となります。ゴールが決まった場合は、特にシュートを打つ意志がなかったとしても最後に触った選手のプレーはシュートとしています(但しオウンゴールは除きます)。セットプレーや2m未満の距離で相手DFなどにブロックされたシュートはポイント対象となりません。
常本:0.32
小泉:0.20
広瀬:0.00
■まとめ
これら各項目の数値をまとめた上での特徴について整理しよう。
まず、ここ数試合起用されている常本だが、彼の特徴はやはり守備能力の高さ。これは見ている側が思っている以上にキャリアを積んできた小泉、広瀬よりも若干抜けているレベルなのかもしれない。彼の場合、予測や感度の良さもさることながら、アジリティも影響している気がする。例え予想外な対応を強いられても、運動能力でカバーできるアドバンテージがある。仮にこのまま鹿島で試合経験を積んでいければ、予測の精度やカバー範囲も広がり、内田篤人のようなDFも夢じゃないかも。
反対に広瀬は改めて攻撃の局面で持ち味がでるSBだと。現在の出場機会はルヴァンカップがメインだが、今後チームがボールを保持したい状況や、保持して違いを生み出したい場面によっては出番が回ってくるかもしれない。
ザーゴ体制でスタメンを確保していた小泉は今回参考にした数値の方では、他2人に上回るものはなかった。攻撃の広瀬、守備の小泉、バランスの常本と捉えていたが、小泉と常本は逆なのかもしれない。状況によっては、ユーティリティが故に器用貧乏化する可能性もあるので、ぜひ持ち味を発揮してもらいたい。
■引用元
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
