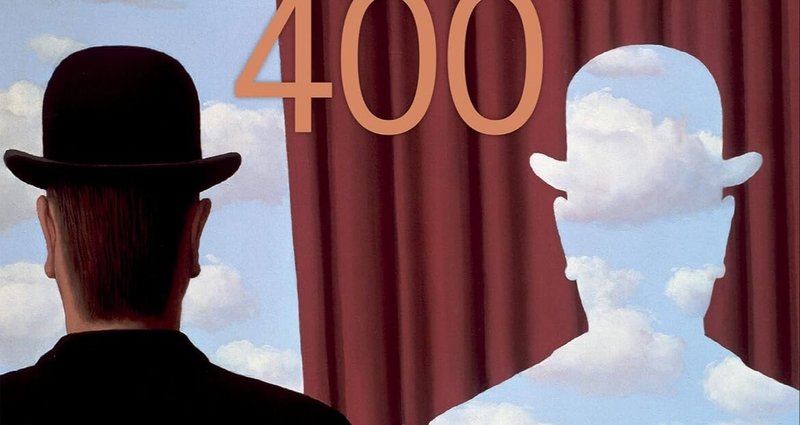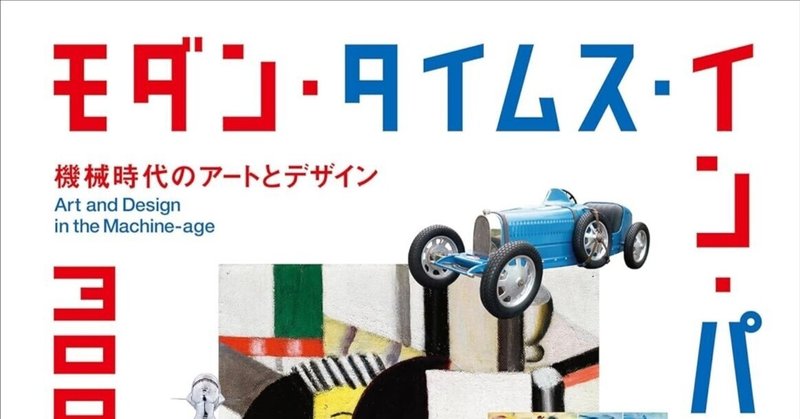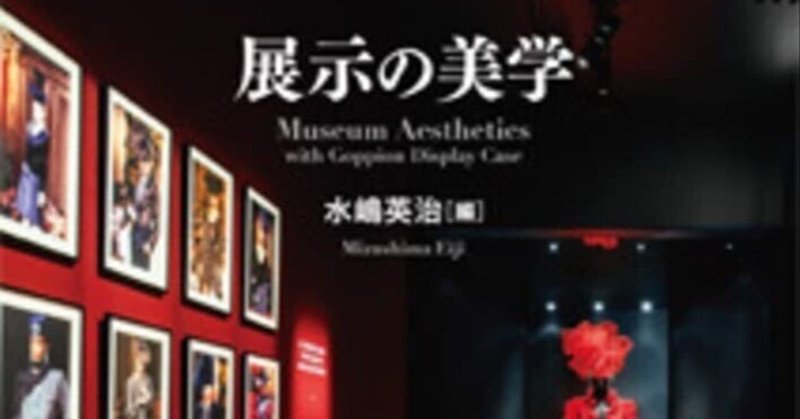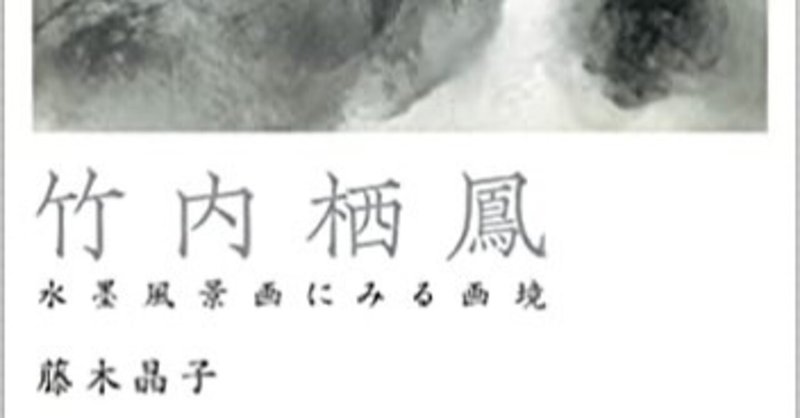#美術館

【美術ブックリスト】 一般財団法人長野県文化振興事業団『シンビズムの軌跡 信州ミュージアム・ネットワークが生んだアートプロジェクト』
2015年に長野県が文化振興元年を宣言し、翌年長野県芸術監督団事業がはじまった。芸術監督に就いた本江邦夫氏の提唱で、長野県内の公立、市立の美術館施設、フリーの学芸員の共同企画によって展覧会を開催することとなり、その展覧会シリーズが「シンビズム」と呼称されることとなった。 2018年から4回の展覧会が県内14会場で開かれ、若手の現代作家から戦後美術史を語る作家まで、総勢65名の県ゆかりの作家を紹介。学芸員自身が作家を選び、所属を超えて切磋琢磨しながら企画、開催された。 足掛