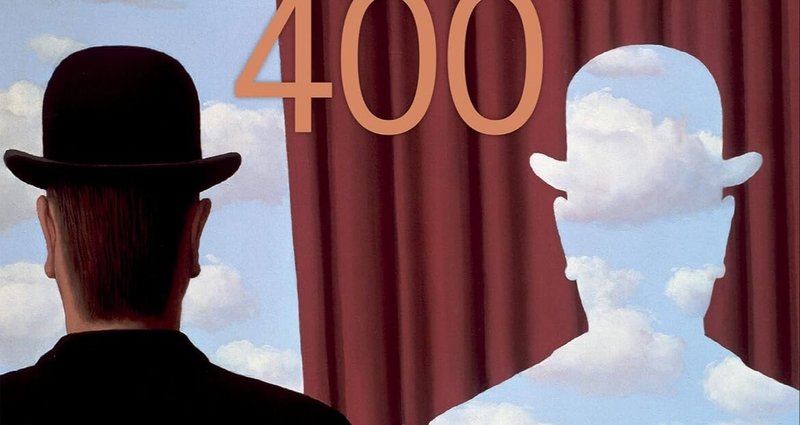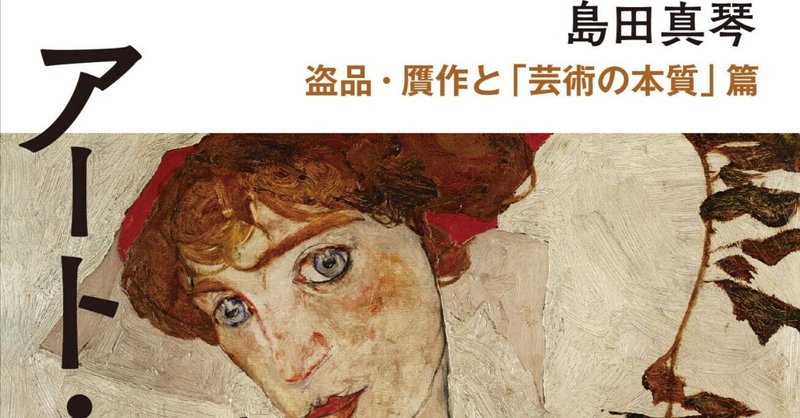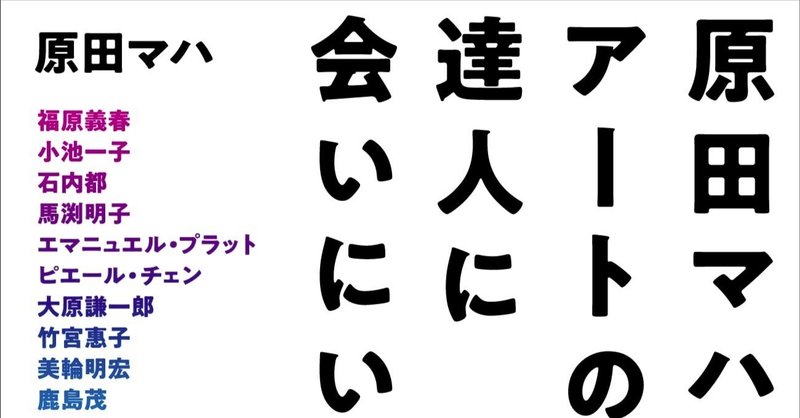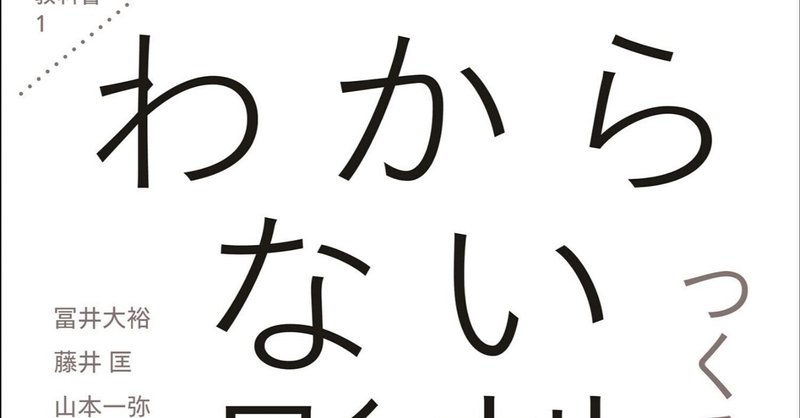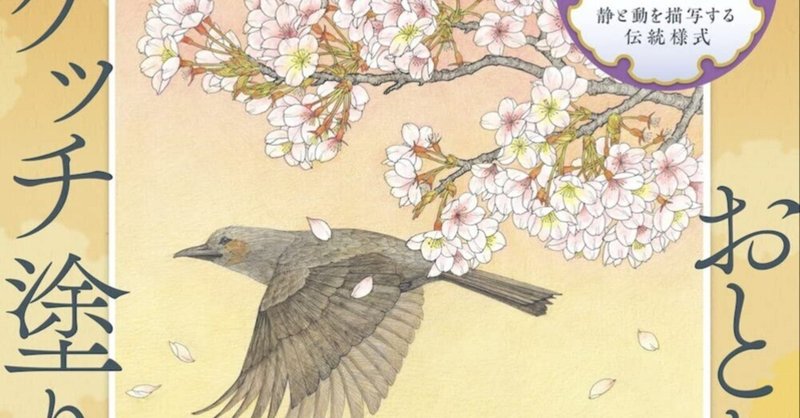2023年5月の記事一覧
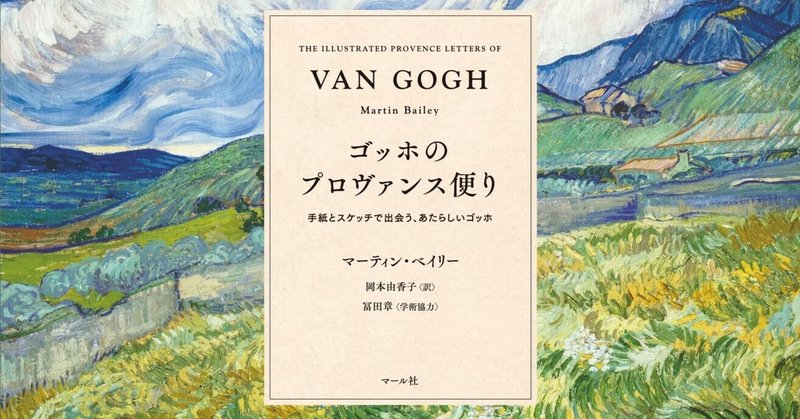
【美術ブックリスト】『ゴッホのプロヴァンス便り 手紙とスケッチで出会う、あたらしいゴッホ』 マーティン・ベイリー著、岡本由香子訳
ゴッホが南フランス滞在中に残した260通の手紙の約半数を収録しつつ、それとは別に解説が付されていく。 制作中の作品について、色について、構図についてなど、いま目にすることのできる作品が出来上がるまでの過程が分かるものや、画家の仕事について、病院など生活についてなど、「ゴッホ自身が語るゴッホ」を読むことができる。ほとんどは弟のテオに当てたものだが、その妻ヨーや、ゴーギャンに綴った手紙もある。 著者はアートニュースペーパーの記者で、ゴッホ研究の第一人者とのこと。 図版多数。巻末に