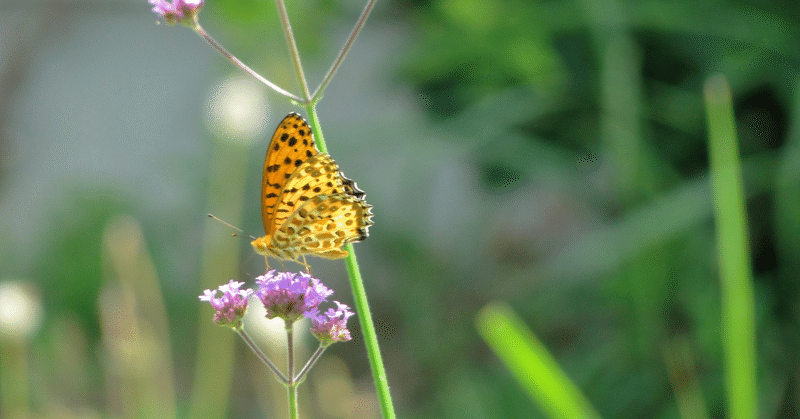
ホームセンターのコンシェルジュ#3『となりのプロから』
インタビューのつづきになります。
前回の話はこちら
ネットや他店舗で得られなかったもの
Nさん:我々がこれから若い方達の購買層を増やしていくには、若い方の情報網に私たちがどう情報を放るかだと思います。
そういう方たちに「このホームセンター内に家具の専門店があることや、相談できる店員がいることを」知ってもらい、お店に足を運んでくれる仕掛けを作らなければと思っています。
水鳥:実は私も、インテリアショップや家具小売店をまわった後に、「一応ここのホームセンターにも家具があったから、ベッドもあるのかな?」と、あまり期待をせずに来たので、「有名ブランドのベッドなどは置いてないのかな?」などと大変失礼な気持ちでした。
そしたら有名ブランドから、名前こそメジャーではなくてもリーズナブルで良い商品など、さまざまな価格帯の商品があり、それぞれのブランドのことを初めてフラットに教えていただけました。
それこそがネットでも、他の実店舗でも得られなかった、本当に知りたかった情報だった気がします。
紆余曲折があって今の売り方に
Nさん:話がずれるかもしれませんけど、それが私達の業界の生き残り方です。
今は綺麗ごとに聞こえるかもしれませんが、この業態を企業として維持していくには、他の競合がしない、その隙間に入っていかなければお客様が私たちを評価してくれません。
例えば価格が強みの他社と、同じような商品を作って同じように売っていては生き残ってはいけないわけです。
そこでリスクは伴いますが、ワンマーク上を目指さなければいけない。それが人です。だから商品知識や人間力が欠けているといけないのです。
水鳥:では今後もホームセンターでありながらも、専門店としてお客様の困りごとを聞き、その接客力で根強いファンを作っていくことを、企業としての強みにされるということですね。
Nさん:ただ、ここまで来るにも最初からこうだったわけではありません。
以前こういうお客様がいました。「家具を買いたいけど、近くには安価な商品を中心に扱う小売店の一店舗しかない。品質の高い家具を選べる店が近くにはない」と、その言葉が響いたんです。
私がこの会社に採用されて、家具の売り場のある専門店ができた当初、会社の考え方は今とは逆でした。
お求めやすい価格の商品を中心に品揃えし、多くの店員を配置せずとも、お客様が商品説明などを読んで、自由に買えるような方向性で考えられていました。
しかし、それをずっとやっていたら、この売り場は今なくなっていました。
その都度、その都度、商品を入れ替えて思考錯誤する中で、価格と比例した良い物を用意する必要性を感じました。
そんなお客様から見捨てられてしまうという恐怖感が、専門店を今の業態でオープンした5年目くらいにあったのです。
じゃあやり方を変えましょう!と、こういったデザインや品質の、きちんとした物を用意して、お客様に見ていただきましょうという、今のような売り方になっていきました。
水鳥:そういう過去があり、今があるのですね。今後は接客販売の仕事として、こうありたいなどの思いがあれば聞かせてください。
Nさん:最後に接客のことで締めるとすれば、接客はマニュアル通りにはいかないということです。
大きな企業であればあるほど「こういう質問には、こういう風に返しましょう」など、お客様からの質問に対する答えのパターンなどがマニュアルであります。
しかし我々の場合はそうではいけないので、足りないのはここだと気づきました。
どこのホームセンターも、日用品や消耗品売り場の接客は全てマニュアルです。マニュアルは誰もがフォルダなどから見ることができるので、新入社員なども対応が可能です。
しかしそれに対して、お客様がきちんと受け取ってくれているかは「?」です。
水鳥:そういうマニュアルでは対応できない、何かを提案できることが大事ということですね。
Nさん:そこを私たちの業態の壁として、どう人を育てるかが大きな課題になります。
経験の浅い人達には場数を踏むことや、失敗も多く経験することが大事だと伝えています。
そして分野を問わずいろいろなものを見たり、商品知識をつけることで、自信を持った振る舞いにつながる。それが大切だと思います。
インタビュー後記
ベッドという大きな買い物を前に、私は不安や疑問を抱えていました。しかし売り場のNさんに相談することで、納得のいく決断ができ、その接客に感動しました。
人を感動させるほどの接客とは何なのか?
今回お話を伺って見えてきたのは、競合の多い小売店の世界で、お客様に必要とされなければ生き残れないという危機感があったこと。
そのためにお客様の『形にならない生活の悩みを解く』ための質問力と提案力が必要であり、物を売ろうとする売り手の都合を感じさせない距離感が、『次もこの人から買いたい』と思わせる信頼感や顧客のファンを作るのだろうと確信しました。
その高い接客技術は、これまでの経験と知識から培われたものであり、今後接客AIが出現しても、人が根底にある想いを話したいと思う相手は、やはり人なのではないかという思いを強くしました。
取材依頼時から、真剣にこちらの話に耳を傾けていただき、たくさんのお話を聞かせていただいたNさんに心から感謝いたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
