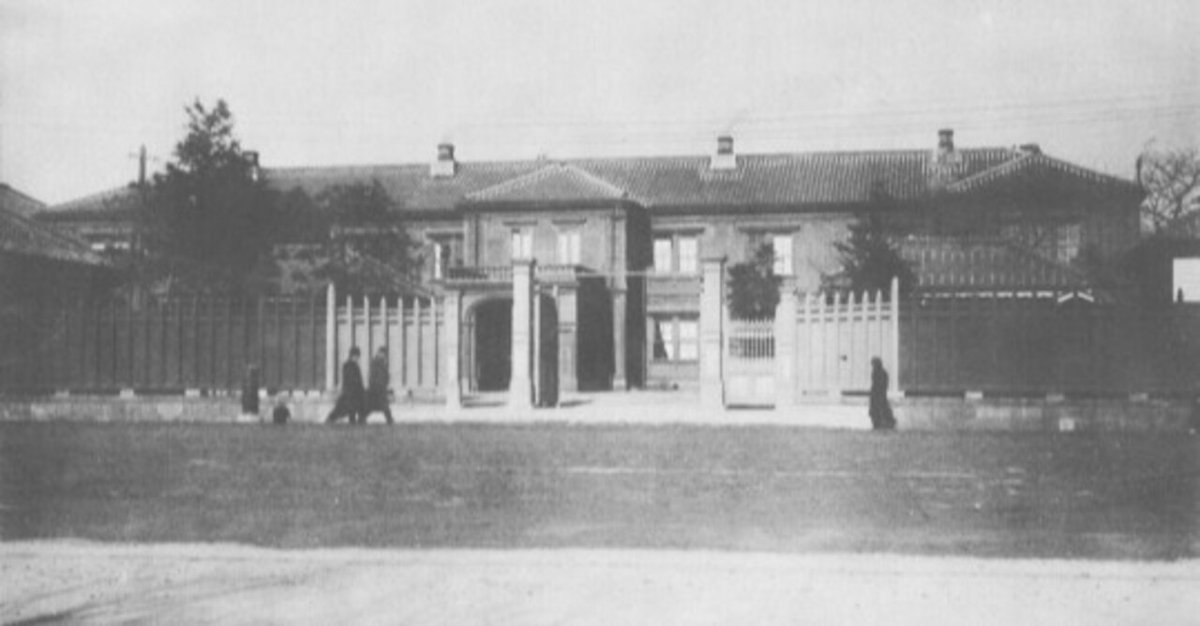
文部省時代から続く通信制高校の面接指導への問題意識
公立の通信制高校で数学の教員をしていますかとうです。
通信制高校には,全日制高校や定時制高校のような「授業」は存在せず,「面接指導」がそれに相当します。
「学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編」には,「授業の在り方」については記載はありませんが,「面接指導の在り方」については明確な記載があります。
面接指導においては,個別指導を重視して一人一人の生徒の実態を十分把握し,年間指導計画に基づき,自宅学習に必要な基礎的・基本的な学習知識について指導したり,それまでの添削指導を通して明らかとなった個々の生徒のもつ学習上の課題について十分考慮し,その後の自宅学習への示唆を与えたりするなど,計画的,体系的に指導することが必要である。
https://www.mext.go.jp/content/20200716-mxt_kyoiku02-100002620_1.pdf
面接指導は「個別指導を重視する」ことをベースとして,「自宅学習に必要な基礎的・基本的な知識を指導する」「その後の自宅学習への示唆を与える」ことが必要であるとされています。
通信制高校の学習の中心が「自学自習」であることが,学習指導要領の中にもよく現れています。
※学習する場所が必ずしも自宅である必要がないため,「自宅学習」の代わりに「自学自習」という表現を使用しています
現在の学習指導要領は抽象的な文言で面接指導がどう在るべきか書かれていますが,かつて文部省時代の学習指導要領には,もっと具体的で踏み込んだ表現で,面接指導に対する問題意識についても書かれていました。
面接指導の本来の在り方は個別指導である。しかし,多くの学校は生徒数と教員数の関係で一斉面接授業形式をとっている場合が多い。この場合でも年間計画に基づき一定の単元の授業に終始したり,次回のレポートのヒント授業になったり様々である。一斉指導形式の面接指導でも学習の主体が生徒であり,居住地学習に必要な基本的,基礎的学習知識を授けたり,過去のレポートの添削をとおして個々の生徒のもつ学習上の弱点について十分考慮した指導が望ましい。そうでないと面接指導が単に時間数を満たし,単位を修得するための時間稼ぎということになる。(文部省,1980)
現在の学習指導要領と比較すると,かなり強い言葉で面接指導の現状やそれに対する問題意識が書かれています。
この学習指導要領を書いた人の中には,これらの記述を通して現場の教員に伝えたいメッセージがあったのではないかと感じました。
「面接指導の在り方は個別指導である」から始めて,「学習の主体が生徒であり,居住地学習に必要な基本的,基礎的学習知識を授けたり,過去のレポートの添削をとおして個々の生徒のもつ学習上の弱点について十分考慮した指導が望ましい」で終わるだけよいところを,あえて授業ではない面接指導を「一斉授業形式」と表現し,「一定の単元の授業に終始していないか」「次回のレポートのヒント授業になっていないか」と問うことで,通信制高校で実施されている面接指導に警鐘を鳴らしています。
言わなくても意味としては伝わるけれど,それでも言いたくなった,言わなければ,と思うような切迫した実情があり,あえて言ったのではないかと思うのです。さらに,「授業」という言葉を使用するあたりに,皮肉すら込められているのではないかと感じてしまいます。
「あえて言う」で思い浮かんだ別の例として,東京大学のアドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)も紹介させていただきます。ここにも東京大学の強い危機感が現れているように感じます。
入学試験の得点だけを意識した,視野の狭い受験勉強のみに意を注ぐ人よりも,学校の授業の内外で,自らの興味・関心を生かして幅広く学び,その過程で見出されるに違いない諸問題を関連づける広い視野,あるいは自らの問題意識を掘り下げて追究するための深い洞察力を真剣に獲得しようとする人を東京大学は歓迎します。(東京大学)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_01_17.html
少し脱線してしまいましたが,話をもとに戻します。
1980年に文部省が学習指導要領で面接指導の在り方について強いメッセージを出してから,40年以上が経った現在,面接指導の状況はどう変化しているのでしょうか。
公立の通信制高校の現場で働いている自分の感覚としては,ほとんど変わっていないのではないかと思います。
現に,私も通信制高校に異動してきた直後の面接指導は,講義を中心とした一斉授業形式で,前回のレポートの内容の解説授業をしていました。不登校経験者が多く,対人関係に苦手意識を抱えた生徒も多いため,指名して発言させたり,ペアやグループでの活動を取り入れたりすることも避けていました。
その結果,面接指導はどうしても一方向のものとなってしまい,学力層の幅が広い通信制の生徒のほとんど誰にも響かず,大きな挫折を経験しました。
このままではまずいと思い,「面接指導とはそもそも何なのか」と考え,試行錯誤している最中に,同僚の教務主任から文部省時代の学習指導要領を紹介してもらいました。これまでの自分の状況と全く同じだと大きな衝撃を受けました。
そして,面接指導は個別指導を重視しなければならない,授業ではなく面接指導をしなければならないと強く決意しました。
次回はこれらを踏まえて,具体的にどのような面接指導を改善させたのか,現在実施している「数学Ⅰ」の面接指導について書きたいと思います。
