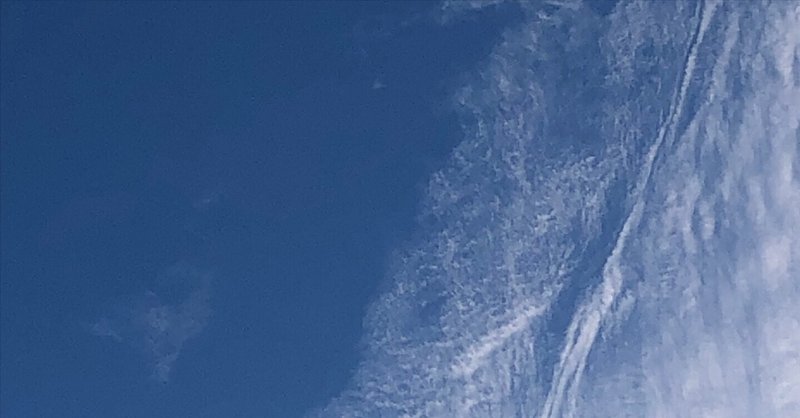
読書ノート 「レンマ学」① 中沢新一
近年の最重要書物のひとつと確信している『レンマ学』。思いつくまま取り出していく。すでに私の血となり肉となる部分もあるが、まだまだ、そんなに甘いものではない。ゆっくりいきましょ。
目次
序
第1章 レンマ学の礎石を置く
レンマ学の発端/源泉としての南方熊楠書簡/大乗仏教に希望あり
生命の中のレンマ的知性
第二章 縁起の論理
大乗仏教と縁起思想/プラジュニャーと縁起/レンマ的論理
空論から縁起へ/レンマ学は否定神学ではない
第三章 レンマ学としての『華厳経』
大乗仏教の王/レンマ的知性の充満する法界/法界の思考法
ロゴス的知性を包摂するレンマ的知性/マトリックスとしての法界
第四章 脳によらない知性
『華厳経』から華厳哲学へ/法蔵の達成/『大乗起信論』による補填
分別と無分別/タコのレンマ学
第五章 現代に甦るレンマ学
直交補構造/澄観の「四種法界」/進化する華厳法界
第六章 フロイト的無意識
フロイト的無意識を超えるレンマ的無意識
アーラヤ識としての無意識/フロイト的無意識のレンマ学的再検討
第七章 対称性無意識
無意識の位置/機械状無意識/法界と統合失調症
レンマ的知性に内在する「対称性」/バイロジックのレンマ学的理解
第八章 ユング的無意識
ユング心理学とレンマ学/シンクロニシティとレンマ学
「元型」のレンマ学的理解/不生不滅の法界
パウリのレンマ学的思考
第九章 レンマ的数論(1)
数に潜むレンマ的構造/縁起による「数」/法蔵の数論
レンマ的数の構造/量子数とレンマ的「数」/レンマ学と量子論
第十章 レンマ的数論(2)
数の発生/「数」から数へ/境界領域の光景
モナドとレンマ的「数」/リーマン予想のレンマ学的解釈
岡潔の数学思想のレンマ学的本質/ハイデッガーの存在論的数論
第十一章 レンマ派言語論
デカルト派言語学/言語の内部の直交補構造
ミニマリストとしての華厳学/詩的言語とレンマ学
異邦の言語学
第十二章 芸術のロゴスとレンマ
自己組織型としての言語/音楽と言語
サピエンスの言語としての詩/絵画とレンマ
エピローグ
付録 一 物と心の統一
二 レンマ的算術の基礎
三 心のレンマ学/A Lemma Science of Mind
あとがき
レンマ的知性は、ロゴス的知性を複雑高度に発達させたからといって、生まれるものではない。粘菌の知性活動を知って驚いた生物学者の中には、粘菌の示すようなレンマ型の知性は、ロゴス型コンピューターを並列にネットワーク連結することによって作りだせると考える人たちもいるが、その仮説は成功しないと私は予言する。また近い将来に量子コンピューター(量子コンピューターの原理はスピン量子化を用いた超並列ロゴス型コンピューターである)が開発されたとしても、レンマ的知性の機械による再現はうまくいかないだろう。
それは、非時間的な縁起の理法によって作動するレンマ的知性と、時間を介して線形的な情報処理をおこなうロゴス的知性とが、根本的に異質な知性だからである。レンマ的知性をロゴス的知性に落として変換することは難しくないが、ロゴス的知性からレンマ的知性を生み出すことはできないのである。
(第四章 脳によらない知性/『華厳経』から華厳哲学へ)
「法界」とは、存在の全域、「縁起」とは、事と事を繋いでいる相互連関。
「縁起」は、相互連関を保ちながら、事物が生起することを意味している。
「縁起」は、事物どうしが「相即相入」することによって起こる。
あらゆる事物は「空」に基づいた共通構造を持っているので、他の事物と「相即」することができる。
そして顕在と潜在の複雑な過程を経ながら、縁起の全体運動が起こっていく。
「ロゴス」は「集められた事物を並べて整理すること」
ロゴス的知性と「因果」の論理は相性が良い。
(第一章 レンマ学の礎石を置く/大乗仏教に希望あり)
量子的な「数」が示す状態Xは、「部分」と「全体」が予定調和を保ちながら変化している。つまりどの局所的な場所も孤立しておらず、変化はいつも全体的なのである。このようにして量子的な「数」は「非局所性」を本質とする。
パウリがユングから「共時性」についてのアイディアを聞いた時すぐに思ったのは、瞬時にして情報が心の全域に伝わっていく「元型」的無意識と、非局所性を本質とする量子空間との間に見出される著しい共通性だった。量子的な「数」はマトリックスで表現される。ユングの元型的無意識はいかなる線形的秩序(言語もその中に含まれる)にもよらないやり方で、高次元的空間の中に情報を走らせている。量子論的な「ニュメロイド」と心理学的な「プシコイド」の間に存在していると思われるつながりに、パウリは強く惹かれた。
リッツの結合則・・・二つの振動を合成した時、この法則が満たされていれば、合成後の振動数が居場所を失って消えてしまわずに、マトリックスの中に残って作用を続けることができる。
(第九章 レンマ的数論(1)量子数とレンマ的「数」)
「ものごとはつながりのあることによって生ずる」が、
「すべての現象は相互依存の関係で成り立っている」という意味を引き出し、
「すべての現象は縁起するゆえに、固定的な実体を持つものはなく、固執する対象もない」という意味に広がっていく。
ブッタは人生苦のおおもとを老死の中に見た。
なぜ老死があるかといえば、生につながって生起する現象であるからだが、生は有に縁起していることによって、有=存在世界のなかに一定の身分を得ることになる。有の世界に置かれた生は、そこで自分の内部に外のものを取り入れる(取)ことに執着する。つまり有は取につながって縁起しているのである。
この取の基底をなしているのは愛を求める渇愛である。
そして渇愛には憎悪・怨恨・憤怒などのネガティブな欲念が伴う。まさに愛こそが人間苦の根底をなし、取と一体になって強力に人間の感情生活を駆動している。
愛は感情を持つ生物に特有のものである。
外界からの刺激を受けて発動する感情を受とする。愛はこの受につながっていて、自分の外にあるものに対して苦楽の感情を味わうことになる。愛が外界の触れ合うには触の働きがなければならない。五感の働きのことである。この触はそれを感覚として受け取るための器官がなければならない。すなわち触は六つの感覚器官である六処に縁起している。
感覚器官からもたらされる刺激を、受・想・行・識のような心の作用に組織立てているもののすべてを名色と総称する。私たちの心身のことである。この心身のあるおかげで、人間は官能を働かせながら、苦の源泉である外界の対象や出来事に巻き込まれ、緊縛され、身動きがつかなくなっていく。
心身そのものである名色に縁起することによって識が起こる。名色が識に組み立てられ、統一されて認識作用がつくられる。この識は奥底では生命活動そのものにつながっており、愛や感覚にもつながっている。それらすべての識の働きが統一しながら、主観(自分)と客観(自分の外)を生み出すのである。この識の働きが積極的に外界に向かっていくとき、行すなわち行為が発生する。
ブッダはこうした縁起の全過程が、無明に突き動かされている、と考えた。
妄想のゴーグルのようなものを、あらゆる有情が着想しながら生きている。そのゴーグルは目が覚めているときも寝ているときもはずれない。そのために生そのものが無明によって起こり、無明の上に生物の認識作用が形成されることになる。無明は縁起の全過程に浸透し、あらゆる縁起の項目が、無明に動かされて染まっているとも言える。無明を原基として、縁起につながれた全過程が駆動しているのである。
(第二章 縁起の論理/大乗仏教と縁起思想)
縁起によって生成していくこの世界の実相(リアリティ)を把捉しうる知性、その知性は「般若(プラジュニャー)と呼ばれる。
「般若経」では、「あらゆる事物は相互につながりあっている」という縁起の考えは、「空」の思想として語られる。ナーガールジュナ(龍樹)は、ブッダの縁起法をめぐる説法にあらわれた思想を、「あらゆるものは相依相関しあっているから、ものには自性や本体はなく、空である」という空論的論理に研ぎ澄ませた。
インド人は人間の思考が、肯定、否定、否定でもなく肯定でもない、肯定にして否定、の四つの場合の組みあわせでできていることを、古くから見出していた。
ヨーロッパ論理学では、このうち二つの、肯定と否定だけを取り出し、三つの規則(同一律、矛盾律、排中律)をもとに論理道具を作った。
・でない・そして・または・ならば・すべての・存在する、の六つの論理記号を用いるだけで、すべてのロゴス的論述は表現できる。
否定でもなく肯定でもない、「両否の論理」を指して、山内得立は「レンマの論理」と呼んだ。古代ギリシア人は物事を分別する通常のロゴスとは異なる、直観によって全体の様相を一気に把握する知性のことをレンマと呼んだ。
ナーガールジュナの「中論」において頂点に達する空論に対して、北方の大乗仏教徒は、別の解釈と表現をもたらそうとした。
「法界」は心
人物は、世親(ヴァスバンドウ)、無着(アサンガ)、弥勒(マイトレーヤ)
①色即是空・・・・・ナーガールジュナはこれに焦点を当てて思想を展開
②空即是色・・・・・北方の大乗仏教徒はこちらに焦点、有に近づいていく空
「唯識論」と呼ばれた。
「空は充実した力を内蔵する時空の原基(スパティウム)であり、諸現象はその空から生起する、故に諸現象と空は一つである」「空である心に諸現象のいっさいが生起する(三界は心である)」
色即是空の空論と、空即是色の唯識論とを弁証法的に統合する「華厳経」が中央アジアに出現した。
(第二章 縁起の論理/空論から縁起へ)
華厳経は、ブッダが悟りを得てからまだその内容を人間に語りだす以前の、第二七日すなわち第二週目のできごとと設定されている。
ここでブッダは、自分の悟りの内容を、人間ではなく、高貴な存在たちに向けて語っている。レンマ的空間の様相や法則、構造について比喩を駆使しながら自在に語っている。
ヴァイローチャナ(毘盧遮那)、マイトレーア(弥勒)
線形性でない思考、言語
句構造(S+V+O+C)
完全な充満状態から隙間だらけの句構造へ、多次元的な非線形言語から線形言語の二次元平面へ、レンマ的知性からロゴス的知性の平面へと、「射影」されていくにつれて、意味の豊かさは減っていく。しかしそれにもかかわらず、真理は間違いなく伝達されていく、というのが『華厳経』の言語思想である。
十の普遍
一切の世界を一本の髪の毛の中に収め、一本の髪の毛を一切の世界に広げていくことができ、一切の衆生の身体を一つの身体におさめ入れ、一つの身体を一切の衆生の身体に広げていくことができ、言語で表現できないほどに長大な時間を一瞬の思考に収め、一瞬の思考を言語で表現できないほど長大な時間に広げていくことができ、一切の経験(法)を一つの経験に収め、一つの経験を一切の経験に広げていくことができ、言語で表現できないほど広大な広がりを一つの場所に収め、一つの場所を言語で表現できないほど広大な広がりに拡げていくことができ、無量の有情(生命)をひとつの有情に収め入れ、一つの有情を無量の有情に拡大していくことができ、無量の非情(非生命)を一つの非情に収め、一つの非情を無量の非情に拡大していくことができ、一切の想念を一つの想念に収め、一つの想念を一切の想念に拡げていくことができ、一切の言語音を一つの言語音に収め、一つの言語音を一切の言語音に拡げていくことができ、一切の過去・現在・未来の三世を一つの時間に収め、一つの時間を三世に拡大していくことができるようになる。(普賢行品第三六)
一即多、他即一ノ思考法
六波羅蜜
惜しみなく与える能力、戒律を堅固に守る能力、苦痛や侮辱に耐える能力、双刃する能力、心を安定させる能力、知恵を得る能力
華厳経によるレンマ的知性の海図
法界の構造は楼閣・曼荼羅
【第十一章 レンマ派言語論】
言語は人間の心/脳に内蔵されている生得的能力である。
心/脳=レンマ的知性とロゴス的知性の合成体→「アーラヤ識」
ロゴス的知性は、「事物を時間軸に沿って並べること」によって、心的秩序をつくりだす。それゆえ言語は、語彙素、意味素を統辞構造にしたがって「並べる」ことで成り立っている。
上記の深層構造は、発話されることで表層構造にあらわれる。
その際にも時間軸が決定的な役割を果たす。
生成文法理論は、言語のこのロゴス的統辞面に焦点を合わせる。分別知のもとは文であるが、この文の構成原理をあきらかにしようというのである。
文は、階層構造を持った句構造に分解される。
名詞句NPに新しい前置詞PPを付加することで、無限の文を生み出すことができる。この繰り返し規則が言語の創造性を表現している、とチョムスキーは考える。
この事態を華厳学的に表現すれば、事法界に理法界が貫入して理事無礙法界の様態が心=法界に形成される過程に対応している。事法界のみでは語彙目録に統辞方的な秩序を与えることはできない。また数を次々と数えていくこともできない。世界の差別相をとらえる事法界に、平等一如の理法界が働きかけなければ、言語も数も生まれることができない。このことから判断すると、心/脳に理事無礙法界の様態が発生できるようになったときはじめて、言語をしゃべり数を数える能力を持ったホモサピエンスが出現したということになる。
言語音は言語の表現面に属していて、意味範疇のかかわる内容面からはほんらい独立している。そして言語面は「響き」でもあるので、表現面の全体性は響きによって統一されているとも言える。
文の規則は文法的な文を集合の中に囲い込み、そうでない文を排除する、こういう判断のすべてを、無意識が瞬時におこなっている。
言語を主にそのロゴス面から観察する生成文法が文を無限に創造できる言語能力に注目してきたのに対して、言語を主にそのレンマ面から研究するソシュール的構造主義は、言語の体系性や全体性の方に注目してきた。アーラヤ識に内蔵された言語能力は、ロゴス的知性とレンマ的知性の合成体である。それゆえ、現代言語学にあらわれたこの二つの有力な学派の主張するところは、そのまま言語の二重の本性に対応しているといえる。
ソシュールによる言語の「通時態」と「共時態」への分解
通時態と共時態の二つの軸(連辞の軸と範列の軸)は広がりをもたない点で交わっている=「直交」している。この関係を「直交補構造」とする。
直交補構造は、量子力学の世界でしばしば用いられる構造であるが、それと同じ構造が言語にも潜在していることを、ソシュールは突き止めていたと考えて良い。
アナグラムは「言葉の下に隠れている言葉」である。その言語活動では、一つの語彙素の意味は文全体によって決定され、単語の綴りが文全体に「散布」されている。すなわちアナグラムにおいては、分別知をもたらすロゴス的な統辞法的秩序の下に、相依相関しながら全体で運動していく法界縁起的なもう一つの言語活動が働いているのである。その意味でソシュール言語学はレンマ派言語学の考えの身近にあると感じられる。
神話が生まれる場所は、時間と空間が一つに溶け合って、消えていく無意識の思考にある(レヴィ=ストロース)
生成文法の「ミニマリスト・プログラム」必要最小限の要素と操作

文法の必要最小限の要素と操作は「併合」と「移動」。
「併合」いくつかのものをあわせて、ひとつのものにすること(広辞苑)
「さて、突然変異は個人に起こるものであり、集団に起こるものではありません。ちなみに、それはとても小さな繁殖集団(アフリカの一角にいたらしいヒト科生物の小集団)であったことがわかっています。その集団のどこかで何らかの突然変異が起こり、大躍進へと至ることになりました。それは一個人の中で起こったに違いないのです。一人の中で何かが起こり、それが子孫に受け継がれました。その変異は、非常に短期間のうちに集団を席巻したようですから、自然淘汰の観点から言ってなにか利点があったに違いありません。小さな集団における非常に短期間の出来事だった可能性があるのです。さて、それはどんなものだったのでしょう。最も単純な仮定は(それを疑う理由は見当たりません)、人類の祖先が「併合」(Merge)を獲得した、というものです。つまり、既存の心的対象(またはある種の概念)をとり、そこからより大きな心的対象を形成することを可能にする演算を獲得したのです。それは併合です。併合を手に入れた途端に、無限の階層的構造表現(及び思考)が利用できるようになったのです」(チョムスキー「チョムスキー言語の科学」より)
生成文法:心/脳に併合の演算を獲得したことで、人類は無限の階層的構造表現を利用し、言語を形成できた。
華厳学:人間の心=法界の仕組みを、「相即相入」の演算でアーラヤ識が形成され、「理事無礙法界」が創出する。
華厳学では、「相即相入」を可能にしている条件として、「空ー有」を上げている。
「相即」ではメタファー(隠喩)が、「相入」ではメトミニー(換喩)が生まれる。
セミオティック機能(クリステヴァ)=幼児の心=コーラChora(プラトン)=アーラヤ識=振動体の中から自然に圧縮・重ね合わせ=併合や、置き換え=移動の秩序が生まれてくる。
とりあえずここまで。次の②がいつになることやら…
よろしければサポートお願いいたします!更に質の高い内容をアップできるよう精進いたします!
