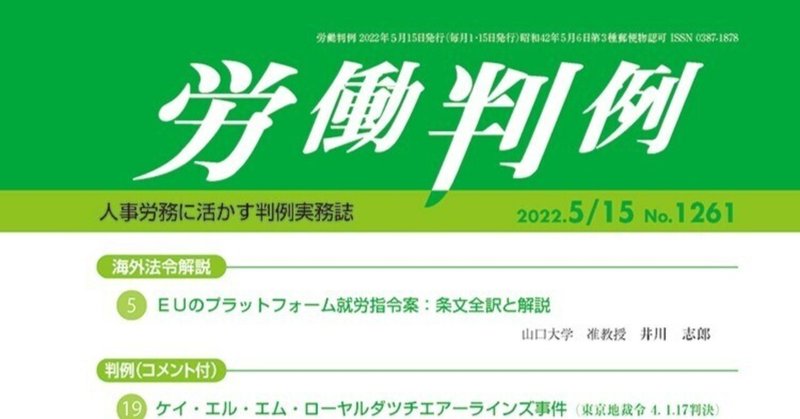
労働判例を読む#396
今日の労働判例
【みよし広域連合事件】(徳島地判R3.9.15労判1261.87)
※ 週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)
※ 司法試験考査委員(労働法)
※ YouTubeで3分解説!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK
この事案は、消防署員Eが、業務外で、その知人の飲酒運転によるひき逃げ死亡事故に際して、一緒に飲酒を重ねて同乗していたことに関し、地方自治体Yは消防署長Xに戒告処分(懲戒処分)を与え、そのために昇給が遅れました。Xは処分の違法性を主張し、裁判所も違法性を認めました。
なお、みよし広域連合は、三好市と東みよし町によって構成され、広域行政・消防などの事務を担っています。
1.Xの職責
裁判所は、Xが事故当時、うつ病により休職していたことから、Xの職責の範囲を限定しました。
すなわち、休職中はEの言動を監督していないから、この期間の直接の監督義務違反は認められないとしました。他方、休職前には、このような事故が発生しないために署員を管理監督する責任があり、これに違反する場合には責任が発生し得る、としています。
けれども、結果的にXの管理監督責任を認めました。
それは、所長として管理監督すべき部下は多数に上り、実際に直接管理監督するのは、より下位の管理監督者であること、実際Xは、折に触れて飲酒運転や暴行など私生活上も指導を行っていたこと、等から、その責務を果たしていた、と評価されました。
さらに、仮にEの日頃の言動に問題のあるようなことをXが知っていた場合には、Xの責任が認められる場合もあり得るとしつつ、そのような事情もない、としています。
2.実務上のポイント
これが、懲戒処分ではなく人事上の処分(配置転換や人事考課など)の場合はどうなるでしょうか。
その場合には、人事処分が有効となる可能性が比較的高いようにも思われます。それは、懲戒処分のようにペナルティーとして悪質であることが求められるのではなく、所長としての適性が問われるからです。すなわち、具体的な危険を回避するための対応が求められるのであれば、懲戒処分にも相当し得るでしょうが、より一般的に、各消防署員の仕事に取り組む姿勢や日常生活の過ごし方などまで含め、消防署や消防署員に対する社会の信頼を損ねるべきではない、という指導教育も含めた管理能力が、人事評価の場合には盛り込まれ得るように思われるからです。
この点で特に注目されるのは、所長としての管理監督義務の内容です。
この事案では、飲酒運転や暴行などの明らかな違法行為の予防についての指導教育が問題とされています。具体的な業務指示にとどまらず、私生活上の言動についてまで指導教育が必要とされているので、やはり上級管理者の職責の範囲は広範囲に及ぶことが理解できます。
しかし、本事案で問題とされているのは、私生活上の問題と言っても、飲酒運転や暴行などの明らかな違法行為を防止するための指導教育に限られます。地域住民から信頼されるような言動、というところまで広く指導教育し、消防署の規律や品格を維持することまで議論されていません。
このような点から、懲戒処分の場合と人事処分の場合とでは、同じような管理監督義務であっても、その内容や程度に差が生じうるのではないか、と思われるのです。
もっとも、本判決も含め多くの裁判例でこのような違いを意識的に明示して議論しているものはなかなか見かけられません。筆者の個人的な意見として、参考にしてください。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
