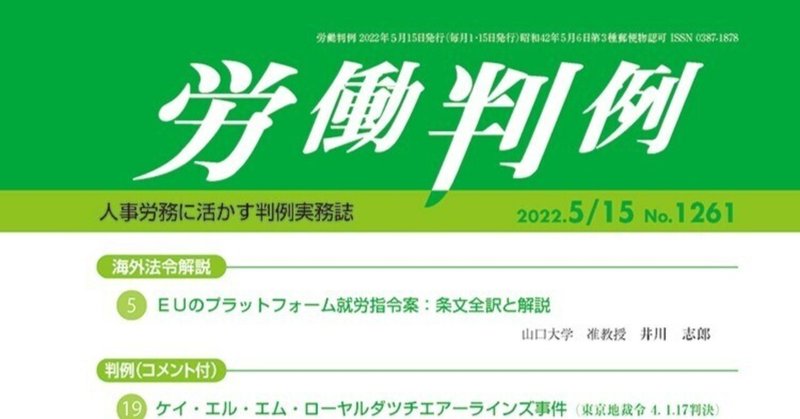
労働判例を読む#394
今日の労働判例
【ユナイテッド・エアーラインズ(旧コンチネンタル・ミクロネシア)事件】】(東京高判R3.12.22労判1261.37)
※ 週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)
※ 司法試験考査委員(労働法)
※ YouTubeで3分解説!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK
この事案は、コンチネンタル・ミクロネシアYに在籍し、成田ベースを仕事の拠点としていた客室乗務員らXが、Yのユナイテッド・エアーラインズ(UA)による吸収に伴う事業再編によって、客室乗務員の業務がYに発注されなくなることなどから、度重なる労使交渉の後、解雇された事案です。
2審は、1審と同様、解雇を相当と判断しました。
整理解雇の判断枠組みやその概要は、1審の解説(「労働判例読本2021年版76頁」)をご覧ください。ここでは、グループ全体で整理解雇の有効性を検討するのか、Y単体で有効性を検討するのか、という点について検討します。
1.グループ全体か単体か
Xらは、Y単体ではなく、UA全体の中で、整理解雇の有効性(いわゆる整理解雇の4要素)の検討を行うべきである、と主張しています。つまり、UA全体でXを受け入れる努力が必要だった、という点がポイントになります。
もしそうであれば、解雇の必要性や再配属の可能性(解雇回避努力)も大きく状況が変わってきます。実際、解雇回避努力に関し、グループ会社の中にも働く機会を見つけるように努力することが求められる場合もあります(「マルマン事件」大阪地判H12.5.8労判787.18など)。
これに対して1審2審は、いずれもY単体で判断する、としました。
別法人であって、就業規則も異なり、労務管理も別である、などという形式的な理由を縷々指摘していますが、そのような形式だけで決まるのではないことは、上記マルマン事件などからも理解できます。そこで、本事案とグループ全体で検討している事案との実質的な違いがどこにあるのかが問題になります。
この点で特に注目されるのは2点あります。
1点目は、Y単体で検討すべき理由として(技術的には、Xの主張、すなわち解雇の翌年にYとUAが合併していたのだから、一体として見るべきであるという主張に対する裁判所の判断として)示されたものです。そこでは、UAとUAの労働組合の間の統一労働協約の締結が必要だが、そのような見通しすら立っていなかった、と説明しています。UAの労働組合は、外国籍の従業員を先に解雇することをUAに約束させるなど、非常に強い力を持っており、Xもこの労働組合に加入できなければUAで働けない状況だったのかもしれません。もしそうであれば、外国籍の従業員よりも米国籍の従業員を重視する労働組合の方針があり、UAの意向だけでXを受け入れるのが非常に難しい状況にあったことから、UAグループ全体でのXの受け入れを判断しにくい状況だった、ということになるでしょう。
2点目は、再編プロセスです。労判の解説の中で、その過程が図で整理されています(1261.40)が、UAとYの親会社の業務提携から始まり、Yの親会社の合併が先行し、最後に、本解雇の翌年にYがUAと合併しました。
このプロセスの評価については2通りあり得ます。
1つは、Xが主張しているとおり、解雇の翌年には合併しているのだから、XのUA内での配属先も模索すべきである、という評価です。けれども、裁判所はこのような見方を否定しています。
もう1つは、Xの解雇等、Y単体のリストラ(Xの解雇も含む)が終わったのでUAと合併できた、むしろグアム路線の乗客が減少していき採算が悪化していくYを救済するのだから、その前提としてUAがYを受け止められる状況、すなわちしっかりとリストラが完了していなければならなかった、という評価です。UAとYの業務提携から合併に至るこのような背景や経緯については、分からないことが多いので推察の域を出ませんが、日本人のグアム観光客の継続的な減少によって構造的に採算が取れなくなっているYを、UAが救済合併した、という要素は多分に含まれているようです。そうであれば、Yを合併する(救済する)前提に、Y自身によってリストラを完了させ、身軽になることがその条件になるでしょう。つまり、この場合にはXの配属先をUAの中に求めることは、合併の前提に反することで不可能、ということになります。
1審2審いずれも、このプロセスについて詳細な認定を行っていないのは、UAとYの間の合併契約や、その前提となるLOIなどの契約により、合併に至るまでにYが達成すべき条件やプロセスが開示できなかった事情があるのかもしれません。しかし、もしこのような事情があれば、仮にXの請求どおり解雇が無効となってしまうと、(合併契約などの規定次第ですが)UAとYの合併自体が無効となったり、UAに採用された他の多くの従業員が解雇されたり、などの大きな混乱を招くこともあり得ます。
2.実務上のポイント
少なくとも言えることは、グループ全体で受け入れる必要があるのか、当該会社単体で受け入れ可能性を模索すれば良いのかについて、グループだからといってそれだけで決まる問題ではなさそうだ、ということです。
ただ、もともとグループ会社であった場合と、本事案のようにグループ会社として後から合流する場合とでは、グループ全体で受け入れることの可能性や現実性に違いがあるでしょう。その違いをもっと明確に示してもらえれば良かったとも思いますが、今後の整理解雇の参考になる視点です。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
